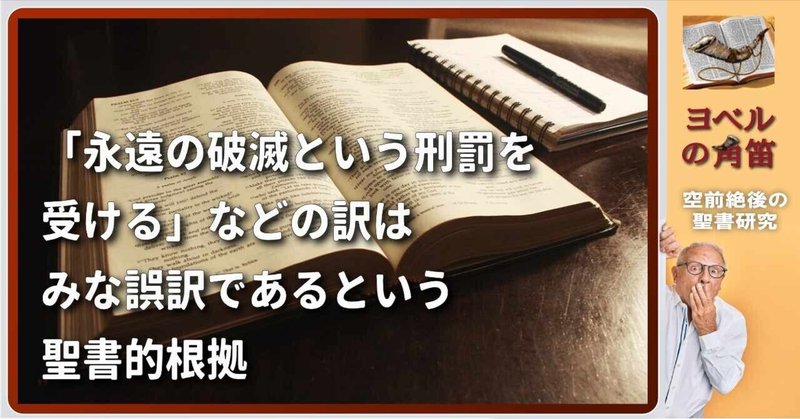
「永遠の破滅という刑罰」などの訳はみな誤訳であるという聖書的根拠
《主イエスは、燃え盛る火の中を来られます。そして神を認めない者や、わたしたちの主イエスの福音に聞き従わない者に、罰をお与えになります。》2テサロニケ 1:8
この記事では主に【2テサロニケ 1:8,9】の聖句を中心に扱います。
ここで「罰を与える」と訳されている語は「ギ語:エクディケシス」です。この語をそのような断定的な語に訳すことが不適切であるという幾つかの聖書的根拠をあげてみましょう。
《まして神は、昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために【裁き】(エクディケシス)を行わずに、彼らをいつまでもほうっておかれることがあろうか。 言っておくが、神は速やかに【裁いて】(エクディケシス)くださる。》ルカ18:7,8
「エクディケシス」をどうしても「罰を与える」と訳したいのであれば、なぜここでは、神は昼夜求めている人たちに「罰を与えずに」放置されることはない。神は速やかに「罰を与えて」くださると訳さないのでしょうか。
イエス・キリストがここで教えられたのは、神はご自分に求めているものに対して、法的な根拠に基づいて必ず顧みてくださる。ということです。
同じ語が、まったく正反対の意味をもつ語に訳されていることに違和感をお覚えませんか。
《神の御心に適ったこの悲しみが、あなたがたにどれほどの熱心、【弁明】(エクディケシス)、憤り、恐れ、あこがれ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。》2コリント7:11
或いは、「神の御心に適った悲しみが、多大の「罰を与える」ことをもたらす。」となぜ訳さないのでしょうか。
本来の「エクディケシス」という語は「法的な処置の正当性」というニュアンスを伝える語です。少なくと「罰」という意味は全くありません。勝手な意味を付け加えているわけですから、「誤訳」と類と言って良いでしょう。
せいぜい「裁きを与える」と言う訳が適切でしょう。「裁き」はどちらの場合もありえます。
付け加えておくなら、「燃え盛る火の中を来られます」というのも殊さらにオーバーな表現で原語は単に「燃える火の中で」という意味であり「来る」などという単語は存在しません。
これは「大患難」の経験を通して精錬されることを意味していると思われます。
では次にもう一つ後の聖句。
《彼らは、主の面前から退けられ、その栄光に輝く力から切り離されて、永遠の破滅という刑罰を受けるでしょう。》2テサロニケ 1:9
永遠の【破滅】(ギ語:オレスレス)という【刑罰】(ギ語:ディケ)
この表現もよく考えると奇妙な日本語で、瞬時に破滅したらそれでお終いでしょう。それとも永遠に渡って破滅し続けるのでしょうか。どう考えても文脈と訳語が適切ではないようです。
さて「神を認めない者や、福音に聞き従わない者」(前節)は「永遠の破壊」ということですが、「破壊される」つまり直ちに消滅するのなら、わざわざ「面前から退け」たり「栄光から切り離す」必要などありません。
最後の「刑罰を受ける」の部分ですが「ギ語:ディケ」という語は、先程解説した「法的な処置の正当性」とういう意味の「エクディケシス」は(エク(~から、という前置詞 + ディケ)という語から成り立っています。つまり語根は同じものです。
この「ディケ」は使徒28:4では、(口語訳では【ディケー の神様」)と音訳されていますが、どの日本語訳も「正義」と訳しています。基本的な意味は「法的処置」という意味だからです。
同じ語がある場所では「刑罰」、別のところでは「正義」と訳されているのです。ですから、「刑罰」という特定のイメージを植え付ける根拠はないということです。
さて【破滅】と訳されている「オレスレス」は聖書中にわずか4回しか使われていません。使用例が少ないので、他の聖句との比較が難しいですが、パウロだけが用いているこの語を彼がどんなニュアンスで捉えていたのかを探って見たいと思います。
残りの3つもすべて引用して一つずつ検証してみることにしましょう。
《(父の妻をわがものとしている)このような者を、その肉が【滅ぼされる】(オレスレス)ようにサタンに引き渡したのです。それは主の日に彼の霊が救われるためです。》1コリント5:5
「その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡した」というこの表現が具体的にどんなことを指しているのか分かりませんが、少なくとも、その目的は「彼の霊が救われるため」であるということですから、「オレスレス」が罪人に対する死刑や絶滅を指すのであれば、「主の日に霊が救われる」ことなど決してないはずですから、この語がが必ずしも文字通りの「破滅」を意味するけではないことは確かです。
《人々が「無事だ。安全だ」と言っているそのやさきに、(彼らに)突然、【破滅】(オレスレス)が襲うのです。ちょうど妊婦に産みの苦しみがやって来るのと同じで、決してそれから逃れられません。》1テサロニケ 5:3
「人々」とは誰でしょうか。突然「オレスレス」に襲われる「彼ら」とは誰でしょうか。
対比されているのは、「主の日が、盗人のように突然あなたがたを襲うことはない」(5:3)ということですから、目覚めている人以外、「ほかの人々のように眠っていないで」(5:3)という、クリスチャン以外のすべての人です。
主の日には、クリスチャン以外の人々も裁きに遭います。それは「羊とヤギ」に分けられる全人類であり、そのうちの「羊」は御国を受け継ぎます。
「オレスレス」の遭遇は「妊婦に産みの苦しみがやって来るのと同じ」ということですから「オレスレス」は文脈から言って「大患難」を指していることは明らかです。
主の日にクリスチャン以外の全人類が、突然、全滅することはありません。
ですから、2テサロニケ 1:9 の「オレスレス」を「破滅」と訳しているはこれまた誤訳と言わざるを得ません。
《金持ちになろうとする者は、誘惑、罠、無分別で有害なさまざまの欲望に陥ります。その欲望が、人を滅亡と破滅に陥れます。 金銭の欲は、すべての悪の根です。金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出て、さまざまのひどい苦しみで突き刺された者もいます。》1テモテ6:9,10
「(金銭への)欲望が、人を【滅亡】(オレスレス)(と【破滅】(アポレイヤ)に陥れる」
《金の好きなパリサイ人たち》ルカ16:14という表現があります。しかしパリサ人は絶滅などしていません。
「アポレイヤ」は例えばマタイ 7:21にも見られます。「滅び【アポレイヤ】に通じる門は広い」
更にはマタイ 26:8,9では高価な香油をイエスの足に注いだ女に対して、弟子たちが憤慨して、「こんなむだ [アポレイヤ] なことを するのか。」と記されています。
この語の字義は[ cut off ](切断、切り離される)という意味であり「バインの旧新約聖書用語解説辞典」では、『 絶滅(消滅)を意味するものではなく 。 むしろ、完全な「取り消し」に伴う結果的な損失を強調する。』と説明されています。
「アポレイヤ」の意味するところに一番近い訳語は「滅び」ではなく「無効」というのが的確でしょう。
「誘惑、罠」は同義語とは言わないまでも、似通ったニュアンスの言葉で、同様に「オレスレス、アポレイヤ」も若干のニュアンスの違いはありますが、意味の近い別の単語を羅列することにより論理を強調しています。
「オレスレス」の使用例を比較してみますと、パウロがこの語にどんなイメージを持っていたかが見えて来ます。
関連したキーワードを列挙してみますと、「退けられ、切り離され、苦しみが来る、信仰から迷い出、苦しみで突き刺され、無駄に終わる(アポレイヤ)」などです。
福音を退け、目覚めていなかった人々は、突然に裁き主と直面し、大患難を経験することを通して精錬され、法的に正当な処置を受けることになります。
しかしそれは、破壊でも、絶滅でも、死でもありません。
関連記事:
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
