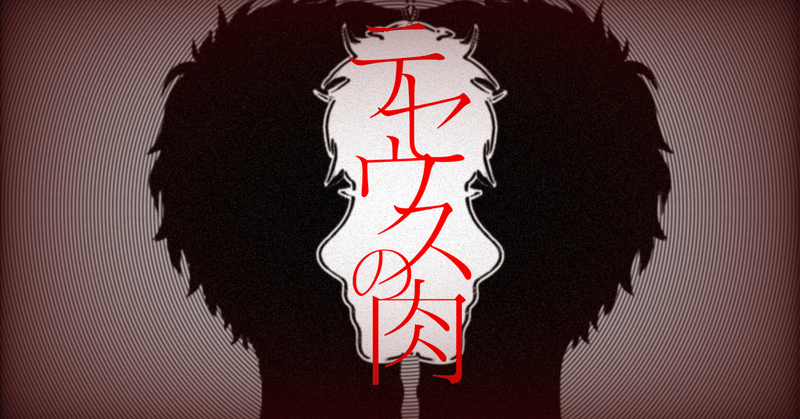
長編小説『テセウスの肉』第20話「188日目(駒早祭2日目)①」
駒早祭二日目。最終日。
この日は、ベストカップルの結果が発表される。私たちはまあ、自己アピールをほとんどしていないし、雅人の件でよくない噂も広がっている。だから望み薄ではあるが、それでも結果発表には足を運ぼう。というか、エントリーしたカップルは一応全員参加が原則になっていた気がする。
もはやほとんど別人のような見た目の雅人は、一応マスクと伊達メガネで誤魔化しつつ、午後の結果発表を私と一緒に待っていた。まだ昼前だというのに、飲食店をやっているゼミやサークルはどんどん食べ物を売り込んでいる。
私と雅人は、ベストカップルの表彰時刻の午後三時まで学祭を回ることにした。雅人はいつ残りの体が入れ替わってしまうか分からないので、私と常に一緒に行動し、あまりにも混雑する場所は避けることにした。
「どうする真希ちゃん、何か食べる?」
雅人に聞かれるも、出店数が多すぎて目移りしてしまう。パンフレットを見ても、飲食店だけでざっと一〇〇はあるのではないか。
「なんか、人酔いしそうだしあんまり重くないのがいいかなあ」
私がそう言うと、雅人はすぐさまパンフレットの出店紹介ページを捲る。私もそれを覗き込み、二人でちょうどよさそうな店を探した。
「これなんかどう? トルティーヤだって」
「いいかも! ありがとう。雅人はもっとがっつり食べたかったら他の店もついてくよ」
「俺もトルティーヤ食べたいから大丈夫! ありがと~」
昨日、あんなことになって、今目の前にも痕跡が残っているのに、私たちはいつもの私たちで、それが心強いような、これでいいのかと不安になるような複雑な気持ちだった。
目的のトルティーヤを売っている店前で商品を受け取ろうとしたとき、それは突然私の目に飛び込んできた。
雅人の目。
雅人の口。
雅人の髪。
雅人の身長。
雅人の歩き方。
――を持つ、別人。
それは私の目が追うより早く人混みに消え、視界から消える。私はすぐさま、トルティーヤを受け取った雅人の腕を引き、衝動的に叫んだ。
「雅人! 今、御船朝哉が――!」
それを聞いた雅人は、すぐさま私の方に向き、大丈夫だった!? と言った。
「あ、いやもしかしたらそうかもしれない人を見かけただけで」
「よ、よかったあ……」
雅人は強張らせた顔を少しだけ緩め、ため息をつく。そして、私たちはトルティーヤの出店から少し離れ、街路樹の下で受け取ったそれを食べながら話した。
「そいつ、俺の姿をしてたってこと……?」
「……うん。間違いないと思う」
トルティーヤを大きな一口で頬張った雅人は、もぐもぐと咀嚼しながらうーむと唸る。そして、少し考えたような仕草をした後、口の中のものを飲み込んで言った。
「探し出して、会ってみる?」
やっぱり、それを考えていたみたいだ。元々家まで行って会おうとしていたわけだし、それにこの人混みであちらが何かしてくるとは思えない。
「……そうだね、そうしよう」
御船朝哉に会って何かが解決するという保証はどこにもない。朝哉が全ての元凶なのか、はたまた別に黒幕のような存在があるのか。ただ、こうしているうちにもいつ雅人の体が完全に朝哉になってしまうのか分からない。一刻も早く、朝哉に会って何か情報を掴みたい。
私たちは、十二時半を回ったところで、朝哉の捜索を始めた。放送などで大々的に探すわけにはいかないので二人で端からしらみつぶしである。まさか学祭が二日連続で人探しになるなんて思いもしなかった。
探し始めて三〇分。この人混みと広さでそう簡単に見つかるわけがなかった。
「さ、三時に間に合うのかなこれ……」
雅人が苦笑しながら言う。
「そんときはそんときでしょ!」
半ば投げやりに私は言った。そうだ、そのときは仕方ない。
*
そのときは、あっさり来た。結局、ベストカップルの結果発表まで残り五分となっていた。私と雅人は待機席につき、他の候補者カップルたちに囲まれる。
ベストカップルの結果発表は、昨日ゲスト芸人がネタを披露したメインステージで行われるようだった。ステージの背後には大きなモニターが設置されており、お金がかかっているなという印象である。私たちの他に七組のカップルがエントリーしており、お互いに敵意を向けあっている。私たちは、もうこの投票にあまり執着していないので、この空気が耐え難かった。
「それでは、ベストカップル最終投票を行います!」
スピーカー越し、音割れ寸前の放送サークル員の声が会場に響く。これ会場の外まで響いているんじゃ……?
最終投票。どうやら、ベストカップルは期間中の投票の他に、今日会場に来ている客の投票も最後にリアルタイムで集計し、足されるらしい。
「エントリーしたベストカップル候補の皆さん、どうぞ!」
私たちはカップルごとに手を繋ぎ、ステージに横並びで上がった。運がいいのか悪いのか、私たちはステージ中央に位置取られている。
「では、現時点での投票数を見てみましょう!」
背後にあるモニターが色を変えるのが分かった。振り返ると、そこには私たちカップルの名前と、その横に投票数、帯グラフが分かりやすく表示されている。
一位は三年生の有名カップル。三七一票。
二位は二年生の美男美女カップル。三三二票。
そして、三位に私たちの名前があった。二九〇票。
それ以下は大きく差がついており、彼らは分かりやすく落ち込んでいた。私と雅人は変な噂が出回っていたし、自己アピールもほとんどしていなかったのにも関わらず、結構いい順位にいた。会場にはざっと一〇〇人以上の観客が集まっている。一応、三位までなら逆転の可能性もあるが、まあ望みは低いだろう。
「――まだまだどうなるか分かりません! それでは、各カップルたちに一言ずつコメントをいただきたいと思います!」
放送サークル員は元気よくそう言った。
聞いてない! 聞いてなんですけど!?
私と雅人は顔を見合わせ、そして他のカップルを見る。彼らも同じく困惑しており、これはやはり事前に言われていたものではないことを悟る。アドリブ力でも見られているのだろうか。でもなんで? いや、まあいい。とにかく何を言えばいいか考えなきゃ……。
右端のカップルから順にマイクが回される。私たちはほぼ中央なので四番目。まあ適当に、「投票してくださいね~」とか言っておけばいいだろう。そう思って、隣のカップルからマイクを受け取った。
その瞬間。
まさに私がマイクを口に近づけた、その刹那。
大きなノイズがスピーカーを劈くように響く。背景のモニターの色が変わる。
「え」
間抜けな私の声がマイクに乗ってしまった。
それと同時に、スピーカーから声が聞こえた。
『あれ? 陰毛ちゃんじゃん。久しぶりに見た』
――それは、中学時代の、男子の声。
頭が回らなかった。ただただ、何も分からず、振り向く。
そこには、大きなモニターに、中学時代の教室が映し出されていた。
『これは、帆波真希の中学時代の映像です。あれ、髪の毛がもじゃもじゃの、陰毛ちゃんって呼ばれてる女の子が、帆波真希』
その映像の撮影者のものらしき声が、篭った音で聞こえた。声に加工が施されており、声の持ち主は分からない。
でも、この喋り方ってどこかで――。
その時、映像にカットが入り、時間が少しだけ飛ぶ。場面は同じで、私が転んでいる。
『なにこれぇ?』
『もしかして、ラブレター?』
映像からの笑い声と、会場の騒めきが私の頭を搔き乱す。視界の端で、放送サークル員が困惑しているのをとらえた。
私は、この映像の日をはっきりと覚えている。私が傷つき、痛みを知り、見返してやろうと決意を固めた日。忘れられない、忘れたい一日。
『帆波さん、これ誰から!? どこで!?』
私が女子からふらふらと手紙を奪い取ろうとする滑稽な姿が映る。
『いいからッ……返して……ッ』
声にまったく自信が感じられない。
ああ、このころの私って、こんなに弱かったんだ……。
再びカットが入り、場面が進む。どこか遠くで「止めなさい!」と大人の声が聞こえた気がするけど、誰も聞く耳を持たない。
『どれどれ……〈帆波真希さんへ〉! うわあホントに陰毛ちゃんへじゃん!』
またカット。
『きっも! 陰毛ちゃんに告るとか異常性癖だろ!』
『やッやめて……!』
あの頃の気持ちが、甦る。私はステージの上で俯いて、震えているしかなかった。雅人は私の肩を抱き、大丈夫、大丈夫と声を掛けてくれている。
大丈夫。この後、のえりーの助けが入るはず。廊下から、のえりーが……。
カット。
『ほらね。ニセモノ。残念でしたあ、陰毛ちゃん勘違い乙』
手紙を真っ二つに破く男子。
なんで……。
その悪意ある編集に、私はただただ涙を流すことしかできなかった。大勢の前で、過去の屈辱を、トラウマを流されて、何もできずに震える自分。悔しくて悔しくて、死にそうだ。なんで、誰が、何の目的でこんなこと……。
その時、私はモニターを見上げると、画角が大きく変わっていることに気づいた。それまでは、廊下の外からだったのが、教室の中で隠し撮りしているような風になっている。
『お前みたいなブスのこと好きになるやつなんていねえよ』
その男の声で動画は終わる。
そして、真っ黒の背景に後付けしたような音声が流れ出す。
『帆波真希。今でこそ綺麗になっているけど、昔はこんなに滑稽で、ダサくて、残念な子だったんだよ。みんな騙されないで。帆波真希は見た目がコンプレックスで、見た目だけ磨いて、中身は二の次の女。顔だけで彼氏を選ぶ性格ブス。帆波真希は、そんな女』
ああ、そうだ。それは間違いじゃない。その通りだ……。だけど……。
「真希ちゃん」
すすり泣く私に、雅人が言う。
「真希ちゃんは、そんな人間じゃないよ」
雅人が私からマイクを取り上げる。覚悟を決めたような顔で立ち、大きく息を吸った。
「みなさん、聞いてください」
騒ついていた会場が、一気に静かになり雅人に視線が向く。
「俺は、真希ちゃんを中学の頃から……さっきの映像のずっと前から好きでした。それは、真希ちゃんは真面目で、努力家で、優しくて、俺に勇気をくれたからです。そんな真希ちゃんは、クラスの心無いいじめによって、見た目に強いコンプレックスを持ちました。それは事実です。自分のことが嫌いになったり、自分の存在意義が分からなくなったり。そういう暗闇を経験しました。でも。それでも、真希ちゃんは頑張ったんです。みんなを見返したい。自分を認められるようになりたい。そういう思いで、今だって毎日頑張って、その結果こうして俺を幸せにしてくれています」
会場は、観客は、静かに雅人の声を聞く。
「だから、だから……」
私は、立ち上がった。足も手も、震えていなかった。
涙は涸れ果てた。私は、私は。言わなきゃ。
雅人からマイクを受け取った。
「ごめんなさい!!!」
音が割れる。キーンとマイクがハウリングする音に、会場中が耳を塞いだ。
「あ、ごめんなさい! 音……、じゃなくて、私、謝らなきゃいけなんです!」
雅人が私の顔を見つめる。私も雅人を見る。
「……雅人、ありがとう。でも私、そんなにえらい人間じゃない」
マイクを握りなおす。その場にいる全員が、私を見ていた。もう誰も止めようとしていない。ことの成り行きを、一〇〇人、いや、おそらくもっと増えて三〇〇人以上が見守っている。
「見た目にコンプレックスを持って、自分が嫌いになって、最初はいじめてきた人たちを見返してやろうって気持ちだけでした。でも、でもいつしか、見た目にこだわっていくうちに大切なものを見失いました。自分も他人も、見た目だけで測るようになって。見た目だけを重視するようになって。雅人に出会う前も、告白してくれた男性は見た目を理由に振って、雅人も……多分見た目で付き合おうって決めて」
ああ、話し続けるのが辛い。自分を曝け出すって、こんなにも怖いんだ。
「最低ですよね……こんな、ルッキズムが正しいと思い込んで生きてきて、許せない人はたくさんいると思います。……でも、最近気づいたんです。思い出したんです。見た目だけじゃ、人は作られていない。中身――心が、記憶が、感情が人間なんだって。例え見た目が全部変わったとしても、その人はその人で、揺らがない」
雅人の手を握る。
「私がどれだけ自分の見た目を美しく磨いても、中身が弱いんじゃ意味がない。……でも私は今、見た目を変えられて幸せです。矛盾してるかもしれないけど。でもそれは、私が昔と変わらない強い心を持っていたから得られたものです。そして、その思いは人の中身から生まれるもの。それがあったから、私は今幸せ。忘れてしまっていた、見た目以外の価値を、私は思い出したんです。許してほしいだなんて言いません。でも、私はもう、見た目で人や自分を判断しない。雅人が例えどんな姿になったとしても、愛しています」
そうだ。
私は、負けない。中学時代、酷い仕打ちをしてきたクラスメイトにも。こんなところで、隠し撮りを晒す人間にも。雅人から体を奪う奴にも。弱い自分自身にも。
前を見据え、マイクを下ろした。司会の放送サークル員が、我に返ったようにマイクを持ち直し、沈黙を破る。
「えっと、ありがとうございます! お、思わぬハプニングもありましたが、続けさせていただきます。続いてのカップルの方――」
残りのカップルたちは、ものすごく気まずそうに一言コメントを残し、私たちを恨めしそうな目で見た。そして、最後のカップルがコメントを終えた後、ついに最終投票が始まる。
「では、会場にお越しの皆さん! 七組のカップルの内、一番推せると思ったカップルを、モニターに映っているQRコードから飛べる投票フォームから選んで送信してください!」
観客たちは次々とスマホを取り出し、投票を始めた。投票時間は十分間。その間、私たちはステージ裏の待機スペースに座らされた。
「……雅人」
私は雅人に、思っていることを話すことにした。
「あの動画……誰が撮ったか分かった」
雅人が、ピクリと反応する。
それは、嘘だと思いたかった。だが、これしか考えられない。考えられないのだ。
「……だ、誰なの?」
「…………驚かないでね」
私は念を押す。事実だとしたらこれは、これは私たちにとって、最悪な真相だ。とてもじゃないが、冷静ではいられない。私は震える手を握り込み、大きく息を吸って、吐く。言いたくない、できれば心の奥にしまっておいて、知らなかったフリをしたい、その推察を口に出した。
「のえりー」
不安を解消しようとどうでもいい雑談をするカップルたちの中、私と雅人だけ、別の時間を生きているような錯覚に陥る。雅人は、一瞬驚いた顔をし、そして私に問う。
「な、なんでそう思ったの……?」
もっともな疑問である。雅人視点では根拠の薄い話だ。
「順を追って話すね」
私は時間を確認し、残り六分ある投票時間で説明を始めた。
「最初に違和感を持ったのは、雅人から中学時代の話を聞いたとき。あのラブレター、私はイタズラのために作られた偽物だと思ってた。それで私は深く傷ついたんだけど、のえりーはあれが雅人が書いたものだって知ってたわけでしょ? だったらなんで今まで私にそれを教えてくれなかったんだろう」
雅人は、何も言わずに頷く。
「それで、その違和感が確信に変わったのが、今回の映像。あれ、完全にのえりー視点なんだよね。最初の画角が廊下から。次が私を助けに来たから教室内。それに加工で分からなくしてあったけど、あれのえりーの喋り方だったと思う。微妙な癖が抜けてない……あと、あの子実行委員の手伝いしてるから、ああいう風にモニターに細工もできたはず……」
映像を操作するスタッフは、私たちのいる待機スペースから確認ができないが、もしかしたらそこにのえりーがいるのかもしれない。
「…………それが、真希ちゃんの考えなんだね」
雅人は言って、目を瞑る。
きっと、葛藤している。私のことを信じるか、のえりーのことを信じるか。
「……うん。真希ちゃんを、信じる」
目を開き、私を見る雅人。雅人の顔はもう、雅人ではない。でもそこにいるのは間違いなく雅人で、私の味方だ。
不意に、待機スペースの入り口が開く。
「すみません、エントリーした皆さん、出番です」
私たちは、ステージに上がった。
計八組のカップルは、先程と同じ順に並んで立った。観客は三〇〇人を超えているようで、会場はほぼキャパオーバーの状態である。
「それでは」
放送サークル員がマイク越しに声を張った。
「結果発表のお時間です」
ステージに、会場に緊張が走る。しかし私と雅人は、全く別のことを思っていた。
「栄えある第五十七回駒早祭ベストカップルに選ばれたのは」
大袈裟なドラムロールが鳴る。それは十分すぎるほど溜めをつくって、観客を煽る。もういいだろうと思う直前で、バーンと最後の一音が鳴った。
「海原雅人、帆波真希カップルです!!」
私は反射的に振り返り、モニターを見た。いや、まさか。そんなはずない。あんなことが起きて……。
モニターには、間違いなく私と雅人が一位であることが、数字で示されていた。会場で入れられた票のほとんどが、私たちに入れられている。
信じられない。まさか、三位から逆転するなんて、思いもしなかった。
でも、今はそれよりも、私の心を支配しているのは待機スペースでの会話だった。のえりー。彼女のこと。それは、横に並んでいる雅人も同じだった。口元に笑みを貼りつけ、目は笑っていない。
「おめでとうございます!!」
歓声と拍手が、響き渡る。
観客の多くがスマホのカメラをこちらに向け、この瞬間を必死に切り取ろうとしていた。照明が眩しい。太陽が西に傾いて、夕焼け前の静けさが空に宿る。その空と会場の距離は遠くて、まるで私の心とこの光景がどこまでも乖離しているのを象徴しているようだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
