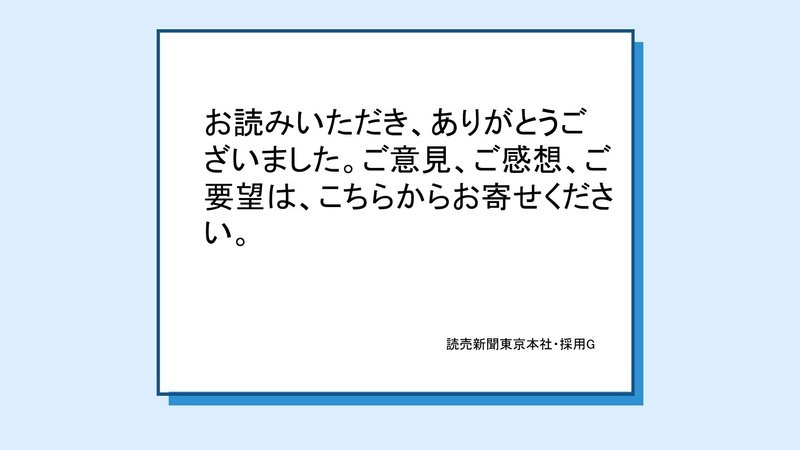新人記者の心じゃわめぐ夏
こんにちは。読売新聞東京本社・採用Gの田中です!
今回は、青森支局の新人記者が、「青森ねぶた祭」に実際に参加した様子をルポで描いた連載記事「りおのカーニバル」(7月27日付~、青森県版、全5回)の舞台裏をご紹介していきます。
【若手記者のキャリア】
本題に入る前に、読売新聞の若手記者のキャリアを簡単に紹介させてください。
読売新聞の場合、新人記者は約2か月の研修を経て、地方総支局に赴任します。そして、そこで約5年を過ごします。東京本社の管内では、支局ごとに、記者は計20数人というところがほとんどでしょうか。これは、県庁所在地の「親支局」、その地方の主要都市にある「ミニ支局」に勤める記者も含めての数、です。若手記者は、支局にいるあいだ、警察、高校野球、地方自治体の行政、選挙などなど、いろいろなジャンルの取材を経験し、東京へ。東京本社では、各取材部(代表的なものとして政治部、社会部などが思い浮かびますが、かなり細分化しています)で専門性を高めていくーーというのがざっとした流れです。
【青森が第一希望】
今回ご紹介するのは、22年入社の稲葉りおさんです。現在は、警察担当ですので、青森県内の事件事故の取材を担当しています。実は、稲葉さんは私が昨年秋に人事部に着任した当初、内定者としていろいろな学生向けイベントを手伝ってくれていました。元気いっぱいなイメージがある一方で、稲葉さんは首都圏育ちだったはず。青森生活は不安でしたか?

「いえ、首都圏にいたからこそ地方勤務は楽しみでした。実は、青森、一番で希望を出しました」。将来は基地、原発といったテーマでの取材を考えているのだそう。一方、苦手なのは、「方言を正確に聞き取ること」。楽しみに赴任した青森ですが、勤務を始めた頃はやっぱり休日はどっと疲れが出て、せっかくの休日でも出かけたくない…となってしまうこと度々。最近になってやっと自分なりのペースをつかめるようになり、休みの日は県内各地にドライブして見聞を広めることにしたそうです。その感じ、私も分かります。
さて、青森で、今年一番の話題は、何と言っても新型コロナウイルスの感染拡大で中止が続いていた「青森ねぶた祭」(8月2~7日、青森市)の3年ぶりの開催でした。踊り手「跳人(はねと)」の練り歩きに、武者や古代中国の英雄などをかたどった色鮮やかな人形灯籠。現場の熱気を、どうやって読者に伝えていくか、支局内ではデスク(記者の原稿を見て、直す先輩記者)も交えて議論したそうです。そんな中で、稲葉記者の提案は、「踊り手の目線から、動画を撮影しよう」というもの。踊り手の目線を体験するには、稲葉さんも練り歩きの列に加わらなければなりません。「いっそ、飛び込んで全部やってみるしかないんじゃない!?」という話に発展していきました。
【そして連載へ・・・番外編も】

祭りを「体験」し、その記事を執筆することになった稲葉記者。ある記事が念頭にありました。
「実はヒントになったのは、同期のまりちゃんの記事なんです」。まりちゃんというのは、同期の松本茉莉記者(盛岡支局)のことですね。松本記者が、警察学校に入校した体験をまとめた岩手県版の記事は、採用Gでも当時話題になりました。「ルポっていう手があるんだな、と改めて新鮮に感じたんです」。
お手本の記事も見つかり、何となく原稿のイメージができてきました。ところで、まだ決まっていないものがあります。それは連載の「タイトル」です。デスクが示したタイトルは、「りおのカーニバル」。もちろん、稲葉記者の名前に引っかけています。稲葉記者はこの段階で、「いきなりオヤジギャグだけど、ちゃんと読んでもらえるのかな」とかなり不安になったそうです。
しかし、もっと差し迫った問題もありました。地方支局の若手記者は毎年東京に巣立っていきます。つまり、前回のねぶたの取材を経験した記者は支局に2人だけ。デスクや支局長だって異動していきますから、取材のノウハウがあまり残っていません。そこからの準備は大変でした。数少ない経験者の先輩に祭りの様子やしきたりを聞いたり、資料を読みこんだり。「有名なお祭りなので、関係者の方も取材には慣れていらっしゃると思うんですが、やっぱりこちらに知識が無いとインタビューしていても、会話が続かなくなってしまうんですよ。だから、やっぱり事前の勉強は大切だなと思いました」
7月、高校野球取材の合間を縫って、「ねぶた小屋」や、お祭りの関係者のもとに足しげく通った稲葉さん。「りおのカーニバル」は、①ねぶた師の方に「弟子入り」して、ねぶたの彩色を手伝い、②囃子(はやし)方の演奏に合わせて「跳ね」の練習、③浴衣など、跳ね人衣装の着付け、そしてもちろん、④熱気あふれる本番のルポ、計4回が無事、青森県版を飾りました。オンラインでも公開していますので、こちらは実際に読んでいただいた方が早いと思います。稲葉さんの「心じゃわめぐ」(心躍る)様が、伝わってきます!

当初4回予定だった連載は、反響も大きなものだったそう。ねぶたの解体を見届ける涙の⑤「番外編」を急遽掲載し、全部で5回に延びました。稲葉さん自身も担当する警察署に電話した際、「りおのカーニバル読んでます」と言われて、とてもうれしかったそうです。記者仲間や地元の人とも、雑談を交わすきっかけがひとつ増えました。
やはり、読者の方の反応を頂くのは、とても励みになるようです。稲葉さん、これからも楽しい記事をどしどし書いてくださいね。
【発端となった動画のこと】
ひとつ忘れていました。そういえば、企画の発端となった動画はどうなりました?
もちろん、無事公開されています。
祭りの本番では、稲葉記者は夢中になって「跳ね」ていましたので、撮影は2年目の先輩記者、吉田明日香さんが担当しました。読売新聞にはプロのカメラマンが多数いますが、吉田さんは取材記者ですよね。動画の撮影は初めてでしたか。
「実は高校時代に文化祭などで映像制作していて、大学時代は1年間、アメリカ・ニューヨーク州に留学し、映像制作を学んでいたこともあるんです。アルバイトで子どもたちに動画編集を教えていたこともあります」。吉田さんが好きな監督は台湾のエドワード・ヤンとのこと。
(ちなみに、読売新聞には学生時代の留学を経て入社した吉田さんのような方もいますが、入社後に社内の留学制度を使って留学する人も大勢います。ご参考までに、編集局では、2013年度以降、今年度の留学予定者を含めて10年間で50人が海外に留学しました。語学のほか、自分が関心を持っている専門分野を勉強する人もいます)
と、想像以上に本格派でした。余計なことをお聞きしますが、テレビ局の就職は考えなかったのでしょうか?「映画を作るにせよ、ドキュメンタリーにせよ、人の心に訴えるのに、大事なのはストーリーだと気がついたのです。ストーリーを語るには大事なのは、言葉、文章だなと思って、新聞記者の道を選びました」。
といっても、記者になってから動画を担当するのはやはり初めて。ねぶたの動画は、コンテづくりなどを東京本社のオンラインの部署に相談。スタビライザーなどの機材を東京本社から借りて、デジタル一眼で撮影しました。支局の同僚にも手伝ってもらっています。

実は、この動画、画期的な部分があるんです。それは、音声のナレーションがついていること。読売新聞としては前例のない取り組みでしたが、「ナレーションがあった方が、稲葉さんの気持ちが伝わると思います」と強く主張した吉田さんの粘りで表現の幅が広がりました。この取り組みをきっかけに、支局ではもっと動画を活用していこうという話が盛り上がっているそうです。青森支局の今後の取り組みに、どうかご期待ください!
#若手のシゴト①
(取材・文 田中洋一郎)
※肩書は、執筆当時のものです。