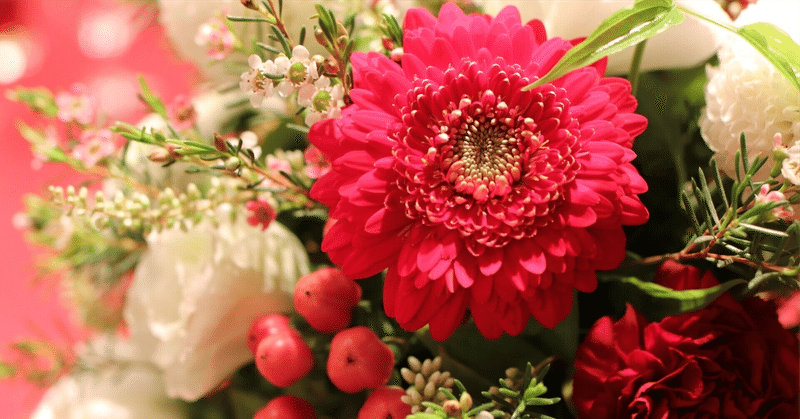
「アルジャーノンに花束を」
タイトルにある通り「アルジャーノンに花束を」を読み終えて、感想を忘れないように書いておきたいと思う。
きっかけ
もともとヨルシカが好きで、「アルジャーノン」という「アルジャーノンに花束を」をもとにした曲があり、原作を読んでみたいなと思ったのがきっかけ。色々ひと段落して今年は本を読むぞ!と意気込んだ一冊目。
知識
知識は得れば得るほどいいと考えていた。なのに冒頭で「教養は人と人との間に楔を打ち込む可能性がある。」と言われて衝撃が走った。それとともに納得もした。
知識を得れば得るほど世界が広がって見えなかった世界に入っていくけれどそれは同時に永遠に終わりのないもので、必ず知らないものが出てくるし、上には上がいると思い知らされる。私はその話の輪に入りたくて必死で教養を身に着けているけれど、確かにその間にあるのは教養の楔だった。
教養の楔は人間の違い。歩んできた道の違い。100人に100人の教養があって全く同じ知識や経験を持つ人はいない。
筆者のキイスさんが言いたいのは知能を得ることは役に立たないということではなくて、共感のこころこそが本質的なことなんだと思う。「国の、種族の、宗教の、異なる知能レベルの、老若男女の立場に自分を置いてみること。」とある。自分とは違う他者を認め合ることは自分を認めることでもある。知能は手段でしかない。
変わっていったのはチャーリーなのか、周りの人なのか。
チャーリーは知能を得ていったりそれらが全て崩れ落ちていったりすれども、アルジャーノンという存在に心を配る優しさは変わらなかった。
知能を得る前も得た後もチャーリーは一人の優しい人間であった。
チャーリーは知能を得たとたんに傲慢になったかのように周りの人は話すが、そうではなくて、変わったのはチャーリーに対する周りの人々の態度だ。人は誰かと比べずにはいられない。劣等感を抱え無意識に誰かを下にみている。安心していた自尊心が揺らぐと不安になる。この本はそんな部分をチャーリーの知能の変化を通して露骨に映し出している。
そうか。もう一度この本を読むなら、注目してみる点はチャーリーではないのかもしれない。
難しく考えすぎてきちゃったので単純化しよう。
「アルジャーノンに花束を」と願える人になろうと思う。それだけでいい。
ついしん
訳者あとがきをよんで、翻訳家になるのも可能性の一つとしてありかもと思った。知性が変わるごとに変わっていく言葉遣いを翻訳するの難しそうで楽しそうに思った。原作も読んでみたい。AIが進んで広がっていく中、小説などにはAIに出せないニュアンスが大事になると思う。AIに比喩はできない。本が好きだし表現も好き。その表現の仲介って素敵かもな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
