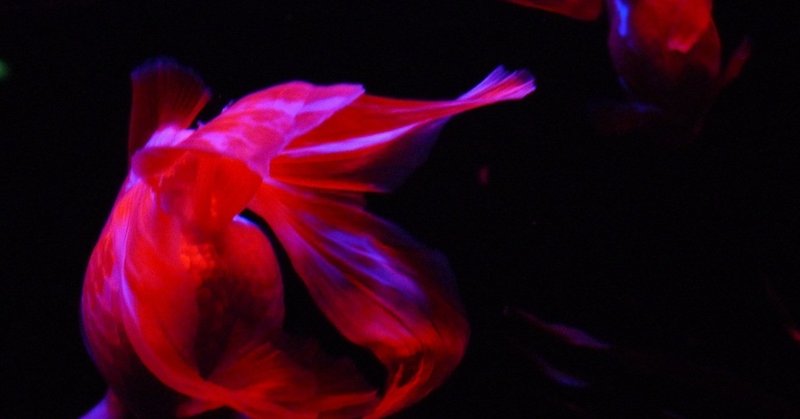
四月ばかの場所2 キャバクラ
ルームシェアを提案してきたのは四月ばかのほうだ。
三年前まで、四月ばかは吉祥寺に住んでいた。それから長野の山奥、沖縄、タイと住居を転々としたのち、旅先のトルコで同じくひとり旅をしていた日本人女性と出会った。
彼女は四月ばかより年上で、瀬戸内海の離島に住んでいた。行動の早い四月ばかはすぐさま離島で彼女と同棲生活を始め、それはつい先日まで続いていた。彼女が、この春から織物の勉強をするため南米へ行ってしまったのだ。
彼女が帰ってきたら結婚して島に定住するつもりだということ、その前にもう一度東京で暮らしたいということ、しかし東京は家賃が高いからシェアメイトが欲しいこと、そしてそんな突然の提案を快諾してくれそうなのはあたしくらいしかいないことを、深夜の電話で言われた。
あたしはすぐに「いいよ」と応えた。断る理由がなかったからだ。
物件はあたしが探した。
四月ばかは吉祥寺に住みたいと言ったけど、あたしは嫌だった。吉祥寺は好きだし、職場もあるけど、あたしと四月ばかが吉祥寺でルームシェアするのはなんだか「いかにも」という感じがする。
しかし、あたしが不動産屋でインスピレーションを感じた物件は、最寄り駅の欄にばっちり吉祥寺と書かれていた。
実際に見せてもらうと、「ああ、ここだ」とわかってしまった。じゃんけんで、相手が何を出したかを認識する一瞬前に勝敗がわかってしまうときの、あの感じ。
あたしが「ここにします」と即決すると、その高校球児のような若い不動産屋の社員は「もっと見てみなくていいんですか」と言った。
本当に最寄り駅は吉祥寺なのだろうか。
諦めきれず、あたしはストップウォッチを手に、そのマンションから駅まで歩いてみた。すると、吉祥寺駅よりも三鷹駅のほうが若干近いことがわかった(1分47秒の差だが)。
それを発見したあたしは嬉しくなってテンションが上がってしまい、電話口で「それ見たか!(三鷹)」と声を張り上げた。四月ばかは「ばーか」と、笑いを含んだ声で言った。
かくしてあたしと四月ばかは、三鷹駅からも吉祥寺駅からも微妙に遠い、家賃十万五千円のマンションで二人住まいをすることになった。
奇しくも四月一日、冗談のような日から。
「さつきちゃん、引越し終わったの?」
ドレスに着替え終わってフロアへ出ると片倉マネージャーが声をかけてきた。懐かしいユーロビートが大音量でかかっている。
「終わったよ」
「吉祥寺でしょ? 店近くなってラクでしょ」
「三鷹だよ」
店長がガラス張りのブースからひょいと顔を出し「今日から送りいらないんだって?」と言って、またすぐ顔を引っ込める。ブースにはターンテーブルがあるのに、店長はいつもCDしかかけない。
「うん。駅に原付置いてきたから」
「帰り、気をつけてよ。客に家ばれないようにね」
「はーい、気をつけますー」
この吉祥寺のキャバクラで働き始めてもうすぐ一年になる。待遇もまあまあいいし、人間関係もうまくいっているけれど、そろそろ辞め時かなと思ってはいる。一つのところに長くいるのは好きじゃない。
「はい」片倉マネージャーに、この店では「金券」と呼ばれている伝票のバインダを手渡される。テーブル番号を書く欄に「10」と書いてあるのを確認して、10番テーブルへ向かう。何色もの照明が壁やソファを踊るように滑っていく。
「お待たせしましたぁ! 10番シートのお客様よりィ、さつきちゃんご指名です、おめでとォー」
店長の白々しいマイクコールを聞きながら、指名客のヒロ君のとなりに座る。ヒロ君の白いシャツが、ブラックライトに照らされてくっきりと光っている。
「お待たせー。一杯もらっていい?」
ヒロ君が焼酎の水割りを飲みながら頷く。ダメと言われることはないのだけど、あたしはどんな常連さんにも一応お伺いをたてることにしている。
何にしよっかなー、と金券の先を顎に当ててリズムをとりながら、呟く。ウエイターを呼び止めて緑茶ハイを注文すると、ヒロ君が意外そうな顔をした。
「珍しいね」
いつもは最初の一杯は生ビールを飲む。
「ビールはカロリー高いでしょ。昨日ね、三年ぶり会った奴に太ったって言われたの」
「太ってないじゃない」
「三年前はもっと痩せてたんだよ」
ウエイターが緑茶ハイを持ってくる。千五百円の冷たい緑茶だ。
「かんぱーい」と小さくグラスをぶつけると、「それって男?」と聞かれる。
「一応、男」
「何それ」
笑いを含んだ優しい声だけれど、眼鏡の向こうの目はひんやりしたままだ。
「男なんだけど、そういう風に見てないから。幼なじみなんだ。だからお互い男とか女とかなくて。双子みたいな感じ。あ、向こうのほうが二つ上だけど」
十六歳のときに知り合った四月ばかは幼なじみと言えるのだろうか。
「へぇ、仲いいんだ」
「妬いちゃう?」
「ちょっとね」
あたしがわざと棒読みで「えへー」と言うと、ヒロ君は上を向いて大げさに笑った。営業職の男の人にこういう笑い方をする人が多い。
「ヒロ君もいる? し……」親友、と言いかけてやめる。
「すっごい仲いい女友達」
「男だったらいるけど。女友達でそこまで仲いいのはいないな」
「そっかぁ。あたしの周りの子もみんなそう言う。だからね、わかってもらえないんだよねー。すっごい大好きで仲良しなんだけど恋とかじゃないの。でも親友って言葉好きじゃないから使いたくないし、でも友達っていうとニュアンス伝わらないし」
だから四月ばかのことを人に話すときは「幼なじみ」と言うようにしている。
「親友って言葉、嫌いなの?」
「嫌いー。恥ずかしい。安い」
「なるほどね」
ヒロ君は三十六歳のバツイチだ。清潔感があってお金もそこそこ持っていて、もてそうな感じがする。何より聞き上手だ。ついつい、本当に思っていることを喋ってしまう。
嘘だけを喋るよりも、たまに本音を混ぜるほうが、より『さつき』を演じている気分になる。
初めてキャバクラで働いたのは四年前だ。それからもう十軒以上の店を渡り歩いている。
そこが自分にとって「居場所」になってしまうことが怖くて、指名が増えて店に必要とされ始めると逃げ出してしまう。
あたしがいてもいなくてもいい。
それが、あたしの理想の環境だ。
お店を変えた子は普通、前のお店でのお客さんを新しいお店に呼んだりするけれど、あたしはその都度携帯も名前も変えてリセットする。キャラもよりやりやすいように変えていった結果、今の感じに落ち着いている。
始めの頃は本当のことばかり話していた。作家を目指して小説を書いていることも素直に喋ってしまっていた。
今はもう、店では小説を書いていることは言わなくなった。「芥川賞とってデビューできるといいね」などと頓珍漢なことを言われるのにげんなりしたからだ。「芥川賞はその半年間に文學界、文藝、新潮、すばる、群像に掲載された作品の中から選ばれるのであって、すでにデビューしている作家が受賞するものなのだ」というつっこみも、どうせ興味がないだろう。
一番げんなりしたのは、ある若いサラリーマンの相手をしていたときだ。
「作家? すげー。本とか読むの?」と言われ、「当たり前だろ」と思いつつも「読むよ」と応えた。
「誰の読むの?」と聞かれ、あたしが読んでいる作家の中で一番この男でも知っていそうな「村上春樹」と答えたら「誰それ? 頭いい系の本?」と言われた。
村上春樹も知らないなら「誰の読むの?」なんて聞くなよ。一体誰なら知ってるんだよ。
辟易して、それ以来店で小説の話はしなくなった。読書家のヒロ君にだけは作家になりたいことを打ち明けた。
次の話
サポートしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。いただいたお金は生活費の口座に入れます(夢のないこと言ってすみません)。家計に余裕があるときは困ってる人にまわします。サポートじゃなくても、フォローやシェアもめちゃくちゃ嬉しいです。
