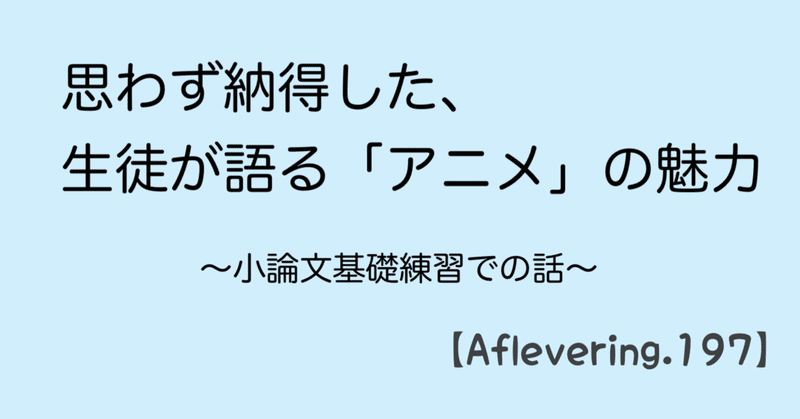
思わず納得した、生徒が語る「アニメ」の魅力(小論文基礎練習での話)【Aflevering.197】
「私たち個人ができる体験は限られています。歴史が教えてくる人間の過去の過ちや悲しい事件を繰り返さないためにも、それを疑似的に体験することはとても大切なことだと思います。」
無知・無関心が最も危険な状態だと言われる社会の中で、私たちは世の中で起こっていることをどれぐらいリアルに感じることができているのでしょうか。また、過去の歴史から学んだことを忘れて新しい過ちをおかしてしまっていないでしょうか。
そんなメッセージを発してくれたのは、私が現在日本語のサポートをしている13歳の生徒です。今日はその授業で話し合った内容について記録しておきたいと思います。
中高生のエッセイ指導
子どもの日本語講師として対象となる子どもの年齢幅は非常に広く、4〜5歳の日本語レッスンに始まり、国際バカロレア(IB DPやMYP13〜16歳)の生徒の日本語学習のサポートもしています。
現在、学習言語が英語の中学生をサポートしており、日本語力の維持やエッセイ、学校の学習補助を行っております。
論理的に考え表現する
日本の学校教育も変わりつつあるようですが、日本の教育を受けている子どもたちは、自分の言葉で説明する機会やそれを文章で表現する活動などがまだまだ足りていないようです。そういった訓練を受けないまま、IBのカリキュラムに入ったりすると求められる力が異なるために、自分でプレゼンをして相手を納得をさせたり、エッセイという形で表現するのに苦労している子がいるようです。
また、日本語が第一言語となる場合、日本語で思考や分析をする力がないと第二・三言語の力にも影響してくるのではないかと思っています。
簡単な基礎練習
新しいスキルを身につける場合は、子どもが答えやすいお題で練習してもらいます。今回は、初めて論理的な文章を書くための初めてのトレーニングでした。「難しい」というイメージをあまり持たせないために、自分の好きなもので論理的に話をする活動に取り組みました。
小論文の最終的な目標は、自分が考えていることを理由や根拠を明確にして読み手に納得してもらえることだと考えています。
しかし、「言うは易し、行うは難し」という言葉があるように、これを実践するには継続的なトレーニングが必要です。そのため、日常の中でも論理的に物事を考える練習をしてもらいます。
初回のテーマ「好きなものを語って、聞き手を納得させよう」
「テーマへの理解・分析」と「表現するスキル」は分けて考える
いきなり環境問題や人権問題などに取りかかっても、スキルが身についていない状態で難しいテーマに取り組んでしまうと、本人が何に引っかかっているのかが分かりにくくなることがあります。スキルが未熟なのか、テーマに対する理解が足りないのか、どちらなのかが分からないと、「自分はエッセイが苦手なんだ」と思い込んでしまうかもしれません。また、初めにそういった苦手意識を持たせてしまうと、それから自分で文章が書けるようになるまで余計に時間がかかってしまいます。
ということで、まずは気持ちよく論理的に考え話をするスキルをつけるため、簡単で楽しめるお題を使って学習を進めてもらいます。
ステップ①まずはたくさんアイデアを出す
最初に行うのは、ただただ思い付いたことを書き上げてもらいます。論理的に考えることが苦手な子どもの特徴として、まずこの発想が全く思い浮かばないということがあります。エッセイを書き上げるまでには、いくつものステップを踏んでいく必要があります。ひとつひとつのステップを学習者に明確にしつつ、一体どのステップで詰まっているのかを理解することができれば、安心して学習に取り組むことができます。
もし、アイデアが出てくるところで止まってしまう場合は、アイデアを出すことをサポートしていきます。具体的なエピソードを思い出してもらって、それを抽象化して言葉にする練習をしていきます。
ステップ②アイデアを少しずつ整理する
アイデアをたくさん出した後は、情報の取捨選択をしてもらいます。初めて文章を読んだ人に「なるほど!」と思わせるために、どの情報が必要でどの情報が必要ないのかを考えるのは難しいことです。つまり、客観的に考えることができるかどうかが鍵になるのです。
ステップ③どんな順番で話すとよいのかを考える
はじめに基本的な型(「問題提起→意見→理由・根拠→結論」特に初めは意見、理由・根拠、結論を重点的に)を伝え、身近な例を使って私が説明しますが、実際にやってみないことには論理的に考え表現する力は付きません。
そのため、先ほど取捨選択したアイデアの順番を並べ替えてもらいます。中には、情報の取捨選択と順番を同時に行う子もいます。無理やり型にはめる必要はないのでそれでも構いません。
基礎練習「大好きなアニメの魅力をどう伝えるか」
「私の好きなものは日本のアニメです。」
その日担当していた生徒は、日本のアニメが大好きだそうです。日本のアニメがなぜ好きなのか、その魅力は何なのかを上手く伝える内容を考えてもらいました。
ステップ①「なぜアニメが好きなのかを考える」
アニメの魅力を人に伝えるためにはどうしたら良いのか、初めは困っていた様子でしたが、自分の好きなアニメをいくつか出しつつ、その共通点を探りながらアニメの魅力について考えてもらいました。
その時、生徒は自分が日頃無意識だった部分にも思考が及んでいき、自分がアニメのどんなところに魅力を感じているのかを客観的に考えることが少しだけできるようになったようでした。
ステップ②「情報を取捨選択する」
ステップ①で出てきた複数のアイデアを、「この話を入れた方が分かってもらえるかな」や「初めて聞く人にはそこまで言っても分からないな」など、相手を想定した情報の取捨選択をしてもらいました。
ステップ③「順番を考える」
最後に、まとめ上げたアイデアをどの順番で伝えると良いのかを考えてもらいました。初めは私が提示した型にはめてまとめてもらいました。その理由は、インターの学校でも同じようなパターンで教えられるケースが多いからです。果たしてその構成で相手が納得できるのかを再度考えてもらい、修正が必要だと感じたところは考えてもらいました。
生徒が出した結論「アニメで心が育つ」
冒頭にも掲載した通り、基礎練習を通してその生徒はとても大切なことに気づくことができました。何気なく好きだと思っていたアニメに対して、「実はこんな魅力がある」ということに改めて気づくことができた。自分の世界観の広がりに喜びを隠しきれない様子でした。
アニメ作品を見ることで疑似的な世界の体験をすることができます。もちろん、アニメの種類にもよりますが、人の命が失われるというのはどういうことなのか、争いが蔓延する世界に住む人々の心はどうなるのか、憎しみの連鎖など、日常で体験してしまうと取り返しのつかないような残酷なことを擬似的に体験して、自分ならそういった問題に対してどう向き合うのかを考えるきっかけを与えてくれます。
また、そういった擬似的な体験という意味であれば、小説や漫画などもあります。それについても、アニメは文字の読み書きのレベルを問わず、見る時のハードルが低く、アニメーションを楽しみながら見ることもできるし、友達と一緒に見てその内容について議論することも楽しめると述べてくれました。
初めての基礎練習でしたが、発想を広げて自分の考えをまとめることができていたので非常に素晴らしい成長だと思い、その事を伝えました。
「できた!」という達成感を大切に
論理的に考え、相手に正確に伝えることは学校内に限らず人生において大切なことです。むしろ、文化や価値観が多様化している時代の中ではこういったスキルは、平和な世界を実現するためにも必要です。
しかし、こういったスキルはすぐに身につくものではなく、継続的な学習によって培われていきます。
今回、生徒は自身の成長を感じることができ、「考える楽しさ」を味わうことができました。自分の成長を感じて喜ばない人なんてほとんどいないでしょう。そういった成長する喜びを感じさせたり、学習に対する不安と向き合う手伝いをすることが講師の役割であり、継続的に学習するために必要なアプローチなんだと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
