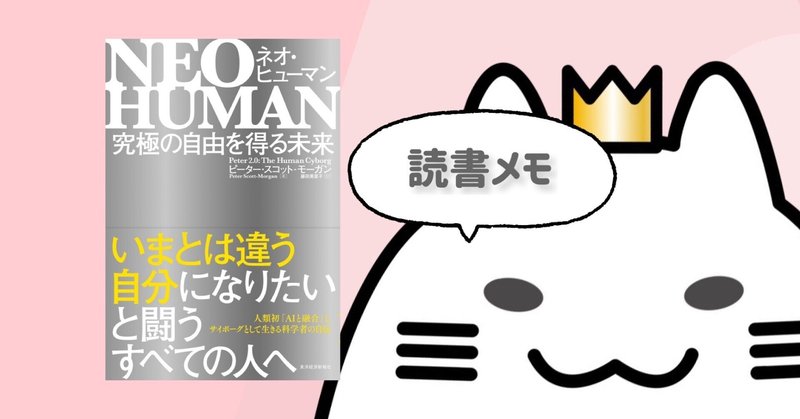
【読書メモ】NEO HUMAN ネオ・ヒューマン: 究極の自由を得る未来
ピーター・スコット・モーガンさんというイギリスの科学者の方のお話です。
難病にかかったもののサイボーグ化することで、声や移動、健康など自由を得た、自由を得ることの大切さを語っています。
Amazonのレビューでは辛口のものも多いのですが、「サイボーグ化」等の技術面よりも彼の人生が叙情的に語られる点が好みを分けるのかなと思いました。
個人的にはノンフィクションとは思えないBL展開に興奮しながら(著者はゲイと公言されていて、長らく連れ添ったパートナーがいます)、技術面はさておき読み終えました。
残念ながら2022年6月に64歳で亡くなられて、そのニュースでこの本を知ったのはさみしい気持ちではありました。
しかし彼が残したものというのは、今エンターテイメントとして楽しまれているVRを一般の人に広めるというよりも、
日常生活が困難な方が困難じゃない状態で暮らせるためのツールとしての可能性を強く伝えたと言えるでしょう。
「僕らは、僕らの人生を取り戻すためにVRを使いたいんだ」
福祉分野はなかなか「豊か」とは程遠い世界と感じます。
著者が難病にかかったことは幸運なことではありませんでしたが、今後多くの方の、もしかしたら自分の、自分の家族や周囲の幸せな人生につながるのではないか?ということを考えました。
とにかく見どころは恋愛
この本が「最後まで読めない」という方も多いと思われますが、「サイボーグ技術」を期待しすぎるとやはり打ちのめされそうです。
この本は恋愛コーナーにあっていいほどの愛に包まれています。
逆に技術面は「ふんふん」と読み飛ばしてしまうくらいに、クライマックスは!どうなるの!!という気持ちでページをめくることになりました。
最高に中二病の作者、人生が完璧なボーイズラブ
著者は科学者ですが、若い頃から芸術分野にも才能がありました。
自らファンタジー性の強い物語を書き、しかも日本でいうところのボーイズラブという点に腐女子としては興味をひかれました。
しかし著者の若い頃というのは、1960年代くらいでしょうか。
ゲイというものが今よりも差別的に思われていた時代ということがわかる学生生活が綴られています。
脱線しますが、イギリスとゲイの話を最近よく見描けるような気がします。
NETFLIXの動画(漫画原作もあります)「Heart Stopper」、NHKドキュランド「11歳、僕はゲイとして生きていく」など。
この本ではイギリスで「シビルパートナーシップ制度」という、男性同士・女性同士のカップルが婚姻関係の男女と同等の権利が得られるようになった歴史的な法改正のことも書かれています。(彼らが結婚したため)
本当にまだまだ無知なことが多いのですが、教会、聖職者、エスタブリッシュメント(特権階級)このあたりの方々が特にゲイを迫害してきたということが伝わりました。
日本だと差別や無理解はもちろんあるんですが、イギリスの場合とは大きく違いそうだと理解できてきました。
(脱線の脱線ですが日本だとBLとして長らくエンタメ消費してる感じが私の中では最近モヤモヤしています)
話は戻りますが、著者が伴侶として添い遂げることになるフランシスという方がいます。
その出会いから著者が最後の声を出すその瞬間まで、なかなかありえんほどのドラマティックさ!!!!
いやいやこんなの創作でしょ!!!!
と思わず言いたくなるほど、完璧に理想のボーイズラブ。
これはバカにしてるんじゃなくて、本当に、マジで、これが現実に起きた話だったら、創作が色褪せる。
いや、創作は創作で魅力的なのですが、
ノンフィクションでこんな話ある?????と驚きと、もちろん彼らが出会うべくして出会い、互いに尊重し協力して長年過ごしたと思いをはせ涙が出ました。
サイボーグ化が医療・福祉分野に広がる可能性は
本にもありますが、ALS(MND)をわずらってさまざまな治療・肉体へ技術を施すことで莫大なお金がかかったことが書いてあります。
よく、車いすを自分の体に合うようににオーダーするだけで時間もお金もかかるという話も現実に聞きます。
著者も企業や大学などと協力しながらサイボーグ化を進めていましたが、はしごを外されるようなショックな出来事もありました。
そこでスコット-モーガン基金というチャリティー団体を作ります。信頼できる理事を据え、以下のような言葉を財団設立の際のミーティングで伝えています。
言うまでもなく、この財団は今現在、障害に立ち向かう手段を1つも持たない人にとって希望の道しるべとなるでしょう。
今後さまざまな分野で研究の成果があらわれるのではないかと期待しています。
繁栄する権利
これからは、私のような人々が本当の意味で繁栄するための方法を探究するのだ・・・。
繁栄、という言葉が最近身近に感じたのは
台湾のデジタル担当総務委員のオードリー・タンさんが「長寿と繁栄」とハンドサインをしていたからでした。
(「長寿と繁栄」とハンドサインはスター・トレックというドラマの中で出てくるようです)
繁栄、という言葉を耳にすると、「子どもを残す」ような「人そのもの」が増えることをイメージしていました。
人が生きる、生きているということも繁栄なのだなというイメージができました。
生きる、というと自分のことだけのように感じます。
そこで繁栄と言うと世界とつながるような、広がりが出るような気がします。
今の時代、
生産性が高い、労働力として大いにプラスになる人が評価されてしかるべき、
(特別な理由があってもなくても)働かざる者食うべからず的な論調が強いといいますか、
生きるのに何らかの理由や能力が必要なのでは?という気持ちにさせられるような論調というのか、窮屈な気持ちになることが多いです。
生き物ってそんなことなくて、生きられれば生きるし、死んだら死ぬくらいのラフな存在だと思うのですが、
考えること、周りとバランスを取ることが逆に命取りになってる感じというのでしょうか。
結構しんどいなって思います。
この本も著者の栄光がつづられているので「おいおい、私こんな人生の戦い方できないよ!」という気持ちもありますが、
著者が人生の中で度々無力感を感じている部分と、愛を重視した情緒的な部分がなかなかいい感じに「私もがんばろ!繁栄しよ!」って思えました。
とにかく「厚くて読みきれるかな?」という不安は消えて、小説のように楽しめる本でした。
科学の本というより、めちゃめちゃいい恋愛小説です!
創作のための消耗品や本の購入をします。ご協力お願いしますm(_ _)m
