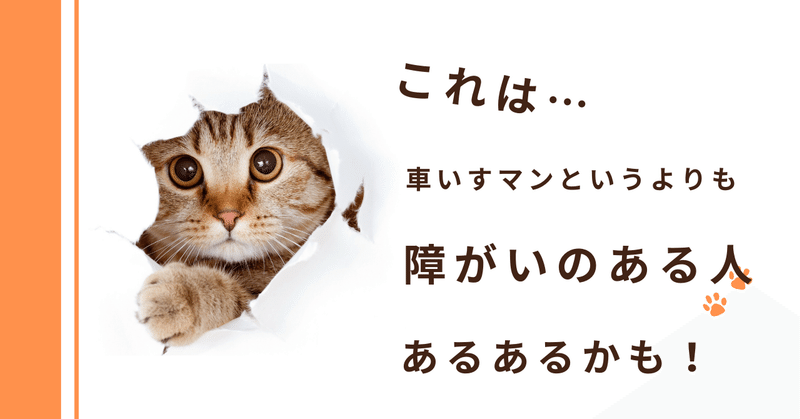
障がいのある人(障がいを持ったら)って、みんな仲間?一緒?仲良し?和気あいあい?じゃなきゃダメですか~ひとまとめにしていいのかな?
今回の記事は、関係者が読んだら激怒するのかもしれないのですが…
以前、以下の記事を書いたことがあります。
読んだ人はどのように感じましたか?
・苦労したんだな~
・よく頑張った!
・感動した!
・大変な思いだったろうな…
・そもそも、ひねくれた考えだったお前が悪いだけ!
・どこの世界でも同じようなことはある、大げさだ!
・もっと良い方法があるぞ!
・要領が悪い、だから時間がかかったんだ!
以上のようなことではないかと予想しています。
それでは、こんなふうに感じた人はいませんか?
へ~障がいのある人の世界って、それまで生きていた通りでは受け入れられないのかな?だったら、生きづらさそうで嫌だな…
僕の経験から書かせてもらいますが、障がいのある人の世界?(特に他人と共に生活をしたり、同じ場所にいる場合)は、「にこにこ笑顔・交わり・ふれあい・和気調々・仲間・協力・共存・真面日は悪・群れなければ…」といったようなニュアンス?が結構あるように思います。
ですから、「中途であれば、健常なときにも負担なくそのような生き方をしていた」・「生まれつきであれば、そのような事を好む性格である」のであれば何も問題がないのかもしれませんが、その逆であったなら、かなり生きづらさを感じるのかなと思います。
たとえば…
全国的な調査で、入浴や会話、昼食や日中に家を離れる目的などで、障害者デイサービスセンターを利用している在宅で暮らす障がいのある人で、本心では行きたくないという人が若干名いるようです。
それは、全国どこの障害者デイサービスセンターも似たような特色であることと、以下のような人間性?性格?生き方?の人がいるからではないかと思います。
・人がいる場所よりも、一人でいた方が気楽
・会話をするより、テレビやパソコンの画面を見ていた方が楽しい
・レクリエーション活動を無理矢理させられるより、家でゲームをしていた方が良い
・読書ばかりしてきた私は、場の空気が合わない
(やかましい?)
・ずっと国会議員を務めてきた自分には、場の空気が合わない
(低レベル?)
・暴力団に長くいた俺には、場の空気が合わない
(みんな仲良く平和に和気調々など、くそったれだと思う?)
・利用者の年齢層が高くて(低くて)話が合わないから行ってもつまらない
・そもそも人が嫌いだから、場にいることが苦痛
障害者デイサービスセンターの特色がどこも似通っているのは、万人受け狙い(運営資金確保目的?)もあるでしょうから、ある程度は仕方がないのはわかります。ただ、障がいのある人を「ひとまとめにしてしまっている印象」があるように思えて仕方がありません。
障がいがあれば、これまでの生き方や考え方・性格など関係ない…
みんなひっくるめて、集めてしまえばいい。
食事や入浴が出来るのだから、それで良いじゃないか?
…
そうでしょうか?
障がいのある当人が嫌で行きたくなくても、家庭の事情でどうしても日中家を出なければならない・入浴をどこかでお願いしなければならないことも多いと思います。
それならなおさら、行き場?を選べるようなアイデア(デイサービスの内容?)はないのでしょうか?
たとえ障がいがあっても、自分の思いを尊重できる?選択できる?事柄が、今よりどんどん増えていけば、今回のような問題は減ってくるのではないかなと思うんです。
…
すいません、生意気に書いてしまいました。
そんなことわかっているけど、なかなかうまくいかないのかもしれませんね…
…
何かよくわからない記事になってしまいましたが…障がいあるなし、生きづらさを感じることがないような社会を望んでいます!
あっ…そうだ!
最後になりますが、「車いすマンあるある」なのかもしれない2つの記事をこれまで書いていますが、今回の件は車いすマンだけではなくて、障がいのある人全般に言える「あるある」なのかもしれません。
いかがでしたか?
読んだよ〜ってことで、スキを押してもらえたら、今後書いていく励みになりそうな気がします。
できましたら、これからもたくさん手紙を送りますので、どうか目を通してほしいです。
サイトマップまでいかないかもですが…趣向が似た記事を集めた各マガジンの紹介をします。(クリックしてください)
覗き方?の参考になればうれしいです!
伝えたいメッセージをみなさんへ~😊
※あと、いつもスキを押してくれたり、フォローしてくれたり、コメントを頂けるので光栄で励みに思っています。感謝です!これからもたくさん記事を書きたいです✨
僕が書くすべての記事(手紙)は、長い時間かけて継続して書いてきた記録や、そうでなかれば得られないであろう考え方や貴重な体験を基にしています。いただいたサポートは、その評価だと捉えさせていただき、それを糧に今後も多くの記事を書いていきますので、どうかよろしくお願いします。
