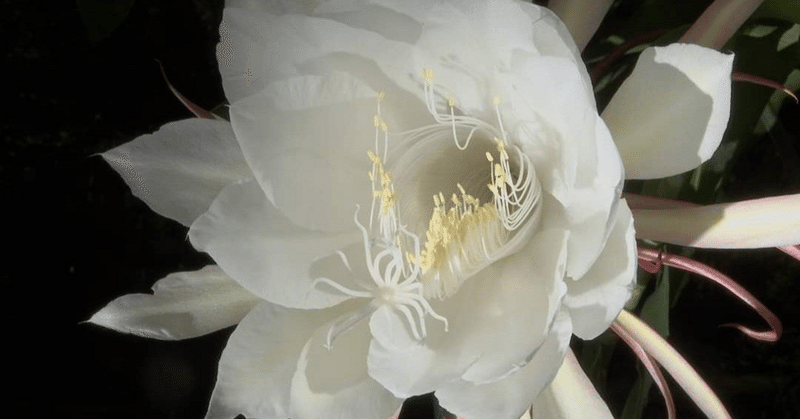
第四十二話
「まったく、なんで私があんたみたいなヤブ医者と一緒にいなきゃいけないんだか。もう手当が終わったならとっとと帰ればいいだろ」
「誰がヤブ医者だよ!」
「あんたに決まってるだろ?先代は名医だったが、後継が放蕩息子のあんたじゃ先が思いやられる」
「いつの話してんだ?俺はもう心を入れ替えて立派な医者やってんだよ」
「人間の本性なんてのはどんなに取り繕っても変わりゃしないさ。心入れ替えたんじゃなくて、結局家業継ぐのが一番楽だと気づいて親に泣きついただけだろ?」
「おまえなあ!」
先程まで目の前にいたはずの小春の姿が消えうせ、頭上から男女の諍う声が聞こえる。真っ暗な視界を払うように目を開くと、声の先に、佐知と公孝の姿があった。
「源さん!」
「源一郎!」
二人は源一郎が目覚めたことに気づくと、弾んだ声をあげたが、すぐ心配そうに顔を歪める。一瞬、二人の表情の意味がわからなかった源一郎は、自分の目から涙が溢れていることに気づき慌てて涙を拭った。
「大丈夫か?」
公孝の声に、肉親を気遣うような優しさがこめられているのは、職は違えど、二人が特殊な環境で育ってきた幼馴染であるがゆえであろう。公孝は、玉楼が昔から世話になっている、堕胎を専門とした中条流の医者だ。
若い頃は親の脛齧りの遊び人で、佐知が遊女だった頃も一悶着あったらしいが、昔から兄貴風をふかせては、源一郎を弟のように可愛がり、ありとあらゆる遊びを教えてくれた。源一郎にとって憎めない、気心の知れた大切な友人なのだ。
「まったく無茶しやがって、傷は思ったより浅かったが、おまえ最近ちゃんと飯食ってたか?遊女の自殺止めようとして、自分が刺されてぶっ倒れるって、そんな間抜けでひ弱なこっちゃこれから楼主としてやってけないぞ」
目覚めたばかりでぼんやりとしていた思考が、公孝の言葉で全てを思い出し血の気が引く。
「お凛は!母さんは!」
源一郎の切羽詰まった声に答えたのは佐知だった。
「折檻部屋です」
源一郎はすぐさま立ち上がり向かおうとしたが、身体を起こした途端ひどい目眩におそわれ、再び布団の上に座りこんでしまう。
「何やってんだよおまえは!今日は一日しっかり休んでろ!」
「休んでる場合じゃない!」
珍しく声を荒げ反論する源一郎を、公孝は面食らったように見つめる。
「んだよ、こっちは心配して言ってやってるのに、どうしたんだおまえ?」
「どうしたもこうしたもない!早くしない
とお凛が殺されちまう!」
源一郎の叫びに、公孝が辛そうな表情で答えた。
「まあ…確かにあのお吉さんの怒りようじゃありえるかもしれないな。逃げ出しただけならまだしも、おまえに怪我までさせちまったから…」
「だからいっそのこと、自死させてやった方がよかったんですよ」
公孝が全て言い終わらぬうちにそう言い放った佐知を、源一郎は驚愕し尋ねる。
「…おまえまさか、わざとお凛がどこにいるか答えなかったのか?」
「源さんは、忘八の折檻が実際どんなものか見たことないでしょ?胡蝶が足抜けした時、家出してましたからね」
源一郎の疑問を肯定するように、佐知は語りはじめた。
「あの日、胡蝶は見せしめのように、私らの前で折檻されました。硬い竹篦で、血飛沫がとび失神するほど何度も何度も叩かれて、最後は忘八達に乱暴に姦される。あれを見せられてから、玉楼の女達が足抜けすることはほとんどなくなりましたよ。お凛だって、あんな目にあって苦しみ抜いて死ぬよりも、自ら死ねた方がきっとよかった。中途半端な優しさは、かえって女を苦しめるだけです」
『なんで!なんで死なせてくれないの!』
佐知の言葉は、憎々しげに自分を睨みつけてきたお凛の形相と叫びを思いおこさせ、源一郎は、五臓六腑が壊死していくような苦痛と罪悪感に見舞われる。
「おい、いくらなんでもその言い方はないだろ!大体胡蝶は、そんな目にあってもちゃんとここの座敷持ちにまでなったじゃねえか!最後は心中しちまったが、生きてたからこそ、本気で好いた男と出会えたんだろう」
源一郎を庇う公孝を、佐知は冷めた瞳で見やり答える。
「胡蝶の時は歯止めになる楼主がまだ元気だったからね。でも、今や女将さんを止められる人間はだれもいない。あれだけの折檻受けて生き抜けたのは、胡蝶が並の女じゃなかったからだよ。いや、あの胡蝶だって、高野屋の御隠居様がいなかったら、河岸の切見世でのたれ死ぬだけだったかもしれない」
居た堪れない思いで深く項垂れていた源一郎だったが、突然閃くように顔を上げ、佐知に命じた。
「……佐知!今すぐ筆と紙を持ってきてくれ!早く!」
怪訝そうな佐知を急かしながら、今度は公孝に土下座して頼みこむ。
「公ちゃん頼む!今から書く俺の手紙を高野屋の御隠居様に届けて欲しい!多分今日なら中見世の松葉屋にいるはずだ!」
「え?突然どうした?俺だってそんな暇じゃ…」
「頼む!一生のお願いだ!これから先公ちゃんの言うことなんでも聞くから!なんなら今度うちでただで遊んでもらってもいい!頼む!この通りだ!」
少しの間考えあぐねていた公孝も、必死な源一郎の姿に絆されたのか、渋々ではあるものの、そこまで言うならと首を縦にふってくれた。
「いいんですか?そんな約束をして?」
丁度手紙を書く道具一式を持ってきた佐知が不服そうに尋ねてきたが、源一郎はいいんだと深く頷く。
(もう二度と、後悔はしたくない…)
身体を引き摺るように文机に向かい、用意された筆を握りしめた源一郎は、祈るように言葉を綴る。たとえ一か八かの賭けであっても、これ以上何もせず、ただ見ているだけの人間ではいたくなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
