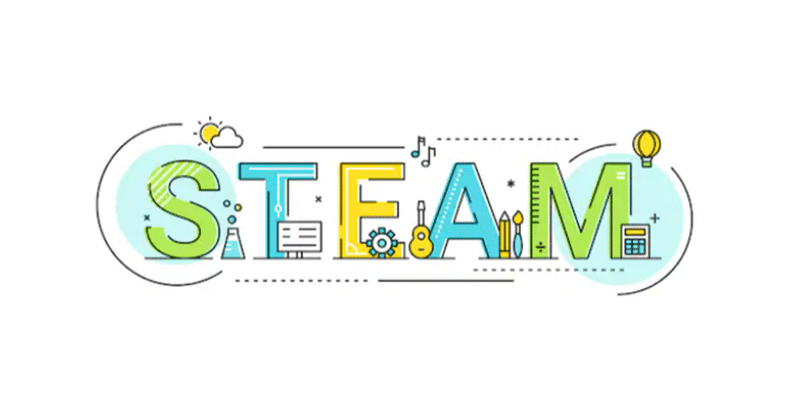
STEAM教育?なんだそれ
STEAM教育という言葉、小学校教員はどれぐらい知っているんだろう。私は半年前まで知らなかった。
学校で働いていれば、教育全般の情報はある程度入ってくる。学習指導要領が変わること、英語やプログラミングが必修になること、道徳が教科になることなど。教育に関するニュースも興味がないわけではない。
でもSTEAM教育という言葉は、全く知らなかった。
STEAM教育との出会い
私が知ったのは2月に行った筑波大附属小の研究会の初日。筑波小では「STEM+総合活動」と呼び、その研究会で授業公開と協議会が行われていた。その日、見たい授業のなかった私は、なんとなくそこに参加した…というのがSTEAM教育との出会いだった。
※ STEAM教育とは
【S】…Science(科学)
【T】…Technology(技術)
【E】…Engineering(工学)
【A】…Arts(芸術)
【M】…Mathematics(数学)
の頭文字から構成されている。当初【A】はなく「STEM教育」(=理数系重視の考え)だったが、近年芸術要素の重要さが着目され【A】が加わった。
筑波の研修会では、
・東北大学教授の堀田龍也氏(プログラミング教育推進の中心人物)
・放送大学教授の中川一史氏(日本STEM教育学会副会長)
の話を聞くことができた。
そのときの記録を私は次のように残している。
STEMについて全く知らずに参加したのだが、分かったのは次のこと。
①近年注目されている教育観であること
②筑波小の行っているSTEM教育の目標は「イノベーションを作り出す力を育てるために、子どもが決めた課題解決を通して、科学・技術・数学・芸術に関わる内容を横断的・発展的に学習すること」としていた。
③なぜ「STEM教育」なのかを考える際、根本にあるのは社会の課題(超高齢化、生産人口や自治体の減少など)である。それに対応するために「個々の生産性を上げる」「未来を描く力をつける」ことが必要であり、そのためのSTEMである。具体的には、タブレットなどの情報機器を使いこなし、情報モラルも持ち合わせていること、もう一つは今の課題解決のために「こういう作業が必要」で「ここからはAIに任せてもいいね」と判断できる力を身に着ける必要がある。
※今読むと、貴重な話を聞けてたんだなと思う(この2か月後プログラミング教育に深く関わるなんて考えもしなかったけど、不思議な縁を感じる)。。。STEM教育とプログラミング教育のつながりを初めて知った研修会だった。
STEAM教育とプログラミング教育のつながり
堀田先生の話を整理すると
「社会の課題」を解決する力をつけるために「未来を描く力」をつけ、それを実現するために「コンピューターに任せる部分と人がするべき部分を考えられるようにする」。そのためにプログラミング教育をしていく、ということ。これ「プログラミング教育で創造する力を身に着ける」と考えているしくみデザイン代表の俊介さんと考え方の根幹は同じだ。
私は運よく筑波の研修会に参加したから、そして今企業研修を受けているからこそ「プログラミング教育」と「STEAM教育」のつながりやその大切さが分かるけれど、学校現場ではそんなこと言われなかった。
学校現場でのプログラミング教育の意味とは
学校で言われるのは、「Socity5.0」。
情報化社会だ→子どもがコンピューターに詳しくあるべきだ→だからプログラミング教育だ。という流れ。
こう捉えていたら「臨時休校で授業時数が足りないのに、プログラミング教育なんてしている暇ない!」って考えに至るよなぁって思う。
本当はコロナで世の中が大変になっているからこそ「未来を描ける力」を身に着けられるようにしなきゃいけない。子どもの将来を考えてプログラミング教育やろう!…っていうのが筋なんだろうけど。
でも学校の「やらなきゃいけないこと」も分かる…。既定の授業を終わらせないといけない、学力テストもある、保護者の要望もある。現場からしたら「STEAM教育?なんだそれ」って感じなのかもなぁ。
「プログラミング教育」について学校に伝える場合、ここも絡めた情報発信が必要…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
