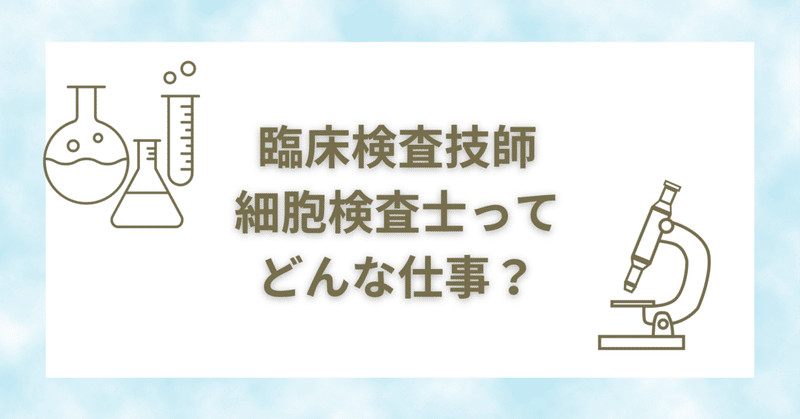
臨床検査技師、細胞検査士ってどんな仕事?
私、大事なことを忘れていました。
“『臨床検査技師』とか『細胞検査士』とか書いてるけど、朝活サロンで知り合った方は『臨床検査技師』も『細胞検査士』も知らない人の方が多いじゃん!!!!”
自分のTwitterに医療系の方が多すぎて忘れてました…(汗)
ということなので、私がやっていたお仕事について書いていきます。
臨床検査技師
臨床検査技師とは病院などで血液や尿の検査をしたり、心電図やエコーをとったりする人です。
採血をすることもあります。
健康診断などでとった血液を調べているのが、臨床検査技師です。

基本は検査室の中にいるので、みなさんと関わる機会はあまりありません。
採血や心電図、エコーをとっている技師さんは患者さんと関わることが多いです。
ちなみに、養成所を出てからの私は5年間ずっと採血に関わってきました。
他の検査にも携わってきましたが、採血をしていることが圧倒的に多かったです。
採血ならお任せください(笑)
臨床検査技師になった後、実はたくさんの認定資格がとれます。
認定資格をもっていると、その検査のスペシャリストになれます。
エコー検査のプロである"超音波技師"や、がんの細胞を見極める“細胞検査士”など…。
私も緊張検査士という資格をとろうと思って勉強していたんですが、去年体調を崩してあえなく直前で受験を断念しました…(泣)
他にもとりたい認定資格がたくさんありましたが、なかなか就職が難しくて…。
誰か雇ってくださーーーーーーーーい‼︎‼︎‼︎‼︎‼︎
よく働きますよーーーーーーーーー‼︎‼︎‼︎‼︎‼︎
なんて叫びたいです(笑)
細胞検査士
ここからが私の本気の見せどころです(笑)
熱量を入れて書きます(笑)
この資格、臨床検査技師がとれる認定資格の中でも難関の一つです。
合格率は25%くらいです。
(一次試験で半分、二次試験で半分が不合格だそうです)
私は専門学校を卒業してすぐに養成所に入って細胞検査士の資格をとりました。
簡単に説明すると、「がんの細胞を見つける」という仕事です。
「えっ…?何それ…?」ってなりますのね(笑)
もう少し詳しく説明します。
ヒトの身体の一部を採取して標本にして、それを顕微鏡で見て「がんの細胞はあるのか?ないのか?」を"形態学的"に調べるのが、細胞検査士の仕事です。
この仕事のポイントは、"形態学的"にです。
「形態学」は、生物の構造や特徴を肉眼的に見ていきます。
「えっ…?細胞を見るだけで何が分かるの…?」
「細胞ってどれも同じじゃないの…?」
そんな声が聞こえてきそうですが、私達が勉強している理由がしっかりあります。
人体にはたくさんの組織、細胞があります。
それらはすべて同じ顔、形をしているわけではありません。
一つ一つの正常な細胞を見極めて、異常な細胞やがん細胞を見つける…。
簡単そうに思えて、これが難しいんです。
大人しそうな顔のがんや、悪そうな顔の良性の腫瘍。
(※細胞の見た目を"顔つき"と私は言っています)
まるで人間のようにそれぞれ個性があります。
それを見極めなくてはなりません。
しかも、ただ細胞を見ているだけではいけません。
何故がんが発生するのか、どういった治療がなされるのか。
細胞検査士はそういった知識も必要になります。
自分の決断がヒトの人生を左右してしまうかもしれない。
そんなお仕事であると、私は思っています。
養成所時代に講師の先生が
「細胞検査士は、内科の専門医よりも知識が必要」
と仰っていました。
これはどの検査にも当てはまりますが、細胞検査士は必要になる知識が多いと思います。
難しい試験も、結局全ては患者さんのためになるからだと私は考えます。
時には胸が痛くなる判断も必要です。
だからこそ、一生懸命勉強していく資格だと感じます。
ざっくりと説明させていただきました。
いかかでしたか?
「世の中、こんな資格があるんだ〜」
って思っていただけたら嬉しいです。
またお会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
