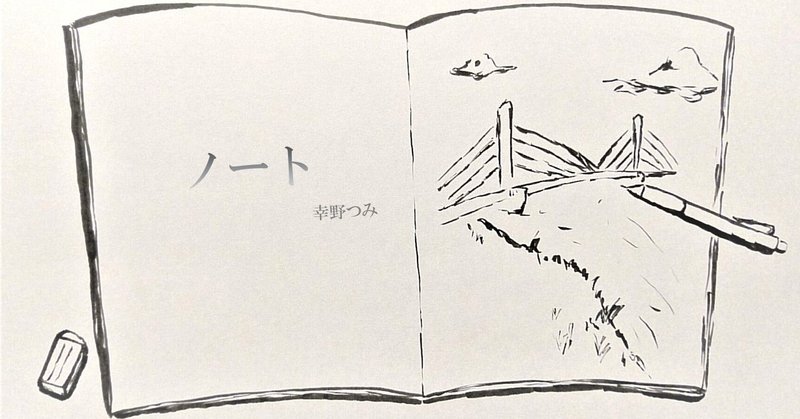
【短編】ノート【幸野つみ企画】【お題小説】
お題小説企画「ノート」
幸野つみ自身が提案したお題小説企画の自分の作品です。
お題は「ノート」。
今回僕以外に2人、同じお題で短編小説を書いていただいており、本日7月1日に公開していただく予定です。
ぜひ読み比べてお楽しみください!
喜多 漠路@ちょんぱんきんたんさん↓
アセアンそよかぜさん↓
スキやコメントお待ちしています!
また、noteはもちろん、twitter等で拡散していただけると嬉しいです!
小説について
「ノート」というお題ですが、そのまま「ノート」という題名にしました。
北海道旭川市が舞台の物語です。
noteを利用するクリエイターの皆さんの心に響く作品だと思います。
約9000字なので、本でいうと十数ページ程度だと思います。
10分程度で読み終わると思いますのでぜひぜひお気軽に読んでみてください!
あらすじ
「自分探しの旅に出よう、本当の自分は遠くにいる……」
過労による体調不良で仕事を休み、実家のある北海道旭川市に帰ってきた青年。
仕事復帰を目指して先輩から薦められた自己啓発本を読もうとするが……
ここから本編です
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
ノート
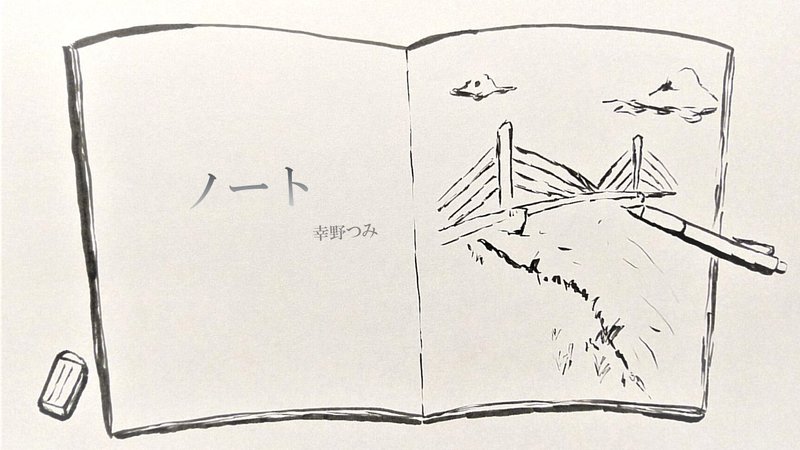
1/6
『自分探しの旅に出よう 本当の自分は遠くにいる』
吹き付ける柔らかな風に押されるままに本を閉じ、改めて表紙に目をやってタイトルを口に出してみたが、わがままな風がもう一度びゅうと音を立てて僕の声を掻き消した。
顔を上げるとみなもに反射した日差しが眩しかった。
目の前には大きな川が流れている。河川敷は広く整備され緑が鮮やかだ。川上に目を向けると巨大な橋が架かっている。ツインハープ橋と呼ばれるそれは、旭川のシンボル的な存在で、大きな橋を支えるために太い二本の支柱からいくつものケーブルが走っており、その名の通り二つのハープのように見える。そう考えると、橋の下から流れてくる川は、ハープが奏でる優しいメロディのように思えた。
川を見ていると落ち着く。
僕の故郷旭川は、「川の町」と呼ばれている。今目の前を流れている忠別川(チュウベツガワ)の他に、美瑛川、牛朱別川(ウシュベツガワ)、その他たくさんの小さな川が次々に合流を繰り返し、最後には石狩川へと流れ込み、遠く札幌の方まで続く大河を形成する。恐らく、この町が巨大な盆地に位置しているため河川が集まるのだろう。
家から学校へ向かう際も毎日毎日大きな川を越えて向かっていた。自転車通学の際には大きな橋を渡るのが大変だったことを僕はぼんやりと思い出した。
匂いや水の音が懐かしく、絶えることのない水の動きは飽きずに見ていることができた。ごちゃごちゃだった頭の中のあれこれを一緒くたにして流していってくれる気がした。
立ち上がってお尻を軽く払う。伸びをすると肩に痛みが走る。しかし、数日前までは筋肉が凝り固まり電撃が走るような鋭い痛みだったが、今の痛みは筋肉痛に似ている気がする。強烈な凝りが徐々に解れてきている過程に生じる痛みなのかもしれない。あるいは、これから翼がこれから生えてくる予兆なのかもしれない、と考えて小さく笑った。
リュックサックに本を放り込む。しばらくここにいたはずだが、読まなければ、と思っている本さえ大して読み進めていない。それは、なんてのんびりとした時間の使い方なのだろう。何かに追われるような気分は決してゼロになったとは言えないが、実家に戻ってきてからようやく肩の力が抜けた気がする。こんな気分は一体いつ振りだろうか。こんな風に川を眺めるのはいつ以来だろうか。
何となく自分の両の手を見つめる。傷痕がいくつか残っている。細い左手首には銀色の腕時計が不恰好にぶら下がっている。
そろそろ昼食の時間か。
僕は堤防の上へと向かい家路についた。
2/6
「あ、箸ないね、箸、箸」
母が慌ただしくキッチンへ走っていく。
「あ、スプーンがいいか。ねえ、どっちがいい?」
目の前のダイニングテーブルでは山盛りのチャーハンが一皿、湯気を立てている。
「……どっちでも」
「じゃあスプーンの方が食べやすいしょ、ね」
僕が答えを言い切らないうちに母はスプーンを持ってくる。
「私、午後は買い物行ってくるからね」
母は再びキッチンに消える。
いただきますは小さく呟くだけにして、食べ始める。
「あんた午後一人になっちゃうけど暇しないのかい?」
キッチンの中からでも母の声はよく通る。
「暇って……」
散々一人暮らしをしてきた息子をまだ子供扱いするのか。そもそも主治医や上司からは何もしないでゆっくり休めと言われている。
「……まぁ、本でも読んでるから大丈夫だよ」
「あー、その本? こっち帰ってきてからずっと持ち歩いてるねぇ」
母は持ってきた味噌汁をテーブルの上に置き、代わりに僕の傍らから本を持ち上げしげしげと観察した。
「この表紙の人、知ってるよ。たまにテレビ出てるもね」
チャーハンを咀嚼しながら表紙に目をやる。
青空に続いていく一本道を背景に、一人の男性の胸から上が写っている。白いTシャツにジージャン。大きな帽子。顎に手を当てて微笑みながらこちらを見ている。
「有名なのかい? この人」
「……有名らしいよ?」
「流行ってんのかい? この本」
「……流行ってるらしいよ」
母はふうんと言って本を僕に押し付け、再度キッチンへと戻り冷蔵庫をあさった。
「なしてあんたこんな本読もうと思ったのさ」
冷蔵庫の中に向かって話し掛ける母の声もよく通る。
「こんな本って……」
「あんた昔から小説は好きで読んでたけど、あんまりこういった説教くさい本は、お父さんが買ってきてあげたって読まなかったしょ」
母はキムチが入ったタッパーを持った手で器用にこちらを指さした。
「……そんなことない、と思うけど……」
言いながら、そういえばそうかもしれない、と思う。
母はすごい。何も考えずに好き勝手に喋っているようでいて、急に相手の核心を突くようなことを言ったりする。いつもドタバタと忙しなく周りなんて見えていないようでいて、息子である僕のことは何でも見透かしている。何だか腹立たしくもあり、しかし、すごい、と思う。
僕は目の前に置かれたキムチを眺めながら、言葉の続きを考えた。
「……あっち出発する前に、大学の先輩に薦められたんだよ。『そういう時はこういう本を読め』って」
「お母さんもたまに旅したいなぁ」
「……」
他人の話を聞いているのだろうか。やはり周りのことなんて気にせず好き勝手に話しているように思える。マイペースにまたキッチンへと引き返していく母を見て、僕はスプーンを置き腕組みをした。
「旅ね……母さんはさ、旅に行けるとしたら、どこに行くの?」
「えー、迷っちゃうな、やっぱり恵山かな!」
母は迷わずに答え、とうもろこしの盛られた皿を持ってきた。
「エサン……? ていうと……」
「そうよー、お母さんのふるさと!」
満面の笑み。両手を広げる謎のジェスチャー。危なっかしいから皿を早くテーブルに置いてほしい。
恵山は、北海道の道南地方にある。現在は函館市に吸収合併された、と以前母から聞いた気がする。
「せっかくの旅なのに、ふるさとに帰るの?」
「だって。しばらく帰ってないんだもん。久し振りにあの海が見たいの」
母はテーブルに皿を置くとすぐにきびすを返した。とうもろこしは茹でたてのようで視界に湯気が漂った。
「海だったら……例えば……南の島とかさ」
背中に声を掛けると、母は振り返って大袈裟に首を振った。
「そうじゃなくて! 私が、楽しい時も、辛い時も、毎日毎日見ていたふるさとのあの海が見たいの!」
「……ふるさとね……でもそれじゃあ……」
僕は、ぼんやりとしながら、昨日余った餃子が運ばれてくるのを見ていた。
でもそれじゃあこの本の意図とは正反対ではないか、と思った。
僕もそこまでこの本を読み進めた訳ではないからわからないが、題名にある「遠く」とは、例えば海外を指しているのではないだろうか。距離的な意味だけではなく、自分とは遠い存在である、異文化が溢れる場所を指しているのではないだろうか。それに対して自分が生まれ育った故郷というのは、真逆の存在に思えた。
「……でもそれじゃあ……自分探しにはなんないね」
「そう?」
「……え?」
「自分が生きていた場所なんだから、探せばきっと自分がいるしょ」
窓際に吊り下げられた風鈴が、りん、と一度鳴った。子供の頃から聞いていた、懐かしい音だった。
「なんていうんだべ、原風景ってやつ? 私にとっては海と、火山の岩肌と、落ち着いた街並みと、港と船が、心の一番奥底にある風景。転んだ場所も、怪我した場所も、全部あそこだ。あそこで見たものだとか聞いた言葉、小さい町だけど活気のある感じ、悪く言えば大雑把で良く言えばおおらかな人達……あれが私を形作ってるんでないかな」
僕は母の顔を見つめた。
「あんたにとっては、ここ、旭川ね」
母はうふふと笑った。
本当に、母の発言はいちいち僕の心を揺さぶるから、困る。
僕は再びスプーンを手に取り、チャーハンを頬張った。
「あんた今日の午後暇なら、自分の部屋ちょっと整理してよ。教科書とかノートとか、段ボールに入れてそのまま取っておいてあるから、要らないんだったら捨てちゃって」
「……だから暇っていうか……ていうか……母さん」
僕はこちらに近付いてくる母を睨んだ。
「……昼間からこんなに食べられない」
母の右手にはカットされたスイカが、左手にはヨーグルトの入った器があった。
「えーこれくらい食べられるしょ」
やはり、何も考えていないのだろうか。
3/6
働き過ぎ、と言われたが、よくわからなかった。自分と同じように、あるいは自分以上に働いている同期や上司がいることは噂で聞いていたから、胸を張って僕は働き過ぎですと言うことはできなかった。
今思えば、会社から「休め」と言われてから実家へ帰るまでの約一週間、僕は結局休んではいなかったように思う。
久し振りに自炊したものが食べたいと思いカレーを作った。せっかくもらった時間を有効に使うために、できていなかった部屋やトイレやお風呂の掃除を済ませ、床の上に積み上げられていた書類の山を整理した。始めると止まらなくなって珍しくコンロやベランダまでも掃除した。夜になると溜まっていたテレビ番組の録画を消化し、買ったあと放置していた漫画を読んだ。変な噂が広まる前に自分から知人へ近況を知らせようと思い、たくさんのメールを書いては送った。早く元気になって会社へ戻らなければと思い、できる限りのことをしようと考えた。インターネットでメンタルヘルスについて検索し、肉を食べればよくなると知れば肉を買いに行って食べた。ブルーライトカットの眼鏡でいつも視界が薄暗いのも気分が落ち込む原因の一つではないかと思い付くとすぐ、眼鏡を新調しに向かった。
旭川の実家へ戻ってからはガソリンが切れたように眠り続けたが、それまではブレーキの利かなくなった車のように、ひたすら行動して、行動して、行動した。
その行動の一つが、先輩と会うことだった。
大学時代にサークルでお世話になった、活動的な先輩。彼が大学を卒業してしばらくしたあと精神的不調により仕事を休んでいるという話を聞き、まさかあの人に限ってそんなことがあるなんてと在学生の間で噂した。その約一年後、先輩はサークルに顔を出し、復職、そして転職したことを笑顔で皆に話した。
僕が休んでから連絡した人の一人が、先輩だった。すぐに「こんな時こそ俺の出番だな!」と冗談めかした返事が返ってきて、先輩は僕をご飯へと誘った。
憧れの先輩だったし、同じような経験をした人の話はきっとためになるはずだと思い、僕は先輩の誘いに応じた。
「俺はね、カンボジアに行ったんだ」
先輩は日本酒を片手にそう言った。先輩の行きつけだという店の個室で、卓を挟んで先輩と向かい合って座った。
「カンボジア、ですか」
「そう。学生時代も色々海外巡ったけど、次に行くならカンボジアだなと思ってたんだ。時間もバカみたいにあったし。人生観変わるかなとか思って」
先輩は笑ってお猪口に口を付けた。
「いいですね」
僕は頷いてウーロン茶を飲んだ。
「いやまぁ、人生観変わるってのは大袈裟だけど。そういう時ってどうしても家に籠りがちになっちゃうからさ、なるべく積極的に外の世界に出るのが大事なんだよ」
先輩はそう言って刺身を一切れ食べて、美味いなと言ってすぐ飲み込んだ。
「自分とはどんな人間? 自分が生きている日本の東京ってどんな場所? そういうことって、ただ生きているだけじゃ見えてこないからね。他人と触れ、別の環境を知ることで、わかってくる。自分っていうのは相対的にこうなんだ、日本っていうのは比較的こうなんだ、てね」
僕も続いて刺身を口の中へと放り込んだ。味はよくわからなかったが、僕はこれ美味しいですねと言ってウーロン茶で流し込んだ。北海道の食材の美味しさが普通だと思って育った僕は、道外で暮らすようになってから味わうということを諦めていた。
「海外旅行に行って、日本人ってやっぱり、気が小さくて神経質で、優しくて真面目なんだなって。俺はやっぱり旅行とか、異文化に触れることが好きなんだなって再確認したよ。まあ恥ずかしい言い方ではあるけど……自分探しの旅って奴?」
「……なるほど」
「お前だったら、どこ行きたい?」
「え?」
僕は瞬きを繰り返した。
旅行は好きだ。行ってみたいところはたくさんある。だが、僕は言葉に詰まった。北陸、山陰、四国、九州……海外なら……パリかローマか……。しかし、そう答えるのは何だか気恥ずかしく思えた。どれもこれも、先輩にとってのカンボジアに値するような答えではないように思えた。どれもこれも、ひどく貧相で幼い考えに感じた。
「そうですね……どこがいいですかね……」
僕が言葉を探している間、先輩は手際良くスマートフォンを操作していた。
「この人」
先輩が画面をこちらに向けて見せてくる。
「知ってる?」
一冊の本の表紙が表示されていた。
「あ、はい、知っています。えっと……」
表紙に写っている男は、具体的に何をしている人だったかはぱっと出てこなかったが、若者にとってのカリスマ的存在、というイメージの人物だった。
「この本、おすすめだよ。俺も仕事休んでた時期にこれ読んだんだ。読書をすることも同じで、色んな人の考えに触れることになるからね。いわゆる自己啓発本とか新書とかって、何となく毛嫌いする人もいるけど。ジャンルに囚われずに何でもかんでも読んでみようと思ってね」
僕は先輩からスマートフォンを受け取って、改めて画面を見た。
「自分探しの旅に出よう、本当の自分は遠くにいる……」
先輩は満足げに笑うとお猪口を口に付け、ぐいと傾けて、中身を空にした。
4/6
美味しかった、と母がいなくなった部屋で呟いた。
結局多少残したもののついつい箸が進んで昼間から食べ過ぎてしまった。満腹だ、と思いつつも、とうもろこしを一つ持ち、本を小脇に抱えて、ダイニングをあとにした。
階段を上りながら、母のことを考えた。
母は、僕が会社を休んで電話した時も、自分が帰ってきた時も、「久し振りにあんたもお墓参りに行く?」だとか、「今日のご飯、あんたが大好きな餃子でいい?」だとか、くだらないことばかりで、「今後どうするの?」といった真面目なことは聞いてこなかった。やはり何も考えていないのか。息子のことが心配ではないのか。気を使って話題を避けているのかもしれないが、僕は苛立っていた。「今後どうするの?」と聞かれたところでわからないのだが、「わからない」と答えるだけでも少し楽になれる気がしていたから、話を聞いてくれない母を恨んだ。
自室へ戻ると空気がこもっていた。今は使っていない部屋にも関わらず物がごちゃごちゃと多い。というより、使っていないからこそ、物置のような存在になっているのだ。
窓を開けると、風と虫の音が部屋へ舞い込んできた。
勉強机とセットになった古びた椅子に腰掛け、僕は例の本を開いた。
四ページ読んで、本を閉じ、とうもろこしにかぶりつき、一旦一階へ戻って手を洗い、麦茶をコップに注いで持ってきて、そしてもう二ページ読んで、また本を閉じた。
しばらくぼんやりとしていたが、母から部屋のものを捨てるように言われたのを思い出し、僕は腰を上げた。
部屋の隅に置いてある段ボール箱を開けてみると、昔どこかで嗅いだことのある、心が落ち着く匂いがした。
懐かしい教科書の表紙が目に入る。英語、数学、資料集……。取り出していくと、奥にざらざらとした厚紙の表紙の冊子が出てきた。
卒業文集だ。
手に取って、何が書いてある訳でもない表紙を眺め、どんなことを書いただろうと思い無作為にページを開く。が、急に嫌な感覚が胸に込み上げてきてすぐそれを閉じた。悲しみとも恥ずかしさとも悔しさとも、一言では言い表せられない。心の中で太陽が雲に覆い隠されたような、そんな気分だった。
将来の夢、とか、書いたんだっけ。だとしたら、何て書いたんだっけ。
少なくとも、「将来、心を病む」なんて書いていないことは確かだ。つまるところ、僕が思い描いていた未来にはいない、といえる。
背中にじんわりと汗がにじんだ気がした。
卒業文集を床の上の教科書に重ね、箱の中身を出す作業に戻る。
そもそも何故僕は今の職業に就いたのだろう。
理由はない。
いや、強いて言葉にするならば……。
勉強しなさいと言われた。大学に行きなさいと強いられた覚えはないが、大学へ行った方がいいんだな、と感じていた。数学や理科の方が少しだけ得意だったから、理系の大学を受験した。いつ就職説明会に行きどんな会社を受けるべきかといった情報は、サークルの先輩から後輩へ受け継がれており、僕もそれに従って行動した。いくつか面接を受けたうち、今勤めている会社から内定をもらい、そして、今に至る。
簡単にいえば、まわりに流されたから、だ。
音楽、家庭科、体育の教科書を取り出しながら、思考にふける。
では本当は、僕は何をすべきなのだろうか。
いや、何がしたいのだろうか。
わからない。
やはりどこか遠く、自分探しの旅に出るべきなのだろう。
そう考えて手が止まる。
ふと、段ボールの奥に紙袋が入っているのが見えた。今は閉店してしまった、旭川の老舗デパートの紙袋だった。
取り出して中を覗くと、使い込まれたノートが何冊も入っていた。
5/6
風がやんでいて静かだった。
僕は紙袋ごと勉強机の上に置き、再び椅子に腰掛け、ノートを一冊開いた。
シャープペンシルで書かれたその内容を見た瞬間、はっとした。胸の中で小さな泡が弾けたような感覚だった。今まで影も形もなかったはずの記憶が、振り返るといつの間にかそこにあった。
ぱらぱらとめくる。
次々と泡が弾ける。
それは、僕が小学生の頃から書き続けていた作品だった。大人になった目で見ると、作品とは呼べないくらいにそれはとてもつたなかった。くだらない落書きだった。ページごとに書いてある内容が違うし、テイストもころころ変わっており、支離滅裂。雑多なネタ帳といったところだ。
一瞬、恥ずかしさが込み上げる。「黒歴史」という言葉が頭をよぎる。
しかし、次の瞬間には好奇心が心を支配し、再び僕はページをめくっていた。
これを書いていた当時だって、誰かに見せる程の自信は持っていなかった。
しかし、今自ら読み返してみると不思議と強く惹き付けられた。
次第にページをめくる手がゆっくりになり、じっくりとノートの世界に入り込むようになっていく。
あるページは、眩い程の希望を伴ったまっすぐな正義感が描かれていた。
あるページは、燃えたぎるような怒りに溢れた必要以上に過激な描写だった。
そしてまたあるページは、無機質で淡々とした風景描写だった。
これを書いたのは僕だ。
僕の部屋の段ボールから出てきたのだから当然であるが、僕は改めて実感していた。
僕はこれを書いていた。
この勉強机に向かって、何時間も、何十時間もノートを書いていた。誰かに褒められるためでもなく、ただひたすらに書いていた。暑い日も、寒い日も。雨の日も、雪の日も。母に見せる訳でもなく、友達に見せる訳でもなく、がむしゃらに書き続けていた。チャーハンを食べた後の昼間も、西日射す夕方も、塾から帰ったあとの夜中も。
一冊見終わって、もう一冊を手に取る。
これは、昔飼っていた猫のことだな。
これを書いていた時は、そうだ、あのマンガにハマっていたんだ。
ああ、これを書いた時は、そうか、あの子が好きだったんだ。
そしてこれは、通学途中に毎日見ていたあの川だ。あるページでは穏やかに、またあるページでは軽やかに、あるいは時に荒々しく、その時々の僕の心を反映したかのようにその川の様子がノートに収められていた。
窓から強く風が吹き付けた。
その瞬間、僕は自分が風になって、窓の外からこの部屋を覗き見たような錯覚に陥った。部屋の中で、少年の僕が目を輝かせてペンを走らせている光景を、僕は見た気がした。
心の中で大きな泡がばちんと弾け、続けて隣り合った小さな泡も連鎖するように弾けていった。
6/6
「ちょっと聞こえてるのー? ご飯だよー!」
母はノックしながらそう叫び、そしてほぼ間髪入れずに扉を開けて部屋に入ってきた。
僕は我に返って、ノートから目を上げた。びくりと動いたせいで机に不安定に乗っていたノートが床に散らばった。
母が一階から呼ぶ声は、聞こえてはいたはずであるが、意識していなかったようだ。
椅子に座り直して窓の外を見ると、すっかり日が傾いていた。カーテンも閉めず、部屋の電灯もつけず、勉強机の灯りだけつけて読みふけっていたのだ。
「あれ。なんか余計に散らかしてない?」
母は部屋を見渡し、そして僕が持っているノートに目をやった。
「あ。そのノート」
「え、これ、見せたことあったっけ」
母が覗き込んでくるので僕は何故だか慌ててノートを閉じた。
「別に。中は見たことないけど、あんたが熱心にノート書いてるのは知ってたに決まってるしょ。大体、そのノートを段ボールにしまったの、誰だと思ってるの」
「そ、そっか……」
「てっきりあんたはそっちの道に進むんだと思ってたけどねぇ……ねえそれ面白いの?」
「え?」
不意打ちの質問に僕は戸惑った。
「えっと……お母さんが読んでも別に面白くはない、かな……」
やはり母は答えなど聞いていないようで、僕の横を通り過ぎ、窓のカーテンを閉めた。
「……でも……これ……捨てたくないなぁ」
僕がそう呟くと、母は振り向いてこちらをじっと見つめてきた。
「だったら、捨てなきゃいいしょ」
母はまるで子供にするように、僕の頭をぽんぽんと優しく叩いた。
一瞬たじろいだが、僕は母の顔から視線を逸らせずにいた。
「……だって母さん、この段ボールの中身、捨てろって言ってなかったっけ?」
「要らないものあったら捨てればって言っただけ。要るんでしょそれ? なら捨てなきゃいいべさ」
「あれ……そうだっけ?」
母は僕の問い掛けを気にせず、「あ」と声を出して、机の隅に追いやられていた読みかけのあの本を取り上げた。
「この本、借りてもいい?」
「え……」
表紙の男の顔がちらっと目に入る。先程までとはどこか印象が変わったように感じた。
手元のノートに目を落とすと、部屋の中で一心不乱にノートに向かう少年の姿が脳裏に浮かんだ。
そして僕は母を見上げた。
「うん、その本は、もう、いいかな」
そう言って笑うと、母もうふふと笑い、「今日はあんたが大好きなカレーだよ」と、また脈絡のないことを言って、そのまま部屋を去っていった。
カーテンが風に膨らんで、僕の背中を優しく撫でた。
「……餃子が大好き。カレーが大好き。あの人、僕のこと、何でも知ってるみたいだ。やっぱりすごい」
僕は先程落としたノートを拾い上げ、読み終わったものとそうでないものに分けて机の上に置いた。
少なくとも、僕の場合、「自分」は遠くにいないようだ。
僕はあの本の作者とは違う。そしてあの先輩とも違うのだ。
恐らく答えは僕の中にあったのに、気付けないでいた。
僕は椅子から立ち上がり、空になったコップを持って、勉強机の灯りを消した。
カレーを食べ終えたら、またこのノートを読み返そう。
そして明日、ノートを新しく買ってこよう。
やるべきことは他にもたくさんあるのかもしれない。この先の人生どうするべきかはまだわからない。
でも、今はただ、もう一度ノートに「自分」を書いてみたい。ノートの中で自分探しの旅に出たい。
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
この作品は幸野つみが企画したお題小説企画の作品です。
お題は「ノート」です。
同じお題で小説を書くと作者によって内容は似てくるのか、まったく違うのか……ぜひ他の方々の作品もあわせて読んでみてください。
読んでいただきありがとうございました。
ぜひぜひスキしてください。
フォローやコメントもしていただけたらとても嬉しいです。
また、noteはもちろん、twitter等での拡散もどんどんしていただきたいです!
あとがきはこちら↓
幸野つみのその他の短編を読みたい場合は下記リンクからどうぞ!
↓幸野つみの短編小説を集めたマガジン
↓前回の短編小説
最後まで読んでいただきありがとうございました。
幸野つみ
いただいたサポートは旅行代にしたり、カレー代にしたり、自由に、かつ、大切に使わせていただきます! コメントやTwitter等でのシェアもよろしくお願いします!
