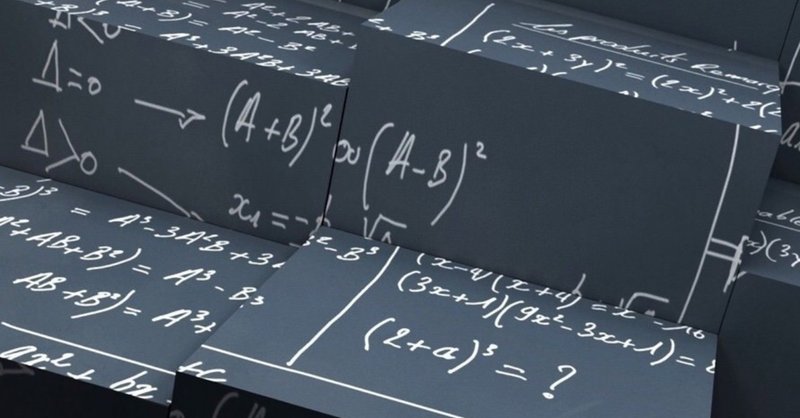
環境か、それとも遺伝子か。
これは78回目。最近、「いってはいけない」に続いて、「もっといってはいけない」という本が出版され、大いに売れているそうです。著者は、大変な勇気を以て世に問うたのでしょう。恐らくリベラルからは、激しい批判と非難、中傷さえ浴びせかけられていると思います。しかし、「人権」という建前の下、実はなんとなくそうではないかと誰しも疑念を抱いている点を、わたしたちはともすると「できるだけ見ないように」してきた嫌いがあります。しかし、それで本当の人権は守られるのでしょうか。
:::
一体、人間がそうなるのは、環境によるものなのか、それとも遺伝的特性が継承されるためなのか。この古くて新しい論争は、未だに明確な定説がない。
深く突っ込めば突っ込むほど、人権に深く関わってくる問題だけに、取り扱いは非常に注意を要するテーマだ。
一番この二つの対立論争が激しいのは、かつて犯罪学においてだった。今では、どちらかというと誰もこの分野に言及したがらない。敬遠されているのだ。一方、大変な物議を醸しているのは、ご存知病理学や、薬学・バイオ研究などである。
もともとこの環境決定論と、遺伝子継承説は、犯罪学においてイタリアのチェザーレ・ロンブローゾが、犯罪者の形質というものに共通点があるという仮説を立証しようとしたことで、欧州で大論争を巻き起こした経緯がある。
ロンブローゾは、処刑された人間の頭骨を383体を解剖分析し、さまざまな生きた人間の形質とあわせて、骨相や顔相などに犯罪者の共通点があることを仮説し、犯罪者は生来犯罪者になるべくその遺伝的形質が継承されるとした。
ロンブローゾによって、当初主にイタリアで広まったこの遺伝子継承説に対して、猛然と反駁したのは、フランスを中心とした環境決定論である。
ヒラメのような顔の非対称性と犯罪者の顔相の非対称性の関連付けといった、かなり無理な(本人は大真面目だったかもしれないが)ロジックは、さすがに批判も多く、けっきょくロンブローゾの説は、今では擬似科学として片付けられており、現在ではほとんどかいまみられていない。
ロンブローゾ自身、もともと彼の仮説によれば、遺伝子継承的な形質の有無によって、犯罪者になる確率は70%としていたのが、後に30-40%に下方修正している。
しかし、その後世の中は、社会主義・共産主義の世界的な流行と歩を同じくして、環境決定論が社会学の主流となっていった。環境こそが、人間を変えてしまうのだ、ということだ。
たとえば、(どこの国のことか失念してしまった。イタリアだったか?)某国で死刑廃止論が高まった。死刑存置論者たちは激しく抵抗し、「そんなことをしたら、犯罪が増えるではないか」と反論した。が、結局死刑は廃止された。すると、犯罪は目に見えて増加した。死刑存置論者は「それ見たことか」と鬼の首でも取ったようになり、「だから死刑を復活させるべきなんだ」と主張。死刑制度が復活した。ところが、その後も、犯罪は増え続けたのである。一体これはどうしたことか?
つまり、一応の解釈とされているのが、死刑制度の有無は、犯罪の増減とは無関係であるという仮説。あくまで犯罪の増減は経済状態の良し悪しによって左右されるのだ、というわけだ。これで、環境決定論者の声が社会の大勢を占めるようになった。
そのリベラルにして、環境決定論者の牙城が、もろくも揺らいでしまったのは、遺伝子の形質が継承されることによる病理の継承という大問題である。俗に言う、「ガンの家系にはガンが多い」という俗説が、単なる俗説ではなく、十分に蓋然性のあるものだということが、DNAの発見によって明らかになってきてしまったのだ。
実は、DNA(デオキシリボ核酸)は、1869年にスイスのフリードリッヒ・ミッヒャーが発見していた。が、これはその役割を、細胞内におけるリンの貯蔵と考えていた。その後、さまざまな研究と論争の結果、1952年、ADハーシーとMチェイスによって、DNAが遺伝物質であることが決定的になった。Jワトソンとチェイスが、DNAの二重螺旋(らせん)構造を明らかにしたのは、その翌年である。
こうなると、単純に環境が決定する、箱を変えれば人間も変わるという単純なものではなくなってくる。その結果、見たくもない、知りたくもない自分の遺伝的形質というものを、現代のわれわれは否応でも直視しなければならなくなった。
「蛙の子は蛙」なのか。それとも「鳶が鷹を生んだ」なのか。いずれにしろ、教育という分野は、この遺伝という効果を危険視して触りたがらない。ひたすら環境決定論一本槍で(少なくとも日本では)走り続けてきている。その結果が、「ゆとり教育」であり、その反動としての「土曜日登校の復活」だったり、右に左に大揺れを繰り返す試行錯誤を繰り返しているのだ。
今この両論の、相譲らない激論に、ひとつの道筋をつけようとしている試みがある。双子の行動原理を徹底的に、そして緻密に研究している慶応大学のチームによると、どうも双子の場合、同じ遺伝子が継承されているにもかかわらず、二人の環境を違えてしまうと、一方にはその遺伝的特性が発生してみたり、もう一方には発生しなかったりするというのだ。
つまり、遺伝子か環境かという、二者択一の世界ではなく、どうやら遺伝子は潜在し続けるが、環境によってそれが発現したり、潜伏したりするという仮説がでてきている。圧倒的に、遺伝子決定論が強いとはいえ、環境変化によってはそれが発動したり、発動しなかったりするわけで、結論としては遺伝子と環境の交互作用ということを受け入れざるを得ない。
教育という場においても、実はそこまで踏み込んだ個体と全体のバランス、個体の特性の吟味などをしなければならなくなってきている。これは今の教育現場の教師たちに負わせるには、あまりにも酷なほどだろう。いずれにしろ、遺伝子という燃料を起爆させるトリガー(引き金)になるものの大きな要因の一つに環境というものはある、と考えるのが現実的なようである。
かつて、わたしが小中学生のころ、試験の成績の順位が廊下に張り出されて大恥をかいたものだ。昔は、精神論が主体の教育論だった。人間、頑張ればなにほどのものにか成れる「はず」だという考えである。
一方現在はその反動で、通信簿ですら比較がほとんど無いような「よくがんばりました」「もう少しがんばりましょう」・・・一体なにを評価しているのか、まったく意味不明になっている。これは、人間はみな平等であるから、比較評価するべきではないというリベラルな発想が教育や社会の大前提になっているからだ。
どちらも間違っているのである。
人間は違って当たり前。能力や資質に違いや格差があって当たり前なのだ。それを、努力を無理強いしようと、綺麗事の理念で見て見ぬふりをしようと、どちらも現実の問題にまったく対応できないのである。
かつて世界でも有数の教育水準の高さを誇ったこの国が、今では先進国中最低といってもいい教育内容である。
突き詰めていえば、遺伝子は決定的である。環境もそのトリガー(引き金)にはなる。しかし、もっと重要なのは、どちらがどうであっても、問われているのは人間の徳質なのだ。その違いや格差があってもなお、平等であるとは一体具体的にどういうことなのか、そこに思いが至らないのだ。
今の社会も教育も、この一番大事な希求にまったく応えようとしていないようだ。語るに落ちたというべきか。国民の品格が音を立てて崩れつつある。そう言ったら、いささか言い過ぎだろうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
