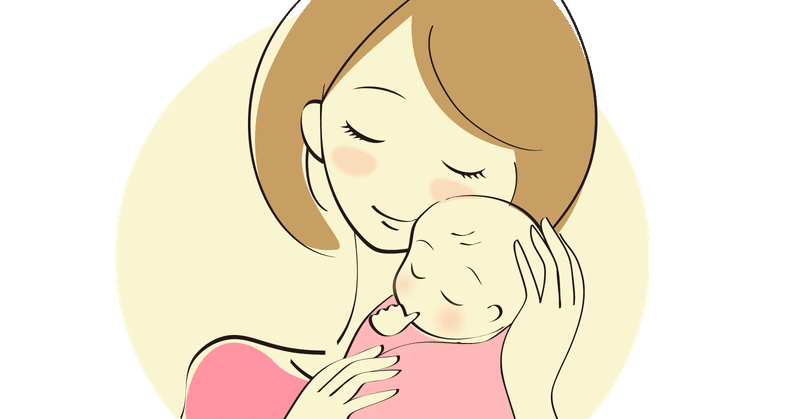
【みこ仏教】小林正観さんが初めて腑に落ちた日
仲良くして下さる人の中に勧められる本で、良いとは思うんだけど、いまいち脳天に直撃するほどではないな、多分分かってないんだろうな、と思う著述家が何人かいる。
パッと思いつく方を挙げさせていただくと、中村天風、安岡正篤、小林正観、稲盛和夫などだ。きっと、稲盛和夫さんなんて、もっと神格化されると中村天風とか安岡正篤になるのかもしれない。
小林正観さんは、みこちゃんにとって微妙な位置づけだった。
でも、この本はとてもしっくりきて、初めてみこちゃんに小林正観を勧めてくださる方の気持ちがわかったような気がしました。確かに、これはみこちゃんのツボに入るところです。
出会えてよかった。読了したら小林正観さん、きっと好きなる。
(^-^)
例え話で、キサー・ゴータミーのお話が出てきます。
キサーゴータミーという母親が、やっと歩けるようになったばかりの一人息子を亡くしますが、わが子の死を受け入れることができません。見かねた町の人が、「お釈迦さまだったら、息子さんを助けることができるかもしれない」と伝えます。
彼女はすぐに「息子を助けてください」とお釈迦さまのもとをたずねました。この時、お釈迦さまは「その子を助けたければ、これまで誰も死人が出たことのない家から白いケシの実をもらってくるように」とおっしゃいます。
「ケシの実ならなんとかなる」。わが子を助けたい一心で町中の家々をたずねたキサーゴータミーでしたが、「ああ、なんということだ。自分の子どもだけが死んだと思っていたが、町中の方がみんな家族の死の悲しみを受け入れて生きているのだ」と、死はどこの家にもあることに気づかされたのでした。
小林正観さんは、さっきの本で、このお話をこう解釈します。
どこの家からも死者が出ていることを知った女性は、そこで初めて「はっ」と気がついたに違いありません。自分だけのことではなかった、自分の子供のことだけではなかった。この子の死を受け容れることが、自分にとって楽であり、当たり前のことなのだと気がついたのではなかったでしょうか。
悩み・苦しみとは、「思い」を持っていて、その思いどおりにならないことを、思いどおりにしようと思うこと。
悩み・苦しみは、受け容れた瞬間から消滅するのです。事実をいかに受け容れるか、その一言につきます。
小林正観さんが好きな人はめちゃくちゃ好きなので、ここでこんなことをいうと、叱られそうなんですが、これは別に普通の解釈だと思います。
それに、悩み・苦しみは、受け容れた瞬間から消滅するというのはそうかもしれないけど、みこちゃんとしては、これでは死んだ子供がかわそうなので、自分が楽になるために受け入れるというのは、単なる自分のエゴであり、みこちゃんの人生観に反するのでこの小林正観さんの感受性は受けいられれない。
と、ここで、いつも小林正観さんの理解は止まっていたのです。
でも、ここを読んだら、小林正観さんの言っていることの意味がわかったような気がしました。
いま目の前に起きている最高の幸せとは、
淡々とした何も特別なことがない日々、普通に家族がいて、普通に仕事があって、普通に食事ができて、普通に歩くことができて──それが、とんでもなく幸せなんだ……
ということです。
それが分かったら、目の前の現象について、「これが気に入らない、あれが気に入らない」とは言わなくなります。感謝の心が増してくると、文句を言わなくなる。そして、突き詰めていくと、夢や希望もなくなる。
「感謝」プラス「夢や希望」の総和を、一〇〇とします。
「夢や希望」が九〇なら、「感謝」が一〇になり、「夢や希望」が一〇なら「感謝」が九〇になる。「夢や希望」がゼロになると、「感謝」が一〇〇になる。
これが最高の至福の時。私は人生の中で最高の幸せをずうっと味わいながら生きていて、至福の時をずっと味わっています。
そこでは、何にも特別なことは起きていない。普通の日々が、普通に続いているだけなのです。
「感謝」プラス「夢や希望」の総和を、一〇〇とします。
ここで、腑に落ちました。
そして、これが総和の引き算になる。これはびっくりで、とてもとても腑に落ちました。
「夢や希望」が九〇なら、「感謝」が一〇になり、「夢や希望」が一〇なら「感謝」が九〇になる。「夢や希望」がゼロになると、「感謝」が一〇〇になる。
大切なのは、ここでいう「夢や希望」というのは、本来持つべきではない夢や希望のことであり、努力でなんとかなりそうな夢や希望を、努力もせずに断念するのは、今流行りの単なる怠け者の言い訳だということです。
自分に能力がないとか、努力がつづなかいので夢を諦める、これを煩悩を捨てることだと間違って仏教を解釈する。これは、イソップの酸っぱい葡萄と同じ話で、単なる負け犬の遠吠えにすぎません。
でも、子供が死んでしまったこと、それを生き返らせることは、とても不自然な夢や希望です。
お釈迦様は、夢や希望に二種類の区別をしたとみこちゃんは思います。
良い夢や希望というのは、悟りを開いてそして、自分だけが悟りを開いて満足するのではなく、また下界に降りて、今度はまだ迷っている、かつての自分と同じように苦しんでいる人たちを菩薩道で救うこと。
この悟りがかなった後の夢や希望を、修行が苦しいからと言って、上手く瞑想できないからと言って断念するのは、とてもずるい、自分の心を騙す行為に他なりません。イソップの狐みたいな人生にいいことなんて何かあるんでしょうか。
でも、お釈迦様はキサーゴータミーに、望んではいけない夢を捨てることを諭されたのだと思います。
ここが、仏教をかじりはじめの人がよく、都合よく誤解しているところで、お釈迦様はただの一言も、欲求そのものを否定したことはありません。悪い欲求=煩悩を滅することだけを諭してきました。感情を殺せ、反応しない人間になれ、なんて一言も言っていない、全部、それは仏典のたらめな誤読です。
小林正観さんは、この「夢や希望」がゼロになると、「感謝」が一〇〇になる。という言葉で、<間違った>「夢や希望」がゼロになると、「感謝」が一〇〇になる。とうことを言っているのだ、やっとそう分かりました。
間違った希望を捨て去れば、子供の死を受け入れ、短い時間ではあったけど、自分に出産の喜びや我が子に出会えた喜びを、感謝の気持とともに感じることができる。
これなら、イソップの狐の負け犬の遠吠えとはまったく違う。
煩悩を棄却するとは、感謝という言葉と対で考えればよいのだ。
これが、今回みこちゃんが小林正観さんから読み取ったものでした。
こうして書いてみたら、とても自分でも納得できました。
さっき読了したら小林正観さんが好きになるだろうと、書きましたが、もう好きになりました(^-^)。
記事を書き終わったら読もうと思って、わざと残してあった数ページを読むことにします。
きっと、まったく違った気持ちでこれからは小林正観さんの本を手にできそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
