
だって自分の人生だから。―「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」を読んで
発売前の本をAmazonで予約するなんていつぶりだろう。そもそも、誰かのエッセイとやらを買うなんて初めてかもしれない。
そんなことを考えながら、華麗なる親指さばきでポチっとしたそれは、エッセイ「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」。
著者は“100文字で済むことを2000文字で書いてしまう”でおなじみの、はたまた“令和の時代にnoteで一番成功した女“でもおなじみの、岸田奈美さん。
情報過多で波瀾万丈すぎる毎日を笑いあり涙あり言葉で綴る作家さんで、次の広辞苑の改訂では「新進気鋭」の例文に「岸田奈美」の名が刻まれるといっても過言ではないほどの勢い。
2019年9月に、「弟が万引きを疑われ、そして母は赤べこになった」がバズっていたことをきっかけに、のちに時の人となる同世代の岸田さんを知り、時同じくして「書くこと」を生業にしていること、時同じくして「福祉」に携わっていたこと(岸田さんは「バリアバリュー(障害を価値に変える)」株式会社ミライロの創業メンバー、わたしは社会福祉士をしていた)から、勝手な親近感をもってファンになることはや一年。そんな岸田さんが初エッセイを出版されるとなれば手に取らない理由はない。
今日は、その岸田さんが主催している、同じ時間に、同じ本を読み、読書感想文を書く「#キナリ読書フェス」に参加すべく、課題図書のひとつでもある「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」を読んでの読書感想文を、中学生ぶりに書いてみようと思う。どきどき。
はじめに、岸田さんの半生を。
・中学2年生のときに父親が突然死
・高校1年生のときに母親が車いす生活に
・弟がダウン症
「ふたりはプリキュア Max Heart」のオープニングテーマが聞こえて来そうなほどの一難去ってまた一難っぷり。まわりの人がつい「つらいことばかりの人生を、よくがんばってきたね」と声をかけ、ねぎらいたくなるのも分かる。
でも、岸田さんはエッセイの中でこうつづった。
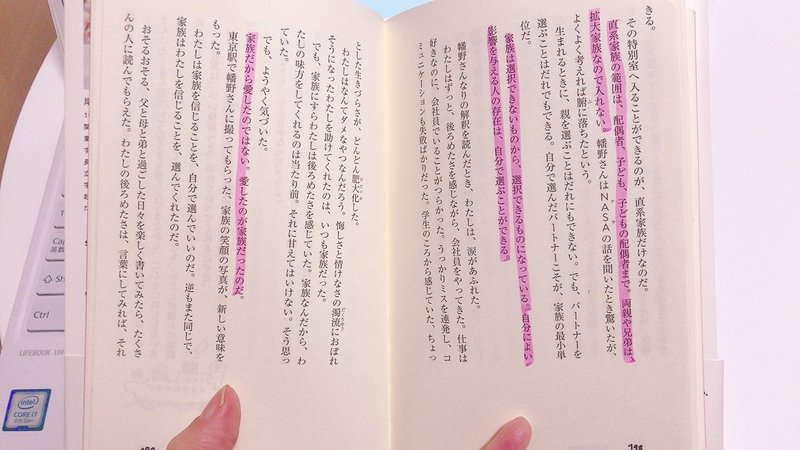
「わたしにとって生きるというのは、がんばることではなかった。ただ毎日『死なない』という選択をくり返してきただけの結果だ。」
この言葉を読んだとき、思わず“どきっ”とした。
わたしが“どきっ”とした理由。それは、たしかに岸田さんに起きたこれらは「つらいこと」であり、ご自身も「初めての人に話すとわりとギョッとされる家族構成」とはいうものの、時間をかけてその全てをポジティブに置き換え、またつらい思い出すらも人生の大切な一部として愛おしく抱き締めているイメージしかなかったから。
「ただ毎日『死なない』という選択をくり返してきた」ということは、かたや「死ぬ」という選択肢を並べていたということ。毎日、「今日は死ぬ」か「今日は死なないか」から「死なない」を選んできたということ。きっと今日も「死なない」を選んでいるということ。
同じだと思った。
なにがって、わたしと。
わたしは毎朝、今日1日を「生きる」か「死ぬ」かを選ぶことからはじめる。わたしが今これを書いているということは、今日まで「生きる」を選び続けてきたということ。明日の朝のわたしがどの選択をするかは誰にもわからない。
そうするようになったのはいつからだろう。
時間はぐぐぐっとさかのぼり、これはきっと物心がついた頃のこと。わたしは幼少時代から大人になるまで「自分で選ぶ」という経験が人より圧倒的に少なかった。
わたしの家には、何を食べるのか、何を着るのか、どこに出かけるのか、テレビは何を見るのか、だれと友だちになるのか・・・、あらゆることに暗黙の決まりがあって、それを読むことを無意識に強いられていた。
これはきっとどこにでも起こりうることで、だれもが乗り越えるステップなのかもしれない。だけど、今ここで書き切れないほどいろんな事情があって、幼少時代のわたしには「これがいい」「これが好き」「これはイヤ」「あれがしたい」と言える余白がこれっぽっちもなかった。
特に悲しかったのは、小学生のとき、当時流行っていたファッション雑誌を読めなかったこと、大好きなドラマを見られなかったこと、大好きな歌を歌えなかったこと、友だちとプリクラを撮りに行けなかったこと。
わたしが「自分はこう思う」を主張することで、一瞬でも波風がそこに立つのなら言わないでおこう。自分が我慢をすれば丸く収まる、それがクセになっていった。
そのくせ、反抗期と言われる時期にはあいにく死にかけて、この期に及んで反抗できる期を逃してしまった。16歳にして、がん疑いを告げられて、9時間におよぶ大手術をした。“疑い”で済んでよかったものの、あれよあれよと再発をくり返した。モーニング娘さんのザ☆ピースのアウトロ並みに、これで最後かと思ったらぶり返し、結局3回も大手術をした。家族にとんでもない迷惑と心配をかけてしまった。自分は欠陥品だ、どんてもないハズレくじを引いた。身心ともに疲弊した。
そして、いろんなことを諦めた。
まずは自分が物理的に出来ること、そして家族が納得することの選択肢の中から、身の丈にあった無難な選択肢を消去法で採用するようになった。
本当はやりたいことがたくさんあった。一人暮らしをしてみたかったし、県外の大学に進学もしてみたかった。そのあと、福祉の仕事に進んだけれど、あらゆる選択肢を知り、それを選ぶ許可が自分に出せていたら、違う道を選んだかもしれないとも思う。
そんなこんなで、「自分で選ぶ」を放棄し続けてきたわたしは、いざ大人になるとあらゆる場面で困るようになった。
自分の気持ちがわからないのだ。感情そのものに不感症になってしまったようだった。
たとえば、スーパーに行っても何を食べたいかがわからない。お給料が入っても何が欲しいかがわからない。「最近なにか楽しいことあった?」と聞かれてもわからない。好きも嫌いも、快も不快もわからない。
こんな毎日が、明日もあさっても、5年後も10年後も続くなら、それは絶望でしかない。だって何も感じないんだから。わたしは、まるでパイロット不在のガンダム。ただ「外身」があるだけ。「わたし」じゃない。
そんな自分をなんとか変えたいと思った。
いや、変えないといけないと思った。
こんなわたしではきっと誰かを愛し家族を持つどころか、自分ひとりの人生すらも全うできないままリタイアしてしまいそうだったから。
そう思って、半強制的に「自分で選ぶ」ためのトレーニングをはじめた。やることは簡単。「世間一般的にはこうだから」「みんなはこれを期待しているから」「これが普通だから」といった、あらゆる当たり前を疑って、日常の中の小さな小さな選択を大切にするだけ。
早起きは三文の得だから早起きするんじゃなくて自分が起きたい時間に起きる、時間が来たから食べるんじゃなくておなかがすいて食べたいと思うから食べる、流行りだからじゃなくて自分が着たいものを着る、そんなささいなこと。
その中のひとつが、今日1日を「生きる」か「死ぬ」かを選ぶこと。「悲しむ人がいるから生きる」は自分の人生を生きているとは言えない。自分で選んだ「生きる」を今日も生きたい。「生きる」も「死ぬ」も自由な中で選んだ「生きる」には価値と責任がある。自分の人生のハンドルを握るのは自分だ。そう決めたんだ。
それから2年をかけて、わたしの人生は大きく変わった。
まずは仕事が変わった。
4年と少し勤めた福祉の仕事をやめた。福祉の仕事は好きだ。だけど、あらゆるルールにしばられてしまう働き方はわたしには並々ならぬ苦しさがあった。愛嬌だけで乗り越えてきたもののおっちょこちょいのすっとこどっこいで怒られてばかり。なにより致命的なのは、人と話すのが苦手ということ。3人以上の場ではひと言も発せないまま何時間でも過ごせてしまう。そのくせ、インターネット上ではこれでもかといきりちらせてしまうもんだから、付いたあだ名はネット弁慶。だから、インターネットで個人で物書きをする仕事を選んだ。
そして住む場所も変わった。
学生時代に田舎から都会へ出る夢は叶わなかったけど、それは本当は自分がやりたかったこと。だから大人になった自分で叶えてあげようと思った。自分で働いて、自分で作ったお金で、つい1週間ほど前に上京した。自分が住みたいと思った街に、自分が住みたいと思った部屋を借りた。
ほかにも関わる人、自分が触れるもの、身につけるもの、大切にするもの、その全てが大きく変わった。わたしにとって時間の使い方は、命の使い道だ。
これは全部自分で選んだ。自分が選んだんだ。今わたしのまわりにあるものは全てわたしが選んだ。わたしの手が届くこの世界はすべてわたしが選んだものでできている。
「家族」以外は。
わたしは「家族」という言葉を聞くだけで身体がぎゅっとこわばるくらい、「家族」という最小にして最強のコミュニティに苦手意識がある。その理由は、先に少し触れたように、わたしにとって「家族」が安心出来る場所ではなかったから。
幼少時代から家族が喜ぶことを選び続けてきたわたしにとって、家族という存在は想像以上に大きく、強くて、しぶとい、呪縛のようなもの。
もし、今でも家族にNOを突きつけられたらYESがひるがえりそうになる。それでは過去に逆戻り。それだけはごめんだ。
わたしが上京をしようと思った本当の理由のひとつは、「家族」と物理的な距離を取ること。もともと一人暮らしはしていたけど、だけどもう少し。決して縁を切るわけじゃない、家族は大切、だと思う。だけど物理的な距離をとるというアクションで、遠回しに家族にNOを伝えたかった。今、わたしの手が届く世界に入ってきて欲しくないと。それが今のわたしには必要だと。
当然家族は反対した。
「こんな時期に引っ越ししなくてもいいのに」「地震が来るかもしれないのに」「今は地方にみんな引っ越してるのに」、ああいえばこういうの権化か。
挙げ句の果てには「富士山が噴火するよ」と言うので、「そのときはみんな死ぬからもういいよ」と伝えた。本当は「そういうところがイヤなんだ」と言いたかった。
同時に感じたのは、家族を選ぶことへの後ろめたさ。なにはともあれ愛をもって育ててくれたはず。いや、家族だから、こんなわたしを仕方なく育ててくれたのだろうか。家族にとってのわたしは大切な家族だったのだろうか。そんなことが、ぐるぐると頭をかけめぐる。考えたって答えは出ないのに。
そんな中で改めて読んだ「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」には、こう書かれていた。
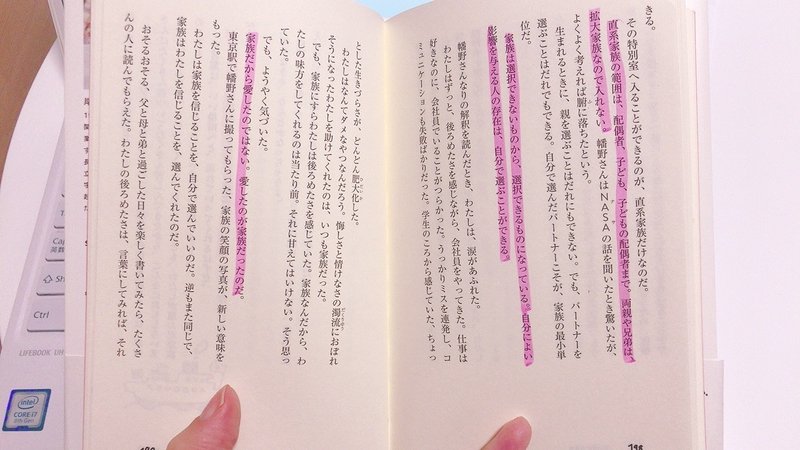
ここからは、幡野さんの本『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(ポプラ社)に書いてある話だ。
NASAにおける家族の定義は、ふたつある。ひとつは直系家族、もうひとつは拡大家族だ。
スペースシャトルが打ち上げに失敗し、大事故になったとき。乗組員の家族はパニックになる。いち早く心理的・医学的なサポートを行うため、医療チームや支援スタッフと一緒に、家族は特別室で打ち上げを見守ることができる。
その特別室に入ることができるのが、直系家族だけなのだ。
直系家族の範囲は、配偶者、子ども、子どもの配偶者まで。両親や兄弟は、拡大家族なので放れない。幡野さんはNASAの話を聞いたとき驚いたが、よくよく考えれば腑に落ちたという。
生まれるときに、親を選ぶことはだれにもできない。でも、パートナーを選ぶことはだれでもできる。自分で選んだパートナーこそが、家族の最小単位だ。
家族は選択できないものから、選択できるものになっている。自分によい影響を与える人の存在は、自分で選ぶことができる。
幡野さんなりの解釈を読んだとき、わたしは、涙があふれた。
わたしもこの解釈に触れたとき、モヤモヤとうずまいていたある種の罪悪感から救われたような気がした。
わたしは選んでよかったんだ。わたしには選ぶ権利があったんだ。たとえそれが家族だとしても。わたしにはYESの選択肢もNOの選択肢もある。
だって自分の人生だから。
いろんな荷物を、時間をかけてひとつひとつ下ろしながら、少しだけ身軽になった今、なんだかすがすがしい気持ちでいる。
「会ってもいい」「会わなくてもいい」、「帰ってもいい」「帰らなくてもいい」、「関わってもいい」「関わらなくてもいい」そんな状況になったとき、それでもわたしはあの「家族」を、今度は自分で選ぶのだろうか。
そしてそんな気ままで、出来損ないのわたしもまた、家族にとっての「家族」なのだろうか。
その答えはわからない。ただひとつ、少しだけ確かになったことは、苦しかったこと、悲しかったことはたくさんあるけど、28歳にしてはじめてほんの少し「家族」を大切に思えるようになったこと。それでも帰る場所はここだと思えたこと。
そして家族に連絡をした。
「お正月、帰るからね」。
「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」はわたしの人生において大切なテーマを考えさせてくれるきっかけになり、何度だって読み返したい、大切な一冊になった。このきっかけをくれた岸田奈美さんに心から感謝します。
< #キナリ読書フェス 課題図書>
もし「サポート」をいただけたあかつきには、もっと楽しくて、ちょっぴり役立つ記事を書くための、経験とお勉強に使わせていただきます🌼
