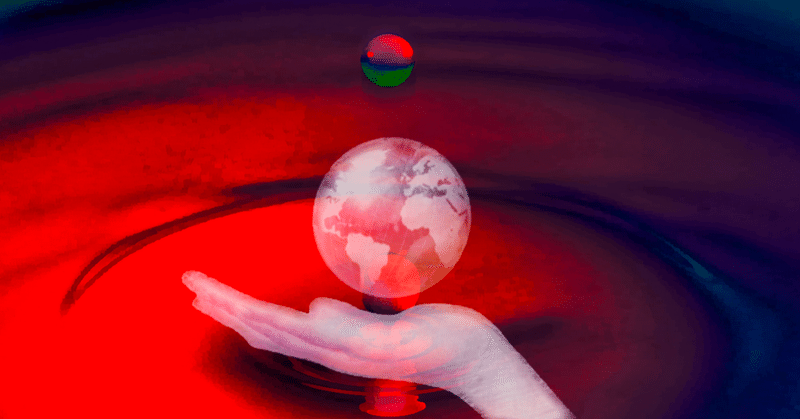
魔都に烟る外伝/還(めぐる)~The 1st part~
※サブタイトルは変わってますが、『魔都に烟る外伝/終宴の始まり〜part17〜』からの続きになります。
***
目の前一面に広がる凍った湖。
それは、一年を通してぬるむことはなく、まして、とけることもない。
その畔に佇む、クライヴと倭(やまと)、そして、10歳程の少年の姿。
冬の凍てついた空気は澄み切っており、怖いほど静謐な空間を作り出していた。
外界から遮断されたようなその空間の中で、外套を纏い、片手で少年を抱き寄せているクライヴが、長い黒髪に白い着物、銀鼠の袴姿の倭と見つめ合っている。
向かい合い、視線を交える二人の間に、他の存在は何もなかった。
クライヴが大切そうに抱える、その少年すらも。
*
*
*
クライヴと倭の間に産まれた息子レイは、間もなく11歳になろうとしていた。
母親譲りの黒い瞳と髪、両親からバランス良く受け継いだ、美しい絵画のように整った顔立ちに長い手脚。そして、性質(たち)までが二人に良く似ており、吸い込まれそうな黒い瞳に感情の色は薄く、到底、表情豊かとは言えない。だが、それでも人目を引く存在ではあった。
母・倭と暮らしながら、ありとあらゆる力と知識を受け継ぐために過ごす日々を、父親であるクライヴは、母国との間を行き来しながら見守っている。
会話の復習がてら、ヒューズと庭の散歩をしながら話しているレイを眺めれば、産まれたての我が子を両の手に抱いた重みを、クライヴは今でもつぶさに思い出すことが出来た。常に胸の内にあり、折に触れ辿らずにはいられない、あの不思議な感覚と共に。
そして、レイだけではなく、ヒューズも確実に成長しており、今やフレイザーに劣らぬ立派な執事となっていた。彼がいれば、レイのことは安心して任せられる──クライヴがそう確信出来るほどに。
フレイザーやヒューズとの連携はもちろん、国王リチャードが心を入れ替えて政務に励んでいること、また、オーソンの動きが鳴りを潜めていることもあり、この10年余り母国の情勢は何とか均衡を保っていた。クライヴの嚇しが効いているにせよ、少しの動きもないなど珍しく、俯瞰して考えて見れば、オーソン自身が本領を発揮するには一定の条件が必要と推測が出来る。つまり、レイ同様、ガブリエルの身体が成長しなければ動きが取れないことは一目瞭然と言えた。
とは言え、油断は出来ない状況下、ひと役買っているのは倭が放った『使役』である。クライヴが倭の元に留まっている間、彼女はフレイザーの元に『代わり』となる者を送り込んでいた。クライヴ本体ほどの力を持ち合わせていなくとも、ある程度の緩衝にはなる上、倭を通して向こうの状況が『視える』利点もある。クライヴの持つ感覚や文のやり取りでは、物理的な距離があり過ぎるため、これは大きな助力となっていた。
そんな倭の助力に対し、クライヴも己の持つ力で報いている。当然、倭は普段通りに『役目』も熟しているため、遠方を訪れなければならないこともあるが、クライヴはその遠征に必ず同行した。よほど特殊な案件でもない限り、クライヴがいれば基本的に他の援護は必要なく、そういう意味では最高の組み合わせとも言える。
何より、レイの誕生によって僅かながら展望がきいたことで、気がかりだったライナスにも、マーガレットを救えなかった謝罪、今後の計画も説明するに至った。
「……レイが産まれて10年も経ったとは……つい、この間、産まれたような気がするが……」
倭を腕に抱き、語りかけるでなくひとり言のようにつぶやくと、声に反応して目を開けた倭がクライヴの胸の上で小さく頷く。
「はい。もう、私が教えることもほとんどありませぬ。伝えられることは全て伝えました故……あとは、引き継ぐのみにございます」
その言葉に、クライヴの動き全てが止まった。
「……倭……」
「……はい?」
それは最後の夜──。
呼びかけたまま言葉は続かず、クライヴの脳裏には、数年前に倭と交わした会話が否応なしに甦っていた。
***
レイが歩き始めた頃であった。
一般的な子どもに比べれば、傾向としては言葉少ない性質(たち)ではあったが、それでも何かとしゃべるようになり、行動範囲が広がり始めた我が子を眺める日々。何かをやり始めたと思えば、何が気に入らないのか一人で癇癪を起こして怒り始めたり、何なのかわからない『何か』を飽きもせず眺めていたり。
クライヴは、常に不思議なものを見る目を向けていた。
(……面白い生き物だ……)
何もわかっていないような顔をしつつ、クライヴと倭のことを、他の人間──ヒューズや五百里、手伝いの者など──ときちんと区別して認識しているらしいことがわかる。時に、わざわざクライヴを選んで目の前に立ち、両手を大きく挙げることがあり、どうやらこれは『抱き上げてくれ』と言う意思表示であるらしい、などと、そんなことを知ったりもする。
クライヴが母国から戻った直後は、特に纏わり付く傾向が強いこともわかって来ていた頃で、そのことを考えただけでも、彼を他の者とは違う『特別な対象』と認識していることは確かであった。
「……倭……これは……私は何を望まれているサインなのだ?」
クライヴの脚に抱きつき、懸命に押し引きをしている……ように見え、暗号解読を倭に頼む。
「貴方と外(おもて)に行きたいのではありませぬか?」
「……なるほど……」
片手でひょいと持ち上げ、庭に連れて行けば散々クライヴを引っ張り回す。木陰に座っていれば腹の上に乗って来て、あっという間に寝てしまう。
(……解せぬ……)
そうは思いながらも、決して悪い気分ではなかった。
ただ、夜、ぐっすりと眠っている寝顔を見るたびに不思議な気持ちが湧き起こり、正直なところ、クライヴは己の感情に困惑していた。そのため、とっくにレイを寝つかせた宵の刻、髪を梳いている倭をベッドの上から眺め、夜ごと思いを巡らせるのが常になってもいる。
「……倭……」
呼びかける躊躇いがちな声。
「はい?」
その声音に何かを感じ、倭が手を動かしながら振り返った。
クライヴの中に、話したいことはいくらもある。だのに、脳内は何から話せば良いのか収拾がついておらず、呼びかけたは良いが言葉に詰まってしまった。ここまで来ても言い淀む様子に、倭が不思議そうな表情を浮かべる。
「クライヴ?」
ここしばらく、彼が何か言いたげなことに気づいてはいた。
「どうしたのです?」
手を留めて櫛を置き、倭がゆっくりと近づく。続きを促す気配に答えられず、クライヴは仕方なく手を差し出した。その手と顔を不思議そうに見、それでも躊躇いなく預けた手が強く引き寄せられる。
「……クライヴ?」
腕の中から見上げて来る倭の視線を感じ、クライヴは空(くう)を仰いだ。
「……やはり、私は間違っていたのかも知れぬ……」
倭が一瞬、瞬きをとめる。
「何を、です?」
「……そなたに協力を仰いだことだ……」
返答自体に躊躇いはなかった。だが、息と共に後悔をも飲み込むようにしながら、言葉だけを吐き出したのは明らかであった。
「……何故(なにゆえ)です?」
クライヴは、つい今しがた倭が梳いていた髪に、味わうように指を通し、そのしっとりとした感触を確かめた。
「……今になって思う……私はあの小さなレイに背負わせたくないのだ……この重荷を……」
そうして洩らす言葉に、今度は倭が息を飲み込む。
「クライヴ……レイとて、いつまでも小さな子どものままいる訳では……」
「……わかっている……」
苦しげなクライヴの返事に、倭は自分の答えが僅かな緩衝にもなり得ないことを感じ取った。
「……確かに、数年後には大人になる。そなたより大きく、私より強くもなろう。……だが……」
言葉を途切らせ、手に絡め取った倭の髪に顔を埋める。
「……成長したレイに何かを課すのなら、選択のしようもある……己による判断も。だが、このように産まれた時から本人の与(あずか)り知らぬことを、本人の意思とは関係なく、否応なしに背負わせるなど……しかも、私が受け継いだものより遥かに重いものを、だ……」
「………………」
「……このような気持ちになることがあろうなどと、考えてもみなかった。自分では当たり前に引き継いで来たもの……そこに少しくらい上乗せされたからと言って大差ないはず、などと……」
「クライヴ……」
戸惑う倭に二の句を継がせず、クライヴは己の気持ちを吐露した。
「だが、今、レイを見ていて思う。『その時』を迎え、万が一にも力及ばねば、当然あの子に生きる道はあるまい……オーソンが生かしておくなどとは、到底考えられぬからな。そなたや私が手助け出来る状況であれば良いが、保証はない……」
苦しげな表情に、かける言葉を無意識のうちに探す。だが倭には、クライヴの中にいわゆる『父性』が生まれた訳ではないことはわかっていた。彼が抱く気持ちは、我が子だからではなく、自分以外の人間であれば誰に対してでも生じるものなのだ、と。
そのことを、倭は太王太后アリシアの言葉から理解した。彼女の『他人の弱さは知る』と言う言葉から。故に、彼の不安を取り除くことは出来ないまでも、ある程度の安心感を与えられる言葉があるとすれば、それは一つだけだと考えた。
「レイの力がオーソンに及ばぬ、なとど言うことはありえません」
確信に満ちた倭の言葉に、クライヴが視線を向ける。その言葉は決して気休めなどではなく、クライヴと己の持つ力を正しく理解し、見極めた上での判断であった。
「貴方の力と、私の力と、双方全てを持つレイが、他の誰であろうと及ばぬ、なとど、絶対にありえませぬ」
力強い言葉に納得は出来る。だがそれでも、クライヴの心は晴れることはなかった。そんな問題を通り越した上での感情であったから。そして、何より、クライヴのためにと放った次のひと言が、却って逆効果になるなどと、倭は想像し得なかった。
「そのために私は、私の持つ力の全てをレイに譲り渡します……私の何もかもと引き換えても……」
瞬間、倭は勘違いかと思うほどの衝撃を感じ取った。自分の身体を抱えるクライヴのありとあらゆる箇所、その筋肉が、心と共に張り詰めたことを。
「……クライヴ……?」
驚いた倭を、見開かれた洋紅色の瞳が見つめ返している。倭の方が困惑する程に。
この時の倭には、クライヴの懸念に『己の考えが及ばぬ事実』が含まれていることまでは読み切れていなかった。それは、二人の違いが生み出すものであり、仕方のないことでもあったのだが。
「……どうしたのです?」
困惑を隠せないまま、倭は訊ねた。
「……私の方が訊きたい……今のはどう言う意味だ……?」
だが、逆に返って来たクライヴの問いに首を傾げる。
「どう言う意味、とは……何が、でしょうか?」
真実、問われている意味を解していない倭の様子に、肩を掴むクライヴの手に力がこもった。初めて感じる物理的な力の強さに、倭が僅かに眉をしかめる。
「……そなたの言う『何もかも』には何が含まれているのだ……?」
返答には間があった。それは躊躇いや迷いではなく、言うなれば逡巡。クライヴの質問の、真に意味するところを読み取るための、である。
「……何が、と申されましても……言葉の通りにございます」
事実をそのままに伝えようとする倭の声音は、昂りかけていたクライヴの感情を逆なでし、煽った。
「それは、そなたの命をも含んでいると、そう言うことか!」
かつてなく激しくなった語気に、恐れではなく、驚きによって倭が瞳を拡大させる。視線を交えながら互いの心の内を探り、言葉を探す沈黙の中、微かなノックの音が響いた。
『……もし、倭様? 何ぞ、ございましたか?』
様子を窺いに来た五百里の声が小さく重なる。
「大事ない。下がっておれ」
クライヴの腕の中から扉に向かい、何事もなかったように倭が答えると、五百里が遠のいて征く気配。それを確認し、倭は視線を戻した。
「………………」
決まり悪そうに顔を背けているクライヴの横顔を見つめれば、手で口元を覆い、きつい表情を堪らえようとしている。何より、目を合わせようとしないのは、倭の言葉の意味を正しく把握している、と確信してしまったからであった。即答を以ての否定がない時点で、それは是である、と。
「……すまぬ……」
息を吐き出すように洩らす顔には、声を荒げたことに対する後悔が現れていた。微かとは言え、珍しいほど震える声に。だからこそ、倭が告げた言葉の意味を否定したいと堪えていることは、わかり過ぎるほどにわかってしまう。
「……いいえ……」
倭の変わらぬ声音は、己を懸命に抑えようとしているクライヴをさらに揺すぶった。それでも、これ以上、声を荒げないよう必死で堪える。
「クライヴ……私は……」
だが、倭の方も言葉を探しあぐねていた。それでも、伝えなければならないものだけを拾い上げる。
「……貴方から話を聞いた始めから、とうに心を決めておりました」
「…………何……?」
「ご内儀の件がある前から……そう、貴方と初めてお逢いした夜、貴方に協力すると決めた時、どのような形であろうと、私はこの身も命も捧げることになるだろう、と……」
瞬きをとめ、クライヴは倭を見つめた。だが、今、自分の腕の中にいる女の表情からは、何も読み取ることが出来なかった。
「……そのようなことを、いつ、私が……!」
「わかっております、貴方のお心内は……。けれど、私には視えたのです……貴方にお逢いした瞬間に……私は、このために生を受けたのだ、と。……例え、貴方の望み自身は私的なことであっても、それは大極の平らかなることに繋がるもの……それを成すことは、私の存在意義そのものです」
坦々と語る倭に、再びクライヴの表情が険しくなる。
「わかっておらぬ! 私はそなたの命と引き換えにしてまでなどと望んではいなかった!」
それは事実であり、己の命ならともかく他人の命と引き換えにしてまで、などとクライヴが考えるはずもなかった。もちろん、倭がそれを理解していることを、クライヴもわかってはいる。ただ、己を苛む複雑な感情の理由をうまく説明出来ないことが、さらに彼を苛立たせていた。
ほんの僅かなずれもなく、互いを捉え合う視線。
倭は静かに唇を開いた。
「……命はいつか還るもの……」
それは、何度となく倭から聞いていた言葉。だが、感覚的な意味では理解出来ても、根本の捉え方が違うクライヴには、本当の意味で受け入れることが難し過ぎた。
「……要するにそれが“死”であろう……」
そうとしか、認識出来ないもの。
「確かに、肉体は無に……この地に還ります。けれど、魂(たま)は違います……この世の理(ことわり)に還る…………私は、クライヴ……貴方とレイの元に……」
「……もう、良い……!」
言うなり、クライヴは身体を返し、倭に覆い被さった。倭を抱きしめたまま、組み敷いた身体に重なる。
「……抱くことも……触れることすら叶わぬ……それが“死”であろう……!」
苦し気な息と共に吐き出された言葉──それがクライヴにとっての『死』の本質であると、倭は理解していた。しかし、それは、クライヴと逆の観点からの『感覚的な理解』であり、互いの思考の根本的なものとなっている核を理解し合っている訳ではなかった。
二人が正しく理解しているのはひとつだけ。互いが互いの存在意義のある一番深い場所を、誰よりも理解し、わかり合える相手である、ことだけ。それは、男と女としての情愛と完全一致はしない。
協力を仰いだ責任感が皆無だった訳ではなくとも、クライヴが倭の元に留まる時間は長かった。本来なら母国にいても良いはずの時を、出来得る限り倭とレイの元で過ごしている。
しかも、ひとたびレイと言う目的──子を設けた後、二人が男と女である必要は微塵もなく、にも関わらず、クライヴと倭は褥を共にしていた。そこに倭が疑問を呈することも、拒むこともなかったからではあるが、もし、倭がそれを拒めば、クライヴは強行するつもりなどなかったし、だからと言って契約の誓いを破り、他の女を引き入れるつもりもなかった。
「……他に方法は……?」
倭の首筋に顔を埋めたまま、クライヴがひとり言のように問う。
「……何かないのか……」
答えのない間が、クライヴに『可能性』を示唆した。本当にないのであれば、倭は即答しているはずである、と。
「……あるのだな……? 倭……何か方法が……」
天井を見つめて微動だにしなかった倭が、小さく息を吐き出した。
「……どんなことがあろうと、私にはその法を使う意思はありませぬ」
僅かに起こした身体を肘で支え、クライヴが倭の顔を見下ろす。揺るぎない、その表情を。
「レイが女子(おなご)であったなら、もしかしたら私の力の全てを、何事もなく直接的に受け取ることが出来たのかも知れませぬが、男子として生を受けました。……いえ、きっと、あの子は男子でなければならない運命(さだめ)だったのです」
クライヴには、倭の話の征き先が見えなかった。
「……どう言うことだ……?」
訊ねるクライヴの顔を真っ直ぐに見上げ、倭はひと言で答えた。
「だからこそ私は、私の父と母以上の禁忌を犯すつもりは毛頭ございませぬ」
その一瞬、クライヴの中で、思考しようとする動力の全てが止まった。
〜つづく〜
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
