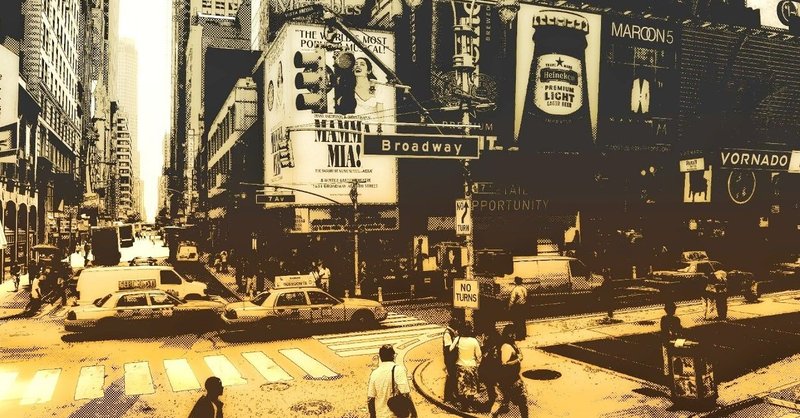
はじまりの日2~社内事情シリーズ~
〔里伽子目線〕
*
その人の名前だけは
決して忘れないようにしようと思った
*
ある夜、課長と食事している時のこと。
「そう言えば、里伽子。ひとつ訊いていいか?」
「はい?」
不意に思い出したような質問に首を傾げる。
「不思議に思ってたんだが……」
「はい」
「初めてきみと食事した時のことを憶えてるか?(※注・『課長・片桐廉〔3〕』&『里伽子さんのツンテケ日記〔3〕』参照)」
「もちろんです」
「あの時、名前のことも話したの憶えてるか?」
そう言えば、家族構成とかスポーツ以外にそんな話もしたっけ。
「はい」
それが?
「いや……あの時、きみ、やけにおれの名前の意味を詳しく知ってただろ? それが何となく不思議だったんだ。あんなに覚えてるもんか、って……」
私は思わずむせそうになった。だけど、そこは鉄仮面で凌ぐ。だって課長のことだから、何か深読みしそうになってるのは間違いない。迂闊なことは言えないわ。
「いえ? たまたまですよ? 他にもいくつか意味を丸暗記してる文字ありますし」
わー。課長の目がめちゃくちゃ疑ってる。何だか可愛いくらいに。(心の中でニヤニヤ)
ん……でも、これはちょっと言えないわね。
にっこり笑い、お代わり頼んで誤魔化して、私は昔に思いを馳せた。
*
「あれ? お母さん? え、お兄ちゃんたちまでいない……」
父の仕事の都合で渡米していた10歳の頃。私はアメリカでも、出来るだけ欠かさないように習い事に通っていた。
その日は日舞のお稽古。向こうでは先生を見つけることも難しく、都合を合わせるのも大変だったけど、私は運良く続けることが出来ていた。
迎えに来てくれた母と兄と弟。買い物に寄った先で、ほんの少し他に気を取られた隙に、私ははぐれてしまった。
「え~皆、どこ行っちゃったんだろう……って言うか、ここ、どこら辺なんだろう……?」
辺りを見回しても、見覚えのある建物が見当たらない。何だかひと気も少ない気がする。一応、英語は話せたけれど、少しずつ不安になって来る。
あちこち、うろうろ歩き回り、お稽古の後の草履ばきで足がだんだん痛くなって来ていた。もう歩けなくて立ち止まり、途方に暮れていたその時。
「 What's the matter ?」
突然、声をかけられ、振り返った私の目に飛び込んで来たのは、陽に焼けて逞しい、背の高いかっこいいお兄さん。顔立ちから東洋人、それも恐らく日本人だとすぐにわかった。
『……あの……お兄さん、日本の方ですか?』
でも、一応、英語で訊ねてみた。もしかしたら、東洋系ってだけの可能性もあったから。
今、思い返せば全くの勘でしかなかったけど、何故かあの時の私は確信を持っていた。国籍に関係なく、そのお兄さんは絶対にいい人だ、って。だから、警戒心もなく、妙なくらいにほっとしていた。
「そんな格好だから、もしや、とは思ったが……きみも日本人か?」
少し驚いた顔をしながらも、今度は日本語。私が頷くと、お兄さんは周囲を見回してから視線を戻した。こっちがびっくりするくらい、真っ直ぐな目だった。
「こんなところで何してるんだ? そんな格好でひとりでいたら、いくら比較的治安のいい場所でも危ないぞ」
「習い事の帰りに買い物に寄って……家族とはぐれてしまいました……」
私があまりに哀れっぽかったのだろう。お兄さんは眉尻を下げた。
「どこではぐれたんだ?」
「……え~と……」
住所がわからなくて、知ってるお店の名前を手あり次第挙げてみる。
「あ~そりゃ、通りニ本間違えてるな。結構、距離あるから連れてってやる」
ありがたい言葉には後光が差してるように見えたけど、そこで私はまた困ってしまった。
「どうした?」
うつむいた私を、お兄さんは心配そうに覗き込んだ。
「……足が痛くて、もう歩けません……」
ホントにもう限界で、実は立っているのも辛かった。でも、こんなとこでしゃがみこんだらダメだ、ってことだけはわかってたから、かなり必死で立っていたのだ。
すると、お兄さんは少し考える様子を見せ、突然、私を抱き上げた。
ううん。『持ち上げられた』と言った方が正しいと思う。でも、その手つきから、私の着物を出来るだけ着崩れないようにしてくれていることだけはわかった。
「ごめんなさい、お兄さん……」
「いいって。気にするな。軽いもんだ」
おとなっぽい雰囲気。中学生なのか高校生なのか、兄の奏輔(そうすけ)よりは少し歳上だろうか。でも、このお兄さんもこんなところにひとり、何をしていたんだろう、と不思議に思う。
(英語上手だし、道も詳しいし、もしかしてこの辺に住んでるのかな?)
そんなことを考えていると、あっという間に見覚えのある場所に着いていた。
「ここらで待ってれば見つけてもらえるだろう」
「はい」
待ってる間も、お兄さんはずっと私を抱いていてくれた。
「お兄さん、ホントにありがとうございます。あの……今度、ちゃんとお礼をしたいので、お名前と住所を教えてください」
そしたら、真面目な顔で考え込んだお兄さんは、少しして優しい笑顔を私に向けた。うまく言えないんだけど、お兄さんの笑顔は私の目にキラキラに映った。
「……そうだな……」
その後、笑顔のままのお兄さんの口からは、名前も住所も出て来ず、不思議な言葉が飛び出した。
「いつか逢えた時でいい。その時までに、絶世の美女になっていてくれ。美女になったきみと再会した暁には、礼にキスのひとつもプレゼントしてくれ」
この言葉に、私はまた困ってしまった。だって、お兄さんが思うように綺麗な人に、私がなれるかなんてわからない。そしたら、いつか逢えても、私はお兄さんに何のお礼も出来ないんだ、って。
「どうしたんだ?」
どうしていいのかわからずに考えてる私に、お兄さんがまた心配そうな顔をした。その目を見た時、私の頭にひとつアイデアが浮かんだのだ。
私はそっとお兄さんの顔を手で挟んだ。驚いたような、不思議そうな表情を浮かべるお兄さんを見つめ、私は顔を近づけてキスをした。
息を飲む音が聞こえてお兄さんが身動ぎひとつせずに固まり、私は足の痛みも忘れ、時間が止まったような気がしていた。
(きっと、このお兄さんにはまた逢える)
根拠のない自信と確信が、私の頭の中を占領する。
「約束の印に少しだけお返しします。いつか綺麗になって、必ずお兄さんに残りのお礼をしますから」
唖然としているお兄さんに、私はそう断言した。今、思えばホントに根拠のない子どもの戯言だ。だけど、お兄さんは笑ったりしなかった。
「……ああ。楽しみにしてる。ぜひ、絶世の美女になって、おれの前に現れてくれ」
真面目な、それでいて優しい顔で頷き、そう言ってくれた。そして、そっと私を降ろし、とびきりの笑顔もくれたのだった。と、その時──。
「あっ! お母さん!」
道の向こうに母たちの姿。
「お。じゃあ、もう大丈夫だな。気をつけろよ」
名前も言わず、そのまま立ち去ろうとするお兄さんに私は慌てた。
「お兄さん、ありがとうございました! でも、名前だけでも教えてください!」
もう一度お礼を言い、そして訊ねると、お兄さんは少し離れたところからちょっとだけ振り返って笑ってくれた。けど、名前を教えてくれようとはしない。焦る私の目に、お兄さんの向こうから近づいて来る、違う男の人の姿が映った。
「こんなとこにいたのか、れん! 行くぞ!」
はっきり聞こえたその人の声。
「悪い、兄貴! 今、行く!」
お兄さんが応えたのも聞こえ、名前は『れん』と言うのだと知った。
「……れん……」
私はその頃から忘れっぽかったのだけど、その人の名前は忘れないようにしよう、と何度も口の中で唱えた。
「里伽子! 探したんだぞ!」
小さくなるお兄さんを見送る私の背に、兄の声がぶつかる。
「お兄ちゃん」
「大丈夫か? 何もなかったか?」
「うん」
ほっとした顔の兄に、弟の手を引いた母が息せき切って追いついて来た。
「里伽子! 心配したのよ!」
「ごめんなさい、お母さん。道がわからなくなっちゃって……」
「だから、はぐれないように言ったのに……でも、よくここにいてくれたわ。良かった」
心底、安堵する母たちに、私は日本人のお兄さんが助けてくれたことを話した。
「あら、まあ、そうだったの。お礼も言えずに申し訳なかったわ」
残念そうに言う母に、私はお兄さんとの約束のことは言わないでいた。何となく、お兄さんと私だけの秘密にしておきたかったのだ。
その夜、私は母に、綺麗なおとなになるにはどうしたらいいのか訊ねた。母がキョトンとした顔で私を見つめる。
「そんなこと心配しなくても、里伽子は綺麗になるから大丈夫よ~」
……すぐにいつもの笑顔に戻ると、私が望んでいることと全く違う、親バカ全開の回答しかくれなかったので、早々に諦めて質問を変えた。
「お母さん。“れん”って言う漢字はどのくらいあるの?」
「いっぱいあるわよ」
……またもや、母の回答は私の望むものになっていない。
「う〜んと……名前で使われるような字は?」
「名前? そうねぇ……一般的なら……」
考え込んだ母が挙げてくれた字は『連 蓮 漣 鎌 廉 簾 錬』の七つ。
「とは言え、もっと難しい字を付ける人もいるだろうし、到底、素直には読めない字の人もいるだろうし……何とも言えないわよ?」
「ううん、大丈夫。ありがとう、お母さん」
一般的に『名前に使われそう』と言うくらいでも七つだ。全部となれば、到底、覚え切れそうもないほどたくさんあり、母が見ている漢和辞典を覗いただけでクラクラしそうだった。この七文字の中に、お兄さんの名前がある、と信じるしかない。
ちなみに、この時の私に『平仮名かも知れない』などと言う考慮はなかった。
部屋に戻り、私はその七つの“れん”の意味を、ひとつひとつ全部書き出した。それから毎日、寝る前に読み返し、ひとつひとつ覚えて行ったのだった。
それはいつしか記憶に定着し、20年経った私の中にもしっかりと残っていた。……あくまで、意味だけは。
*
それがホントに功を奏するなんて……まあ、当時の私は真剣に信じていたワケなんだけど、今となっては驚きだ。『虚仮の一念岩をも通す』と言ったところか……いや、ちょっと違うか。
でも、今ならわかる。
あの時、『おにいさん』が言おうとしてくれていたことの本当の意味が。
『礼なんて考えなくていい』
『きっと、もう二度と逢うことはないだろうから』
そう思って、冗談めかして言ってくれたのであろうことが。
けれど、そこまで読み取るには、私はあまりに子ども過ぎて、尚且つ考えが回らない性格だった。それを知ってか知らずか、『おにいさん』は呆れたり笑ったりせず、ただ真っ直ぐに受け止めてくれたんだ、ってことも。
まあ、それにしてもアレだ。そこまでは良かったけど、詰めが甘いところがやはり私だ。課長の名前を初めて知った時、少しもピンと来なかったって、もはや笑えるレベルでホントに如何にも私すぎる。
そうは思いながらも、まだ怪訝な表情で視線を向けて来る“廉さん”をスルーして、私はお代わりのワインを飲み干した。
~おわり~
*
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
