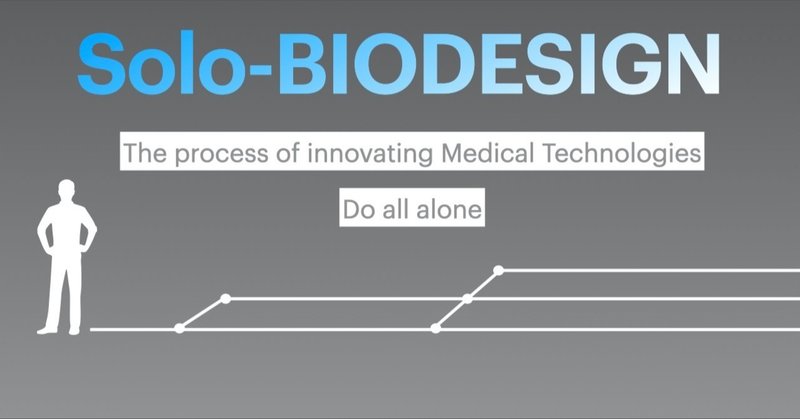
ひとりBIODESIGN 疾病の基礎5
今回はBIODESIGNの疾病の基礎の章の疾病生理学で取り上げられている「疾患の進行過程」を糖尿病を題材として実践していく。
以前の記事の続きとなるため、興味がある方は、こちらの記事も読んでみてほしい。
さて、糖尿病の進行過程だが、1型糖尿病と2型糖尿病は分けて考える。なぜならば、発症までの機序が少し異なるからだ。
1型糖尿病の場合、3つのタイプに分けられており、激症、急性発症、緩徐進行の分類がある。激症の1型糖尿病は、ウイルス感染などがきっかけとなり、数日間で膵β細胞が破壊されていく。症状は「日」単位で進行していき、高血糖に伴う症状が出現して、平均4日のうちにインスリン治療が必要となる。急性発症型は、自己免疫機序によって、膵β細胞が「週〜年」単位で進行していく。β細胞が正常時の20%以下に低下した際に、高血糖に伴う症状が出現して、糖尿病として発見される。高血糖が出現してから、インスリン治療が開始されるまでの期間は、約5週間らしい。緩徐進行型は、「年」単位でインスリンの分泌能力が下がっていく。
2型糖尿病の場合、遺伝因子などでインスリンの分泌が少ない「インスリン分泌障害有意」である場合とインスリン抵抗性が高い「インスリン抵抗性有意」である場合、またその中間のタイプがある。いずれのタイプであっても、過食や運動不足、ストレスなどが原因でインスリン抵抗性が高くなった時に、糖尿病が発症する。正し、インスリン分泌障害が大きな「インスリン分泌障害有意」な人は、軽度な肥満で発症し、「インスリン抵抗性有意」な人は、高度な肥満のときに発症するという違いがある。
1型糖尿病、2型糖尿病いずれの場合でも、糖尿病であることが判明した場合には治療が行われることになる。しかし、食生活や生活習慣の改善がなされない、血糖管理が適切に行われない場合は、インスリン抵抗性が徐々に上がっていき、高血糖状態の時間が長くなっていく(もしくは常に高血糖状態)。すると、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害、動脈硬化症などの合併症を発症することになる。
合併症となった場合には、そちらの治療も同時に行わなければならず、QOLが大きく低下する場合もある。例えば、糖尿病腎症が進行すれば、週に3回通院して1回4時間程度の透析を行わなければいけなくなる。。。
さて、まだまだ調べなければいけない部分は残っているだろうが、一旦BIODESIGNの疾病生理学の実践は終了したとする。今後の章で必要なときに追加で調査を行い、不足分を補うことにしよう。
最後に疾病生理学でのプロセスをまとめると、下記の様になる。
①正常な臓器などの機能を知る
②疾病がどの様に機能に影響するのかを調べる
③病気を特徴づけるリスクファクターとの因果関係を調べる。
④疾病の進行について調べる
この様な順番で興味のある疾病に対してアプローチを行えば、システマチックに知識を得て、情報を整理できるはずだ。医療関連の仕事をしている方、医療に関係のある勉強や研究を行っている学生は、試してみてはいかがでしょう。
次回は「臨床症状」に関しての説明と実践を行っていく予定である。ここまで読んでくれた読者の方、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
