
『駅前・噴水・絵描き』
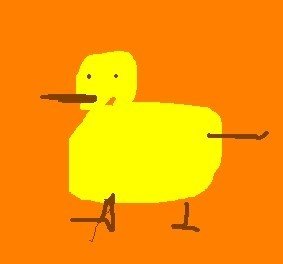
「本当にイイ女というのは、ルックスや経済力で男を選んだりしない。才能に魅かれるんだ」
ボクが学生時代バイトしていた、『マキコ』というクロワッサン専門店で働いていた、先輩のサイトウさんが、そう言っていた。
サイトウさんが言うには、人間を含め、すべての生き物には「優秀な子孫を残す」という目的があり、そのタメにはお金より、見た目より、才能をチョイスするのがベストなんだとサ。
そう言うサイトウさんは才能どころか、お金にも見た目にも恵まれない、30過ぎて、チェリーのフリーターだったので、みんなから『チェリーター』と呼ばれていたのだが……。
*
その年の夏、弟のお気に入りプレイスは駅前の噴水だった。弟はまるで、家庭用ビニールプールで遊ぶような感覚で、噴水を使っていた。
この街の住民性が、おおらかだったのか? 時代がまだギリギリ昭和だったので、野性児に対するキャパシティーが、今よりも広かったのか? それをとがめる人は誰もいない。
スッ裸で噴水の中、他人には見えない何かと対決しているかのように暴れ回る弟のことを、ボクと、近所に住む同じ年頃の女の子『キャンディー』ちゃんは、噴水の縁に腰掛け、足だけ水につけながら眺めていた。
「見てみて、あの子マンモスかわいくな~い?」
女子高生たちが、弟のことを指差しながら通りすぎていく。『MIKI HOUSE』のモデルみたいなルックスだった弟は、とにかく可愛がられ、ウーパールーパー並にチヤホヤされた。
それと比べてボクは、実の親にさえ『寝起きのブルドッグ』と比喩される風貌の持ち主だったタメ、うかつに「可愛い」などとお世辞をいうと、逆にイヤミになってしまう恐れがあるので、みんな気を使い、「貫禄がある」とか「耳の形がいい」とか苦し紛れのことを言ってほめた。
弟は、この日もキャンディーちゃんの、
「ウチのプールに遊びに来ない?」という誘いを、
「おまえん家のプールなんかよりも、噴水の方が大きいやい」
とツレナイ態度で、断って来たところだった。
確かにプールと言っても、キャンディーちゃん家にあるのは、ネコのイラストが付いた子ども用ビニールプールだったので、噴水の方が楽しいのかもしれないけど……。
ビニールプールさえも置くスペースのないアパートに住むボクらと比べれば、庭付き一戸建てに住むキャンディーちゃんは、お嬢様と言ってよかった。性格もよく、友達も多かったのだが、いつの頃からか弟のことを気に入り、付きまとうようになっていた。
「暑いわね。お肌が焼けちゃう。日傘持ってくれば良かったわ」
この年頃の女の子は、オマセで大人のマネをしたがるものだ。本当は日に焼けることを、気になどしちゃいないのだが、そんなこと分かるはずもない当時のボクは、
「……日陰」
と、駅のまん前の、日陰になっているスペースを指した。
「あら、そう。それじゃあアチラヘ移りましょうか」
キャンディーちゃんに腕を引かれ、ボクは弟を噴水に残し、日陰へ移った。
「やあ、風時くん。元気かい?」
駅前の路上で、いつも夕方5時ごろから似顔絵を描いているお兄さんが、声をかけてきた。弟の名前と間違えているがボクはそんなこと気にしない。しかしキャンディーちゃんは、そういう訳にはいかないらしく、
「違いますわ。この子は風時じゃなくて、草慈くんの方よ」と訂正した。
「ハハハハッ。そっかそっか、ゴメンゴメン」
お兄さんがゴマカシ笑いを浮かべると、歯茎が“ニュッ”と見えた。お兄さんは、いつも路上で絵を描いているのに、日に焼けず色白で、やせっぽち、髪は適当に伸ばしているだけの、なんて言うか……、『ブ男』としか言いようのない人だった。
「絵……、見せて」
ボクはお兄さんの手にしている、クロッキー帳をのぞき込んだ。お兄さんは、日に1人か2人ぐらいしかいない似顔絵のお客さんを待つ間、駅周辺の光景を自分の好きなようにスケッチしていて、ボクは似顔絵よりも、ソッチの絵の方が好きだった。
開かれたページには、噴水で遊ぶ弟と、縁に座りソレを眺めている、ボクとキャンディーちゃんの姿が描かれていた。
「まあ、素敵なイラストですこと。ぜひコレを私にゆずってくださらない?」
キャンディーちゃんは、首から提げていたディズニーのキャラクターの形をした小銭入れから、お金を出そうとした。
「むほほほ。いいよ、いいよ。お金はいらないから」
お兄さんは独特の感じで笑いながら、キャンディーちゃんを制すると、クロッキー帳のページを剥がして絵をキャンディーちゃんにあげた。
剥がしたページの下から出てきた絵を見て、
「わぁ、キレイな人。誰?」
キャンディーちゃんが、そう言った。
絵は遠目から見た女性の全身像と、その周りの風景を描いたものだった。スラッとしたその人は、なんとなくお嬢様とかお姫様といった感じのする人だった。
「ああ、これかい? コレはホラ」
お兄さんが視線を向けた先に、イラストと同じように女の人が立っている。
「彼女いつも待たされてるんだ。今日も、もう1時間ぐらい待ってる」
携帯電話どころかポケベルさえもない時代、待ち合わせに相手が遅れた場合、人はただ待つしかなかった。
「ねえ、この絵あの人にあげましょうよ。きっと喜ぶわよ」
「むほ、ほほほほほほほ。やめてくれよ。そんなことしたらボクがあの人の事をコッソリと観察しながら、しかもスケッチしていたというのが、なんだか、なんと言うのか、人によってはウス気味悪いと思うかも知れないじゃないか」
この時代、まだ『ストーカー』という言葉がなかった。(あったかも知れないが、誰もそんな言葉使ってなかった)
「そんなことないわよ。こんな素敵な絵だもの、きっと喜ぶわ」
「むほほほほほほ。いいから、いいから」
そうこうしてる間に、背の高い、今考えればおかしな格好だが、当時としては流行のファッションに身を包んだ男の人が現れ、女の人と一緒に去っていった。
「あ~ぁ、残念」
キャンディーちゃんは、そう言った。
*
翌日も、ボクと弟が駅前の噴水に遊びにいこうとすると、どこからともなくキャンディーちゃんが現れ、ついてきた。
遊んでいるうちに、みんなでアイスクリームが食べたいという事になり、ボクらは噴水の中に落ちている小銭をかき集めた。
(ボクの知っているかぎり、日本中どこへ行っても噴水の中に小銭が投げ込まれているが、世界中そうなのだろうか?)
しかし、ほとんどが1円玉か5円玉で、いくら集めても3人分のアイスは買えそうにない。
「おまえ、いっつもおこづかい貰ってんだから、おまえの金で買おうゼ」
弟がそう言うと、キャンディーちゃんは「ベー」と舌を出し、
「残念でした。きょうは私お金持ってないもんね。たとえ持ってたとしても、なんで私のお金でアンタ達にアイス買わなきゃなんないのよ」
と言い、ボクに向かって、
「今日は月刊『美少女コミック』の発売日だったのよ。今月号の付録は『プリンセスブローチ』だったから、絶対買い逃す訳にはいかなかったのよ」
と、事情を説明した。
「しょうがない。こうなったら、山下におごってもらうか」
弟は、似顔絵描きのお兄さんの方へ視線を向けた。お兄さんの名前が、山下なのかどうかは定かでないが、弟は絵描き=裸の大将『山下 清』というイメージから、勝手に山下と呼んでいた。
「むほほほほほ、ダメダメ。古今東西、売れない絵描きっていうのは、例外なくド貧乏って決まってんだから、アイスなんておごれないよ」
お兄さんは、ムリムリといった感じで手を振った。確かにお兄さんの身なりからは、貧乏の匂いがプンプンする。
「じゃあさー、お客さん連れてくるから、そしたらおごってよ」
「そりゃ、お客さん連れてきてくれたらアイスぐらいおごってもいいけど。でも一体どうやって?」
「つかまえてくる」
弟は駅前の人混みのなかへ駆け込んでいくと、何人もいる人の中で、ワザワザいかにも、といった感じのパンチパーマおじさんに声をかけた。お兄さんはそれを見て、思わず、
「Bad choice!」と叫んだ。
弟の連れてきたパンチが、お兄さんのことを睨みつけるような姿勢で、イスに腰掛ける。
お兄さんは、青ざめながら似顔絵を描いている。
「おい、兄ちゃん。ええ度胸してるやないか。いったい誰に断ってこんな所で商売してんねん」
「ヒー、すいません、すいません」
パンチは、お兄さんのことを恐がらして楽しんでいるように見える。
「精一杯、ウマー描けよ。もし似てなかったら、ワレどーされても文句言われへんからな」
「ヒーッ」
お兄さんの筆先がガタガタと震えた。
10分後、できあがった絵のパンチはチョットやりすぎなぐらいに美化されていて、似顔絵と言うにはあまりにも原形とかけ離れていたが、パンチはそれをえらく気に入り、
「おまえ、なかなかスゲーやつだな。ゼッテー才能あるよ」
と、お兄さんの事を褒め、
「オレは○○組の××だ。何かあったら、いつでもオレん所へこい」
と言いのこし、満足げに去っていった。
「ふぅー」
グッタリとため息をつくお兄さんに向かって、弟は、
「山下、ダメじゃん。料金もらってないよ」と、せめた。
「なに言ってんだよ! 金払えなんて言えるわけないだろ。それに、なんでよりにもよって、あんな人連れてくるんだよ!」
「ケッケッケッケッケッ」
怒るお兄さんのことを見て、弟はうれしそうに笑った。
「ゼッタイわざとだよね? あんな人、連れてきたの?」
キャンディーちゃんの質問に、ボクは黙ってうなずいた。
「でも、すごいわよ。あの人のこと、納得させたじゃない」
キャンディーちゃんが褒めると、お兄さんは照れくさそうに笑った。
「ねぇ、次はあのヒトに声をかけましょうよ」
キャンディーちゃんが指をさした先には、昨日と同じように、お姫様みたいな女の人が、立っていた。
「い、いや。もうやめとこうよ」
あまりノリ気でない感じのお兄さんの事を無視して、弟は、
「次こそは、アイスGET」
と言い駆け出し、女の人に声をかけた。女の人がコッチをみて、ニコッと笑うと、お兄さんは固まった。
「前から、ここの似顔絵、気になってたんですよ」
イスに腰掛けた女の人にそう言われ、向かいに座るお兄さんは、「そっ、そ、そ、そ、そそっ、そうですか」
と、明らかにパンチを相手にしていたときよりも、緊張しているようだった。
「キレイに、描いてくださいね」
「はっ、はい!」
お兄さんが、紙にペンを入れようとしたその時、
「おい、何やってんだ。行くぞ」
後ろから声が掛かり、見ると女の人の連れの男が立っていた。
「ちょっと待ってよ。似顔絵描いてもらおうと思って」
「もう時間ねえんだし、別んときでいいだろ。ほら行くぞ」
男は女の人の腕を掴み、やや強引に連れていった。
「ああ、アイスが……」
「……」
「残念ね」
弟と、お兄さんとキャンディーちゃんは、ガッカリとしたようすで、女の人の後ろ姿を見つめていた。
* *
絵描きはいつも、夕暮れから深夜のコンビニでのバイトが始まるまでの数時間、駅前で似顔絵を描いていた。
美術の学校を出て5年。当時はフリーターという生き方が認知されていなく、バイトの収入で暮らす絵描きは無職という肩書きになる。まわりが「バブルだ好景気だ」とうかれているなか、アイスクリーム買う金も、学歴もないブ男はゴミ屑同然だった。
「…………」
絵描きは駅の時計に目をやった。そろそろ道具をしまい、バイトにいく準備をしなくては。
「あの、……すいません」
声の方に振り向くと、夕方、似顔絵を描きかけたお姫様が立っていた。
「……、は、ハイ」
声がウラがえってしまい、絵描きは心の中で、自分のことを罵った。
「絵、描いてくれません?」
「も、も、も、も、も、もちろんです。ド、ドーゾ座ってください」
お姫様は、ニコッと微笑み、折り畳みの小さなイスに腰掛けた。
震える手で描き上げた絵をみて、絵描きは迷った。納得できる出来じゃなかったからだ。似顔絵を描くときはいつも、実物よりもチョットだけ良くなるように意識して描く。しかし、この絵は良くなるどころか、実物の良さをちっとも表現出来ていない。
「あ、えっと、あのー」
上手く描けなかったと説明して、絵を渡すのを断ろうか? 絵描きはそんなふうに考えたが、お姫様が、
「素敵な似顔絵。ありがとうございます」
と言ったので、つい渡してしまった。
お金を払い、立ち去るお姫様。絵描きはもう一度駅の時計に目をやった。バイトは遅刻決定だった。
バイト先で社員に怒られ、絵描きは申し訳なさそうに謝りながらも、心の中では遅刻したのはしょうがないと思っていた。自分には仕事よりも重要なことがある。そっちを優先させたまでだ。
それにしても、あの絵はいただけない。もっとよく描けるはずだ。
「……あの」
絵描きは恐縮しながらも言った、
「今日、早引きさせてくれませんか?」
「バカかテメーは! クビにすんぞ」
*
翌日、いつものように駅前に現れた絵描きは、彼女がくるのを待った。
バイトが終わった後、寝ずに彼女の似顔絵を描き直したのだ。達成感というか、充実した感じが強く、疲労も眠気も心地よく感じた。
噴水では、いつもの子どもたちが遊んでいる。そのうち遊びに飽きて、こっちにチョッカイをだしに来るだろう。
そろそろ、彼女があらわれる頃だ。そして彼女は、いつも待たされる。
駅前にやってきた彼女は、すぐに絵描きに気づき、目が合うと軽く会釈した。
この時点で、絵描きは怖じ気づいた。頭の中、なんどもやったシミュレーションでは、彼女に近づき、「昨日の絵は、あまりよくなかったので、描き直したんです」と説明し、新しい絵を渡す。ただそれだけ、簡単なことだと思っていたが、今はすべてにたいする自信がなくなり、そんなこと出来そうになかった。(おかしな行動じゃないか?)(描き直した方の絵も、結局は大したことないんじゃないか?)(オレは、みっともないナリだし……)そんなことばかりが頭をよぎる。
「きのう、ありがとうございました。すてきな似顔絵」
気がつくと、彼女がすぐそばに立っていた。絵描きは〃ハッ〃として、飛び上がるように立ち上がった。
「ああ、あの、その。よ、よくないんです。あの絵」
「……?」
お姫様がクビを傾げる。
「こ、こ、こ、コレ」
絵描きは、画材と一緒に置いていた、大きめの封筒をお姫様に渡した。
「……?」
お姫様が封を開けると、中から絵が出てきた。絵描きが寝ずに、全力で描き上げたお姫様の肖像画。
それを見て、お姫様の顔がほんのりと赤くなった。
その日から、絵描きとお姫様は、毎日会話を交わすようになった。大抵は天気のこととか、……天気のこととか。まあ、大して話すこともなく、会話が盛り上がるワケでもなかったが、時にはお姫様が、飼っているイヌのことを楽しげに話したり、お兄さんが、好きな画家のことを熱く語ったりもした。
その内に、子どもたちがやってきて画家の周りが賑やかになる。画家もお姫様も、子どもに対してとても優しく接していたので、子どもたちは、よくなついていた。
暑い中、汗だくになって遊ぶ子どもたちに、お姫様がジュースを買ってあげたとき、一緒に絵描きの分も買ってきた。すると絵描きは次の日、お金がないくせに見栄をはり、子どもたちとお姫様にジュースをおごり、1日晩ゴハンを抜いた。
いつも待ち合わせに1時間ぐらい遅れて彼氏が来ると、お姫様は彼氏に気を使ってか、子どもと遊んでいた風を装った。
お姫様が、
「あの子たち、かわいいでしょ」
と言うと、彼氏は、
「おれ、子ども嫌いだから」
と答える。お姫様の彼氏はそういう男だった。
*
ある日の晩。絵描きが似顔絵をそろそろ切り上げて、バイトに向かおうかと思っていたとき、デートを終えた? お姫様が1人で駅へ戻ってきた。
ショゲクリかえった感じのお姫様。赤くなった目元が、泣いた後だということを物語っている。
絵描きはそれを見て、『描きたい』と思った。
うつむきながら絵描きの横を通りすぎ、改札へ向かって歩いていくお姫様。その背中に向かって、絵描きは思わず、
「似顔絵、描いていきませんか!?」
と声をかけていた。
一生懸命、筆を走らせる絵描きと、モデルのお姫様。2人の間に、会話はない。途中、お姫様の瞳からポロポロと涙が落ちた。
その美しさに、絵描きは女性としてというレベルを超えた、被写体としての魅力を感じていた。
彼と別れたことに対して掛ける、なぐさめの言葉も、あなたの瞳がどれほど美しいかと伝えるキザなセリフも言えない。自分はただ描いて表現するしかない。絵描きの筆に力がこもった。
* *
「明日から、また幼稚園始まるの。だから今みたいに、ずっと一緒には遊べなくなるわ」
8月の終わりにキャンディーちゃんが言った。
「これ、あげる」
キャンディーちゃんは、ボクに可愛らしいイラストの付いた卓上カレンダーをくれた。
「見方わかる?」
そう聞かれ、ボクは首を横に振った。
「この赤い、いちばん端の列が日曜日で、幼稚園休みなの。だから朝から一緒に遊びましょ」
「なんでオマエと朝から一緒に遊ばなきゃなんねぇーんだよ。ブス」
弟が口を挟む。
「うるさいわね。アンタに言ってんじゃないわよ。草慈くんに言ってるんでしょ!」
「な、なんだよ。草慈と遊ぶっていうことは、俺と遊ぶっていうことになるだろ」
「アンタ、なにか勘違いしてるかも知れないから言っとくけど、私は別にアンタなんかと遊びたくないのよ。草慈くんのことが好きだから、一緒に遊んでるだけよ!」
真剣な様子で言ったキャンディーちゃんの発言に、ボクらは戸惑った。世の中10人中1人か2人は、富士山よりも阿蘇山のほうが好きだと言う人間がいる。大人になった今なら自然に理解していることだが、この頃のボクらからしてみれば、はじめて会ったそういうタイプの人だった。
「……」
「……」
「日曜日……、月曜日……、火曜日……」
弟とキャンディーちゃんが黙ってしまったので、ボクは意味はないが、とりあえず手にしたカレンダーの曜日を読み上げてみた。
「草慈くん。時計の見方は分かる?」
「……わかんない?」
「いっつも3時ぐらいに幼稚園おわるのよ。だからその後からなら遊べる――」
ボクはその日、時計の見方もキャンディーちゃんに教えてもらった。
*
夏が終わると噴水で遊ぶこともなくなり、ボクらはしばらくの間、駅前へ行かなかった。
久しぶりに駅へ行ったときには、絵描きのお兄さんの姿はなく、その後お兄さんの姿を見かけることも、いつも待ちぼうけをくらっていた優しい女の人を見かけることもなかった。
*
自分の能力に限界を感じたとき、あきらめることが出来ればどれほどラクだろう。人の能力にはソレゾレ限度がある。若いときにはソレが分からないので、アレやコレやといろんな夢をもつ。やがて努力だけでは超えられない自分の限度を知り、その中で出来るだけいい状況をたもとうと頑張る。それが大人になるという事なのだろう。
しかし、中には自分の夢をあきらめきれず、才能の限界を打ち破ろうと、いい歳してティーンエイジャー並みに悩み、もがき、苦しむ人がいる。
10年以上も経ってから、ある雑誌にお兄さんが載っているのを見つけた。
お兄さんはある晩、魅力的な女性の似顔絵を描いたが、自分の能力が未熟で、その魅力を表現出来なかった。それが悔しくて悔しくて、そのことをキッカケに前から考えていた海外に絵の修業に行く計画を実行したのだそうだ。
お兄さんは大したお金も持たぬまま、ステディーな関係目前の女性をほったらかしにして、エドワード・ホッパーというアメリカ人の画家が好きだったので、NYに渡った。
雑誌に載っていた、写真のお兄さんは、顔面自体は変えようがないが、格好はわりとオシャレにきちんとしていた(させられている様にも見えるが)。
おいていかれた女の人は、今度はただ待つだけでは無かったみたいだ。お兄さんのヨコで、相変わらずキレイで、やっぱりお姫様みたいな女の人が笑っていた。
この時になってようやく分かったことだが、お兄さんの名前は『山下』でなく、『谷』だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
