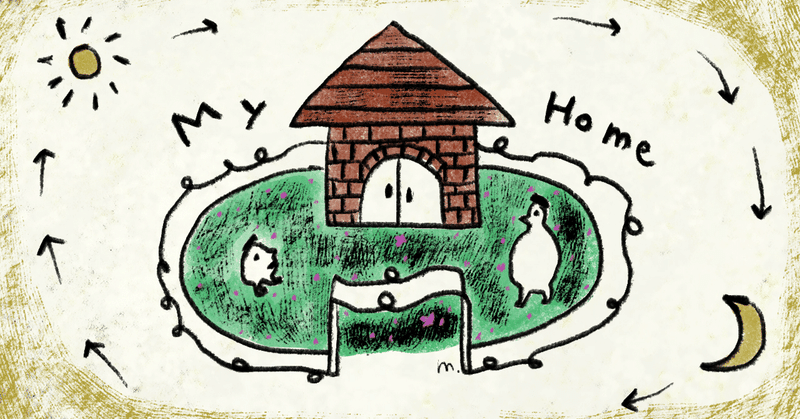
2年縛りどころじゃない!10年以上縛りの住宅ローン控除
菅内閣の時代だったでしょうか?携帯・スマホのキャリアによる2年縛りがなくなったのは・・・庶民に寄り添った非常にありがたい改革だったと思っております。
一方で、人生で一番大きな買い物といわれるマイホーム購入に伴う住宅ローン控除は、その選択を一度誤ると、2年縛りどころではない10年以上縛ってしまう可能性があります。
※Noteはこのような素敵な画像を選べるのですね。感動しました。
1.確定申告を間違えたとき
タイトルからして話題が逸れていそうな印象をもたらしますが、しっかりと回収していきますのでご容赦ください。
さて、確定申告を間違えた時の訂正(我々は是正)の措置で、納税者自らが行えるものは、以下の2つです。
① 修正申告・・・所得金額や納税額が少なかった場合などに自ら行う措置
② 更正の請求・・・修正申告とは逆で所得金額や納税額が多かった場合などに、税務署に対して、修正をお願いする措置
まずはこの2つの措置があるということをご理解ください。
なお、確定申告期限(3月15日)までに間違いが判明した場合には、再度確定申告をやり直すことによって訂正が可能です。
2.どんな時に10年以上縛りが起きるのか
住宅借入金等特別税額控除(以下、「住宅ローン控除」と呼びます。)に関連して、どんな時に10年以上縛りが起きてしまうのか?
それは以下のような場合が想定されます(住宅ローン控除は何かと変更がありますので、令和6年に住宅を住宅ローンにより新築し居住を開始したことを前提とします)。
※厳密な記載は本旨ではないため、多少要件は簡略化しております。
① 新築をした住宅が認定長期優良住宅、低炭素建築物、特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)、省エネ基準適合住宅(エネルギー消費性能向上住宅)であること
② 上記①の住宅(総称して「認定住宅」)については、「その者の選択により」控除限度額等は以下のとおりになります。
・原則の住宅ローン控除の限度額は3,000万円。認定住宅の場合には4,500万円
・原則の住宅ローン控除の控除期間は令和6年居住開始の場合には10年(令和5年までは原則のローン控除も新築など一定の場合には13年でした。)、認定住宅の場合には13年
ここでのポイントは②の太字にした「その者の選択により」になります。
つまり、認定住宅の新築の場合には、無条件に限度額は4,500万円、控除期間は13年になるわけではないのです。
それを誤って、確定申告書の記載において、原則の住宅ローン控除の内容を記載してしまった場合、10年以上縛りが見事に誕生してしまう、というカラクリです。
3.いくら損をしてしまうのか
予め断っておきたいこととして、住宅ローン控除は所得税額が限度であり所得税がいくら生じているか、又は借入金額によってもいくら損してしまったかは変わるわけであるため、人によって変わります。
一定の前提を置いた上での試算は可能となります(こちらでも居住年を令和6年としております。)。

上記は極端な例ではあるが、選択を誤ったことにより、納税者は120万円近くの損失を被ってしまう可能性があることがわかります。
4.ちょっと待て!更正の請求はどうした!?
結論から申し上げますと、更正の請求ではどうしようもありません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070529/pdf/03-05.pdf
上記のリンクにもあるとおり、原則のローン控除により計算したことは、「課税標準若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当しないからです。
更正の請求が対象としているのは、①法律どおりでない処理をしてしまった又は②計算ミスがあったの2点のみだからというものです。
つまり、認定住宅の新築などを行った場合でも、原則のローン控除を採用するか、特例を採用するかはいずれも法律の規定に従った正しい処理であるというものです。
リンク先は医師の社会保険診療報酬に係る必要経費(概算経費か実際にかかった経費のいずれかを選択)の判例を拠り所にしたものです。
これと同じように、上場企業からの配当につき、複数の選択肢が用意されてますが、後になって「こっちが税金少なくなるはずだったから、やり直そう」もできない仕組みになっています。
5.2年目以降はどうなる?
「わかった1年目は諦めよう、ただし2年目以降は認定住宅の新築などとして特例として取り扱ってくれるんだよね?」と考えたくなるお気持ちはよくわかります。
ですが、実際には国税庁の見解である通達はそれを真っ向から否定してきます。

第10項が認定住宅の特例のお話だだとご理解ください。
つまりは、一度目の確定申告書の提出があった以外の特例適用年(ここでいう2年目以降)についても、一度目の確定申告書の選択を取り消せない、と遠回しに書いているわけです。
更には古いものですが、「翌年分以後における選択替えの可否」として質疑応答も存在します。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070529/pdf/03-04.pdf
こちらが私がタイトルから申し上げてきた10年以上縛りの正体です。
6.常識的に考えよう
単純に最大3,000万円×0.7%の控除か、最大4,500万円×0.7%の控除のどっちがいい?と聞かれた際に、後者を選択しない人はどれほどいるだろうか。
国の将来を憂いて、3,000万円×0.7%の控除でいいです。という人がいないわけではないが、多くの人は控除額が大きい方を選択するのではないだろうか。
税の執行にも配慮をし、1回(1年といった方が適切だろうか?)の選択ミスであれば諦めがつく人もいるだろうが、10年~13年引っ張るというのはどうしてもやりすぎとしか思えない。
ましてや、税務申告に慣れた法人に対する規定ではなく、個人に対する規定でその措置はいかがなものかと思えてならない。
マイホームは一生で一番大きな買い物であり、そのような人々の心情に寄り添うのが所得税ではないのだろうか。
住宅ローン控除はいわば身近な税額控除であるべきであり、初めて所得税の申告をする(2年目以降は年末調整に戻り、申告の機会はない)方でも対応ができ、かつ、間違えたのであればやり直しが効く、或いは2年目以降に訂正できるといった妥協点があるのがいい税法ではないかと考えている。
菅総理が携帯スマホの2年縛りの解消を「1割では改革ではない」「ドラスチックにやれ」と推し進めたように、この10年以上縛りを問題視する人が増えてもらえれば有難い。
最後の方は文面が荒々しくなってきてしまった印象を自分でも受けておりますが、熱い気持ち故とご理解いただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
