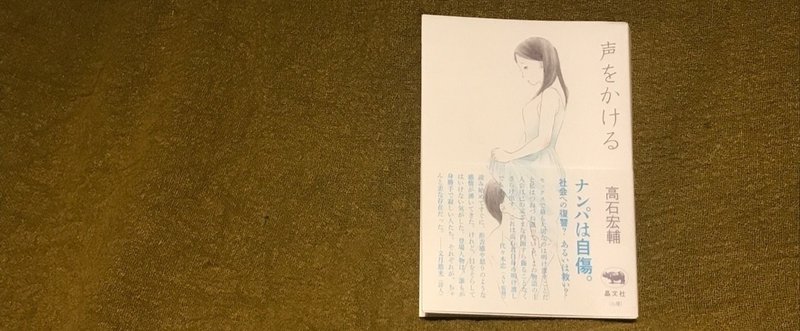
書評『声をかける』高石宏輔
内気なナンパ師の日々。これは一人ひとりが捧げるだろう、《出会い》という名の祈りを綴る、純文学だ。
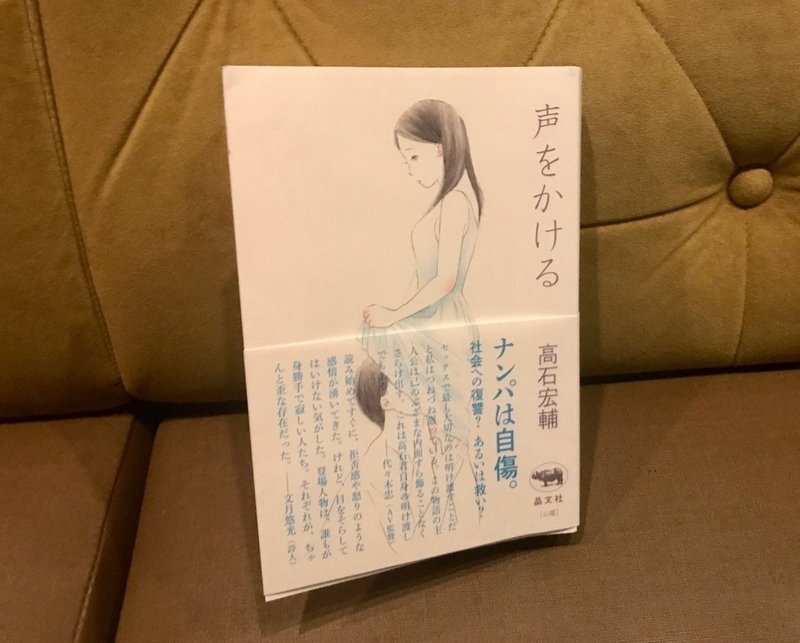
『声をかける』高石宏輔
晶文社 2017.07.20
対人恐怖症の20代の青年が、孤独を抱えながら4000円を握りしめて艶やかな都心のクラブにおどおどと入り、初めてだろうナンパをする。物語はこのおどおどとした内省から起こされて、その内省の静かさと息遣いとトーンのまま連綿と、甘い雨がしとしと夜中に降るように、青年が年齢も仕事も心持ちも言葉遣いもばらばらなむすうの女性に向けたナンパを繰り返す日々の描写へとつながっていく。
わからない。わからないけれど、わたしにとっては気持ちの良い予感がする、このまま進みたいって思う、この感覚だけがふるふると前に進めばいいなと願う。
著者高石さんの綴ることばはほろほろほろと、そろそろそろと、読み手の胸のなかに染み込んでくる。ナンパ、という行動の驚き感をそっと寝かしつけるみたいに小さな声が寝室でつぶやかれるみたいにトーンを保ち、とろとろとろと読書という形すら忘れさせて、ただ言葉とイメージとそこに置かれた会話のその1秒後を見続けるためだけに、目の前にあるページをめくらせる。109ページにたどり着くまでそれは溶けたみたいにとろとろとろと、連綿と流れるようにやわにしびれさせるみたいにしてめくらせる。
ちなみにこの本の109ページには凄い事件があるわけじゃない。特段のリズムの跳ねや屈折があるわけでもない。けれどこのわたしにとって、自然に目が今いる部屋の窓ガラスにふうっと上がり、低く流れるクレイダーマンの指の音をピアノの音をそれなんだなと意識させたのだった。
108ページのただの続きの、109ページ。多くの人がそれでもここで目をあげるのだとしたら、いや、その先は別に考えることでもなくて、なぜならそれはこの心地の良さを削ぐことだろうとぼんやり思えているからそれはもういい。
わたしはカウンセラーやナンパ師本人ではないけれど、カウンセラーやナンパ師(自称されなくても彼らはおそらくそうだったろう)たちと袖をすり合わせ、そして主体的には文章や書籍について考えながら身体を使いながら、生きてきてしまった。だからこの高石さんの綴る文章が読み手のこめかみあたりをとろとろとろと溶けさせて、大きく揺さぶることも本を読んでいるんだという行動自体すらも意識から脱落させて、ただそこにあるイメージだけに委ねさせられる綴り方を選んだこととそれを出来る技術のことをすごいと思う。
刺したり跳ねさせたり驚かせたりしーんとさせたりそれでそれで? と急き立てたり、書き手がいろんな転調を加えながら、読み手を飽きさせることなく気持ちよく、なんらかの目的をもって没頭させる文章というもののことを長年の商慣習と手癖をもって「よいものである」つまり「いっぱい売れるものである」と思って生きてきた。それはおそらく間違いでもない。けれどもぱっきりひとつきりの正解でもない。
男と女が出会う仕草を少しずつ新しくして、違う肌や快楽や気持ちを重ねながら、とろとろとろと波音の繰り返しみたいな穏やかでいて少しだけ景色を塗り替えていく今作の環境映像みたいな表現は、喜怒哀楽や事件性や強さを含ませる多くのエンターテイメント的な読ませる的文章とは別の次元で超絶技巧の必要なものだと109ページで思い出した、なぜならわたしが文章のお仕事をしてきてしまったからだとそれは思った。
子守唄や夜伽話には枕に頭をのせた主人や子どもが眠りたいなあという引き込まれる心地よさに棹刺すような、くぼみや違和感や我にかえる感を残してはならないもので、それをみごとに取り除くのは作り手自身の手腕なのだけれども受け手にはそのはからい自体も気に留めさせてはいけなくて、なぜならとろんと幸せに眠ってもらうことが大切なので、だからこそ寝室にぼんやりと残るのはただのさらさらとした連綿としたその続きの物語だけなのだと思っている。
高石さんのとろとろとろと溶けさせるような小さくて低くて痛ましい会話や地の文やストーリーがいろんな人の胸に入ったりなじんだり時に誰かに嫌だと反発されたりディスられたりしながらそのまま本屋に商品として置いてあって、それがいつかの誰かを通過していくさまというのは素敵だなあと思っている。
強く何かをぐいぐい変えてもらったり、分かるよ、分かるよ、と共感みたいに思えることを差し込んでもらうだけが、誰かに本や表現をもらうことの手段ではないと思う。それは甘い夜中の雨のようにしとしとと胸のなかでページをめくらせて、ふと109ページ目に顔をあげたときにおぼろな何かが漂っている、それはそれだけでよいことなのだと、今はそんなふうに思っている。
『あなたは、なぜ、つながれないのか ラポールと身体知』という2年前の著作が、読書界にさわさわと与えた声を今日、思い出した。
それは今思っても、さわさわとしたものだった。性体験に関わる表現、しかもカウンセラーでナンパ師の本、そうしたものに触れればどうしたって個別の思いで感情的になるだろうと想像したのに、読んだ、と話した人びとは、きついディスや拒絶や激しい同意の涙も大きな声も表さず、ふっと穏やかな顔を見せてくれていたことを思い出す。
それはこの新作を読み終わる、彼らの表情にもつながるんだろうか、とちょっと思う。
だけれど、そんな想像もすぐに手放してしまった。なぜならわたしはここにある甘い雨の音を、もう少しだけ聞いていたいだけなんだと、からからに晴れた東京の夏の夕べを眺めながらも、そんなふうに思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
