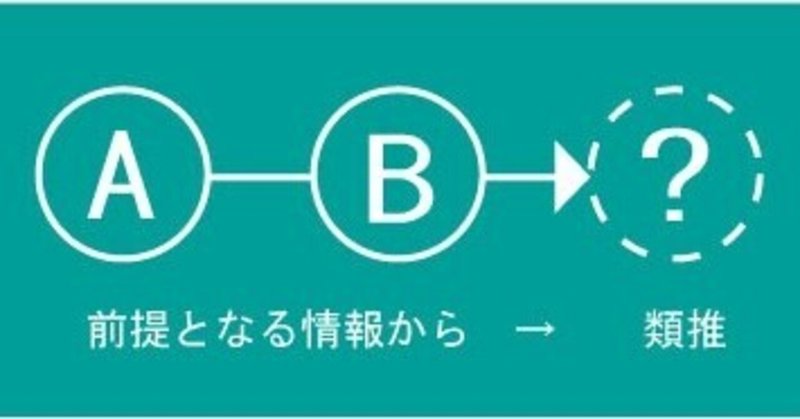
思考力を問う系の国語の問題と、それに対する対策法
この問題は何を問いたいの?
まずはこちらの社会の問題をご覧ください。
1971年から開発が始まった千葉県佐倉市のニュータウンでは、開発を進める企業が長期間にわたって街づくりを続けている。具体的には、新しく販売する住宅を年間200戸に限定している。このような制限を行っている理由は何か。30字以上40字以内で述べよ。 (‘21久留米大学附設高)
先日、来年度の適正検査系の教材作りの参考にしようと高校入試社会を指導している知り合いと意見交換をしていたときに、こんな問題を紹介してもらいました。
ぱっと見簡単そうな印象を受けますが、いざ解こうとすると取っ掛かりがわからないような問題です。
この問題のポイントは「ニュータウン」というキーワードと、「長期間にわたる街づくりのための年間200戸という制限」の部分です。
ニュータウンは都市の過密化への対策として郊外に新たに建設された新しい市街地のこと。当時短い期間で一気に作られたために、現在ニュータウンには居住者の少子化や高齢化が進んでいるものもあります。
この知識をもって「長期間にわたる街づくりのための年間200戸という制限」という部分を見れば、おのずと「居住者の世代が偏らないようにするため」という解答の糸口にたどりつけるわけです。
最近増え始めた「思考力を問う問題」
この問題は最近の中学入試でもよく見かける思考力を問う問題の典型であるように思います。
もちろん国語でもこうしたパターンは存在していて、分かりやすい例でいえば、’21年の開成中学校で出題された第1問の問5など。
問5(設問)傍線⑤「今まで何度も見てきた顔なのに、ひとつひとつが、拓也の知っていた和子とはちがっているように思えた」とありますが、拓也がそう感じたのはなぜだと考えられますか。五十字以上、七十五字以内で説明しなさい。 (‘21開成中学校)
この問題はここまでの情報を踏まえて「論理的に推論」できる妥当性のある解答を求める問題です。
こうした出題は思考力を問うことを目的に改革された大学入試共通テストでも存在しており、二つの相反する題材を一歩引いた視点で見たときに共通する主張を考えさせたり(‘22共通テスト)、ある小説に対する書評を持ち出して、それとは反対の観点からの評価をしているものを選ばせたりという形で出題されています。
大学入試の中心にある共通テストでこうした方針が打ち出される以上、今後このパターンの問題は増えてくる可能性があり、きちんと対応できる思考力を身につける必要があるといえるでしょう。
「思考力を問う問題」に答える力の身につけ方
では、こうした問題に対応するにはどういった訓練をすればいいのでしょうか?
これらの問題は①前提となる情報から法則を導き出し、②それを設問条件に適用させて類推するということを行っているといえます。
情報を抽象化し、別の事象に当てはめるという頭の使い方です。
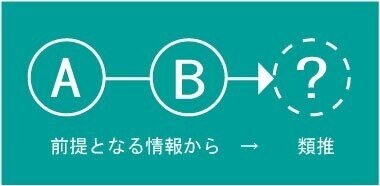
こうしたパターンの思考を苦手としている子は多いように思いますが、実はもうすでに結構使っていることだったりします。
たとえば、理科でBTB溶液にレモン汁を加えると何色になるかというのも実は同じ。
この問題はBTB溶液がどういう条件で何色になるかと、レモンの水素イオン濃度を知っているからこと導ける問題です。
さらにもっと日常生活に根ざしたところでいえば、小さいころに雨の日にマンホールで転んだ経験から、表面がすべすべしていて濡れた物体の上は注意して歩くというのだってそう。
ある情報を抽象化して別の事象に当てはめるということは結構身近な思考法なのです。
こうした思考パターンを意識して国語に適応できるようにするには、日ごろから抽象化する訓練が必要です。
もっともやりやすい練習は、小説や物語文の主人公の性格を本文にある行動や心情変化から自分なりに言語化するというものでしょう。
これは先にあげた①に該当します。
さらにそれに慣れてきたら自分の中で特定の状況を想定して、自分が書き出したその主人公の性格ならどのような反応をするかを考えて書き出してみてください。
これが②に当たります。
こうした訓練を少しずつでいいので長い期間続けていると、こうした思考を問う問題がむしろ解きやすくなるはずです。
もしお子さんが問題を解いている中でこうしたものに出会ったら、ぜひこのやり方を思い出してください。
少しだけ解くための糸口にたどり着きやすくなるはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
