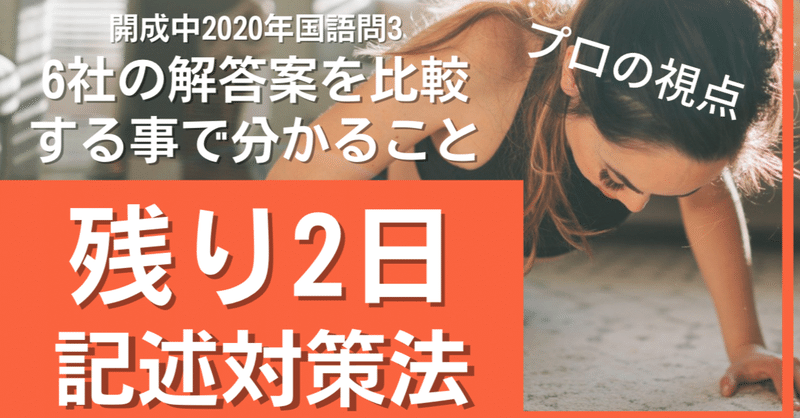
直前記述対策!6つの開成中の記述案比較から記述の総仕上げ!
こんにちは。
いよいよ2/1が近づいてきました。
入試に向けて直前の調整も完成に近づきつつある人も多いのではないでしょうか。
僕は昨日関東の中学校を志望する子たちの直前対策を終え、要約ひと段落ついたというところです。(結果はドキドキですが...笑)
さて、今回は直前期の勉強に少しでも役に立つように、開成中学校の問題を例にとって、記述答案のブラッシュアップの仕方と、直前期に役立つ活用法について説明したいと思います。
具体例が開成中学校ばかりですみません。(説明ごとに学校を変えると情報収集に時間がかかりすぎてしまうので...)
記述解答に正解はあるの?
「記述解答には唯一絶対の答えがあるのでしょうか?」
国語の講師をしていると、よくこう言った質問を受けます。
これに関しては①基本的にはプロが模範解答を書くと近しいものになるが、②違う形でも正解になることもあり、③問題によっては意見が割れることもあるというようになります。
質問に答えているようで答えていないのでは?と思われるかもしれませんが、正確に伝えようとすると、こんな感じになってしまうのです。
まず分かりやすいところで①と②についてです。
多くの記述問題は、おそらくプロが書いた物であれば大枠は一致します。(次のテーマの解答を比較してみてください)
それは、a出題者が設問で問いたい内容の根拠の範囲が同じで、b設問の仕方や文字数から記述答案には一定の方向性が生まれるからです。
仮に使う表現が違っても(特に言い換えが必須になる開成中などは)、aとbは変わりません。
そのため、正解の解答には一定の方向性が出てくるわけです。
一方、模範解答とはまるで違うけれど正解であるという②のタイプの解答もあります。
これは、aの出題者が問いたい内容を完璧に捉えた上で、bを意識せずに書いた場合です。
例えば「xだからYである」という解答を想定した設問があったとして、これご「YなのはXだからだ」となっていても意味は変わりませんので正解になります。
こうした場合が模範解答と違う正解のパターンです。
因みに、こういった解答は、独学で勉強をした子や飛び抜けた国語力の子に表れがちです。
通常、そこそこ難しい文章の内容を理解するために、子供たちは設問意図を読み取っていくわけですが、そのために解答が一定の方向性に収まるようになります。
しかしそうした習慣を知らなかったり、そもそも理解力がありすぎてそんな事をする必要がなかったりすると、設問要求を考えずに解答にするため、一定の方向性とは異なる解答に仕上がるわけです。
最後に③について。
問題によっては、そもそも解答が複数に割れる可能性を帯びた物があります。
(関東で言えば桜蔭中の広範囲を踏まえる問題や開成中の「考えるられるか」を問う問題、関西で言えば洛星中の問題など)
こうしたパターンの場合は解答作成者によって大きく見解が異なる場合があるので、複数の比較検討が必要ですし、対策をする場合にはプロに添削をして貰うことが必要になるでしょう。
(因みに僕はこのパターンの問題を教えるときは手に入る複数の解答とその答案の意図をまとめたプリント&本人解答の添削で対応します)
これが記述答案に正解はあるの?に対する僕の答えです。
さまざまな会社が紹介している解答例を並べてみた
さて、解答に関して一定の方向ができることをお話ししてきましたが、次はそれを具体的に見ていきたいと思います。
扱うのは2020年の開成中学校の問題です。
パッと調べて手に入るラインで並べてみました。
⓪独自作成解答
プライドの高さから自分より目立つ人に否定的な物言いのカナの態度を好意的に思ってはいないが、一部でこうした強さにあこがれも抱いている。
他人の解答にコメントする以上、まずお前が出せよという話だと思ったので、まずは僕なりの解答を示します。
設問から相異なる感情を入れるべきと判断し、上記の解答としました(詳しくはこちらからお願いしますhttps://note.com/zyukenurawaza/n/ne280d9088b88)
さて、ここからはウェブや大手の本からの引用です。
まずはこちらから。
①開成中学合格対策ドクター
https://www.chugakujuken.jp/kaisei/kokugo/gouhi_kokugo/2020_gouhi_kokugo/
自分より目立つ存在を否定するカナのプライドの高さにうんざりする反面、自分にないカナの強さにあこがれる気持ち。
異なる二面の心情をきちんとかかれた上で非常に綺麗にまとまっている印象です。
② inter-edu
https://www.inter-edu.com/nyushi/kaisei/
カナの他人への攻撃的な口ぐせには嫌気がさしているが、その姿勢は自分にはなく尊敬できるものなので、何も言う必要がないと思っている。
続いてはこちら。
「見てみぬふり」をした理由を効果的な口癖に対する嫌気と表した物です。
そして後半は本文の語句に忠実にしたものかと思われます。
③ 株式会社受験ドクター
https://youtu.be/TKir0TE667E
自分より目立つ人を否定するカナのプライドの高さにうんざりしている反面、自分にはないカナの強さにあこがれる気持ち。
①と近い切り口です。これも必要な情報が込められたいい回答といえるでしょう。
④声の教育者
自分以外が目立つことを許せないカナの言動に閉口はするが、衝突をおそれず自己主張するカナの、自分にはない強さを認め感心もしている。
https://www.yotsuyaotsuka.com/chugaku_kakomon/system/classes.php?id=10
出版されていることもあり、最も無駄のない綺麗な解答であるきがします。受験生が「閉口」を使いこなすのは難しいなという印象です。
⑤四谷大塚
自分が優位に立つために、目立つ者をすべて否定するカナを快く思わないが、その自信たっぷりの物言いには思わず同意させられてしまう強さがあると思う。
大体の説明は他の解答と同じです。
文字数的にも整っていて、試験会場で受験生がたどり着くとしたら最もリアリティのある解答なのかなあと思います。
以上、自分の解答と合わせて6種類を載せてみました。
当初予想した以上に、共通する部分が多い解答だと思いませんか?
よく練り込まれた問題ほど、このようにそれぞれの解答が似通ったものになります。
だからこそ僕は、こうした解答を活用することで直前期の勉強に役立てることができると思っていて、それを今回は紹介しようと思います。
記述解答の活用法
難関校ほど、さまざまな解答が示されています。
で、せっかくこうしたものが誰でもアクセスできるのであれば、活用しない手はないなというのが僕の率直な感想です。
そもそも僕自身先にも書いた通り、解答が割れそうな学校の問題に関しては多種の解答を比較しながら、最大人数に効果のあるだろう解説を模索します。
そんなことをしている教える側の視点から、今回は複数の模範解答を活用した直前の対策法を提案したいと思います。
まずひとつ目が、それぞれの解答を用意して、異なる部分を比較検討し、「なぜその部分の表現がバラつくのか」をノートにまとめるという勉強法です。
それぞれの解答で表現が割れるということは、実際の受験生でも試験中に答えが導きづらい部分ということです。
そこを比較検討し、言語化できれば、当日迷った際の最後のひと足としての効果が期待できるでしょう。
もうひとつの使い方が、それぞれの解答が、本文のどこを根拠に用いているかを考えながらノートにまとめるというものです。
もちろん模範解答の根拠となる部分の大枠は共通している場合が殆どですが、細かな部分でいうと、差異があることがあります。
それぞれが示した模範解答に違いがある場合はそこに差異があることは間違い無いでしょう。
こうした細部の思考を追う練習をしておくと、本番で「唯一の答え」を探さなければならないという思考から、「答えの可能性が高い範囲に辿り着こう」という思考が身につく可能性が高まります。
入試の多くが満点解答ではなく7割弱を取ればいいことを考えると、こういう「あたりの付け方」が意外と合否を左右する一点になることが、特に国語の場合は少なくありません。
その「わずか数点の可能性」を上げるために有効だと思うのが、この解答根拠のノートまとめです。
以上二点、もちろんこれが効果的な学校とそうでない学校もありますし、そうした学習が直前の伸びにつながるか否かはそれぞれのお子さんのこれまでの勉強や特性にも左右されます。
ただ、上記のお話に心当たりがある、あるいは納得していただける保護者の方のご子息なら(あるいはあえて大人向けに書いているこの文章が理解できる君なら!)、きっと活用できるはずです。
まだまだ、時間は残されています。
もしその残り時間のわずかなお役にでも立てたなら幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
