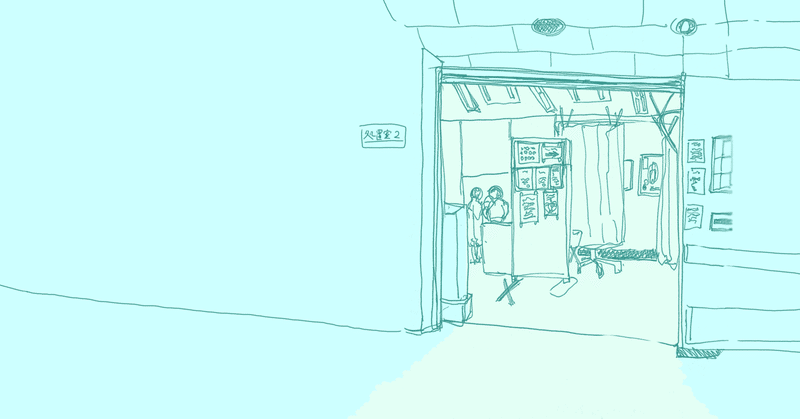
1年生日記(13日目)
ウッチャンは「あと数センチで彼岸に手が届く」ところまで行き、しかしその後此岸にものすごい勢いで戻って来たことがある。
3年前、3度目の心臓の手術のすぐ後のことだ。
あの時のウッチャンは、わたしがシロウト目線で数えただけでも25個のシリンジポンプ、3台の吸引機、人工呼吸器、人工透析器、ペースメーカー、アイノフロー、それからエクモと呼ばれる補助循環装置、その他諸々のなんだかわからないものたちに繋がれていた、あれがウッチャンにとって過去最大の医療機器装備だったと思うし、ICU在床期間も過去最長だった。わたしはこの当時、目の前におきていることへの理解が追い付かず、管だらけの我が子の横で、
「なんやしらんけど、大変なことに…」
意識の無い3歳児の手を握りあとポカンとするばかりで、この時いつも柔和な笑顔を絶やさない小児心臓外科医の先生が、渋い表情で告げた
「この状態からあと1日…いや2日、離脱できなければ、違う方向に切り替えましょう」
この言葉の意味を当時のわたしは全く理解できていなかった。そもそも補助循環装置であるエクモというものがなにかをよく分かっていなかったし、それを装着していること自体が、結構な危機的状況であるということもいまひとつ分かっていなかった。先生のあの言葉が「この先は看取りに移行します」ということだったのではと気が付いたのは、つい最近のことだ。
これの2日後に機能不全に肺と心臓の機能を代行していた補助循環装置(エクモ)からの離脱に成功、次いで人工透析器から離脱し、まるで樹のように枝分かれしたシリンジポンプ台からひとつ、またひとつとポンプが消えていった。
わたしは状態が少しずつ上向きになっていくことが嬉しくて、当時はまだ青い鳥のマークだったSNSで「子どもの状態が少しずつ、良くなっています」という意味合いのことを当時何度も呟いている。有難いことに、この時まったく見も知らない遠くの皆さんがウッチャンのことを心配してくれていて、その方達に現状をお知らせしなくてはと思ったもので。
するとそのつぶやきのリプライの中にこんなものがあった(引用リツイートだったかもしれない)。
「そのICUで死んでいく子もいるのに、よくこんなこと書けるな」
同じように病気のお子さんや家族のある人がそう思ったのかと、リプライをした人のアカウントのbioを見に行くと「医大生」とあった。真偽の程はわからないし、その人の言葉の意図していることも、画面上の短文だけではちょっとわからなかった、それがただの揶揄なのか、立場と経験ゆえの訓戒なのか、それともまた別のなにかなのか。
この時わたしは「娘が死の淵から戻ってきた」ということが自分にとってはこの上なく幸福なことであって、同時にその幸福が、それとは対極の状況にある誰かにとってはこの上ない暴力だということを、知らない訳ではなかったと思う。
ただ、病児や障害児の子のある界隈は、その幸福と暴力のグラデーションが常に変化し続けている場所なので(昨日元気だった子が突然急変し、今日看取りの覚悟をした子があくる日何故だか持ち直したりすることもある)、わたしはそういうことをここではあまり意識することがなかった。何かが数ミリずれてしまえば世界が簡単に反転してしまうことを、子どもが生まれてほんの数年で嫌というほど思い知らされるのがこの界隈だからだ。
この時のウッチャンはICUを出た後、明瞭な意識を取り戻すのに相当な時間を要した、更には病棟で何度も謎の痙攣を起こし、四肢の麻痺や低酸素脳症を疑われながらリハビリを続けた。結局術後の肺循環は上手く機能しなかったものの、無事退院していつもの生活に戻ることができている。
この出来事から3年後の春、ウッチャンは無事地域の公立小学校に入学、地域の特別支援学級に在籍しているけれど、今は1日のほどんどの時間をもうひとつの在籍級である1年生の普通級で過ごしている。
小学校の中に6つか7つある支援級は、ひとりの担任教師が大体5名程度の子ども達を担当している。ウッチャンのクラスでは3人がひとりの担任の先生の担当児童として在籍し、それぞれ学年は違うものの一応『同級生』ということになる。3人はそもそも学年が違うので同じ時間に同じ教室で学習をするということはしていない、支援級での授業もウッチャンの場合は1日1時間程度。
これがあまりにも文部科学省が掲げていた支援級教育の文言と違っていたもので、ゴールデンウィーク明けに小学校に来た教育委員会チームの面々にわたしは訊ねた。
「これは、文部科学省の言う『特別支援学級』の姿とちょっと違いませんか」
そもそも特別支援級を希望するにあたって、市の教育委員会からの文書やガイドラインはほぼ存在せず、あったのは『個人のニーズにあった教育』という方針だけ、結局わたしは文部科学省がホームページに提示している『特別支援教育の運用について』等の文書を読んで「なんとなくこういう感じのところか」と想像するしかなかった、学校見学にも勿論行ったけれどその際に見学できたのは情緒級の方だったし、希望していた病弱・身体虚弱児支援教室というのは全くの霧の中の状態のまま4月を迎えていた。
わたしのこの質問には市教委の特別支援学級・統括指導主事である人が答えてくれた。
「市教としては可能な限りどんな子どももできるだけ普通級の中で過ごしてもらう、それを理想としています。ですから決められた時間『絶対に支援教室の方にいなくてはならない』という考え方をしていません」
(え、行政機関って、トップの言うことが絶対ではないのけ?)
わたしはそう思ったけれど、実際低学年の授業分類というのはとても曖昧なもので、図工の時間に何となく国語っぽいことをすることもあるし、算数の時間が4時間目だとそれを早めに終わらせて給食の準備を始めることもある。現場がどのように文部科学省通達を理解し運用するかはすべて現場判断ということなのだろうと、取り合えずは理解した。理解したけれど理想は理想、現実は現実。
実際今、ウッチャンはほどんどの時間を普通級で過ごすことで、支援学級に設置した酸素濃縮機を使わず、酸素ボンベで過ごしている、そしてそれは昼ごろに中身がカラになるのでわたしが交換しなくてはいけない。それなのに看護師は来ないしいない。
『昼に1時間、いや30分、看護師がやって来てボンベを交換して、バイタルのチェックをして、服薬の確認をしてくれたら、わたしも、学校の先生方も、ウッチャン本人も安心なんですが』
統括主事にわたしは訴えた。即応可能な要求でないのは分かるのだけれど、何とかこの子の看護師さんの予算をつけてもらえないですかと、するとそれの返答は
「予算はあるんですよ、しかし人員の方がなんとも」
ということで、金はあるけど人がいないということだった、お金はあるのか我が市。
とは言え確かに学校看護師というのは採用も定着もかなり難しいものだと聞いているし、まあそうでしょうねえとは思う。それでわたしはもうひとつ提案をした、実現するかはわからないけれど、別の市でやっているところがあるのを知っていたから。
「市教の方で訪問看護ステーションと契約すると言う考え方はないですか、そちらの方が直接雇用よりも人員確保は確実じゃないでしょうか」
この件についてはその場で何かが決まるということはないので、持ち帰って検討するということにしかならなかったけれど、年間数センチの歩みでもいい、何とかウッチャンの学校生活を良い方向に進めたい。
このようにしてウッチャンの1ヶ月目の学校生活はほぼ「出たとこ勝負」という感じ。色々揃わない、そしてままならない。
しかしウッチャン自身は予想に反してとても順調だ。小学校入学から今日まで、一度も学校を欠席していない。1日だけ3時間目の終りから登校する日があったけれど、それは大学病院の受診があったから。週の後半の午後には疲れでやや目が映ろになるものの、本人は休む気なんかさらさらないらしい。去年「幼稚園になんか行くもんか」と幼稚園の門扉にしがみついて泣いていたウッチャンと、今、酸素ボンベをゴロゴロしながら小学校の廊下を闊歩している人はもしかしたら別人なのかもしれないと疑う程の変容ぶり。これにはわたしも驚いたし、就学前「週に5日間幼稚園に登園できたことは殆どない」と聞いていた教委の人も驚いていた。
「体力的な問題がクリアできて、支援員からの補助を貰いつつ普通級でずっと過ごせるのなら、それこそが自分達の理想とする特別支援教育です」
そういうことらしいけれど、どうかなあ、現実はそう簡単だろうか。
ウッチャンは自分と同じクラスのお友達が自分とはちょっと違うのだということを、既によく分かっている。ウッチャンは45分の授業時間にきちんと座っていられるし、先生の指示も大体理解できているし(たまに聞いてないけど)、平仮名も書けるし、算数の『10の補数』も理解できている。しかし同時に余計な荷物を常に携帯し、運動の制限があり、20分休みにグラウンドに外遊びに飛び出すということができない。
健康体ではないからだ。
この普通級のお友達が当たり前に享受している『健康』という幸福が、ウッチャンにとっての暴力になりはしないかということを、入学1ヶ月目のわたしはずっと心配していた。今のところウッチャンは「体育が見学すぎてつまらん」と言っているだけだけれど。
そして逆に、クラスのお友達はこの見た目からして「自分らとは違うよな」というウッチャンをどう見ているのかなあとも思っていた、酸素ボンベ以外に電動車椅子ユーザーでもあるウッチャンは、20分休みや昼休みに外遊びができないし(禁止はしていないけれど、同級生と同じスピードで行って戻って来られないのでほとんど外に行かない)、1時間目と、給食の時間と、5時間目に母親が廊下にやって来てしばらく立っていて時折、ささやき女将みたいに何かを伝えたり、聞いたりしているし。
市教委の人の言う『特別支援教育の理想』は、クラスの中に分断や疎外を産むのではないか、ほんとうに子ども達はそこに共存を見出すことができるのか、そういうことをわたしはずっとなんとなく考えていたのだった。
そんな数日前、給食の後の『ごちそうさまでした』をした後、子どもらが一斉に食器や牛乳の紙パックを片付けている時間に廊下に酸素ボンベを引きずりながらウッチャンが出てきて、そこにある牛乳パックを収めるかごにそれを入れようとしていたら背後に数人の男の子たちがふざけ合いながら迫って来たことがあった。昼休み前の廊下はいつも子ども達で隙間なく埋まっていて、普通の子が真っ直ぐ歩くのにも一苦労の空間だ。
(あ、あぶないな)
わたしがそう思うが早いか、同じクラスのうんと小柄な女の子が、すっと間に入って手を広げてその子らとウッチャンの壁になってくれた。けれどウッチャンは不器用な手つきで牛乳パックをかごに収めようと真剣で、彼女が自分を守ってくれていることに気が付いていなかった。一瞬の出来事だったし、その子も特に何も言わなかったし。
(ありがとうね)
その出来事をすべて見ていたわたしは、その子に目配せしてそう伝えてみたけれど、その子は
(うち別に大したことしてないで、当然や)
そんな表情でそのまま通り過ぎて行った。ウッチャンに「あたしが守ったったで」なんてことは言わず、ウッチャンの母親のわたしにも何も言わないで。
入学1ヶ月、ウッチャンもクラスのお友達も、何となく互いを「そういうものだ」と思い始めているということなのかもしれない、思えば親のわたしも、目の前のウッチャン以外34人の健康なお友達を目の前に「ああこの子達はこんなに元気なのに…」なんてことは思うことなく
「全員可愛いのう…」
と思っているのだし。毎日一緒に過ごしていれば、一見特殊な何かで誰かでも、なんとなくそこにあることが『当たり前』になっていく。これは美談でもなく、偽善でもなく「そういう風にできているんやから、そうなんやろ」と、そういうことなのかもしれない。
ついこの前なんて、ウッチャンが昼食後の薬を飲まずにぼんやりしていたら「なあ、薬は?」と言って通り過ぎて行った子がいて、当のウッチャンはウッチャンで「あ、忘れてたー」とフツーにお薬セットの黄色いきんちゃく袋を取り出していたし。
プールの水にひとさじ青い色を混ぜた所でそれがいちいち目立たないように、ウッチャンもクラスに上手に馴染んでいくといい。
サポートありがとうございます。頂いたサポートは今後の創作のために使わせていただきます。文学フリマに出るのが夢です!
