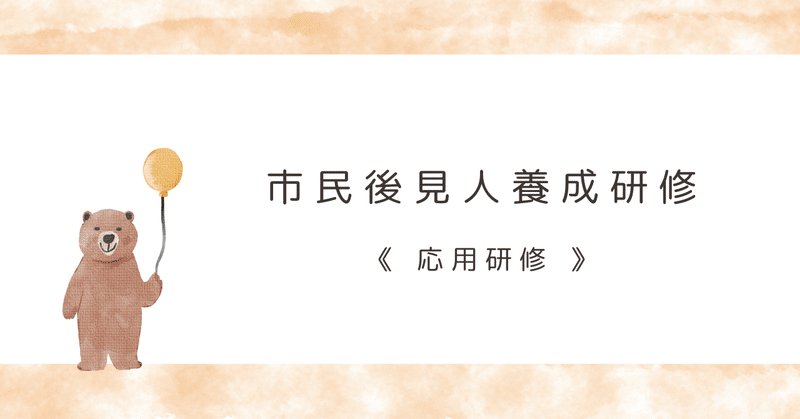
市民後見人養成研修<応用研修> 1日目
2024年4月25日、市民後見人養成研修<応用研修>1日目に参加してきました。
基礎研修が、2月18日に終了し、参加者の方とは約2か月ぶりの再会となりました。参加者は33名。応用研修に進むかは任意とのことでしたが、全員が応用研修を希望されたそうです。私も第1期生として、最後までやり遂げられたらと思います。
今回も、自分のための復習投稿です😊
第1日目
1.開校式、オリエンテーション
2.成年後見制度と市町村責任
3.日常生活自立支援事業の概要と支援員の活動
4.グループワーク
5.レポート提出
●オリエンテーション
・応用研修は実際の記録物の記入方法など実践が中心となるため、欠席した場合の歩行が困難であること。
・グループワークを基礎研修よりも長めに設け、自分の意見などアウトプットする場として活用してほしい。
・レポートの提出はwebから提出も可、記入時間を設けてほしいとの要望があり20分程度の記入時間を最後に作ったこと。
上記について説明があり、講義に入りました。
●成年後見制度と市町村責任
まずは復習から。
成年後見制度とは
①判断能力が不十分な人に対して
②成年後見人などの法律上の権限を持つ援護者をつけて
保護したり支援したりする
③(民法を根拠とする)司法の制度
➡家庭裁判所が運用(監督まで)
後見制度は福祉制度ではないということ、と強調されていました。
●成年後見制度 3つの枠組み(類型)
①判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つ
②日常の買い物をするのも難しい人は後見類型。
成年後見人が付く
③日常の買い物はできるが大きな買い物は難しい人は、保佐類型。
保佐人が付く。
④だいたい大丈夫だけれども援助者がいた方が安心という人は、補助類型。
補助人が付く。
後見・保佐・補助の区別があるのは、成年後見人などに与えられる権限の範囲が違うから。
●両輪のはずが、、
2000年に同時にスタートした制度
介護保険制度 利用者670万人
成年後見制度 利用者25万人
後見制度はなかなか普及しなかった。。
●市町村の責務として・・当面の課題、市町村で解決しなければならない
①申し立てをする人がいない
②お金がない
③緊急性がある
④後見人になる人がいない
地域格差があってはならない
どこに住んでも誰もが守られるべき
成年後見制度は、権利擁護支援のひとつの手段
目的は、地域共生社会の実現
--------------
2限目
●社会福祉法人 社会福祉協議会 職員さんより
「日常生活自立支援事業の概要」
~利用者が自分の意思で契約する援助の仕組み~
日常生活自立支援事業・・社会福祉法に規定
成年後見人制度・・民法に規定
*代理できることの内容が大きく異なる
*対象者も異なる
成年後見人は不要?
●90分のグループワーク
社会福祉協議会の日常生活自立支援事業との違いについて。
後見人の立場であったら、どうかかわるか。。
事例をもとにグループごとに話し合い、終了しました😊
社会福祉協議会って、聞いたことは会ったけれど、具体的な活動について知る機会となりました。
よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはco-YOBOH活動費として大切に使わせていただきます🙇♀️
