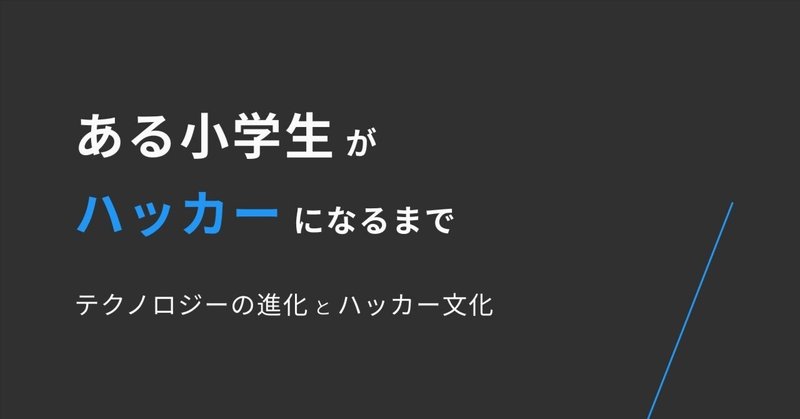
ある小学生がハッカーになるまで(テクノロジーの進化とハッカー文化)
フルスタックマーケティング株式会社の代表取締役CEO・清水優志(@fsm_shimizu)です。
企業のマーケティング活動を支援しています。
最近、とんでもなく面白い本に出逢いました。
『スペクテイター』という雑誌の『パソコンとヒッピー』特集号です。
この本では「パソコンが生まれた背景には、ヒッピーの文化や思想がある」という主張がされています。
この本の中でも、当時のヒッピーカルチャーの渦中で、今でいう「ハッカー」の先駆けとなったコミュニティ「ホームブリュー・コンピュータ・クラブ」について書かれた章が非常に面白かったので、以下に一部引用します。
ホームブリューは当初、共有と協力の精神ではじまった。ヒッピーたちも互いに夜を徹して話し合い、アイデアや部品を物々交換したり…(中略)
このアマチュア技術者によるギフト・エコノミーの実践こそが、のちのオープンソース運動の先駆けで、世界中のプログラマが無償で共同開発し維持するOS(オペレーティング・システム)のリナックスにつながるものの前触れだった。
ハッカーは、みんなのために何かをつくり、それをみんなで味わうのが好きだ。みんなのために自分の能力を無償で提供できる人は、他人との関係を愛せる人だ。そこにはヒッピーと同じ愛情が感じられる。
この文章を読んで、僕の小学生時代の記憶が強烈にフラッシュバックしたので、今日はそれについてnoteを書こうと思います。
2000年代初頭は、家庭用ゲーム機の黄金期
僕が小学生だった2000年代初頭は、コンシューマーゲーム(家庭用ゲーム機)の黄金期でした。
『マリオストーリー』『大乱闘スマッシュブラザーズDX』『ポケットモンスター ルビー・サファイア』『ゼルダの伝説 風のタクト』『カービィのエアライド』など、名作と呼ばれるゲームソフトが山ほど発売されました。
2004年12月にはニンテンドーDSが登場。
小学生の話題の中心は常にDSで、休み時間も放課後も、ゲームをきっかけに友達ができ、仲良くなるのがメジャーな時代。
日中は家族が出かけているという友だちの家に遊びに行っては、お菓子やジュースを持ち込んで、日が暮れるまでゲームに興じていました。
布団の中に隠れて、夜通しゲームをやったのもよい思い出です。
無法地帯だったコロコロコミックの広告
当時の男子小学生の主な情報源といえば、おはスタとコロコロコミックでしょう。
ベイブレード、ポケモン、デュエルマスターズカード、でんじゃらすじーさん… 小学生男子には、ぜんぶがとてつもなく魅力的だったんですよね。よだれを垂らしながら、新しいゲームやおもちゃの情報を仕入れていたのを思い出します。
この頃のコロコロコミックの広告コーナーは、無法地帯。
謎のスパイグッズ(ペン型の盗聴器とか)、絶対に学校で注意される多機能筆箱、明らかに誇大広告な身長が伸びるサプリメントなど、今なら各所から怒られそうな広告が山のように掲載されていました。
そんな中でも異彩を放っていたのが、プロアクションリプレイでした。

ゲームバランスを崩壊させるチートツール
プロアクションリプレイは、いわゆる「チートツール」です。
家庭用ゲーム機のカセットの形をしていて、通常のソフトと同様に挿入し起動すると、開発者モードでゲームを起動できたり、改造用のコードを実装することができます。
例えば、伝説のポケモンを好きなだけ複製することも、マスターボールを999個手に入れることも、自分の好きな色の色違いポケモンを作り出すこともできます。
ゲームバランスを完全に崩壊させることのできる、メーカーからすると絶対に無視できない違法ツールでした。
ゲームのプログラムやデータを改ざんするチート行為は、著作者人格権のひとつとして「著作権法第20条1項」で規定されている「同一性保持権」を侵害するおそれがあります。
しかし、当時のコロコロコミックには、このプロアクションリプレイの広告が堂々と掲載されていたのです。
ちなみに、ブックオフやゲーム専門店にも平然と陳列されていました。
著作権なんて1mmも知らない小学生でしたから、広告を見た僕は喜び勇んで、コツコツ貯めていたお小遣いをはたき、たしか4,000円くらいだったプロアクションリプレイを購入しました。
「大変なものを手に入れてしまった」
プロアクションリプレイで改造コードを実装するには、本体とは別に『秘技コード大全』と呼ばれる書籍を購入し、そこに書かれた文字列を入力する必要があります。
メインメモリ上のデータを書き換えるコードを実行することで、データを改ざんすることができるのです。

この『秘技コード大全』がまた面白く… 「経験値MAX」や「アイテムへらない」など、小学生からしたら夢のようなコードが並んでいます。
僕は「大変なものを手に入れてしまった…」と恐れおののき、コードを実行しては歓声をあげ、自分の持っていないゲームのページも含めて端から端まで眺めては、ゲームを支配する神になったような気持ちに浸りました。
今の自分から見ると「チートなんか使って何が楽しいんだ…?」と不思議に思います。多くの読み手の方もそうでしょう。
しかし、小学生男子というのは奇妙な生き物で、ゲームのシステムに介入してめちゃくちゃにするのが好きだったりするのです。
平凡な小学生だけど、気分はスーパーハッカー
ゲームを支配する神になってしまった僕は、さっそく友だちにそれを自慢して回りました。
ほとんどの子どもはチートツールなんて知りませんし、知っていても使ってみようなんて思いませんから、僕は一躍「なんだかわからないけど、すごいポケモンをいっぱい持っているすごいやつ」になりました。
それに気を良くした僕は「欲しいならあげるよ」と、チートで生成したポケモンや道具を友だちに配っていったのです。
もちろん僕はこのゲームの開発者でも、チートツールの開発者でもありません。僕が改造コードを作ったわけでもありません。
ごくごく平凡な小学生です。
しかし、気分はスーパーハッカーでした。
ゲームが得意な小学生は、それだけでスーパースターです。
同様に、ゲームを改造してすごいポケモンをいっぱい持っているやつも、それだけでスーパーハッカーになれる。それが小学生の世界なのです。
ゲームの歴史は、ハッカーとの戦いの歴史
そもそも、ゲームの歴史はハッカーとの戦いの歴史でもあります。
1983年にファミコンが発売されて以降、改造ファミコンが発売されたり、改造を施したソフトが二次流通したり、違法コピーゲーム(いわゆる「海賊版」)が出回ったり…。
ハードもソフトも、様々な方法でハッキングされてきました。
近年はいわゆるホワイトハッカーが育ってきたこともあり、メーカー側の対策がどんどん巧妙になっています。
それと同時に過去の権利侵害に関する判例も増え、以前に比べるとハッカーは影を潜めざるをえなくなっているでしょう。
ただ、今でもチートツールの開発・公開をする人は後を絶ちませんし、それを利用するユーザーもゼロにはなりません。
例えば『スプラトゥーン』はチート利用者が多いことで有名なゲームです。
ジョブズとビル・ゲイツの意外な関係
実は、冒頭に紹介したホームブリューというハッカーコミュニティも、ソフトウェアの違法コピーなどを繰り返し、それを告発されるなどして問題を起こしています。
そして、なんとその告発主は、かのビル・ゲイツなのです。
「ホビイストたちへの公開状」は、マイクロソフト共同設立者のビル・ゲイツが1976年に初期のパーソナルコンピュータのホビイストたちに向けて書いた公開状である。この中でゲイツは、ホビイストのコミュニティの間で、(特に自分の会社の)ソフトウェアの違法コピーが横行していることへの失望を表明している。
公開状の中でゲイツは、ほとんどのホビイストが、自分の会社のAltair BASICを、正当な対価を払わずに使用していることに対して不満を表明している。
さらに驚くべきことに、告発された側のホームブリューに入り浸っていたのが、何を隠そう、Apple社の創業者であるスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックだったのです。

つまり、スティーブ・ジョブズとビル・ゲイツは、名を上げる前から同じコミュニティの中で、(ハッカーと告発者という立場ではありますが…)交流があったということになります。
ハッカーは、みんなのために何かをつくり、それをみんなで味わうのが好きだ
もちろん、今の法律に照らし合わせれば、ハッカーというのは権利侵害者ですし、明らかな悪者です。
人が作ったソフトウェアをコピーし、(仲間内とはいえ)再配布するのは違法行為だと言えるでしょう。
しかし、ここで改めて、冒頭に引用した文章を再引用したいのです。
ホームブリューは当初、共有と協力の精神ではじまった。ヒッピーたちも互いに夜を徹して話し合い、アイデアや部品を物々交換したり…(中略)このアマチュア技術者によるギフト・エコノミーの実践こそが、のちのオープンソース運動の先駆けで、世界中のプログラマが無償で共同開発し維持するOS(オペレーティング・システム)のリナックスにつながるものの前触れだった。
ハッカーは、みんなのために何かをつくり、それをみんなで味わうのが好きだ。みんなのために自分の能力を無償で提供できる人は、他人との関係を愛せる人だ。そこにはヒッピーと同じ愛情が感じられる。
ホームブリューに参加していたハッカーたちは皆、それぞれの好奇心や探究心に突き動かされるままに、パーソナルコンピューターの未来を描き、それを実現することに心血を注ぎました。
事実、スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックはMacintoshという大発明を成し遂げ、その後に誕生したiPhoneは文字通り、世界を変えました。
現在、スマホを持つ人の数は、世界人口の約半数である40億人を超えると推計されています。2007年のiPhone発売から16年あまり、こんなスピードで世界中に普及したテクノロジーは他にありません。

ハッカーを手放しに称賛・擁護したりするつもりはありません。
しかし、テクノロジーが急速に進化した理由として、ハッカーの存在があることに疑いはないでしょう。
世界を変えるのは「わかもの」「よそもの」「ばかもの」とよく言います。
自分の常識に照らし合わせて「おかしい」「やめたほうがいい」と思うことでも、場合によっては見守ったり、応援したり、自分も参加するような勇気を持ちたいものです。
===============
もし筆者に興味を持ってくださった方がいらっしゃったら、ぜひお気軽に以下のリンクより「ちょっと話してみたい」してください!
案件の相談でも、キャリアの話でも、雑談でも、なんでも大歓迎です。
Twitterアカウントはこちら
https://twitter.com/fsm_shimizu
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
