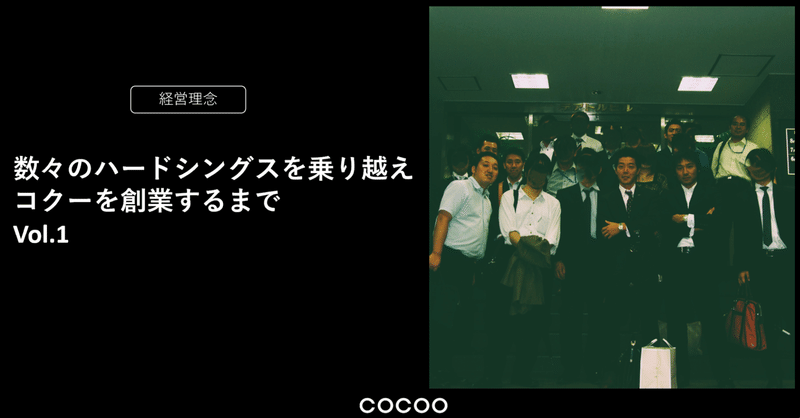
数々のハードシングスを乗り越えコクーを創業するまで ~Vol.1
私は20代~60代までの50年間を10年単位でテーマを持って取り組んでます。
20代で、起業をするためハードワークする
30代で、自ら苦労を買い茨の道を選択する
40代で、事業のベースを創りあげる
50代で、もうひと勝負する
60代で、次世代に託し新しい人生を歩む
前回ファーストステージである20代の話をしたので、今回はセカンドステージである30代(20代後半からコクーを立ち上げるまで)を何回かに分けて話したいと思います。
最初の「3人」
SIerで丸8年、2008年3月31日まで勤務し、そのまま一日も空けず、4月1日に前身会社で第二創業をした私は、そのままの勢いで仕事に取り組んだ。日中はずーっと営業周り、18時以降に事務処理や仕組み作りをし、終電で帰り風呂入った後に採用のスカウト等をこなして毎日3時くらいに寝るという日々だった。体力的には問題なかったが、さすがにこのまま一人では限界があると感じていた。
そんな時、高校時代の友人であった拓こと市川拓磨(現 ITインフラ事業本部 マネージャ)から「ITエンジニアに興味がある」とTELがあった。当時拓は建築関係をやっていたので全くの未経験であったし雇う余裕もなかったので、冗談で「MCPとITILの資格を1カ月で取ってきたらいいよ」と発破をかけたら本当に取ってきてしまった。冗談とは言え約束だったのでジョインすることになったのだが、私自身の仕事がパツっていたので「エンジニアじゃなくて営業やらない?」と誘導し、結局営業としてジョインしてもらうことになった。社員第一号である。社番[100002]
社番[100003]の第二号は秀こと高橋秀和(現 取締役 経営管理部長)である。秀は転職サイトからの応募でエンジニア第一号であった。前職では採用をゼロからやったことは無かったので、試行錯誤しながらなんとか媒体に掲載し面接していた。でも振り返ってみると面接するというよりは「こういう会社をつくりたい!」「一緒にやろう!」という私の一方的なアプローチが9割位を占めていたと思うし、逆にこちらが面接されていたんだと思う(笑)。当時の会社は日本教育会館というビルの7階の一角にあり、入り口が曇りガラスにロゴが書いてあるだけのドアをコンコンと叩いて開けるという何とも怪しさ満点であったからか、秀に内定出してからも承諾までの間、10通以上のメール質問攻めを受けた。最終的に「入社します」とメールをもらった時の全身が身震いした衝撃はまだ忘れていない。それだけ採用というのは双方にとって人生の大切な意思決定の場であるということは、今でも原点として噛みしめている。15年経った今も、入社者の最終承認と顔合わせは必ずしている。

最初の3人が当時を振り返って語っているブログ記事はコチラ↓
【ゆるトーク】コクーの重鎮 オリジナル3(スリー)と思い出の場所を巡りながら、昔話をしてみた。(前編)
https://media.cocoo.co.jp/archives/64
最初の「あったらいいね!」
3人になってからまず始めたこと。それは私自身の最初のあったらいいね!の提案「Tsuki-Ichi」である。
Tsuki-Ichiとは、月に1回集まって会社から情報共有したり皆で飲みながら語り合う場。顧客先常駐というビジネスモデル上、せめて月1回は自社に帰ってきて、社員同士のコミュニケーションをとっていくことで帰属意識を持って働こうという目的のために2007年7月から実施し15年間継続している。
その記念すべき第一回Tsuki-Ichi(2008年7月)の場所がコチラ。

さくら水産の4人席で、拓と秀と私の全社員参加で開催(笑)

「いつかはこのさくら水産を貸し切ってTsuki-Ichiやるぞー!」と熱く語っていたことを思い出す。おかげさまでTsuki-Ichiは15年間継続しているので単純計算すると来月で180回目になるが、次回2023年7月のTsuki-Ichi(期初なので経営方針発表会議)は、700名収容の品川インターシティホールでやる予定だ。こうして振り返ってみても感無量である。

最初の「受注」
事業ドメインはITインフラ領域を中心にと考えていたが、当時は業界もイケイケで伸びていた時期でもあったので、システム開発やIT事務など幅広く挑戦していくことで更なる勢いをつけようとしていた。
営業スタイルも飛び込み&リストに片っ端から電話をするという今から考えれば超非効率な方法を何も疑いなく、とにかく量が大事だ!と言い聞かせながら実践していた。それでも中々思うように仕事が取れないことにフラストレーションを溜めていた頃、懇意にしていたビジネスパートナーからTELがあった。「急ですが今日夜間に名古屋の銀行営業所の両替機のシステム刷新作業があるけど行ける人いますか?」「いれば即受注です」とのこと。そのTELは夕方頃にあり、もちろん行ける人なんかいないのだが受注を逃すまいと「2名行けます!」と即答。外営業から帰ってきたタクに
「今日夜空いてる?」
「空いてますよ、飲みですか?」
「いや、今から名古屋に行こう!」
と無理やり引っ張って、そのまま東京駅から名古屋行きの新幹線に飛び乗り、21:00から翌2:00まで作業をこなした。これが初受注(10万円)となったのだが、何でもやるとは言えまさか両替機システムの入れ替え作業をやるとは思わなかった(笑)。作業が終わった後、飲み屋を探したが、田舎の営業所なので何もなく、駅前に待機していたタクシーの運ちゃんに聞いたら車で20分位のところくらいしか居酒屋は無いと言われ、泣く泣くあきらめて近くのセブンイレブンで缶ビールとつまみを買い、銀行2階の休憩所でしっぽり飲んだ。その時の寂しくも嬉しかったビールの味は忘れないだろう。
最初の「トラブル」
最初の受注は本来の姿ではなかったが(笑)、その受注をきっかけに?!その後は順調に仕事が取れ始めてきたので、採用も並行で進めていた。
当初は未経験若手というよりは上流工程もできるベテランエンジニアを中心に採用をしていたこともあり、ほとんどが私よりも年上であった。前職の会社にも挨拶に行き、ベテランエンジニアがその会社のプロジェクトに参画させていただいた。
ある時、現場近くのカフェにその社員に呼ばれ会話していたところ、カフェの中でいきなりキレて発狂し、コーヒーをこぼしたまま店を出ていってしまった。(残された私は皆から見られその後処理の気まずさといったら無い…涙)。
私自身前職での営業経験で年上の対応も慣れていると自負していたが、当時の会社はまだ仕組みも制度もままならなかったので、全てが後付けで色々とつくっていた時期でもあったので社員も我慢の限界だったのだろう。
その後一切連絡も取れず、それ以来顧客先にも出社することなかった。顧客先でも重要なポジションだったので大問題になったし、せっかく前職の会社に紹介してもらったにも関わらず迷惑をかけてしまった。双方に謝罪をする日々の中、極めつけに数日後にはその社員の弁護士から私宛てに[損害賠償請求の内容証明]が送られてきた。私自身そのような経験もなかったしどう対応すればよいかもわからなかったのでさすがにテンパった。何とか知り合いに紹介してもらった弁護士に相談し、最終的には示談という形で終わったのだが、更に多忙になった上でまだまだすぐにコケてしまう不安定な経営をしていた中、こうした事件が重なったことでさすがに疲労困憊になった。
ただ一方で、この機会には大きな学びを得た。
それは技術や経験という表面的な部分ではなく、私たちが掲げている理念にしっかりと共感し体現できるヒトだけを採用しようと心に誓ったことだ。現在のコクーは理念共感型経営をしていて、すばらしい仲間が集まってきているので、この失敗経験が原点だったと思うと今は感謝である。(←今思うとね。当時はホントに悔しくて泣いた)
最初の「一年」
その後は順調かと思いきや、リーマンショックが起きたので仕事もパタンとなくなったりし、再度ピンチの波が…ただ「ピンチこそチャンス!」と、ちょっとのことでは動じなくなっていた私(仙豆を食べたら以前よりパワーアップするやつ)は、<ITの何でも屋さん>で突出してない会社ではこのまま生き残っていけないと直感し、であればITインフラしかできないけど<ITインフラではどこにも負けないという会社になろう!>ということで、そこにフォーカスした。結果、人も仕事も集まってきた。
おかげさまで1期末には、同じ志を持った仲間が20名位まで増えた。最初の一年は激動であっという間であったが、今いるメンバーが支えてくれてこその今があると、振り返り改めて感謝の気持ちでいっぱいである。
以下の写真は1期末のTsuki-Ichi懇親会後の集合写真。皆若い(笑)

とまぁ最初の一年を振り返ってみたが、5年後にはこの5倍のハードシングスが、さらにその5年後には10倍のハードシングスが待っていることは当時の私はまだ知る由もない…
あれっ⁈夢中でキーボードをたたいてふと右上の文字数を確認したら、広報から目安と言われている3500文字をゆうに超して4000文字になってしまった…まだ1年しか語っていないのに…(汗)
Vol.1は最初の1年で終わってしまいましたが、次回以降はもっとサクサク進捗できるように努めます。
ご覧いただきありがとうございました。
Vol.2につづく…
▼コクーのオープン社内報「みえる!コクー」はこちらから。
▼こちらの記事へのご意見、取材依頼・問い合わせ等は下記のフォームから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
