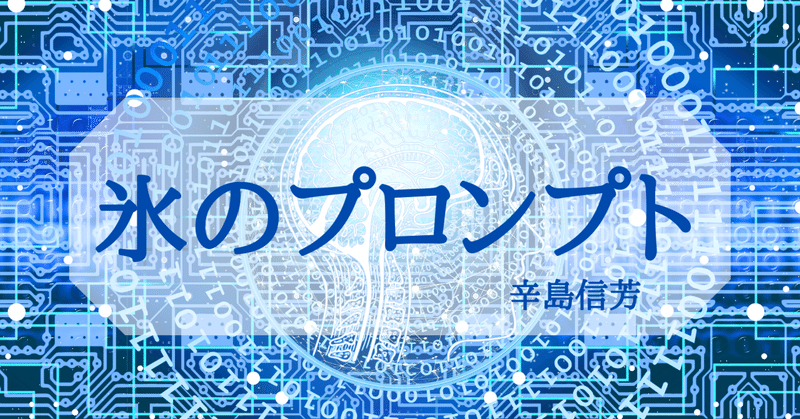
【連載小説】「 氷のプロンプト 」第10話(最終話)
(本文・第10話)
満月の光が一面を照らしていた。
深い別世界を産み出すようなような眩しさで。
ダイニングのテーブルには、ポークソテー、カニクリームコロッケ、ポテトサラダが二食分ならべられていたが、今夜もサランラップがかけられている。
どこかの研究所のロボットような表情で、利成はソファーにもたれ掛かっている。まだ若かった頃の記憶が走馬灯のようによぎっていた。
大学卒業後は、中堅企業を転々としながら営業マンとして日々奮闘していた。朝一番の長々とした朝礼、大声を張り上げての社訓の唱和、成績不振者の吊し上げ。その後は延々と架電して、アポが取れるまで受話器を置くことは出来ない。訪問先の企業から契約書のハンコを押して貰うまで帰社することは許されなかった。
昭和世代に有りがちな特有の根性論。AIが台頭する令和時代にこんな真似したらまっ先にパワハラで訴えられるだろう。
あの頃は携帯電話も普及したばかり、鳴ったら平日休日問わず出なければいけなかった。そのほとんどがクレームだった。理不尽な要求ならまだ楽だった、顧客の言い分がよく分かるからこそ辛かった。ただその分、インセンティブは良く、おかげで貯金だけは貯まっていった。
酒でも飲んでなきゃ、やってられない。よく行く居酒屋では、何人かの常連とちょくちょく話をしたり、馬が合ったら名刺交換をしたりもした。といっても、ノルマのため営業をかけるような真似はしなかった。
ただでさえ休日にも社用携帯がなるんだ、会社とプライベートは極力分けたかったんだろうな。その常連のうち一人が由規子だ、営業事務の仕事をしてたようで、そりゃまあ話の合うこと。
ノルマが達成できない月があって、上司に相当詰められて、その日は半ば酔いつぶれていたんだったけな。そんな時、たまたま由規子が隣の席にいて、介抱してくれた。そこから一気に距離が縮まった。
それから三年経ったかな、蒸し暑い空気に包まれた、あの祭りの夜。あちこちに掲げられた提灯、どんどこどんどこ太鼓が打たれる音がはじけ、屋台からは、香ばしい匂いの煙が漂ってくる。浴衣のカップルたちは手をつなぎ、家族連れの子どもたちは無邪気に水ヨーヨーで遊んでいる。
夜空に散る花火の美しさに見惚れている由規子にプロポーズをした。今思えば、あんな騒がしい中で言わなくてもいいのに、何でだろうな。
起業したときも事務作業のお手伝いしましょうか?と言われたが、家庭に入ってもらうことにした。会社員時代は体育会系の先輩たちに囲まれ大変だった。でも、俺はこうにしたくない、社員が楽しく働ける会社を作りたかったんだ。
由規子はそっと近づきながら横に座る。
「ねえ、あなた?」
「あっそーれ、あっそーれ、そーれそれ」
蚊の泣くような声で音頭をつぶやいていた。
「よほどお疲れのようね。まあ無理もないですよね」
「よーいよい、よいよーい、あっそーれ」
「ゆっくり休養とってから、またやり直しましょう。ね?」
由規子の部屋にある少し大きめの学習机。鍵付き引き出しには、TalkMTCとAPI連携の技術書がしまわれている。それに加え、探偵からの調査報告書の封筒も。
その中には利成が、男と女の密会場から出てくる写真が入っていた。そして、一緒にいた女性の胸元からは深紅の妖しい輝きが放なたれている。
これらを利成が目にすることは生涯無かった。
(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
