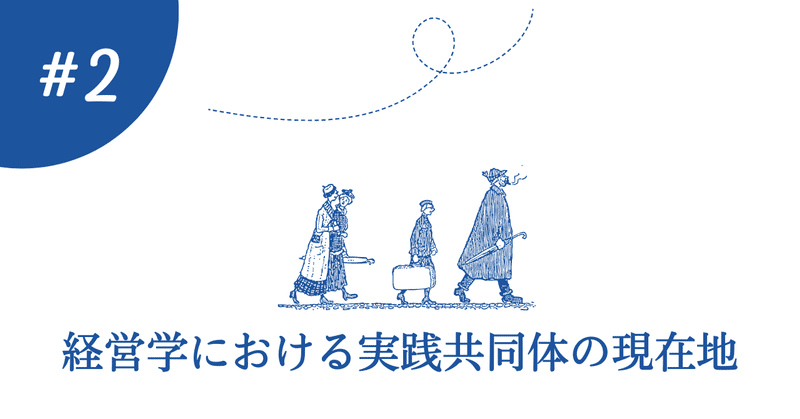
経営学における実践共同体の現在地②
論文検索専用のシステムを使って700以上の論文をリストアップし、そこから具体的な実践共同体を取り扱っている物に絞り込み、日本の研究も加えて約350件ほどの論文をチェックしました。
その結果、原理派と実用派の議論を包摂できる整理として次のような形で分類しました。まずこの第二回では、なぜこのような区切り方をしたのかを解説していきます。

実践共同体はどこにあるのか?
実践共同体は人々の集まりですから社会の至る所にあります。それは物理的な空間を共有していることはもちろん、オンラインでつながることもあります。そのため仮想実践共同体(Virtual Community of Practice)を対象とした研究も多数あり、実践共同体の所在地を一言でいう事はできません。また、素朴に「この会議室によく集まる」とか「Discordでしゃべっている」という状況だけを取ってみてもあまり意味のある議論にはなりません。経営的に語る為には組織との関係性を考えるにあたって意味のあるものの見方が必要です。
そこで今回は縦軸に組織内と外という分け方を置きました。これは上記の通り物理的な話ではなく、実践共同体のメンバーが主として母体となる経営組織に所属しているかどうかという事です。
実践共同体は何のために活動しているのか
経営的に議論するとなれば、絶対に外せないのは「その実践が経営的に意味があるか」という事になります。OJTのように全ての実践が組織成果と直結するわけではありません。先の例で言えば営業として熟達することは経営組織の売上に直結しますが、職場のみんなでパーティーをすることは一見すると仕事とは全くの無関係です。しかし、実はそこでの交流が相互理解を深め、巡り巡って新規事業につながるという事はあり得ます。どのような実践も組織的成果と無関係ではないにせよ(無関係なものもあるでしょうが)、OJTのようなものとパーティーのようなものは分けて考えた方がよさそうです。これは組織外を例に挙げても同じことが言えるのですが、詳しくは各象限の解説に譲ります。
これを分類に反映するため、横軸に実践の志向性を置きました。組織の為の実践なのか、自分の為の実践なのか、ということです。もちろん実践共同体の議論ですからいくら組織の為と置いたとしても、そこにいる個々人が学習し、発達を遂げるのは前提です。この横軸はグラデーションがあって綺麗に分けることが難しいケースもあるのですが、1.組織目的の達成のために、2.組織的にルール化、あるいは暗黙的に慣例化された実践に、3.否応なく(つまり状況によって必然的に)従事しているか否かという視点で分けています。
ではそれぞれの象限が何を意味するのか簡単に触れておきたいと思います。
制度的実践共同体
これはこれまでの例で言えばOJTなどが該当する部分で、組織が最終的な成果に対して目標設定していたり、従業員の参加が予め予定されているものです。ここで制度という言葉を使うのは、組織の多くの人が「それは当たり前だよね」という実践に従事しているからです。最早誰にとっても当たり前な物なので、公式なルールでなくても暗黙的に合意されているものも含みます。それは組織としての過去の成功から導かれた現時点での正解であり、だからこそ従業員は疑問も持たずその実践に参加していくことになります。ここではOJTに限らず、日々の業務の中でその仕事をうまくやるための取り組み事例が多数報告されています。
また、そのような取り組みが成功するには何が影響しているのかという要因の探索が進められているのもこの象限です。小江先生はこういった研究を幅広くレビューされ、その要因を次のように分類されています。

潜在的実践共同体
これは組織内にありながらも、自分たちのやりたいことに基づいて自発的に集まっている人々です。もちろん「新しい技術を開発したい」や「もっと相互理解を深めたい」などの思いには組織的な志向性があるかもしれませんが、これらの実践が組織的なルールや暗黙の合意の下で行われたものではないというのがポイントです。組織の当たり前とは違う形で実践されるため公式な場ではこの実践は観察できないので「潜在的」というわけです。
潜在的実践共同体は、実践共同体が経営学に導入されるにあたって非常に期待をも持つきっかけとなった分類です。この分野の初期的で代表的な研究であるBrown&Duguid(1991)の時点で、組織が規定する方法ではない新しい方法で問題解決するエンジニアの様子が描かれており、実践共同体がイノベーションの源泉となり得る事が指摘されたからです。
その期待の強さ故か、実践共同体はどうすれば経営的な成果を生み出せるかという問いへ傾倒していくあまり、「実践が組織的なルールや暗黙の合意の下で行われたものではない」という視点が忘れ去られ、制度的実践共同体の研究が増えたのは何とも皮肉なことです。なぜならば、組織の管理下にないことによる自由な発想や実践こそがイノベーションの源泉だからです。真に実践共同体からの創造的成果(直線的な技能発達ではない)を期待するならば、やはりこの点は明確に区別して議論すべきなのです。
少し長くなってきたので、残りの二つについては次回に譲るとしましょう。
続く
参考文献
Brown, J. S., & Duguid, P. (1991). Organizational Learning And Communities Of-Practice : Toward A Unified View Of Working , Learning , And Innovation. Organization Science, 2(1), 40–57.
小江茂徳. (2020). 「実践共同体のマネジメント:成功要因に関するレビュー」. 『九州工業大学教養教育院紀要』, 4, 11–24.
