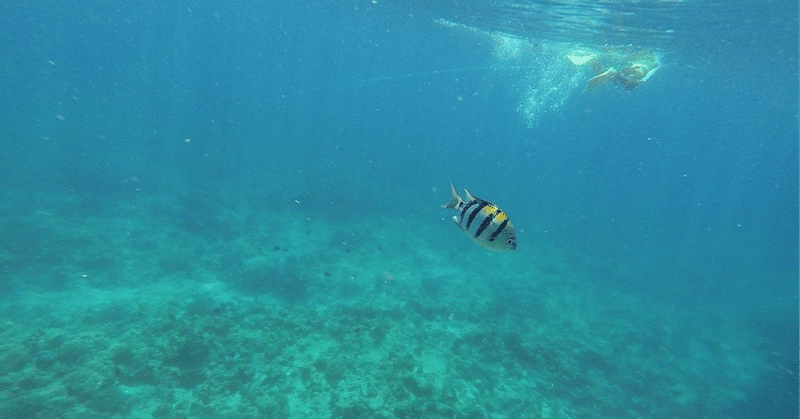
プロダクトをつくろう。そして、そこから「物語」を取り出そう
最近の関心どころから、井庭さんの創造システム理論を紐解いていた。「創造」そのものをシステムとして、人から外部からして捉えることで、その本質を見ようとするアプローチは、「創造」だけに留まらず広く適用が考えられる。例えば、組織システムもその一つとして。
井庭さんの理論では、「創造システム」と関わるためのすべが「パターン・ランゲージ」であり、それは「発見」に導かれるためのメディア(媒介物)となる。創造的な状況に進むには、何かしらの切欠が必要になる。そこでパターンを用いる。パターンによって、自分たち自身にとっての新たな発見を得られるようにする。
ここで、対象を「創造」から「組織」へと切り替えて考えてみる。「組織」も一つのシステムとして見ることができる。数多くのステークホルダーが存在し、イチ個人の判断だけですべてが思うように隅々まで機能するわけではない。たとえ、それが組織を代表する経営者であったとしても。
考えてみれば、この前提(誰かの決定で全部変えられる、わけではない)を置くと組織運営の難易度が飛躍的に高まるがゆえに、「XXXするには、経営のコミットメントが必要」という前提に依り立ちたくなるのだろう。経営のコミットは必要条件ではあるがそれだけで十分ではない。
さらに思い返せば、「実際のところ組織に"芯"なるものがあるわけではなく、自分たちでつくりにいかなければその手触りを得ることはない」という私のたどり着いた結論も、組織を「システム」として捉えれば腑に落ちる。組織が大きくなればなるほどに、絶対的と呼べるほどの意図は見えなくなっていく。
システムが構造であり、当事者間の相互作用であると考えるならば、個人や数名に依る、分かりやすい組織共通の「意図」なるものが存在するはずもない。存在しているように見えるのは、そうと信じる「物語」でしかない。
もちろん、「物語」が良いとか悪いとかそういう話でもなく、ただ、これもシステムにアクセスするためのメディアであるという理解で収まる(創業者の役割とは組織の誰もが自分を当事者だと思える「物語」を描くこと)。
ここまでの整理を踏まえると、「組織変革の手がかりが "プロダクトづくり" になる」という仮説も、後付けで説明がつく。プロダクトづくりそのものが、システムとの関わりを得るためのメディアであり、新たな発見(組織にとって何が必要なのか)と周辺における理解を育む手がかりになるということだ。
あるプロダクトを作り出す意図は、当然ながら何かしらのPSFitを得るためである。と、同時に「プロダクトづくり」と、生み出されるプロダクト、さらにそこから紡がれていく、連続したプロダクトづくりが、組織にとっての「新たな物語」を生み出す契機にもなる。
プロダクトをつくろう。そして、そこから物語を取り出そう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
