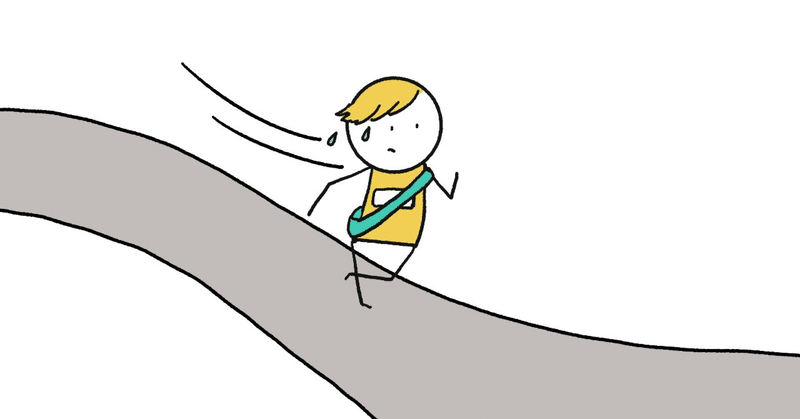
たった1人で始めた会社が横領とケンカを乗り越えて社員200人を超えるまで
おかげさまでうちの会社は年々社員数が増えており、今では200人を超えています。
ただ、ここまでの道のりは「舗装されていないガタガタの道」を進んでいるような感じでした。途中、社員がたくさん辞めてしまったり、ケンカばかりしていたころもありました。
今回は「組織の変遷」についてのお話。
たった1人で始めた会社が、どうやって200人を超える組織にまで成長したのか? そのとき何が起きたのか?
組織作りに関心のある方、現在進行系で組織作りに奮闘している方の参考になればと思い、その経緯について書いてみます。
※ちょっと長いですが、かなり赤裸々に書いたので読んでもらえたら嬉しいです!
近所のカフェが「オフィス」(2016年1月)
始まりは、2016年1月。
最初の「オフィス」は近所のカフェでした。
朝8時に入って夜8時まで居座って、100円のアイスコーヒーを飲みながら作業を続ける毎日でした。今では、この100円コーヒーはもうあまり飲みたくありません。

給料0円で手伝ってくれたエンジニア
エンジニアリングは、前職の同僚のエンジニアである鈴木(@kazuma1218)が副業として手伝ってくれました。
副業といっても無償。僕の起業時の思いである「世界中の人が使ってくれるようなサービスを作りたい」という思いに共感し、無償で手伝ってくれました。最初はもちろんお金がなかったので、めちゃくちゃありがたかったです。
覚えているのは、たしかゴールデンウィークの最終日。朝5時くらいまで彼の家で新機能のデプロイ作業を続けていました。「朝10時には会社に行かなきゃ……」と言いながら付き合ってくれました。
事業が軌道に乗り始めた1年後くらいに、それまでの分のお金をまとめて払いました。
今では、彼はうちに入社してくれていて、大活躍してくれています。初期にもらった恩は絶対に返さないと……と思っています。
組織にするかどうか、一瞬迷う(2016年10月)
事業がうまくいき始めたので10月にコワーキングスペースに入りました。法人化したのは、このタイミングです。

ただ実は、このとき「一人でやっていくのもアリかな」とも思いました。このまま一人でやっていけば、年収1億円を稼ぐ、いわゆる「億プレイヤー」が見えていたからです。一人でそれなりに稼いで、貯金して、早めにリタイアするのも悪くないかも……と一瞬頭をよぎったのです。
だけどそのとき、ふと「そもそもなんで起業したんだっけ?」と考えたんです。僕は「世界中の人が使ってくれるようなサービスを作りたい!」と思って独立しました。そしてそれに対してまわりの人が労を惜しんで協力してくれいていた。そのことを思い出したんです。
結果的に組織化し、世界中の人が使ってくれるようなサービスを作っていくんだという覚悟を、再度決めました。
社員を3人採用する(2016年12月)
最初に誘ったのは、中学の同級生の山崎。
誘いを受けてくれて、いったん雇ったのですが、お互いの期待値が合わなくて(笑)、1週間くらいで「やっぱり前の会社に戻ったほうがいいかも」と告げました。話しあった結果、辞めることになりました。
年が明けて、2017年の1月。
代官山のワンルームのマンションを借りました。10畳くらいの、全部で7坪の一人暮らし用の部屋です。そこに、イケアで机を買って、ニトリで椅子を買って置きました。どちらもお店にあったいちばん安いやつです。
その後、あらためて3人の社員をWantedlyで採用。「さあ、ここから世界を変えていくぞ」と意気込んでいた……のですが……。

横領事件が起きて全員辞める(2017年3月)
入った3人の社員は、3ヶ月も立たずに全員辞めてしまいました。
というのも、そのうちの1人が横領事件を起こしたから。それでなんとなく変な空気になって、結局みんな辞めてしまったのです。
また0に戻りました。
横領された金額は20〜30万円ほど。今思えば、金額的には大したことないですが、それよりも「信頼して採用した社員から裏切られた」というメンタル的なショックのほうが大きかったです。「俺のどこが悪かったのかな?」と眠れない夜を過ごしたこともありました……。
横領されて失意の底にあるとき、一度辞めてもらった中学の同級生の山崎に相談しました。
彼はもともと管理畑で、法務系にも詳しかったので、横領した人と交渉し、返金などの対応をぜんぶやってくれました。そこで「もう一度、一緒にやらないか?」と誘い、そのままうちに再入社することになりました。
その後、彼は管理部長としてバックオフィスを長く担ってくれたのち、今では執行役員として事業サイドの部長をやっています。
社員を「フルスロットル」で採用
採用はこの頃からつねに「フルスロットル」でした。
3人の社員が全員辞めてしまった反省を踏まえて、面接をもう少し丁寧にやるようになりました。
採用媒体は「ビズリーチ」や「Wantedly」や「Green」など目ぼしいものはすべて使っていました。ただ、やっぱり知名度がなかったので特に中途社員の採用難易度は高かったです。
2017年夏には海外進出を決断します。
外国籍のメンバーも積極的に採用していきました。台湾語教室に行ってそこの先生や代々木のインドネシアフェスに行って来ている外国籍の人をスカウトしてきたりもしました。
僕の目標は「世界中の人が使ってくれるようなサービスを作る」こと。早いうちから海外進出の種まきをしたかったんです。今思えば、それにしても早すぎだったなとは思います(笑)。
この時点で社員は7〜8人いましたが、そのうち外国籍のメンバーは2人いましたし、アルバイトを合わせると10人くらいはいたので、いきなり多様性あふれる職場になっていました。10畳しかないワンルームなのに。

築地にオフィス移転(2017年10月)
その後も人が増えていきそうだったので築地の80坪のワンフロアのオフィスに引越しました。築地にした理由は、たまたまいい物件があったからです。
人がどんどん増えていくので、オフィス移転も急ピッチでやらなければいけませんでした。移転する時点で家具が間に合わず、とりあえずマンションからイケアの机を持って行って、それで1ヶ月くらいしのいでいました。

キーパーソンの入社(2017年11月)
このころ、一人目のキーパーソンが入社します。
CTOの渡邉(@miraoto)です。前職はリブセンスで新規事業を担当していたエンジニアでした。
それまでいわゆるピカピカの経歴の中途の人はいなかったんですが、初めてそういった人が来てくれた(笑)。
最初に会ったのは、まだ代官山のワンルーム時代です。ワンルームの中で面接をするので、話す内容は他のメンバーにも筒抜けでした。
面接では「すでにエンジニアが社員で1人いるので、安心して来てください」と言ったのですが、実は直前に辞めてしまって……彼には「すみません。スタートアップあるあるなんで」と言って、謝りました。肩書はCTOでしたが、入社した時にエンジニアは彼一人でした。
渡邉の入社後は、彼自身が優秀なエンジニアをどんどん連れて来てくれました。「優秀なエンジニアの周りには優秀なエンジニアがいる」みたいな法則はある気がします。
渡邉は今もCTOとして活躍し続けてくれています。
初めて「組織」にする
それまでは社員全員が僕の直下だったのですが、この頃に初めて「組織図」を作りました。
社員は15人ほどになっていました。なかには問題児もいました。
たとえば大学を卒業してから、短期間のあいだに何社も渡り歩き、毎回上司と喧嘩して辞めてきてしまったような子。おそらく普通の会社では行くところがなかったので、うちに拾われたような格好でした。
でも、そういう子たちは「逃げるところがない」という意味で覚悟があった。僕の隣の席に置いて、徹底的に教育したらメキメキ成長しました。そういう子たちが、この頃の会社の成長を引っ張ってくれました。
やはり逃げ場がない、覚悟を持った人は強いです。僕自身はそういった子たちに出会えて、とても運が良かったと思っています。
ただ、初期のみんなには悪いのだけど、いま考えると「このメンバーでよくやってたな」とも思います(笑)。

外部パートナーの人たちに助けられる
そんな不安定な初期の組織を成り立たせてくれていたのは、業務委託やクラウドワーカーなど、会社の外部パートナーの方たちでした。
いわゆる”外注”ではありますが、何十人ものネットワークがあって、コンテンツ制作を助けてもらっていました。
僕としてはそういった人たちに対しても、社員と同じように、教育や考え方の浸透に力を入れて接していました。
「何を大事にしなければいけないのか」というマインドセットや「どうやってコンテンツを作っていくのか」というノウハウを何回も伝え、一文字とか行間とかにもこだわって編集していくところをずっと見せていました。
そういったことを通して、社員だけでなく、外部パートナーも含めて「ユーザーファーストの精神」を根付かせることができました。その結果「納品して終わり」ではなく、「ユーザーにとってどういう情報を届けるべきなのか?」を、時間を惜しまずに一緒に考えてくれるような外部パートナーのネットワークができたんです。
このネットワークの存在が初期の会社の成長の原動力だったと思います。
採用は何も考えていなかった
恥ずかしながら、この頃は社員の採用に関しては、あまり何も考えていませんでした。面接でどういうところを見ればいいのかなんてわからない。「まあ、大丈夫そうかな」くらいの感覚で採用していました。
でも不思議と大きないざこざはありませんでした。
優秀な人が集まると、それぞれプライドがあるので衝突するのかもしれませんが、ある意味うちは知名度もなく採用が弱かったので、採用できたのは優秀な人というよりは、何も失うものがないやつばかり(笑)。だから自然と「みんなでいいものを作ろう!」という方向に気持ちが向いていました。
採用した社員は、ほぼ20代。エンジニアやデザイナーといったプロフェッショナル職種だけは30代がいました。
インターンもけっこう採っていて、かなり力を発揮してくれていました。優秀な学生を採るために、Wantedlyでスカウトしたり、友だちの友だちから引っ張ってきたりもしていました。
さらにキーパーソンの入社(2018年3月)
年が明けて2018年。
もう一人のキーパーソンが入社します。2023年現在、執行役員をやっている佐藤(@ykst_1018)です。
出会いは転職サイトの「Green」。Greenには、求職者に対して「いいね」を送る機能があります。今はわからないですが当時はその「いいね」を無料で押せました。スカウトだとお金がかかるのですが、「いいね」であれば無料で押せた。だから、死ぬほど押していました。
そのとき佐藤は、社会人1年目。
前職で営業をやっていたので、入社後も最初は広告の営業に配属しました。まあ、当時は広告のチームに社員は1人しかいないので、配属も何もないのですが……。
やってもらったら、いきなりすごい結果を出してきました。目標対比200%達成が毎週続くような状態です。僕は「どうやったらそんなことできるんだろ?」って思ってました。すごく能力の高い子でした。
その後は、コンテンツ部門や開発部門を渡り歩いてもらって、今では100人くらいの組織を見る執行役員になっています。年齢もまだ28くらい。若いのによくやってくれています。
ケンカが増え始める
初期の頃はみんな仲がよかったのですが、組織が大きくなってくると、それにつれてケンカも増えてきました。
たとえば、20代の子が急に何人もの部下を抱えるリーダーになるわけです。すると求められる期待値はどんどん上がっていく。でも当然、リーダーとしての能力は足りないわけです。そこで僕が「なんでこんなことできないの?」みたいなふうに詰めてしまう。するとそれでだいたいケンカになっていました。
ときには泣いて会社を飛び出して帰ってこないなんてこともありました。それをみんなで探しに行く……。そんなことを繰り返していました。
初期メンバーが会社のDNAを作る
いま振り返ると、最初の1〜2年の「初期メンバー」が重要だったような気がします。そこを妥協すると組織の質が下がってしまうからです。
もし社員が200人いたら、合わない人が10人くらいいてもそんなに問題はないかもしれません。でも20人の会社に合わない人が1人2人でもいると、きつくなる。その人に引っ張られちゃったり、空気も悪くなります。
なので、会社の「DNA」を作る上でも初期のメンバーというのはすごく大切だと思っています。
意識していたのは「居てほしいメンバーが居やすい環境を作ること」です。逆にダメなのは、組織に合わないメンバーが居やすい環境になってしまうこと。
もちろん採用時点でそういうスクリーニングが完璧にできれば、それに越したことはありませんが、やはり中には、採用したけど組織にフィットしない人というのは少なからず出てきます。
よく「辞めるまで待とう」と放置してしまう会社もあると思いますが、僕は合わないと思ったらその人のためにも「合わないと思うよ」とハッキリ言うようにしていました。それがお互いのためになると思ったからです。
もちろんそういう人が転職活動をするとなったら、その期間の給与は払うし、退職に伴っては生活保障の意味で生活に困らないようにお金も払ってきました。
そういうことを初期に逃げずにやってきたのは結構大きいことだったと思います。
ベンチャーも次第に大きくなってくると「仕事はできないけど古くからいる」というだけで幅をきかせてる人がいたりしますが、うちにはそういうのがありません。
だからDNAは正常だし、みんな優しくて仲がいいんです。
初期のうちから管理部門を固められた安心感
最初の社員である中学の同級生の山崎には「管理部門のトップ」をやってもらったのですが、これも僕が事業に集中できるという意味でとてもよかったなと思っています。
背中を預けられる人間が管理部門のトップなのは大きい。そこが信頼できない人物だと、つねにお金や管理系のことを気にしながら事業をやらなければいけないので大変だったと思います。
今は、僕の大和証券時代の同期である木本(@hiromi_kmt)がCFOを引き継いでくれています。新卒で出会って20年弱の付き合いになるのですが、彼女もすごく優秀で信頼できる人です。
「いいこと」を発表する会を始める(2018年5月)
2018年、社員は30人くらいになっていました。
そこで5月に始めたのが「ウィンミーティング」と呼ばれる全体会でした。

初期の頃は特になにかと大変なことが起こります。言ってしまえば、ずっとうまくいかないことばかり。それだと、気が滅入ってくる。そこで「ウィンミーティング」というものを始めたんです。
ウィンミーティングは、成果やうまくいったことを発表する会。
反省会ではなく、いいことにフォーカスした会。「こんなことができました!」「これを達成しました!」と発表したら、みんなで「すごいね!」と称賛するんです。
スタートアップで最も重要な”お祝い”と”コミットメント”のサイクルをうまく回すために、ウィンミーティングはとても大切な会として、今でも半年に一回、盛大に行なっています。
さらにオフィス移転(2018年10月)
2018年10月には、またオフィス移転をしました。
次も築地です。「1年に1回オフィスを変える」という感じで、1年ごとにフロアは広くなっていきました。
新しいオフィスは200坪。前のオフィスが80坪なので、倍以上の広さになりました。ここから人数もバーッと増えていきました。

モノを検証するためのスペースも足りなかったので、目の前のマンションを借りたりもしました。そこで使う家具なんかも普通に「ららぽーと」に買い出しに行ったりしていました。

「バリュー」をちゃんと決める(2019年4月)
社員が増えてきて困ったことがありました。
それは僕の声が届きにくくなっているということ。みんなで共通の議論ができていないと感じることも増えてきて、人がごっそり辞めるようなことも起き始めました。
そこでやっぱり「価値観を揃える」ことがすごく大事だなと思ったんです。社員が辞めてしまったり、揉めてしまうときは、根本の「価値観」が違うケースが多かった。
当時、会社の価値観である「バリュー」はあるにはありましたが、それを浸透させるように頑張っていたかといえば、そんなに頑張っていなかった。
中身も、僕がなんとなく決めたものでした。社長からバリューが与えられても、社員はなかなか「自分ごと」にできません。そこで、改めてみんなで考えてバリューを作ることにしたんです。ワークショップをやって、それまで5つあったバリューを3つに変更しました。
それまでは採用も、パッションや根性を重視していましたが、この頃から「バリューや事業に対する共感」を重視していく方向に変えていきました。

新卒1期生が入社した(2020年4月)
2020年に初めて「新卒メンバー」が入社しました。
この頃から新卒採用にかなり力を入れ始めました。知名度がなく、優秀な中途が取れない中で、会社の中で中心的に活躍してくれていたのはインターンや第二新卒の子たちでした。
なんの気なしに、新卒採用の募集を出してみたら応募が結構来た。BtoCの自社プロダクトがあるベンチャーで、新卒採用をしている会社は意外とあまりなく、ポジショニングが良かったんだと思います。
今では新卒採用が人事戦略の核になっています。
マイベストは「売上を大きくする」とか「利益を上げる」といったことよりも「ユーザーファースト」などの価値観を重視しているので、まっさらな状態の新卒のほうがマイベストの文化や価値観をスムーズにインストールすることができます。
将来的には、そういった会社の考え方の理解度が高い人たちが会社を引っ張っていってほしいと考え、新卒採用をしているんです。今では社員約200人のうち、新卒で採用したメンバーが80人ほどを占めます。




オフィス移転したらコロナでピンチ(2020年)
2019年もさらにグーっと社員は増えていきました。
またオフィス移転です。
次の移転先は、1000坪のオフィスを選びました。代官山のマンション時代から数えれば、7坪(2017年)→80坪(2017年)→200坪(2018年)→1000坪(2020年)と、オフィスの広さは右肩上がり。
……が、そこで始まったのがコロナでした。
他社はオフィスを解約するところもありましたが、僕らは入居することが決まっていたので、そこは腹をくくるしかありませんでした。
せっかく1000坪もあるオフィスを借りたのに、みんな出社できない。「お金がもったいないな」とは思いましたが、そこはもう仕方がありませんでした。

リモートワークは、やっぱり大変でした。
ただでさえ新しい人がたくさん入ってきているのに、リモートワークによって社員とのコミュニケーションが減ってしまう。正直不安でした。
コミュケーションの機会を減らさないため、チームごとにいろいろ工夫をしました。オンラインにはなりますが、全体会も月一で行ない、「ウィンミーティング」も3ヶ月に1回は継続していました。
この頃はちょうど、Zホールディングスとの資本業務提携の交渉も大詰めでした。それもあって本当に大変だった記憶があります。
2020年6月に提携するわけですが、その1年前くらいから裏で交渉を進めていました。提携の話なので、おおっぴらに人に相談できない。会社の中心を担っていた3人くらいのメンバーにしか詳細は話せませんでした。
人事部長が入って採用が変わった(2021年4月)
組織へのインパクトでいうと、人事部長の品川(@shinagawatomoya)が入社してくれたことは大きかったです。それまで人事の責任者はコロコロ変わっていて、彼が来る直前は僕が人事部長を兼任していたくらいでした。
エージェント経由で知り合った彼は、前職のレバレジーズで100人規模の組織を1000人レベルに成長させた人でした。「今の自分たちに必要な人材だと」思い何度も熱心に誘うと、入社してくれることになりました。
彼の入社後は、人事や採用を戦略的に考えられるようになりました。
彼は「どの媒体を使うか?」「どういう採用経路で行くか?」という個別の戦術にはもちろん強いですし、「組織運営の上で何を抑えないといけないのか」「会社のどういうところを採用で訴求していくか?」という全体の戦略も構築することができる。そして、それを実現するためにどうすればいいかも知っています。
人事部長が入ったことで、さらに優秀な新卒を採用することができていますし、この頃くらいから優秀な中途もどんどん採用できるようになりました。
「MONOQLO」元編集長の入社
同時期に入社したのがモノ批評雑誌の最大手である「MONOQLO」の元編集長の浅沼(@asanumaiori)です。
彼もエージェント経由で知り合いました。
マイベストとMONOQLOは「モノを比較する」という点で同じことをやっています。なので「嫌われてるかな」と心配だったのですが、第一声で「mybest、すごいですね」と言ってくれたんです。
彼は純粋にモノを比較することが好きで仕事をしています。そしてそれをユーザーに伝えることにおいて、日本に彼の右に出る者はいないように感じます。「その能力を生かすのは、うちの会社以外にはないでしょう」ということで、比較的スムーズに入社してくれました。
浅沼が入ったことで、コンテンツのクオリティの拠り所ができました。「良し悪し」の基準です。これまではチェックするマネージャーによってコンテンツの基準が違っていて、忙しいと少しゆるくなったりもしていた。そこの基準が、彼の入社によって明確になったのは大きいことでした。
それは他のメンバーの精神的な支柱にもなっています。「クオリティのことで困ったら彼に聞けばいい」という安心感がある。そこは数字には表れにくいですが、そういう人がいるのはとても大きいことだと思います。
優秀な人材が続々入社(2022年1月〜)
2022年には、優秀な人材が続々入社してくれました。(内輪の話ですが3人だけ紹介させてください。)
いま、マーケティング部門の責任者をやっている荒井(@levaraim)。
人事部長の品川が前職で同僚だった人です。荒井もレバレジーズでマーケティングの責任者をしていた経験豊富な人です。彼には今、SEO・広告出稿・広報など、マーケティング全般をかなり広く見てもらっています。
さらに土橋という広告営業のプロフェッショナルも広告部門の責任者として入ってくれました。
彼はもともと「バリューコマース」という広告代理店で部長をやっていて、マイベストの担当者でした。土橋がすごいのは営業力が高いだけではなく、戦略を考えられること。営業が得意な人は、戦略を考えるのが苦手な人が多いように思うのですが、彼はクライアントのニーズやmybestの強み弱みから、全体のマネタイズ戦略を作ることができる。なかなかいないタイプだなと思っています。
2022年の10月には、経営企画の責任者として岸本(@yjksmt)が入社しました。
DeNAでゲームのプロデューサーをやり、そのあと経営企画に移ったような経歴の人です。さらに数社のベンチャーを挟んで、うちに来てくれました。
いままで会社の事業戦略について、真の意味で僕が相談できる人が社内にはおらず、ほぼ僕一人で戦略を考えていました。そこに初めて事業の戦略面で相談できる人ができた。いまは、経営企画部長をしてくれていますが、彼の手腕でmybestがさらに次のフェーズに行けるように感じています。
経営しているといろんな事件が起こる
……というわけで今、社員の人数は200人を超えています。
振り返ってみると、いろいろあって、病んでしまったり落ち込んだりする時期もいっぱいあった気がします。でもほとんど忘れてしまいました(笑)。事業は目まぐるしいスピードで進展するしていくので「やるしかねえ」という感じで、切り替えていくしかないんです。
ここに書けないような、表に出せない事件もたくさんありました。経営をしていると本当にいろんなことがあるんです。
社長をやるというのは、精神的にとてもつらいことばかりです。……でも、だんだん何も感じなくなってきたのも事実です。「傷ついて、再生して」を繰り返すうちに、精神的に強くなったんだと思います。
それに、いろいろあったけど事業のほうは順調でした。結果的にコロナも僕らの追い風になった。「売上はすべてを癒やす」ではないですが、やっぱり心の支えになりました。
*
7年前にたった一人、100円コーヒー片手に始まった会社は、いろんな人と出会って、大きくなっていきました。
それでも、マイベストはまだまだです!
というより、これからが本番です!!
僕の目標は起業当初から1ミリもぶれていません。
「世界中の人が使ってくれるようなサービスを作ること」
これから海外展開も本格的に始まりますし、アプリの開発も進めていきます。
今がいちばん面白い時期だと思います。
ぜひ、一緒に世界を変えませんか?
少しでも興味を持ってくれた人は、こちらのURLから申し込んでもらって、カジュアルにお話ししましょう!
https://my-best.com/company/recruitment

*
Twitterもフォローしてもらえるとうれしいです!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
