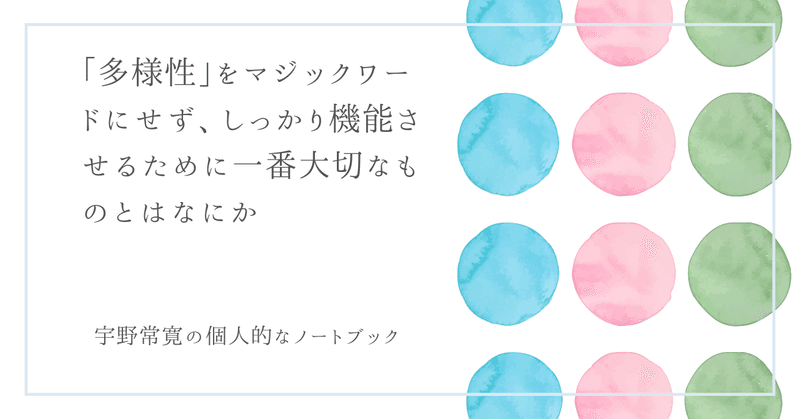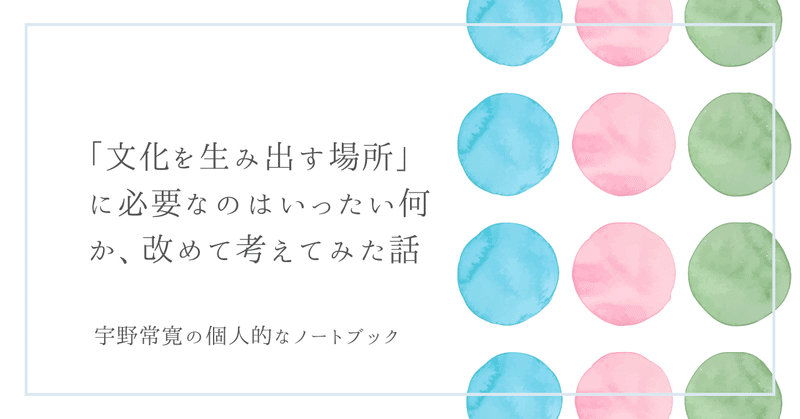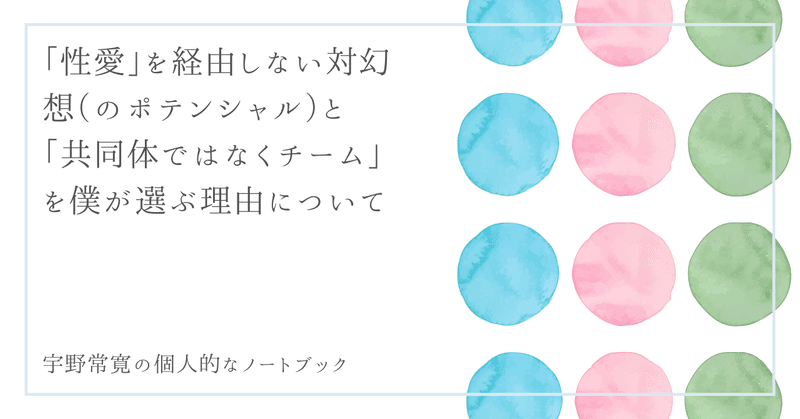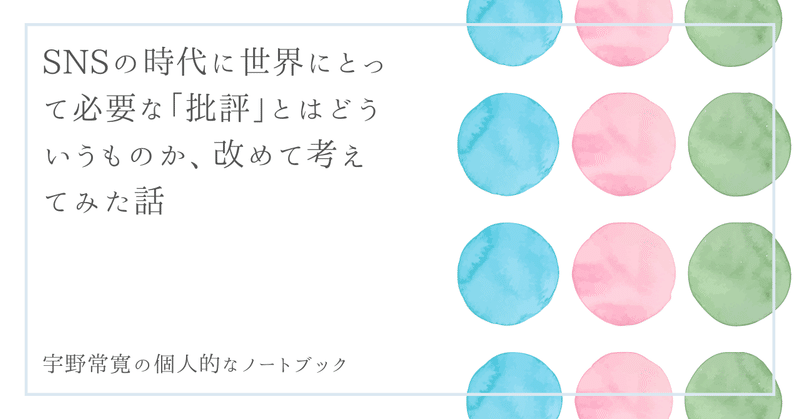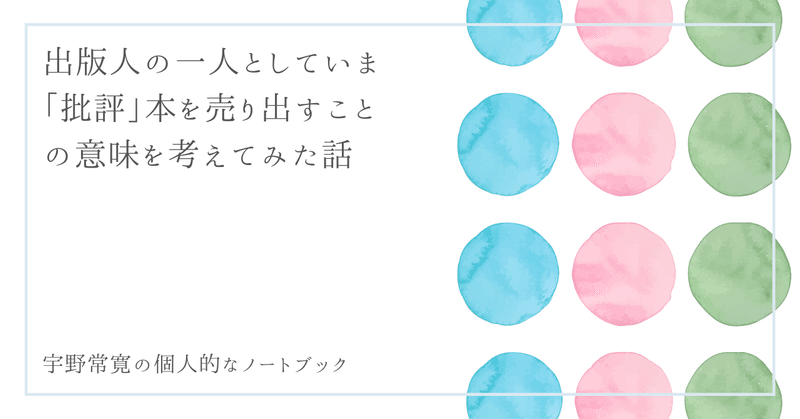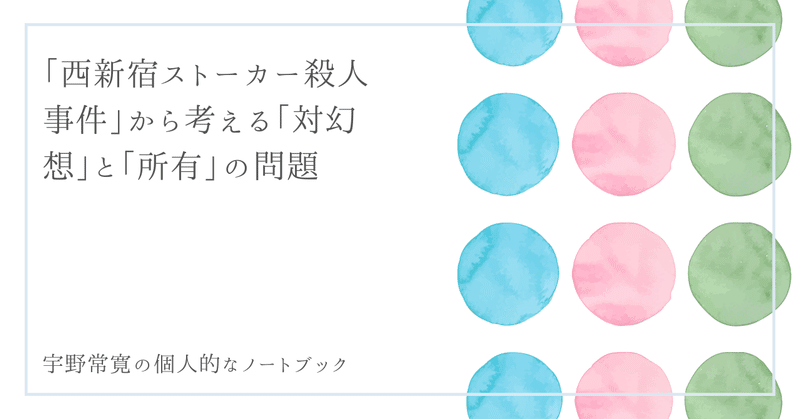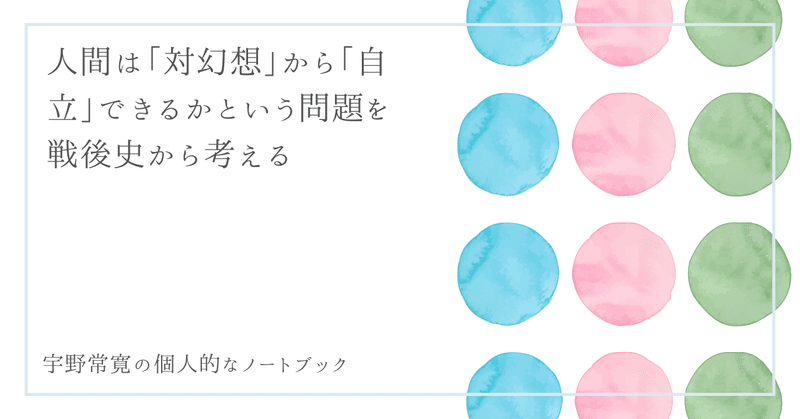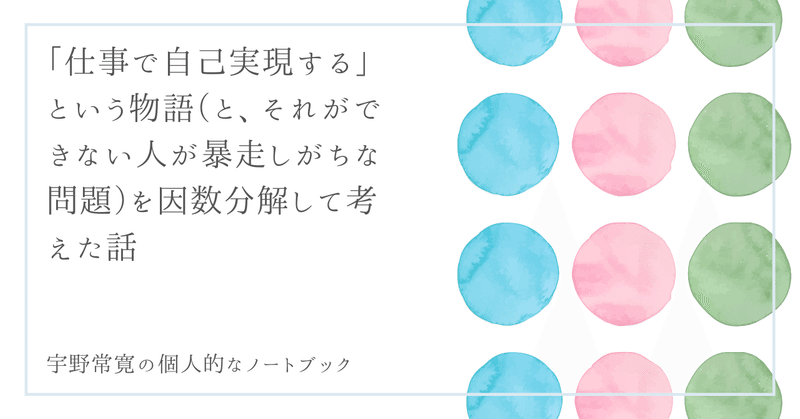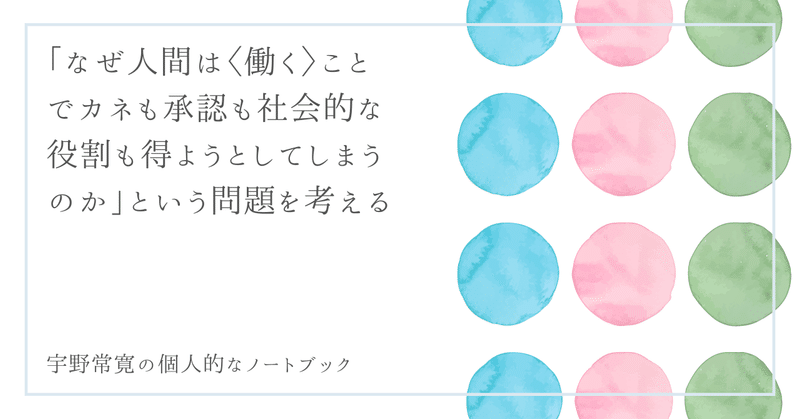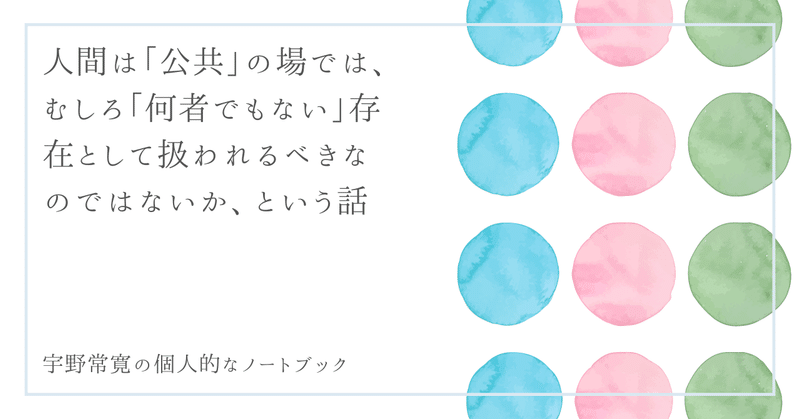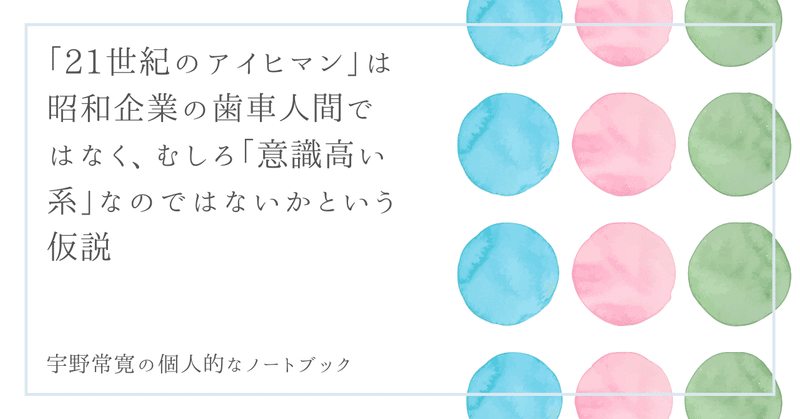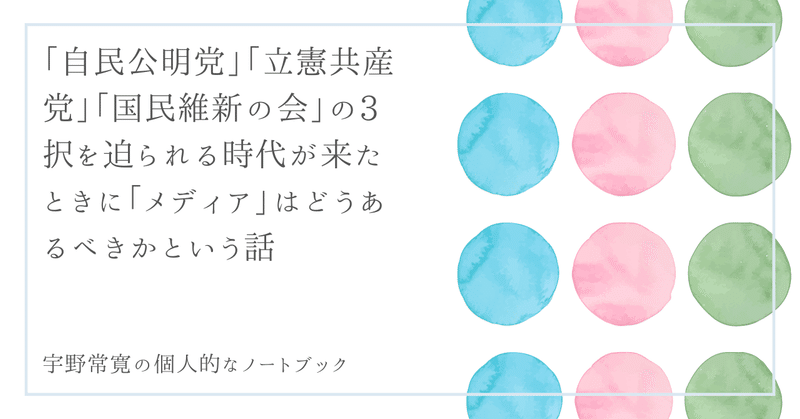宇野常寛
宇野常寛 (評論家/「PLANETS」編集長) 連絡先→ wakusei2ndあっとy…
最近の記事
- 固定された記事

これからの社会は「承認」のゆりかごを充実させるか、「評価」のハードルを下げるかの二択になる(そして僕は後者のほうがいいと考える)話
さて、今日はちょっと変わった話から始めたい。少し前に國分功一郎さんの『中動態の世界』について、書いた。 要するにそこで僕は、彼の述べる『中動態の世界』とは、意外とこのSNSプラットフォーム中心の社会に近く、そして現行の世界(能動態/受動態の世界で記述される世界)と新しい「中動態の世界」がうまく噛み合っていないのではないか、ということを書いたのだ。 たとえば『テラスハウス』事件では、視聴者とメディア(フジテレビ)とプラットフォーム(Instagramと旧Twitter)が実