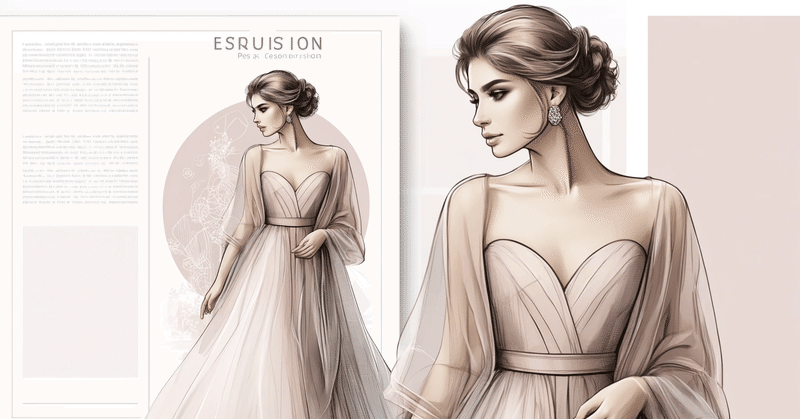
論文まとめ321回目 Nature 体内の炎症反応を制御する脳-体の回路を発見!?など
科学・社会論文を雑多/大量に調査する為、定期的に、さっくり表面がわかる形で網羅的に配信します。今回もマニアックなNatureです。
さらっと眺めると、事業・研究のヒントにつながるかも。
世界の先端はこんな研究してるのかと認識するだけでも、
ついつい狭くなる視野を広げてくれます。
一口コメント
A body–brain circuit that regulates body inflammatory responses
体の炎症反応を制御する体-脳回路
「私たちの体には、体と脳をつなぐ「体-脳回路」があります。この回路は、体の炎症反応を感知し、脳に伝えています。脳はその情報を受けて、炎症反応をコントロールしているのです。この回路を遮断すると、炎症反応が制御不能になってしまいます。一方、この回路を活性化させると、炎症を抑えて炎症を鎮める反応を高めることができました。自己免疫疾患や、重篤な炎症反応であるサイトカインストームなどの治療に、新たな可能性を開く発見です。」
Structures of human γδ T cell receptor–CD3 complex
ヒトガンマデルタT細胞受容体-CD3複合体の構造
「ゼブラフィッシュの脳を使って、個々の神経細胞のシナプス数を睡眠・覚醒状態で追跡。一日の中でシナプス数は増減を繰り返し、睡眠圧(眠気)が高まるほどシナプスが減少しやすくなることがわかった。シナプス数の調節には、神経細胞の種類や樹状突起の部位によって違いがあり、ダイナミックな仕組みが明らかに。睡眠のシナプス調節機能の理解が一歩前進。」
Paternal microbiome perturbations impact offspring fitness
父親の腸内細菌叢の乱れが子孫の健康に影響を及ぼす
「父親の腸内細菌のバランスが乱れると、生まれてくる子どもの体重が低く、重度の発育不良や早期死亡のリスクが高まることが、マウス実験で明らかになりました。この影響は精子を通じて次世代に伝わりますが、腸内細菌叢が回復すれば元に戻ります。腸内細菌叢の乱れは、精巣内の代謝物や精子中の小分子RNAを変化させ、子宮内で胎盤の発達不全を引き起こすことが原因と考えられます。父親の生活習慣が子どもの健康に影響する新たなメカニズムの発見です。」
Airway hillocks are injury-resistant reservoirs of unique plastic stem cells
気道ヒロックは、損傷抵抗性を持つユニークな可塑性幹細胞の貯蔵庫である
「マウスやヒトの気道には「ヒロック」と呼ばれる特殊な上皮構造が点在しています。今回、ヒロックには独特の幹細胞が存在し、毒物、感染、酸、物理的損傷など様々な傷害に強い抵抗性を示すことが明らかになりました。さらに驚くべきことに、ヒロック幹細胞は傷害後に増殖し、気道上皮の6種類全ての細胞型に分化する能力を持っていました。一方、ビタミンA欠乏などの刺激により、ヒロックは拡大し、肺がんの前駆病変と考えられている扁平上皮化生になることもわかりました。ヒロックの発見は、気道の再生メカニズムの理解を大きく変える成果です。」
Geographic variation of mutagenic exposures in kidney cancer genomes
腎臓がんゲノムに見る変異誘発物質への曝露の地理的多様性
「11カ国962人の腎臓がんゲノムを解析したところ、変異パターンに地域差があることが判明。ルーマニアやセルビアではアリストロキア酸による変異の特徴が見られ、日本では原因不明の変異パターンが70%以上の症例で検出された。また、腎臓がんの発生率が高い国ほど特定の変異が多いことから、未知の変異誘発物質の存在が示唆された。世界規模のがんゲノム解析により、がんの原因解明に新たな手がかりが得られた。」
Mechanics of human embryo compaction
ヒト胚の細胞凝集の力学
「ヒト体の形づくりは受精卵が桑実胚へと変化する「細胞凝集」から始まる。本研究では、マイクロピペットを用いてこの過程の細胞表面張力を測定。凝集中、細胞-培地間の張力は4倍に上昇するが、細胞間の張力は一定に保たれていた。また、細胞収縮阻害剤の実験から、細胞収縮力こそが凝集の駆動力であることが判明。ヒトとマウスを比較すると、同じメカニズムながら、ヒトの方が力学的効率が低いことも明らかに。ヒト体づくりの理解が飛躍的に前進した。」
要約
体内の炎症反応を制御する脳-体の回路を発見
体と脳をつなぐ「体-脳回路」が、体内の炎症反応を感知し、脳がその情報を受けて炎症反応を制御していることを明らかにした。この回路を遮断すると炎症反応が制御不能になる一方、活性化させると炎症を抑え、炎症を鎮める反応を高めることができた。単一細胞RNAシーケンスと機能イメージングにより、この神経-免疫回路の構成要素を同定し、その選択的操作により炎症性反応を効果的に抑制しつつ、抗炎症状態を高められることを示した。この脳による免疫応答の変化は、自己免疫疾患からサイトカインストームやショックまで、幅広い免疫疾患の調節に新たな可能性を提供する。
事前情報
体-脳回路が臓器機能、代謝、栄養状態を感知・制御することが知られている。
行ったこと
末梢の免疫刺激が体-脳回路を強力に活性化し、免疫応答を制御することを示した。
炎症性および抗炎症性サイトカインが、異なる迷走神経ニューロン集団と通信して脳に炎症反応を伝えることを実証した。
この体-脳回路の遺伝的サイレンシングにより、制御不能な炎症反応が生じることを示した。
逆にこの回路を活性化させることで、免疫応答の優れた神経制御が可能になることを示した。
検証方法
単一細胞RNAシーケンシングと機能イメージングを用いて、この神経-免疫回路の構成要素を同定した。
この回路の選択的操作により、炎症性反応を効果的に抑制しつつ、抗炎症状態を高められることを示した。
分かったこと
末梢の免疫刺激が体-脳回路を介して脳に伝えられ、脳が末梢の免疫応答を厳密に調節していること。
この体-脳回路の遺伝的サイレンシングにより、制御不能な炎症反応が生じること。
逆にこの回路を活性化させることで、免疫応答の優れた神経制御が可能になること。
単一細胞RNAシーケンシングと機能イメージングにより同定した神経-免疫回路の選択的操作により、炎症性反応を効果的に抑制しつつ、抗炎症状態を高められること。
この研究の面白く独創的なところ
体-脳回路による免疫応答の制御という新たな概念を提示した点。
炎症性・抗炎症性サイトカインが異なる神経集団と通信するという洞察。
回路の遮断と活性化で正反対の免疫応答変化を見出した点。
単一細胞解析と機能実験を組み合わせ、操作可能な神経-免疫回路の同定に成功した点。
この研究のアプリケーション
自己免疫疾患、サイトカインストーム、ショックなど様々な免疫疾患の新たな治療戦略につながる可能性。
体-脳回路を標的とした免疫応答の選択的制御法の開発。
炎症の人為的コントロールによる病態モデル動物の作成など基礎研究への応用。
著者と所属
Hao Jin, Mengtong Li, Eric Jeong & Charles S. Zuker (Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, Howard Hughes Medical Institute and Department of Biochemistry and Molecular Biophysics, Columbia University, New York, NY, USA; Department of Neuroscience, Vagelos College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, NY, USA)
詳しい解説
本研究は、体内の炎症反応を脳が制御する新たな仕組みを明らかにしました。体と脳をつなぐ「体-脳回路」が、体内の炎症反応を感知し、その情報を脳に伝えているのです。さらに脳は、その情報を受けて炎症反応を積極的に制御していることが分かりました。
研究チームは、マウスを用いて実験を行いました。まず、末梢で免疫を刺激すると、体-脳回路が強力に活性化されることを見出しました。炎症を促進するサイトカインと、炎症を抑えるサイトカインが、それぞれ異なる迷走神経ニューロンの集団と通信し、炎症反応の情報を脳に伝えていたのです。
次に、遺伝学的手法でこの体-脳回路をブロックしたところ、炎症反応が制御不能になり、暴走してしまいました。つまり、この回路は炎症反応を適切に制御するために不可欠だということです。
一方、この回路を活性化させると、炎症反応を抑え、炎症を鎮静化させる反応を高めることができました。研究チームは、単一細胞RNAシーケンスと機能イメージングを駆使して、この神経-免疫回路を構成する細胞群を同定しました。そして、この回路の特定の部位を選択的に操作することで、炎症反応を効果的に抑制しつつ、抗炎症状態を高められることを示したのです。
これらの結果は、脳が体の免疫応答をダイナミックに変化させ、制御できることを示しています。自己免疫疾患や、重篤な炎症反応であるサイトカインストームやショックなど、様々な免疫関連疾患の新たな治療戦略につながる可能性があります。体-脳回路を標的とすることで、免疫応答を選択的に制御できるようになるかもしれません。
また、この発見は、基礎研究の面でも重要な意義があります。体-脳回路を操作することで、炎症の程度を人為的にコントロールした病態モデル動物を作成できるようになるでしょう。炎症反応の理解を深め、より効果的な治療法の開発につなげていくことが期待されます。
本研究は、脳と体の相互作用という観点から免疫システムを捉えなおし、脳による免疫制御という新たなパラダイムを提示しました。体-脳回路を介した炎症反応の制御機構の解明は、今後の免疫学研究と医療応用に大きなインパクトを与えるものと期待されます。
睡眠圧が個々の神経細胞のシナプス数を調節する
本研究では、ゼブラフィッシュの視蓋にある単一神経細胞のシナプス数を睡眠・覚醒状態で追跡し、シナプス数の調節メカニズムを調べた。その結果、シナプス数は1日の中で増減を繰り返すこと、睡眠圧が高まるほどシナプス数が減少しやすくなること、シナプス数の変動パターンには神経細胞の種類や樹状突起の部位による違いがあることがわかった。また、シナプス数減少には、アデノシンシグナルの活性化とノルアドレナリンシグナルの抑制が関与することが示唆された。本研究は、睡眠によるシナプス数の調節機構の理解を大きく前進させる成果である。
事前情報
睡眠中はシナプスの数や強度が減少し、覚醒中は増加すると提唱されている(シナプス恒常性仮説)
これまでの研究では、大脳皮質全体や樹状突起の一部でシナプス数の変化が観察されている
睡眠がシナプス調節に必須なのか、それとも許容的な状態なのかは不明だった
行ったこと
ゼブラフィッシュ幼生の視蓋にある単一神経細胞を蛍光タンパク質でラベルし、共焦点顕微鏡で繰り返しイメージング
睡眠・覚醒状態、概日リズム、睡眠剥奪の条件下でシナプス数を追跡
神経細胞のサブタイプごとにシナプス数の変動を解析
薬理学的操作で睡眠を誘導し、シナプス数への影響を調べた
検証方法
FingR-PSD95システムを用いて興奮性シナプスを蛍光ラベル
共焦点顕微鏡による長時間ライブイメージング
画像解析によるシナプス数とシグナル強度の定量
行動解析による睡眠量と睡眠ボウト長の測定
薬理学的睡眠誘導と睡眠圧の操作
分かったこと
シナプス数は覚醒中に増加し、睡眠中に減少する
睡眠圧が高いほど、その後の睡眠中のシナプス減少が大きい
神経細胞のサブタイプや樹状突起の部位によって、シナプス数変動のパターンが異なる
睡眠剥奪後の回復睡眠中は、シナプス数減少が増強される
昼間の薬理学的睡眠誘導では、アデノシンシグナル活性化とノルアドレナリンシグナル抑制が同時に起こる時のみシナプス減少が起きる
この研究の面白く独創的なところ
単一神経細胞レベルで長時間シナプス数を追跡した初の研究
睡眠がシナプス数調節に必須であり、許容的な状態ではないことを示した
睡眠圧の程度がシナプス減少の大きさを規定することを明らかにした
神経細胞やシナプスの多様性を考慮することで、これまでの研究の不一致点を説明できる可能性を示した
この研究のアプリケーション
睡眠とシナプス可塑性の関係性の理解に貢献
睡眠による学習・記憶の制御メカニズムの解明に役立つ
睡眠障害などによるシナプス機能不全の理解と治療法開発につながる可能性
創薬ターゲットとしてのアデノシン受容体やアドレナリン受容体の可能性
著者と所属
Anya Suppermpool, Declan G. Lyons, Elizabeth Broom & Jason Rihel (Department of Cell and Developmental Biology, University College London, London, UK)
詳しい解説
本研究は、睡眠中と覚醒中の神経細胞シナプス数がどのように変化するのかを、ゼブラフィッシュ幼生の視蓋領域の単一神経細胞で初めて包括的に解析したものです。これまで、シナプス恒常性仮説と呼ばれる「睡眠中はシナプスの数や強度が減少し、覚醒中は増加する」というアイデアが提唱されてきました。しかし、大脳皮質全体の平均的な変化や、樹状突起の一部分だけを観察した研究が多く、個々の神経細胞でどのような変化が起きているのかは不明でした。また、シナプス数調節において、睡眠が単に許容的な状態なのか、それとも能動的に働きかけているのかという点も明らかではありませんでした。
研究チームは、FingR-PSD95システムという新しいシナプスラベル技術を用いて、ゼブラフィッシュ幼生の視蓋にある単一神経細胞の興奮性シナプスを可視化しました。共焦点顕微鏡で同じ神経細胞を繰り返しイメージングすることで、睡眠・覚醒状態やリズムを操作した時のシナプス数の変化を詳細に追跡しました。
その結果、シナプス数は覚醒中に増加し、睡眠中に減少するという、シナプス恒常性仮説と一致する変化が平均的に観察されました。しかし、個々の神経細胞を見ると、より多様なパターンがあることがわかりました。例えば、視蓋神経細胞には4つのサブタイプがあり、密に分枝した第2型でシナプス恒常性仮説に合致する変化が顕著だったのに対し、第3型では逆に睡眠中にシナプスが増える例もありました。さらに、同じ神経細胞内でも、樹状突起の部位によって変化のパターンが異なっていました。このように、シナプス数調節には神経細胞やシナプスの多様性を考慮する必要があります。
重要な発見は、シナプス数の減少が睡眠圧の高さと関連していた点です。睡眠剥奪で睡眠圧を高めると、その後の睡眠でシナプス減少が増強されました。一方、睡眠圧が低い昼間に薬で睡眠を誘導しても、シナプス数は変化しませんでした。ただし、アデノシンA1受容体を活性化し、ノルアドレナリンの放出を抑える薬の組み合わせでは、昼寝でもシナプス減少が起きました。つまり、シナプス数減少には、睡眠圧の蓄積に伴うアデノシンシグナルの活性化と、ノルアドレナリンシグナルの低下が重要だと考えられます。
本研究は、睡眠中のシナプス数調節が単に許容される現象ではなく、睡眠圧依存的かつ神経伝達物質によって能動的に制御されていることを示しました。睡眠による適切なシナプス数の調節は、記憶の固定化やシナプス過剰増殖の防止に役立つと考えられ、その破綻は睡眠障害などの病態に関与している可能性があります。本研究で明らかになった分子基盤は、睡眠の機能的意義の理解を深め、関連疾患の治療法開発にもつながると期待されます。
父親の腸内細菌叢の乱れが、子孫の健康に影響を及ぼす
本研究では、マウスを用いて、父親の腸内細菌叢の乱れが子孫の健康に影響を及ぼすことを明らかにした。非吸収性の抗生物質や浸透圧性下剤による腸内細菌叢の乱れは、生まれてくる子どもの低体重、重度の発育不良、早期死亡のリスクを高めた。この影響は精子を介して次世代に伝わるが、父親の腸内細菌叢が受精前に回復すれば、影響は元に戻った。腸内細菌叢の乱れは、精巣内の代謝物やホルモン、精子中の小分子RNAの組成を変化させ、子宮内で胎盤の発達不全を引き起こすことが原因と考えられる。この研究は、父親の腸内環境が精子を介して子孫の健康に影響を及ぼす「腸―生殖細胞連関」の存在を示唆している。
事前情報
腸内細菌叢は、宿主と環境の相互作用の中心的な役割を果たし、ヒトの恒常性や代謝に影響を及ぼす。
腸内細菌叢のバランスを乱す環境要因は、様々な体組織の生理的反応や疾患に関連する。
しかし、腸内細菌叢が生殖細胞系列に及ぼす全身的な影響と、その結果として生まれてくる子孫への影響は不明であった。
行ったこと
受精前のマウスの父親に非吸収性抗生物質や浸透圧性下剤を投与し、急性の腸内細菌叢の乱れを誘導した。
腸内細菌叢が乱れた父親と正常な母親を交配し、生まれた子どもの表現型を解析した。
父親の腸内細菌叢の回復が子孫への影響を元に戻すかどうかを調べた。
腸内細菌叢の乱れに対する父親の生殖器系の動的な反応を分子レベルで解析した。
検証方法
16S rRNA sequencingによる腸内細菌叢の多様性と組成の解析
子孫の体重、成長、生存率の測定
父親の精巣の組織学的解析、代謝物解析、トランスクリプトーム解析
精子のDNAメチル化解析、small RNA-seq解析
レプチン欠損マウスを用いた表現型の検証
体外受精による父親の生殖細胞の影響の検証
胎盤の組織学的解析、トランスクリプトーム解析、タンパク質発現解析
分かったこと
父親の腸内細菌叢の乱れは、生まれてくる子どもの低体重、重度の発育不良、早期死亡のリスクを高める。
この影響は、父親の腸内細菌叢が回復すれば元に戻る。
腸内細菌叢の乱れは、父親の精巣内の脂質代謝物やレプチンホルモンの変化、精子中の small RNA の変化を引き起こす。
レプチンシグナルの直接的な障害は、初期胚の遺伝子発現プログラムに世代を超えた影響を及ぼす。
腸内細菌叢の乱れによる子孫への影響は、胎盤の発達不全に起因する。
父親由来の胎盤は、ラビリンス層の減少、血管新生の障害、梗塞の増加など、ヒトの前置胎盤の特徴を示す。
研究の面白く独創的なところ
父親の腸内細菌叢が精子を介して子孫の健康に影響を及ぼす「腸―生殖細胞連関」を発見した点。
腸内細菌叢の乱れが引き起こす生殖器系の分子レベルでの変化を多角的に解明した点。
レプチンが腸―生殖細胞連関のシグナル伝達において重要な役割を果たすことを示した点。
父親由来の影響が胎盤の発達不全を介して子の健康リスクにつながるメカニズムを解明した点。
この研究のアプリケーション
父親の生活習慣の改善による、次世代の健康リスク低減への応用。
胎盤の機能不全に起因する妊娠合併症の新たな予防法・治療法の開発。
腸内細菌叢と生殖機能の関連性の理解に基づく、不妊治療への応用。
環境要因が生物学的システムに与える影響を理解するための研究フレームワークの提供。
著者と所属
Ayele Argaw-Denboba, Thomas S. B. Schmidt, Monica Di Giacomo (European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Epigenetics & Neurobiology Unit, Rome, Italy) 他
詳しい解説
本研究は、父親の急性の腸内細菌叢の乱れが、精子を介して子孫の健康に影響を及ぼすことを明らかにした画期的な研究です。腸内細菌叢は、宿主と環境の相互作用の中心的な役割を果たし、全身の様々な体組織の生理的反応や疾患に関連することが知られていますが、生殖細胞系列への影響は不明でした。
研究チームは、マウスの父親に非吸収性抗生物質や浸透圧性下剤を投与することで、急性の腸内細菌叢の乱れを誘導しました。その結果、腸内細菌叢が乱れた父親から生まれた子どもは、低体重、重度の発育不良、早期死亡のリスクが高まることが分かりました。この影響は、父親の腸内細菌叢が受精前に回復すれば元に戻ることから、生殖細胞を介した伝達であることが示唆されました。
腸内細菌叢の乱れに対する父親の生殖器系の反応を分子レベルで解析したところ、精巣内の脂質代謝物やレプチンホルモンの変化、精子中の small RNA の変化が観察されました。特にレプチンシグナルの直接的な障害が、初期胚の遺伝子発現プログラムに世代を超えた影響を及ぼすことが分かりました。また、腸内細菌叢の乱れによる子孫への影響は、胎盤の発達不全に起因することが明らかになりました。父親由来の胎盤は、ラビリンス層の減少、血管新生の障害、梗塞の増加など、ヒトの前置胎盤の特徴を示しました。
本研究は、父親の腸内細菌叢が精子を介して子孫の健康に影響を及ぼす「腸―生殖細胞連関」の存在を示唆した点で非常に意義深いものです。また、腸内細菌叢の乱れが引き起こす生殖器系の分子レベルでの変化を多角的に解明し、レプチンがその重要なシグナル伝達因子であることを突き止めた点も評価されます。さらに、父親由来の影響が胎盤の発達不全を介して子の健康リスクにつながるメカニズムを解明したことは、妊娠合併症の予防や治療に新たな知見をもたらすものです。
本研究の知見は、父親の生活習慣の改善による次世代の健康リスク低減や、腸内細菌叢と生殖機能の関連性に基づく不妊治療など、様々な分野での応用が期待されます。また、環境要因が生物学的システムに与える影響を多階層的に理解するための研究フレームワークを提供するものでもあります。今後のさらなる研究の進展が大いに期待される重要な研究成果だと言えるでしょう。
気道のヒロック構造に、損傷に強く多分化能を持つユニークな幹細胞が存在することを発見
ヒロックには機能不明の重層扁平上皮構造が存在し、バリア機能や細胞接着に関連する遺伝子を発現するユニークな基底幹細胞集団を持つ。ヒロック基底幹細胞は上層の扁平バリア細胞を絶え間なく補充し、周囲の偽重層気道上皮に比べて著しく高い代謝回転を示す。ヒロック扁平細胞が下層の幹細胞を傷害から保護するため、ヒロックは毒物、感染、酸、物理的損傷など非常に幅広い傷害に抵抗性を示す。ヒロック基底幹細胞は傷害後に大規模なクローン性増殖が可能で、剥離した気道を再被覆し、最終的に6種類全ての細胞型から成る正常気道上皮を再生できる。レチノイン酸シグナルの阻害下では、ヒロック基底幹細胞が選択的に重層化・角化し、扁平上皮化生の原因となる。ビタミンA欠乏が誘導するマウス気道の扁平上皮化生は、ヒロックの拡大が原因であることを示した。さらにヒトのヒロックを同定し、そこから分離した基底幹細胞が培養下で機能的な扁平バリア構造を形成することを明らかにした。ヒロックの存在は、気道上皮の再生メカニズムの理解に新たな視点を提供する。また、ヒロックが肺がんの前駆病変と考えられている「扁平上皮化生」の発生源の1つであることを示した。
事前情報
気道上皮は6種類の細胞型(基底細胞、線毛細胞、分泌細胞、タフト細胞、神経内分泌細胞、イオノサイト)から構成される。
基底細胞は気道上皮幹細胞として知られ、恒常性維持と傷害後の再生を担う。
「扁平上皮化生」は、気道上皮の前がん病変と考えられているが、その発生メカニズムは不明な点が多い。
行ったこと
マウス気管のwholemount解析によりヒロック構造を同定し、特徴づけを行った。
ヒロック特異的なCreERドライバーマウスを作出し、ヒロック細胞の系譜追跡を行った。
様々な気道傷害モデルを用いて、ヒロックの傷害抵抗性と再生能力を評価した。
ヒロック基底細胞とその周囲の偽重層上皮基底細胞の遺伝子発現とクロマチン状態を比較した。
レチノイン酸シグナル阻害によるヒロックの扁平上皮化生への分化を解析した。
ヒト気道におけるヒロック構造の存在を確認し、その幹細胞特性を培養系で検証した。
検証方法
マウス気管のwholemount免疫蛍光染色とin situハイブリダイゼーション
単一細胞RNA-seq解析とATAC-seq解析
ヒロック特異的なCreERドライバーマウスの作製と系譜追跡実験
ナフタレン傷害、インフルエンザ感染、酸傷害、凍結融解傷害などの気道傷害モデルの解析
三次元オルガノイド培養とALI (air-liquid interface) 培養を用いた機能解析
ヒト気道組織のwholemount解析と免疫組織化学染色
分かったこと
マウス気管には、KRT6A+KRT13+の重層扁平上皮から成るヒロック構造が存在する。
ヒロック基底細胞は周囲の上皮に比べて高い増殖能とターンオーバーを示す。
ヒロック細胞は様々な気道傷害に抵抗性を示し、傷害後の気道再生の源となる。
ヒロック基底細胞は全ての気道上皮細胞型に分化する多分化能を有する。
ヒロック基底細胞はレチノイン酸シグナル阻害に応答して扁平上皮化生を引き起こす。
ヒトの気道にもマウスと同様のヒロック構造が存在し、幹細胞特性を持つ。
この研究の面白く独創的なところ
気道に新たな幹細胞ニッチ「ヒロック」が存在することを発見した点。
ヒロックが非常に幅広い気道傷害に抵抗性を示すメカニズムを解明した点。
1つの幹細胞集団から気道上皮の全ての細胞型が再生されることを示した点。
ヒロックの基底細胞が扁平上皮化生の細胞起源であることを突き止めた点。
マウスで得られた知見がヒトにも当てはまることを確認した点。
この研究のアプリケーション
ヒロック幹細胞を標的とした新たな気道疾患治療法の開発。
ヒロック幹細胞の分化制御による肺がん予防法の開発。
ヒロック由来の重層扁平上皮シートの移植による気道再建術への応用。
ヒロック幹細胞の特性を活用した気道上皮再生研究や創薬スクリーニング系の構築。
著者と所属
Brian Lin, Viral S. Shah, Chaim Chernoff & Jayaraj Rajagopal (Center for Regenerative Medicine, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA; Harvard Stem Cell Institute, Cambridge, MA, USA; Klarman Cell Observatory, Broad Institute, Cambridge, MA, USA)
詳しい解説
本研究は、マウスとヒトの気道に新たな幹細胞ニッチ「ヒロック」が存在することを発見し、その特性と機能を明らかにした画期的な成果です。ヒロックは、これまで気道上皮の恒常性維持と再生を担うと考えられてきた基底細胞とは異なる、ユニークな幹細胞集団を内包していました。
マウス気管のwholemount解析により、KRT6AとKRT13という特異的マーカーを発現する重層扁平上皮構造がパッチ状に点在することが分かりました。この構造はヒロックと名付けられ、周囲の偽重層上皮に比べて著しく高い増殖能とターンオーバーを示すことが明らかになりました。驚くべきことに、ヒロックは毒物、感染、酸、物理的損傷など非常に幅広い傷害に抵抗性を示しました。これは、ヒロックの扁平細胞が下層の幹細胞を保護するバリアとして機能するためです。
さらに研究チームは、ヒロック特異的なCreERドライバーマウスを作製し、ヒロック幹細胞の系譜追跡実験を行いました。その結果、傷害後の気道再生においてヒロック幹細胞が大規模なクローン性増殖を示し、気道上皮の6種類全ての細胞型(基底細胞、線毛細胞、分泌細胞、タフト細胞、神経内分泌細胞、イオノサイト)に分化することが確認されました。つまり、ヒロック幹細胞は気道上皮の再生に必要な多分化能を持つ「スーパー幹細胞」だったのです。
一方で、ヒロック幹細胞にはもう1つの重要な特性がありました。レチノイン酸シグナルの阻害という刺激に応答して、ヒロック幹細胞が選択的に重層化・角化し、扁平上皮化生を引き起こしたのです。扁平上皮化生は、肺がんなどの前がん病変と考えられていますが、その発生メカニズムには不明な点が多く残されています。本研究は、ビタミンA欠乏マウスで誘導される気道の扁平上皮化生が、実はヒロックの拡大が原因であることを突き止めました。
最後に研究チームは、ヒト気道にもマウスと同様のヒロック構造が存在することを確認しました。ヒト・ヒロックから分離した基底幹細胞は、培養下で機能的な重層扁平上皮バリアを形成する能力を持っていました。この結果は、マウスで得られた知見がヒトにも当てはまる可能性を示唆しています。
本研究の発見は、気道の再生メカニズムと疾患の理解に新たな視点を提供するものです。ヒロック幹細胞を標的とした治療法の開発や、ヒロック幹細胞の分化制御による肺がん予防など、様々な応用が期待されます。また、ヒロックの特性を活用することで、気道上皮の再生研究や創薬スクリーニングにも新たな道が開かれるかもしれません。気道疾患の克服に向けて、ヒロック研究のさらなる進展が待ち望まれます。
腎臓がんゲノムに刻まれた、世界各地の変異誘発物質の足跡
https://doi.org/10.1038/s41586-024-07368-2
本研究では、11カ国962人の淡明細胞型腎細胞がん(ccRCC)のゲノムを解析し、変異パターン(変異シグネチャー)の地域差を調べた。その結果、ルーマニアやセルビアではアリストロキア酸による変異シグネチャーが多くの症例で見られた。日本では原因不明のSBS12シグネチャーが70%以上の症例で高レベルに検出された。また、SBS40bなどの変異シグネチャーのレベルは、各国の腎臓がん発生率と相関していた。一方、肥満や高血圧など既知のccRCCリスク因子と関連する変異シグネチャーは見られなかった。本研究の結果は、世界の各地域で変異誘発物質への曝露レベルが大きく異なること、また未知の発がん物質の存在を示唆している。
事前情報
多くのがん種で、世界の地域によって発生率が大きく異なる。これは、従来の疫学研究では特定されていない発がん物質が存在することを示唆している。
淡明細胞型腎細胞がん(ccRCC)のリスク因子として、肥満、高血圧、喫煙が知られているが、地域による発生率の違いを説明できない。
がんゲノムの変異パターン(変異シグネチャー)を解析することで、背景にある変異誘発要因を推定できる。
行ったこと
ccRCC発生率が異なる11カ国962人の腫瘍・正常組織からDNAを抽出し、全ゲノムシーケンスを行った。
変異シグネチャー解析により、各ccRCCゲノムにおける変異プロセスの寄与度を推定した。
変異シグネチャーのレベルと、各国のccRCC発生率や患者の臨床情報との関連を調べた。
901人の血漿サンプルを用いて、未知の変異誘発物質の代謝物を探索した。
検証方法
ccRCCゲノムの一塩基置換(SBS)、二塩基置換(DBS)、挿入欠失(ID)変異を検出
非負値行列因子分解(NMF)とベイズ階層的ディリクレ過程により変異シグネチャーを抽出
変異シグネチャーのレベルを国ごとに比較し、ccRCC発生率や患者情報との関連を統計解析
血漿の未標的メタボローム解析により、変異シグネチャーと関連する代謝物を同定
腫瘍の進化解析により、変異シグネチャーが働いた時期を推定
分かったこと
ccRCCの変異負荷とパターンには地域差があり、ルーマニア症例で顕著に高かった。
ルーマニアとセルビアの多くの症例で、アリストロキア酸関連シグネチャー(SBS22等)が見られた。
日本症例の72%でSBS12シグネチャーが見られたが、他の国ではほとんど検出されなかった。
SBS40b等のシグネチャーのレベルは、各国のccRCC発生率と正の相関を示した。
肥満や高血圧など既知のリスク因子に関連する変異シグネチャーは見られなかった。
血漿代謝物TMAP等がSBS40bレベルと相関し、腎機能低下との関連が示唆された。
変異シグネチャーの多くは、がんの初期段階ですでに検出された。
研究の面白く独創的なところ
世界各地のccRCCゲノムを大規模に比較し、変異パターンの地域差を明確に示した点
アリストロキア酸への曝露が、東欧の広い地域で10年単位にわたり起きている可能性を示唆した点
日本人に特有のSBS12シグネチャーの原因物質が存在することを示唆した点
SBS40bなど、ccRCC発生率と相関する原因不明の変異シグネチャーを同定した点
肥満や高血圧など既知のリスク因子は、変異よりも非変異的なメカニズムで発がんに関与する可能性を示した点
この研究のアプリケーション
将来のccRCC予防に向けて、地域特有の発がんリスク要因の同定と曝露源の特定
特にアリストロキア酸曝露の実態把握と公衆衛生対策の立案
他のがん種でも、高発地域と低発地域のゲノム比較による新規リスク要因の探索
肥満など非変異的リスク因子のメカニズム解明と予防法の開発
SBS40bなどccRCC特異的な変異シグネチャーのメカニズムと意義の解明
著者と所属
Sergey Senkin, Sarah Moody, Marcos Díaz-Gay(Genomic Epidemiology Branch, International Agency for Research on Cancer (IARC/WHO), Lyon, France) 他
詳しい解説
本研究は、世界11カ国から集めた962例もの淡明細胞型腎細胞がん(ccRCC)の全ゲノムシーケンスを行い、変異パターンの地域差を調べた大規模解析です。ccRCCの発生率は世界で大きく異なりますが、その原因は十分に解明されていません。本研究では、ccRCCゲノムに刻まれた変異シグネチャーを手がかりに、地域特有の変異誘発要因の存在を明らかにしました。
解析の結果、ルーマニアとセルビアのccRCC症例では、アリストロキア酸によるSBS22等の変異シグネチャーが高頻度に見られました。アリストロキア酸は、ウマノスズクサ属の植物に含まれる発がん性物質で、バルカン半島の一部で多発する腎障害の原因として知られています。しかし本研究の結果は、その曝露が考えられていたよりも広範囲で長期にわたって起きている可能性を示唆しています。一方、日本人ccRCCの72%からSBS12シグネチャーが高レベルで検出されましたが、他の国ではほとんど見られませんでした。SBS12の原因は不明ですが、日本人に特有の強力な変異誘発物質の存在が示唆されます。
さらに興味深いことに、SBS40bなどのシグネチャーのレベルは、各国のccRCC発生率と正の相関を示しました。SBS40bは多くのccRCCで見られる原因不明のシグネチャーで、年齢や性別とも相関します。血漿メタボローム解析の結果、SBS40bレベルは腎機能マーカーと相関することも分かりました。一方、喫煙関連シグネチャーは喫煙歴と相関しましたが、肥満や高血圧など他の既知のリスク因子に関連するシグネチャーは見られませんでした。このことから、後者は主に非変異的なメカニズムでccRCC発生に関与している可能性が示唆されます。
本研究は、ccRCCの要因が世界の地域によって大きく異なることを示すとともに、アリストロキア酸曝露やSBS12の原因物質のように、従来の疫学研究では捉えきれなかった地域特異的な発がんリスクの存在を浮き彫りにしました。さらにSBS40bのように、世界共通だがccRCC発生率と相関する原因不明の変異シグネチャーも同定されました。今後、これらの変異シグネチャーの原因物質を特定していくことが、ccRCCの予防に向けた重要な課題と言えるでしょう。
また本研究は、高発地域と低発地域のゲノムを比較することで、他のがん種でも新たな発がんリスクを発見できる可能性を示しています。一方で、肥満など非変異的なリスク因子の場合は、変異シグネチャー以外のアプローチでメカニズムの解明を進める必要があります。いずれにせよ、世界規模のがんゲノム解析により、がんの原因解明が大きく前進することが期待されます。
ヒト胚の細胞凝集は、細胞収縮力の増加によって駆動される
https://doi.org/10.1038/s41586-024-07351-x
本研究は、ヒト胚の桑実胚形成過程における細胞表面張力の変化と、その力学的メカニズムを解明したものである。研究には臨床で使用されなかった余剰胚を用い、マイクロピペットによる吸引実験で細胞表面張力を測定した。その結果、細胞-培地間の張力が4倍に増加する一方、細胞間の張力は一定に保たれることで、細胞凝集が駆動されることがわかった。さらに、細胞収縮阻害剤や細胞接着阻害剤の実験から、細胞収縮力こそが凝集の駆動力であり、細胞接着は必要だが張力変化には寄与しないことが示された。ヒトとマウスを比較すると、同様のメカニズムながら、ヒト胚の方が力学的効率が低いことも明らかになった。また、凝集不全胚の張力を解析することで、細胞排除を伴う凝集不全の原因が収縮不全である可能性が示唆された。本研究は、ヒト個体の形づくりにおける最初の形態形成運動の理解を大きく前進させるものである。
事前情報
ヒト胚は受精後、細胞が凝集して桑実胚を形成する
体外受精の研究から、ヒト胚の凝集不全は主に細胞接着の欠陥によると考えられてきた
動物の形態形成の知見から、細胞収縮なども凝集に関与する可能性があるが、ヒト胚での分子・細胞・物理メカニズムは不明だった
行ったこと
研究に提供された余剰ヒト胚を用いて、マイクロピペット吸引法により細胞表面張力を測定
細胞収縮阻害剤と細胞接着阻害剤を用いて、細胞凝集における収縮と接着の役割を検証
正常凝集胚、非凝集胚、部分的凝集胚の張力を比較解析
ヒトとマウスの胚凝集の力学的戦略を比較
検証方法
マイクロピペット吸引法による細胞表面張力の測定
阻害剤処理による細胞収縮と細胞接着の阻害実験
タイムラプス顕微鏡観察による凝集過程の追跡
数理モデルによる凝集シミュレーション
分かったこと
凝集中、細胞-培地間張力は4倍に増加するが、細胞間張力は一定に保たれる
細胞収縮力が凝集の駆動力であり、細胞接着は必要だが張力変化には寄与しない
凝集不全胚と部分的凝集胚では、細胞収縮の欠陥が示唆された
ヒトとマウスは同様のメカニズムだが、ヒト胚の方が力学的効率が低い
この研究の面白く独創的なところ
ヒト胚の細胞凝集の力学的メカニズムを初めて定量的に解明した
マイクロピペット吸引法という独創的な手法で、生きた胚の細胞表面張力を測定した
阻害剤実験と数理モデルにより、凝集の駆動力が細胞収縮であることを特定した
ヒトとマウスの比較から、種を超えて保存された凝集メカニズムの力学的差異を明らかにした
この研究のアプリケーション
体外受精における胚の質の評価と選別への応用
凝集不全の原因診断と治療法開発への貢献
ヒト胚操作の倫理的ガイドライン策定に資する科学的知見
個体発生初期の形態形成メカニズムの理解に基づく再生医療技術の発展
Julie Firmin, Nicolas Ecker, Diane Rivet Danon, Özge Özgüç, Virginie Barraud Lange, Hervé Turlier, Catherine Patrat & Jean-Léon Maître (Institut Curie, Université PSL, CNRS UMR3215, INSERM U934, Paris, France; Université de Paris, Paris, France; Service de Biologie de la Reproduction - CECOS, Paris Centre Hospital, APHP centre, FHU Prema, Paris, France; Center for Interdisciplinary Research in Biology, Collège de France, CNRS, INSERM, Université PSL, FHU Prema, Paris, France; Institut Cochin, Université de Paris, CNRS UMR1016, Paris, France)
詳しい解説
本研究は、ヒト胚の発生初期に起こる細胞凝集の力学的メカニズムを解明した画期的な成果です。受精後のヒト胚は、細胞分裂を繰り返しながら、わずか4日ほどで細胞が互いに密着した桑実胚へと姿を変えます。この「細胞凝集」と呼ばれる現象は、ヒトの体づくりにおける最初の形態形成運動ですが、そのメカニズムはよくわかっていませんでした。
研究チームは、体外受精で使われなかった余剰胚の提供を受け、マイクロピペットを用いて胚の細胞を吸引し、表面張力を測定するという独創的なアプローチで、この謎に挑みました。その結果、凝集の進行に伴って、細胞と培地の間の張力が4倍にまで増加する一方、細胞間の張力は一定に保たれることを発見しました。つまり、細胞外への張力の増加こそが、細胞を互いに押し付け凝集を駆動する力だったのです。
さらに、凝集の過程で細胞収縮を阻害すると凝集が止まるのに対し、細胞接着を阻害しても細胞外への張力増加は起きるものの凝集は阻害されることから、細胞収縮が凝集の駆動力であり、細胞接着は凝集に必要ではあるものの表面張力の変化は担っていないことが明らかになりました。また、凝集しない胚や一部の細胞が排除されるような部分的な凝集不全を起こした胚の張力を測定したところ、これらの胚では細胞収縮に異常がある可能性が示唆されました。
興味深いことに、ヒト胚とマウス胚の凝集メカニズムを比較すると、細胞外張力の増加という点では共通しているものの、マウスの方がより効率的に凝集が進行することもわかりました。この種間の差異は、初期発生のスピードの違いを生む要因の一つかもしれません。
本研究は、ヒト胚の発生初期における力学的な仕組みの理解を大きく前進させただけでなく、着床前診断等の生殖補助医療技術の向上や、初期胚の操作をめぐる生命倫理の議論にも科学的な根拠を与えるものです。さらに、力学的な制御がいかにして時空間的な秩序を生み出すのかという発生生物学の根源的な問いにも、ヒト胚という最良のモデル系を用いて迫ることに成功した点で、高く評価できる研究だと言えるでしょう。
最後に
本まとめは、フリーで公開されている範囲の情報のみで作成しております。また、理解が不十分な為、内容に不備がある場合もあります。その際は、リンクより本文をご確認することをお勧めいたします。
