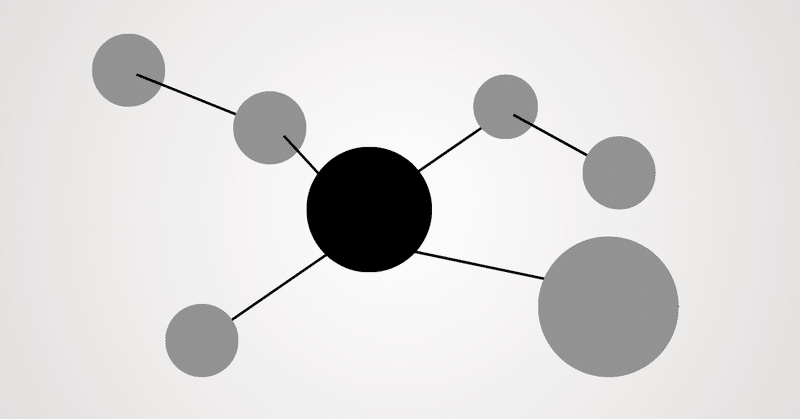
「ソ」ボクな疑問、点をつなぐ。
土曜日にぼんやり寝転がって部屋を眺めていたところ、ひらがなの手書き文字に「ん?」と疑問を感じた。衣類ケースに「その他」という書き込みがあったのだが、その「そ」の字の上の部分が「ソ」になっていたのである。

個人的には、左側のフォントのように「そ」の上の部分はつなげて書いている。ところが自宅内にそうじゃない派がいた。
調べてみると「そ」の文字の上の部分をつなげて1画つまり一筆書きの文字は「Z型」と呼ばれ、点によって2画で書くのは「ソ型」なのだそうだ。そうだったのか。
ひらがなの起源をよく知らないが、漢字から万葉仮名、さらにひらがなに変化したような成り立ちを覚えていた。つまり、ひらがなには、もとになった漢字があるはずだ。
こちらも調べてみると「曽」が「そ」に変化したらしい。ということは漢字の上部に注目するとソ型の「そ」のほうが忠実であり、つなげて1画で書くZ型は簡略化が進んでいる。曽→ソ型→Z型という進化をしてきたのではないだろうか。どうなのだろう?
オトナンサーというメディアでは、上越教育大学大学院学校教育研究科の押木秀樹教授に取材を行い、以下のような見解を掲載している。
「(前略)『そ』の成り立ちの過程を見ていくと、平仮名ができた平安時代から、書いた時の勢いなどによって当該部分がつながったり、つながらなかったりしていたようです。現代の私たちも上部をつなげて書いたり、書かなかったりするのは、その頃からの流れと考えることができそうです」
確かに点で止めるとゆっくり書くことになり、一筆で書くと速い。
この取材記事では、話し言葉にさまざまなニュアンスがあるように、書いた文字にも違いがあり、手書き文字で言葉を伝えるときの「コミュニケーションとして重要」という指摘が興味深かった。
正しい字形はないようだが、現在の小学校教育ではZ形の「そ」に統一されているとのこと。スピードを優先する現代では、一筆書きを推奨ということだろうか。キーボードを使うと関係なさそうではあるが、タッチパネルの認識はどうなっているのだろう。ソ型の「そ」は変換されるのか。
学校で教えるのはZ型とはいえ、ソ型の「そ」を絶滅させてしまうのは惜しい気がする。フォントの場合は仕方ないが、手書きの文字でソ型を使うと、なんとなく古めかしくて奥ゆかしい感じがしないでもない。
PowerPointに使われるフォントでいえば、ほとんどの書体はZ型の「そ」だが、創英角ポップ体とMicrosoft YaHei UI Lightなどではソ型の「そ」になっている。
押木秀樹教授によって書かれたコンテンツを見て気づいたのは「さ」と「き」の下の部分をつなげるか離すかについても書き方が分かれることだ。
游ゴシックやメイリオはつなぐ文字形だが、BIZ UDP明朝/ゴシック、UD明朝/ゴシック、HG教科書体/行書体/創英角ポップ体などでは離れた書体になっていた。
ところで、フォントのデザインに関連しているかもしれないが「点をつなぐ」という意味を、人生全般のメタファとして考えてみたい。
先日、卒業シーズンということもあって、アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズ氏のスタンフォード大学のスピーチを聞き直した。この中で彼は、デザインの発想とみずからの経験を踏まえて「Connecting the dots(点と点をつなぐ)」という重要性を述べている。
ジョブズは若い頃にカリグラフィーを学んだ。カリグラフィーというのは、ペンなどの道具を使って文字を美しく見せるデザインの技法だ。彼は結局のところ大学を中退して、デザイナーにはならなかった。しかし、カリグラフィーを学んだことは、マッキントッシュ(現在のMac)というコンピュータに美しいフォントを搭載するときに生かされた。
経験や知識の点はいつか線になり、線は面を形成するようになる。
いまは点だったとしても、将来的にはその点が何かにつながる可能性を秘めている。点であることを軽視してはいけない。あらゆる学びはムダにならない。Connecting the dotsには、ジョブズが次世代に伝えようとしたそんな想いが込められている。
ジョブズはiPhoneの見えない部分のデザインにまでこだわった。彼の思考でいえば、ひらがなの「そ」のソ型の点をつなぐこと、離すことも大切なこだわりかもしれない。ささやかではあるが、細部に神が宿る。
J-WAVEのラジオで、書体設計士の鳥海修氏のお話を聞いたことがあったが、鳥海修氏がデザインした「愛」という文字をジョブズは絶賛したそうだ。谷川俊太郎氏の詩のためだけにデザインしたフォントもあるという。
書体設計士として、フォントの「そ」「さ」「き」のデザインにどのようなこだわりがあるのだろう。ぜひプロとしての見解を聞いてみたい気がする。
ひらがなの字形に注目することにより、新たな気づきがあり、知識が拡がった。しかし、注意すべきことがある。文字をずっと見続けていると、文字から意味が切り離されて何やら変なものに見えてくるからだ。いわゆるゲシュタルト崩壊と呼ばれる現象である。
たとえば「ふ」の字。ふふふ、と並べると、もやもやして変な気持ちになってしまう。左向きのペンギンが行進しているようにも見えてくる。これはアブナイ。
いろいろな意味で、文字には注意が必要である。
2024.03.25 BW
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
