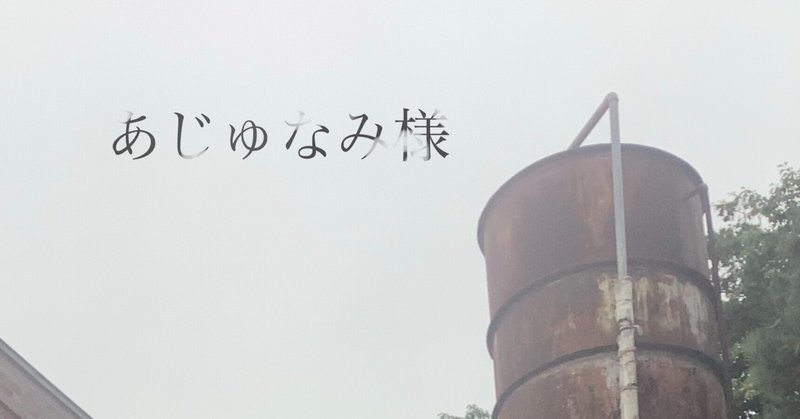
【ホラー小説】 あじゅなみ様 ♯1『私(マユミ)の場合』
私の家には「のっぺらぼう」がいた。
そいつはダイニングテーブルの客席ににいつも静かに座っていた。決して動くことのないそいつを、私は「のっぺらぼう」と呼んでいた。名の通り、顔がないからだ。
正確に言うと、顔は日によって変化する。ある時はワイドショーに出演する有名人の顔をしており、ある時は私の友人の顔になっている。不思議なことに顔によって服も変わるようで、友人の時は私と同じ高校の制服を着ている。どこから用意したのだろうと不思議に思う。
不気味なことに時折、私になることもある。服の種類は少ないようで、いつも制服であった。
とはいえ私は「のっぺらぼう」と友人を、あるいは客人かどうかと間違えることはない。それは「のっぺらぼう」が作り出す顔は蝋人形のように正気がなく、虚な目で空を見つめ、常人ではないことが一目瞭然だからだ。何より「のっぺらぼう」は、常に口をパクパクと上下に動かしている。一定のリズムを崩すことなく、ずっとずっと動かすのである。
「…あんた、なんでここにいるのよ」
「………」
私の問いにも「のっぺらぼう」は答えない。ただ口を動かすのみで、言葉は発せられないのである。
そんな生活は物心ついた頃からであり、既に私は何も思わなくなっていた。むしろ「のっぺらぼう」の顔を見る習慣を楽しんですらいた。
なぜなら「のっぺらぼう」は何か不可思議なことをすることもなく、放っておいても無害な存在だからだ。そこにいるだけであって、私たちはいつも通りの毎日を過ごしている。
しかし、一つだけ厄介なことがあった。それは「のっぺらぼう」は私にしか見えていないということだ。
「マユミ!ごはんよ」
リビングから私を呼ぶ母の声がする。
「はーい。今行くー」
二階の自室から廊下に出ると、同じタイミングで部屋から出てきた弟のノボルと鉢合わせになる。
「あんた、相変わらず酷い顔してんねぇ…」
「…うるせぇよ」
彼は中学二年生で、思春期特有の妄想癖がある少し根暗なやつだった。しかし、根暗な性格とは裏腹に体格には恵まれており、私よりもずっと背が高いので、猫背で俯いた顔と私の目線はよく合いやすかった。
私とノボルがダイニングテーブルに行くと、既に父のタケヒコと母のナオコがそれぞれの席についていた。もちろん客席には「のっぺらぼう」もいる。帰宅時には、スキー競技のオリンピック選手であったが、今はテレビでインタビューに答えていた大学教授の顔になっている。
「先に食べてるわよ」
母はこちらを見ながら、モゴモゴと口を動かした。
「ノボル…マユミも、早く座りなさい」
父は読んでいた新聞を丁寧にたたみ、脇に置くと箸を手に取った。
私たちが食事をするダイニングテーブルはごく一般的な長方形の形をしており、長辺に二人が並び、四人で向き合って食事をする。私と母、父とノボルが向き合う形だ。階段側の短辺には客用の椅子が用意されているが、そこにはいつも「のっぺらぼう」が座っている。そして、それと向かい合う方に大きな窓があり、すぐ横には大型テレビが設置されている。だから、誰かがテレビを点けている間は、常に「のっぺらぼう」は特等席で見ることができるのだ。
「あ、この人、捕まったんだ…」
芸能人が違法薬物の所持で逮捕されたというニュースが流れている。
「この人が出てたドラマ好きだったんだけどなぁ」
母は、少し寂しそうに呟く。
「ドラマ?出てたっけ?」私にはピンと来なかった。
「うん。ほら、刑事モノのやつ…なんだっけ、お父さん」
「えっ…?」
父は既に食事を終え、新聞を読み始めていた。
「悪い…聞いてなかった」
「……もぉーいつも、それなんだから」母が不満を口にする。
私は苦笑いをしながら、父を一瞥する。
母はため息をつきながら、呆れたように父に言った。
「ドラマの話よ。ほら、お父さん、この人が前に出てた刑事ドラマ見てたじゃない。あれ、なんてタイトルだったか覚えてない?」
「あー、アレな…アレは、なんだったかな…」
父は白髪混じりの髪を掻きながら、必死に思い出そうと目を閉じていた。
私はというと「のっぺらぼう」を見ていた。「のっぺらぼう」の顔が逮捕された芸能人の顔にならないかと期待していたのだ。もしなるのだとしたら、ドラマの時の顔だろうか、それとも、逮捕された時のやつれた顔だろうか。
「マユミ、何してるの。早く食べちゃいなさい」
私は母に促され、お茶碗に残った白米を口にすばやく放り込む。
相変わらず「のっぺらぼう」は、テレビを見続けたまま、こちらに反応する様子もない。
「………そうだ」
私の中で、わずかなイタズラ心が燃え上がった。私が以前見たテレビ番組では、大学教授は随分と偉そうで、横柄な物言いをしていた。アナウンサーの質問に対して「君は、そんなこともわからんのか」と言いたげな態度が鼻についていたのだ。私は、お茶碗に残された最後の米粒を器用に箸で掴み取ると、パクパクと口を動かし続ける「のっぺらぼう」に近づける。
あの偉そうな大学教授が、私みたいな女子高生に食べさせてもらっている写真なんかあれば、きっとS N Sでも炎上するに違いない。私は、そんな仕方のないことを思いながらゆっくりと箸を口元に持っていこうとした。
「こらぁ、マユミ。『あじゅなみ様』で遊ぶんじゃありません」
私は思わず、箸を落としてしまった。箸はつま先に当たって、明後日の方向へ転がっていく。それを震える手で反射的に拾おうとしたが、動悸が激しく、体がうまく動かない。
―――今、誰がなんと言った?
私は箸を拾うと、すぐに頭を上げ、辺りを見回す。
父とノボルは既に食事を終え、いつの間にか二人でソファに並びながらバラエティ番組を見ている。
「急に、どうしたのよ?」
母が、こちらを心配そうに見ている。
「お、お母さん……い、今なんか言った?」
「はい?……だから、急にどうしたのって…」
「そ、その前………」
私の耳が正しければ、その声は確かに母の声だった。「のっぺらぼう」が、母の顔で言った可能性もあったが、私が箸を近づけている時も大学教授の顔から変わっていない。
「だから、『あじゅなみ様』で遊んじゃダメよって…」
母は何を気にする様子もなく、いつもの口調でそう言った。むしろ、この異質な存在よりも私の気の方がおかしくなったのでは、と言わんばかりの視線である。
「ずっと……見えてたの?」
「えぇ、そうよ。だって、ずっとそこに居たじゃない」
私は、込み上げる吐き気を必死で抑えようと、胸に手を置いた。
その後、母と向かい合って話を聞く。
この「のっぺらぼう」は、『あじゅなみ様』と呼ばれていて、母も何かは知らないという。
「でも、あなたがそう言い出したのよ?」
母は笑ってそう言った。私が幼少の頃にそう名付けていたらしい。そして母はこの存在を異質なものとは思っていないようだった。まるで、使わなくなった棚が風景に馴染んでしまったかのような言い方をした。
「ねぇ、お父さん『あじゅなみ様』はずっと、ここにいたわよねぇ?」
ソファに腰掛け、こちらに背を向ける父に母はそう聞いた。父は首だけこちらに向けて、声を張り上げる。
「ああ…ずっといたなぁ」
私はどんどん気持ちが悪くなっていく。まるで、私だけが異世界に取り残されたかのようだ。頭がその事実を受け付けない。
「……部屋で休んでくる」
「ちょっと、大丈夫?」
母が心配そうに顔を覗き込んだが、私はその顔を見なかった。もし、その顔が母とは違う『何か』に変わっていたら———と、よからぬ想像が頭をよぎったからだ。
私はリビングを去る時『あじゅなみ様』の顔を見た。薬物で疲れた顔をした芸能人の顔に変わっていた。
それから三日経った、午後0時。私は今、自室にいる。
右手には先ほど夕飯を終えて自室に戻る際に、キッチンから持ち出したナイフが握られている。見慣れぬ緑の柄のナイフであったが、特段気にはならなかった。
―――私は、『あじゅなみ様』を殺す
その決意を固め、もう一度、ナイフの柄を強く握り直す。
階段を降り、手摺りの背後に隠れるようにして顔をそっとリビングに向けると、テレビが点いていた。
暗いリビングにテレビの光が目まぐるしくぶつかり、辺りに乱反射している。誰かが消し忘れたに違いない。スピーカーから漏れる音もわずかながら聞こえていた。
「……いる」
『あじゅなみ様』の背中が見える。これまでは当たり前の光景であったのに、それが今はただただ恐ろしく、そして私にとっての不安そのものであった。
この三日間、得体の知れない存在が私を悩ませ続けていた。いままでは、生活の一分として馴染んでいたからこそ、考え出すと違和感は徐々に恐怖へと変わっていく。
もしいつか動き出して、私たちを襲い出すようになったら。そう考えると不安はピークに達していた。家族の中に、私の味方になる存在は誰もいない。これまでの私と同じように『あじゅなみ様』を受け入れてしまっているのからだ。
私は廊下を抜けて『あじゅなみ様』にゆっくりと近づいた。そっと、距離を
詰めて、摺り足で寄っていく。…その時だった。
がちゃん
私の膝に何かが当たり、床にそれが落ちたのがわかった。
私は落ちた何かを確認することなく、一気に『あじゅなみ様』に近づくと、その背中にナイフを突き刺したのである。ナイフは、ずぶりと突き刺さる。私は、すぐさま踵を返し、廊下を走り抜け階段を駆け上がる。そして、自室のベッドの上で布団にくるまった。
震える手には、ぬめりとしたものが滴っているようだ。布団の中では、暗くてそれがわからなかった。
―――明日、朝になったら……きっと……
一瞬、『あじゅなみ様』が振り返ろうとしていたように見えたが、気のせいに違いない。
2話目
(予告):【母(ナオコ)の場合】
娘は金魚を認識できないようだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

