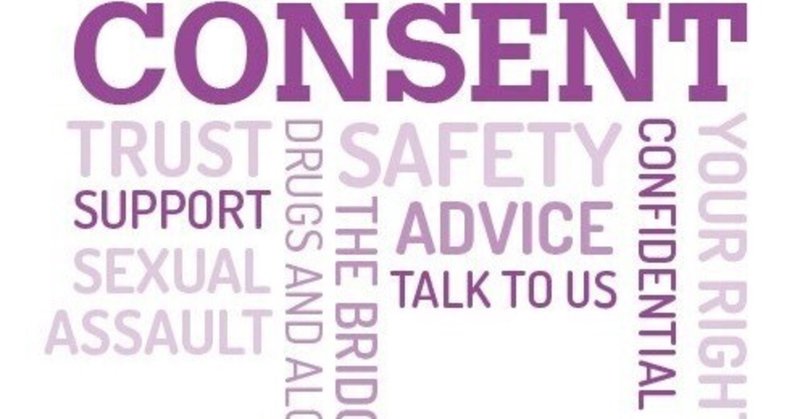
もう一つのchallenge
「challenge」の「挑戦」以外の意味に、「異議を唱える」があります。前回の記事は、自分自身に対しての、単なる「挑戦」の意味でした。今回は、後者の意味でのchallengeについて、創作の観点から書いていきます。
題材について
前回の記事に引き続き、『モジュレーション』を扱います。とある大学の管楽サークルのオーボエ奏者が、「呼吸トレーニング」との名目で指揮者の後輩にくすぐられるお話(m/f)です。前日譚、後日譚的な立ち位置で『書庫』と『打ち上げ』があります。この記事を読む分にはどのお話も読まなくて大丈夫ですが、数行後からネタバレするので、ネタバレしたくない方はリンクに飛んでください。あれ、ステマみたい(笑)
それでは。
主人公・樹里は大学生の女の子。元々は非フェチ、最後にぐら墜ちします。そして樹里をぐら墜ちさせるのが後輩の孝平。こちらは最初からぐり男子です。ぐら墜ちするだけでなく、この二人は最後に付き合います。つまり、フェチ的な意味でも恋愛的な意味でもカップルになります。なぜここまで詳しく書いたかというと、人物関係や構図がこの後書いていく話の要になっていくからです。
challenge
①ジェンダー規範へのやんわりとした抵抗
樹里は先輩、孝平は後輩。樹里は孝平にタメ口で話しますが、孝平は樹里に敬語を使います。正確な年齢をいえば同い年なのですが、学年がズレているのは孝平が一浪しているためです。つまり学力も樹里の方が高いといえます(音楽の知識は孝平の方があります)。また、二人の身長はそれほど変わりません。さらに二人の初キスは、樹里が主導権を握ります。ただのカップルに見えて、そうではないポイントをたくさん仕込んでいます。
一般的に、男女カップルにおいては、男性の身長や学歴は女性のそれより高い方が望ましい、女性の身長や学歴は男性より低い方が望ましい、という規範があります。年齢や立場についても同様の規範(と実態)があります。ジェンダー規範にどれほどの問題意識を持っているかは、性別や環境、経験など、さまざまな要因によって異なるのでしょう。私にとっては、かなり関心のあるテーマです。
フィクションの話に戻ると、正直言って、ただのヘテロ性愛の物語、王道の展開にはもう飽きました。飽きたというより、辟易していると言った方が正しいかもしれません。なので自分の小説では、立場も、学力も、身長も、男女で同じくらいか女性の方が上、という設定にしました。重要なのは、孝平はそれを何ら気にしていないということです。もちろん樹里も気にしていません。つまりこの二人は、規範から解放されて自由な心で恋愛ができているということです。一般的なヘテロカップルから少し逸脱したカップル像が描けていたらいいなと思います。
また、学術的な用語になってしまいますが「有害な男性性(Toxic Masculinity)」をいかに排除するか、自分の小説に男性を登場させるにあたって、この点に最も注意しました。孝平は、謝るべき時にちゃんと謝れる。言葉によって明確な同意を取り、言葉以上の行為には決して及ばない。相手の動揺や拒絶を汲み取って尊重できる。自らの特権性を自覚し、然るべき局面で下駄を脱げる。そんな男性像をつくることも、一つのchallengeでした。(因みに、この二人は同じ学部で、ジェンダー関連の授業で仲良くなったという裏設定があります。)
②さらっと入れたコール番号
本シリーズ2作目の第3章で、ある電話番号が出てきます。
動揺を隠せない樹里に孝平が話し出した。
「この部屋のドアはオートロックなので開ければ普通に出られます。エレベーターは出て右、階段は左です」
「え、どういう―――」
孝平が急に何を言い出したのか分からない。当惑する樹里に構わず孝平は喋り続ける。
「2ブロック左の交差点を曲がった所に交番、その途中に公衆電話があります。#8891です。覚えておいてください。流石にテレフォンカードは持ってないですが僕の財布なら―――」
「分かった。分かったから」
ここまで聞いて樹里はやっと孝平の意図を理解した。逃げる必要があればいつでも逃げられると、そう言っているのだ。
このシーンは、トレーニングの強度と樹里の安全を天秤にかけた結果、ベッドの上でトレーニング(くすぐり)をすることになり、動揺する樹里に孝平が話すシーンです。
「#8891」は、性犯罪・性暴力に関する相談窓口であるワンストップセンターの実際のコール番号です。女性でさえ知っている人の少ないこのナンバーを、敢えて男性の口から言わせました。
男性の部屋のベッドに移動するというのは、たとえ性行為をする訳でなくても、女性にとっては警戒する状況です。そんな樹里に孝平は、逃げ道と助けを求める手段をはっきりと提示します。男性という属性に付随する加害性へのペナルティを自ら提示し、そのための手段を女性に引き渡す。先に特権を手放すことで、可能な限り女性と対等な立場に立とうとしている訳です。それは即ち、樹里を傷つけるつもりはないという明確な意思表示です。
この章のタイトルは「ベッド」。テーマは「同意と信頼関係」です。この章で、樹里が拒絶や躊躇いの色を見せると、孝平は必ず譲歩しています。トレーニングが始まる前、これからくすぐられることに樹里が恐怖していると、孝平は、無理をする必要はないと伝え、可能な範囲で頑張れるかどうかを聞いて確認します。脇をくすぐられることにビビると、脇腹に手を移します。それでも不安がる樹里に、トレーニングの強度を最低レベルまで下げ、すなわち最大限に手加減します。また全体を通して、樹里が頷いてから(つまり同意してから)くすぐる場所に触れたり、手を動かしたりするように描写しています。丁寧に読んだら読み取っていただけるのではないかと思います。
なぜこの点にここまでこだわるか。ただのフィクションと言ってしまえばそれまでですが、フィクションは少なからず現実を反映しているし、逆に、現実は多少なりともフィクションの影響を受けます。AVがセックスの教科書にされてしまうことが多いのが分かりやすい例かもしれません。AVはフィクションどころかファンタジーですが、それでもフィクションがリアリティをもって現実に入ってくるリスクは否めません。創作をする一人として、どちらかの可能性に加担しなければならないとしたら、丁寧に同意を取り、質の高い信頼関係を築いていく、そんな「フィクション」の一部でいたい。これが私の創作へのスタンスです。
最近の傾向
くすぐり小説を書き始めて2年になりますが、最近はくすぐりシーンよりも会話重視になってきています。もともと同意や登場人物同士の関係、バックボーンは大事にしていますが、最近その傾向が強まってきていると自分でも感じています。そしてその傾向を、私は肯定的に捉えています。
それは、AVにおける価値観について知った時に確信したことです。男性向けのAVは、セックスそのもの、もっと言えば「女性をモノにする」という支配欲を満たすような作品が好まれ、その一方で女性向けのAVは、セックスに至るまでのプロセスや、そこでの気持ちやコミュニケーションが重視されるそうです。
行為<コミュニケーション。私が重視していることは、女性向けのAVにおけるそれとまったく同じであるといえます。セックスとくすぐりを同列に語るつもりはないし、映像と文字ではそのメッセージ性は異なるでしょう。でも、「性的な要素を含む創作」という意味では同じです。
私は自分の小説のペルソナは特に想定していないので、女性向けでも男性向けでもありませんが、「女性が書くくすぐり小説」として、今後も自分の作風を大切にしていこうと思います。
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。このような内容を読んでくださった方、そして理解してくださる方に、心からの敬意を表します。
参考
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)、2023年3月19日閲覧
太田啓子(2020)『これからの男の子たちへ:「男らしさ」から自由になるためのレッスン』大月書店
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
