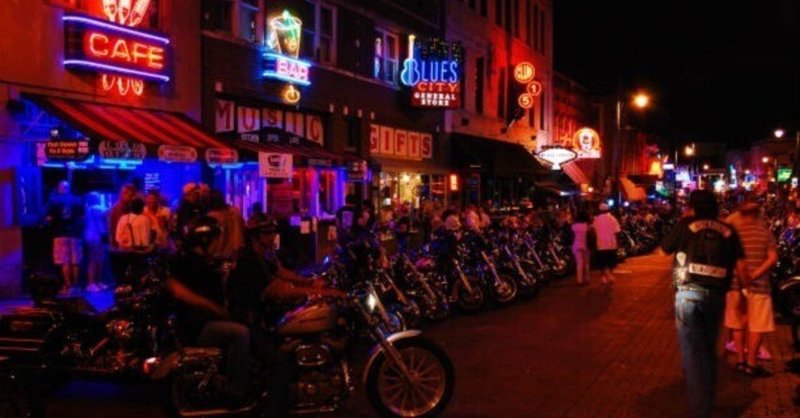
消滅しつつある闇のために
ふるさととしての闇
上野昻志の名前を知ったのは筑摩書房から出ていた映画雑誌『リュミエール』に発表されたいくつかの映画評論によってだった。映画の具体的な運動をとらえることを目指す面白い評論を書く人だな、という印象を持ったが、上野の名は60年代から知る人ぞ知る伝説的なもののようだった。日本サブカルにおける重要雑誌『ガロ』で「目安箱」と題されたコラムを書き始めて注目され、美術評論家の石子順造がひとに上野を紹介する時は「『ガロ』で「目安箱」という評論を書いている上野さん」と、必ず言っていたという。
個人的なことで言うと、平成元年に出された『肉体の時代』には大きな影響を受け、上野が映画評論家として名をあげるきっかけとなった東映やくざ映画のファンとなり、ビデオやDVDで上野の褒める作品を見、あるいはその類の映画を唯一上映していた浅草の名画座に通ったのだった。「3時のあなたの司会者」ぐらいにしか認知していなかった藤純子(富司純子)の女優としての輝きを発見したのも上野のおかげである。
今回のコラムで取り上げてみたいのは1983年に出された『映画=反英雄たちの夢』である。1972年から1981年にかけて書かれた文章で構成されているのだが、時代の変わり目と遭遇した者の戸惑いや苛立ちが生々しく伝わってきてじつに興味深かった。
『肉体の時代』においてと同様に、本書でも闇の変容というものが中心テーマとなっている。序章には「闇の記憶」というタイトルがつけられており、その文章の中で上野は、映画館という施設を純粋に映画を鑑賞するための建物という見方を斥け、仕事にあぶれた者や老人が身を潜めるふるさとのようなものとしてある闇の空間としてとらえ直して次のように言う
映画をやる――すなわちそこには、まず闇があり、そして光があるということである。闇のなかに身を置くことの気安さ。誰からの視線もあからさまに浴びることなく、肩をすり合わせる隣がどこの誰であろうと気にかける必要もなく、まどろんでいようと眠りこけてしまおうと、さらには、死んでしまったとて、とくに大きな音でもたてない限りは、一定の時間はなんの干渉も受けることなく居続けることのできる空間。それは闇があるからこそ可能なことであり、また、この闇を、白昼の光のなかでも抱え込んでいる映画館だからこそ可能なことでもあるのだ。
そこには、都市の中の闇溜まりとしての映画館が見えてくるはずである。闇溜まりには、どこへ行くとも当てどない人々が吹き寄せられてくる。いや、実は、どこに行くとも当てどない人々のまどろみこそが、映画館の闇を、その底から不断に醸成している、というべきであろう。
闇がある限り映画館はある。しかし七〇年代以降、なんともいいようのない明るさが都市を支配していくなかで、闇が留まるべき映画館が次第にその数を少なくしていることもまた事実なのである。
闇の醸成所としての映画館。そのような空間としての映画館のなかでも、とりわけやさしい闇を湛えたものは、やはり、名画座であろう。『映画=反英雄たちの夢』の第三章「われらの映画館」は、「キネマ旬報」連載記事で、「ヤエススター座」や「西荻名画座」などの名画座を中心にまちの映画館の佇まいがルポルタージュされる。そのほとんどが今はもう消滅している。ということは、このことは「どこに行くとも当てどない人々」の行き場所が消滅していることをも含意している。
かつては学生文化の中心地として名画座は確かにあった。神保町の古本屋の雰囲気に連なるというか、テレビなどに飽き足らない知的好奇心の持ち主の必須アイテムであった。名画座に足を運ぶ層と本を読む層は重なり合っていたように思う。それを「闇」という言葉でとらえていたかは定かでないが、表層とは異なる深さの体験を求めて名画座巡りをしていた。表層的なテレビが価値上昇するにつれ、名画座的なものは没落していった。いま流行りのシネコンは、映画の闇よりもテレビの光に近く、妙にファッショナブルだ。
「闇が留まるべき映画館が次第にその数を少なくしている」と上野は言う。七〇年代以降の日本の歴史でにおいて、そのような現象の意義はことのほか重大で、ことは映画のみに収まらない。映画というフィールドで上野が確認した現象は、精神病理学の分野で大陸系の教養で育った何人かの精神科医たちによっても感受されていた。映画館がしだいに消えていくのと並行して70年代以降を生きる人間の精神には何が起きていたのか。
神経症の消滅
ポスト・モダンの時代に精神疾患と向き合う精神科医たちは口をそろえてある歴史的事実のことに言及する。たとえばその一人の立木康介は次のように言う。
アメリカの精神医学会の診断マニュアルDSMが、一九八〇年に発行された第三版において「神経症」のカテゴリーを放棄したことは、ひとつの歴史的事件だった。
ドイツのフロイトを中心にして構築された精神分析学において、「神経症」は「基礎柱」とされる重要な概念であった。人間の根幹を形成する「無意識」は、ある力によって意識の外へとおしだされ、所謂「抑圧」という機制を蒙るのだが、抑圧されたものは抑圧されたままに留まるわけではなく、意識の中に代替物を送り込もうとする。神経症とはそうした代替物のひとつである。また抑圧を通して近代的主体は確立されるというのが近代のプログラムであるのだから、神経症の消滅は、ある意味では、人間精神(近代)の消滅とも言えるのだ。であるがゆえに、立木は次のように言わざるを得なかった。
このように、私たちがこれまで注目してきた現象を「抑圧の不在」という言葉で刺し止めることは、私たちにとってきわめて重要な意味を持つ。というのも、それによって私たちは、「神経症の終焉」という、とても厄介な、しかし精神分析にとっては避けられない問いへと導かれるからだ。
その問いに導かれるようにして、立木は現代文明の実相――闇よりは光を、私的事柄を秘すよりはその露出を、つまりは「私たちの内面にまで一律の尺度を入り込ませようとする無遠慮なエビデンス」を優先する現代文明の歪んだ欲望――を具体的に指摘してそれを告発する。具体的な例としては、雑誌『ピープル』と『ニューズ・ウィーク』の間の区別がなくなり、世間の耳目を引き付ける能力に長け、自分をショー・アップすることに成功した政治家が勝利をつかむという現象。あるいは国内では、「二〇〇五年二月に、ある女性タレントがテレビ番組で過去の万引行為を告白し、テレビ局や警察に視聴者からの抗議が殺到するという騒ぎが起こった」。また別の例としては「コンビニや飲食店の食品ケースのなかに自分が入り込んだ写真をフェイスブックやツイッターにアップロードして悦に入る若者たち」の存在が指摘される。ここにあるのは光当たる空間にすべてをさらけ出したいという奇妙な欲望である。そしてそれへの裏返しとしてアンバランスすぎるほどに「闇」の領域が駆逐されている危機的状況である。「心の闇」を抹殺しろ、という大方の世論に逆らって、立木は闇を回復することこそが急務なのだと慎まし気に異議を唱える。1997年に神戸で起こった連続殺傷事件の少年Aについて立木は次のように述べている。
少年は、残念ながら、心の闇をつくり損なったのだ。ほんとうなら、彼は心の中にもっと深い闇をつくり、彼を現実の殺傷行為へと突き動かすことになった苛烈な欲望をそこにしっかりと繋ぎ止めておかねばならなかったのに。(だから、この事件を教訓として、もしも世の親たちに忠告すべきことがあるとすれば、それはけっして「子供の心をつかめ」ではないはずだ。実際、子供にしてみれば、自分の心のなかに立入ろうとする親などとは、さっさと縁を切りたいと思うだろう。むしろ、「子供の心にもっと堅固な闇をつくる」ことのほうが、子供にとっても親にとっても大事であるにちがいない。どれほど恐ろしい欲望も、そのなかに堅く閉ざしておくことができるように。どれほど残酷な願望も、そのなかに深く沈めておけるように。)
だが、あらゆる空間から闇が消し去られ、メディアがどのような場所にもカメラ=光を入り込ませる社会において、個人がそれと同じ行動をとらないいかなる理由もない。それどころか、私たちは明確にこう問わずにはいられない。むしろ私たちの社会やメディアのほうが、本来ダークサイドにしまわれていなければならない昏い欲望を衝撃的なやりかたでデモンストレートする主体を模倣しているのではないか、と。
1980年における「神経症」という医学用語の消滅は、世界から闇を駆逐し、光の帝国と呼べるものを出現させた。背景には新自由主義というグローバルな経済活動がある。映画や精神分析学が直面したものは、そのような「破滅的頽廃」である。
アルゴリズムという名の光
立木康介同様、DSM第三版における「神経症」の消滅に震撼させられた精神科医のひとりに松本卓也がいる。松本はこの事態の背景に、拡張してやまないアメリカ的な論理の不穏な動きを感受している。松本はその動きに「アルゴリズム」「統計学」という呼び名をあたえ、グローバル経済において覇権を握ろうとするアメリカの意志と似たものを見てとっている。「ここに第三版以降のDSMがもつアルゴリズム化の欲望をみてとることは決して難しいことではない。むしろこの国は、精神医学の領野全体に均質化とアルゴリズム化の思想を流し込んだことによって、その覇権を手にしたのである」(『享楽社会論』)。まるで「GAFA」と称されるプラットフォーマーが、覇権を手に入れることで世界を都合よく均質化していくさまのようである。統計学のフィールドに人間が囲い込まれ計算されることによって利便性や生産性は向上し、経済効率は確かに高まるだろうが、そこでは人間はたんなる経済の駒でしかなくなってしまう。経済奴隷として経済主義という父の言うがままになってしまう。
巨大資本と結託したこのような数字の専制は、ラカン派の精神分析家が近頃「統計学的超自我」(Brousse 2009)と呼んでいるものに相当すると考えてよいだろう。象徴的秩序を統御する大文字で書かれうるような<父>が消滅した時代にあっては、統計学のようなアルゴリズムが<父>の代わりに働くことになる。そのような時代の到来をジャック・ラカンはすでに一九七〇年代中盤に予想しており、それを「破滅的頽廃」と評していたのであった。<父の名>が機能不全となる時代には、「鉄の秩序 ordre de fer」が「現実界における父の名の回帰」として出現し、一種のより悪い父として機能するのである。
生産性と経済効率という「鉄の秩序」を前になす術の無いわれわれ自身の姿を見るようである(沖縄の基地問題を巡る民意も「鉄の秩序」の前に無力である)。1980年の上野昻志が眼にしたものも、「鉄の秩序」とまでは言わないものの、映画を取り巻く環境における映画的運動を停滞させる「一種のより悪い父」である。その「一種のより悪い父」のことを上野は「CMフィルム的感性」と呼んでいる。
1976年から1980年にかけての角川映画の快進撃をうけて、上野はそこに「広告の小説化であり、映画化であり、音楽化であるという」新しい事態の顕在化をみてとっている。『犬神家の一族』という映画は『犬神家の一族』という小説の広告であり、『犬神家の一族』という小説は『犬神家の一族』のサントラ盤の広告として機能し、そのような連動によって広告のほうが商品を作り出すという現象は、消費社会ではすでに普遍化しており、広告こそが世界の中心に位置する世界にあっては、映画の具体的な差異よりもCMフィルムのイメージが優位を保つ文化的趨勢がかたちづくられる。思えば70年代末から80年代前半にかけては広告業界やテレビ業界が全盛を誇っていて、わかりやすさの名のもとに、われわれの感性や思考形態を「一般性」という環境、あるいは今の言葉で言えば「空気」という牢獄のようなものへと閉じ込めようとしていた。「一般性」とは、上野が言うように「支配者のことば」である。それはアルゴリズムという名の光の機能を果たすべく、「常にこう見て欲しいというような一定の文脈を、陰に陽に呟き続けて」いるのである。アルゴリズムの呟きに逆らうには、「人の悪さ」を身につけなければならないが、そうした試みはなかなかうまくいかない。
それこそは、わずか十数秒から三十秒までのCMフィルムの常態にほかならないのである。映画は、本来その運動において、かかる停滞状況を不断に解体していくものだったのである。それができないのは、これら広告としての映画の作者たちが、みずからを縛りつけてくるCMフィルム的感性に対して、抵抗を組織し得なかったからである。
この困難な試みを引き受けている者のひとりに、上野は映画監督加藤泰の名を挙げている。「加藤泰の眼差しは、ただひたすら、黒々とした闇のなかから、ひとつの行為がもがき出てくる瞬間に注がれ、やがて、光が闇に溶けあうさまをも見届けようとはられている」(「黒い画面とひとつの光」)というふうに。最後に、現在の多数派が形成した文化的環境に異議申し立てを試みる精神分析学と映画作家たちの言葉を紹介しよう。
貶められた闇のために
現代が「露出」の強制であることを喝破し、そこに科学テクノロジー、資本主義、メディアの邪まな結託および欲望を見出す立木康介は、古典的な主体に希望を託す。
無意識を読むという文化がいかに往時の輝きを失ったからといって、無意識的なものを通じて、すなわち抑圧を通じて自己を確立するタイプの主体はけっして消滅してはいない。それどころか、これらの主体はじつはまだそれほど少数派になったわけではない、とすらいえるかもしれない。精神分析はかれらとともに、無意識を排除するネオリベラルな科学主義にたいして、ノンをつきつけることをやめないだろう。私たちの内面にまで一律の尺度を入り込ませようとする無遠慮なエビデンスにたいして、徹底的に抵抗し続けるだろう。
また、松本卓也はラカンが提唱する<物>という概念を科学のイデオロギーから守ろうとする。<物>とは「象徴化の以前にあったと推定される原初状態」であり、ラカンによって精神分析の倫理の核心であるとみなされる(臨床における「主体」の瞬間的なあらわれもこれと関係する)。
おそらくそう遠くない未来に、メンタルヘルスの世界は完全に書き換えられるだろう。なぜなら、インセルのクライテリアや彼のような思想(主体の完全なる殲滅)がこの世のすべてを占拠するとき、<物>の次元を認めない科学のイデオロギーはついに絶対知の段階にのぼりつめ、知的な――そして奇怪な――構造物として、体系化された妄想のように結実するはずだからだ。しかしそのとき同時に、私たちは取り返しのつかない破滅的頽廃、あるいはフーコーが予告していた「人間」の完全な終焉を眼にすることになるのかもしれない。精神分析に求められているのは、このような現代精神医学の彼岸への「抵抗」である。
そしてまた、上野昻志は、加藤泰の映画『骨までしゃぶる』という女郎の廓ぬけを描きハッピーエンドで終わる作品を論じた文章(「黒い画面とひとつの光」)のなかで、光の世界にいる主人公の男女と対となる闇に沈んだ一組の男女にスポットを当てる。女はヒロインの友人の女郎であり、一方男は映画の中でほんの一、二カットにしか登場せず、しかも一言も台詞を発しない端役のような存在である。土工を職業とする貧しいこの男は、主人公の女郎の友人を、ひどく残酷に殺してしまうのである。この小さな挿話から、上野は「闇」をめぐる意味を次のように引き出す。
やさしさに飢えているやさしい心が、冷たく拒絶されたとき、その圧殺された感情は、一挙にもっともむごたらしい行為として噴出するというそのことを描いているのである。やさしいが故に人を殺さざるを得ないのであり、残酷に振舞わねばならないほどにやさしい感情を抱いているということは、たとえば、情念の弁証法とも、犯罪の存在論とも言い得るだろうが、加藤泰はそれを、生活の抜き差しならない関係のうちに描きだすのである。
「あんなにやさしいお姐さん」だって、いややさしい心を持っていたからこそ、客に対して冷淡に振舞うのであり、そのように機械的に抱かれることによってのみ、自らのうちのやさしさを失わずにいるということ。それに対して客は、いや、客一般ではなく、あの男は、生活の一切の関係においてやさしい関係から閉めだされているが故に、女郎に、――しかも、具体的に彼が接し得る女といったら女郎しかない――やさしさを求めていくが、拒絶される。表現としてのやさしさを拒絶することだけが、人間としての証であるような生活を生きている女だから、それは当然のことだ。かくて、このような男とこのような女との関係がつきつめられれば、そこに起こるのは、犯罪しかない。
やさしい感情を求める心が、犯罪としてしか現出しないということは、彼らが、彼らの生きてあることの矛盾をなしくずしに解消させていくべき安全弁を持たないということにほかならないが、しかし、まさにそのように描かれているがために、彼らは、生活者として私たちの前に現れるのである。
このような言葉をアルゴリズムは発することはできない。アルゴリズムはイメージとしてある統計をなぞることしかできない。このような言葉は、具体的な闇というか、より正確には、社会の下層部でもがき苦しむ具体的な生活に触れていなければ、発することができない性質のものだ。そして具体的な固有性というものは、アルゴリズムにとっては闇のような異物としてある。
本コラムで取り上げた『映画=反英雄たちの夢』、『露出せよ、と現代文明は言う』、『享楽社会論』は、アルゴリズム社会においては、やはり、「闇のような異物」でしかないのであろうか。アマゾンで調べてみると『映画=反英雄たちの夢』、『露出せよ、と現代文明は言う』は、それぞれ、絶版であり、『享楽社会論』は、1年前の刊行ゆえ、まだ、新刊本として登録されているようだ。絶版本であることは「隠れた名作」の必須条件とも(好意的には)受け取れようが、このような名作を絶版本にしてしまう社会の力学や在り様には憤りを覚えずにはいられない。社会のそうした不条理に対しては抵抗を試みなければなるまい。
1975年前後、そして「夜」「闇」の話題だったので、その周辺の曲を。まずは1975年のイーグルスの「One Of These Nights」を。イーグルスというと、カラリとしたウェストコースト・サウンドが特徴だが、これはどちらかというと、ブリティッシュ寄り。代表曲である「ホテル・カリフォルニア」よりも個人的にはこちらのほうが好きである。
1974年のキング・クリムゾンの最終アルバム『RED』から「スターレス」。B面最後の曲だがいかにも象徴的。そして私にとってのプログレッシブロックも1975年前後に終わった。
最後はもう少し軽く。BONNIE PINKの「Tonight, the Night」(2003年)。BONNIE PINKは贔屓のミュージシャンだが、押しが弱いせいか、いまひとつメジャーになりきれない。最近は見かけないけれど、どうしているんだろう。再ブレークを期待する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
