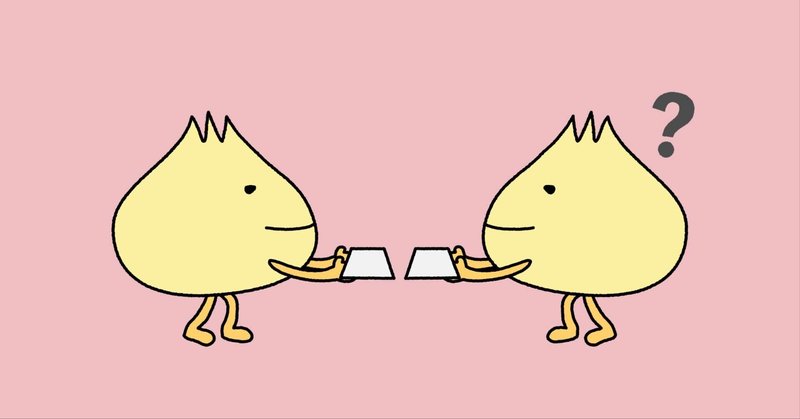
忘れられない名刺
あの名刺だけは忘れられない。いくら全力で忘れようともがいても頭にこびりついて離れない。そんな思い出の名刺がぼくにはある。今日はそんな話をしたい。
遡ること5-6年前。ぼくがアマゾンジャパンという会社で営業担当をしていたときのことだ。今でこそプロダクトマネージャーとして社内で缶詰になってエンジニアとごりごりソフトウェア開発をしているわけだけど、当時はいわゆる営業っぽい仕事をしていた。AmazonのWebサイトに商品を登録してもらうよう担当のメーカーさんと交渉をする。そして売上を増やす施策としてAmazon内外の広告活用やセールへの出品を提案する。メーカーさんの売上の行方がぼくの肩にかかっている‥。そう思うとなんだか身が引き締まる思いで、毎晩遅くまでオフィスに残ってバリバリと働いていた。夢我夢中に仕事をしていると気が付けば時計の長い針と短い針がぴったりと0時を指そうとしている、なんてこともよくあった。「やばい!」と思う頃にはフロアの電気がバババッと一斉に消灯され、暗闇の中で慌ててバッグを引っ掴んでビルを抜け出す。そんなことも一度や二度ではなかったと記憶している。
ぼくは大きく括ると"家電"の事業部に配属していた。いくつかチームがある中で、比較的小さい"楽器・音響機器"のチームにいた。元々趣味でギターを弾いていたこともあって、楽器メーカーさんを担当するこの仕事はすこぶる相性が良かった。楽しすぎて目黒のオフィスまで毎朝ホップ・ステップ・ジャンプという足取りで通勤していたと思う。
そんなある日である。オフィスに着くやいなや「福原くん、ちょっと時間ある?」とそのときの上司に声をかけられた。いつも通りその上司はパリっと糊の効いた白シャツを着てベージュのチノパンを履いていた。そしていつも通り少しだけ機嫌を損ねたディーン・フジオカのような顔をしていた。その日だけディーン・フジオカのような表情をしていたとかではない。そういう顔なのだ。
上司が仕事部屋として使っている小さい角部屋に招かれた。中に入ったあと「さあ、そこに掛けてください」と言われたのでその通りに背もたれのないパイプ椅子に腰掛ける。真向かいに座ってマジマジと上司の顔を見つめると「低血圧のディーン・フジオカはきっとこんな感じだろう」と勝手に想像して勝手に納得した。
ぼんやりとそんなことを考えていると、ディーン・フジオカは (みたいな顔の上司は) 出し抜けに屈託のない笑みを浮かべてこうぼくに告げた。
「福原さん、来週から大型家電の事業部に異動です。」
え?
「大型家電のチームが人が足りてなくてピンチなのです。どうか福原さんの力を貸してほしい。福原さんにはあの有名家電メーカーSを担当してもらいますからね。頑張ってください!!」
なんと。藪から棒である。戸惑いを隠せなかった。ただ少し間をおいてだんだんと腹の底からふつふつと感情が湧いてきた。
おい、これは大抜擢だぞ。有名メーカーSと言えば誰もがその名を知っている大手企業だ。その担当にぼくが抜擢‥。しかもチームがピンチだって!?
‥いや、待てよ。決してカンタンな仕事ではないぞ。責任重大じゃないか。ぼくにそんな重荷が耐えられるだろうか?
‥でも待てよ、これはきっとチャンスだぞ。毎夜のハードワークがきっと実を結んだのだ。このチャンスを見過ごしてはならぬ。きっとこの難関をクリアしたときにはモテ期来るよ。
男、福原たまねぎ、いざ立ち上がるべし!!!
ひとしきり頭の中で一人会議を終えたあと我に返って「はい!頑張ります!ディーン・フジオカさん! (みたいな顔の上司!)」と返事だけして颯爽と部屋をあとにした。
デスクに戻ると早速異動の準備に取り掛かった。さて、まずなにから取り掛かろうか。うーんと頭をひねったあと、パッと閃いた。
そうだ、名刺を作ろう。
有名メーカーSともなれば、きっとお偉いさんの格だってぐっとあがるに違いない。年齢だってぼくより一回り上だろうから、40〜50代ぐらいだと思われる。いや、もっと年輩の方の可能性だってあるぞ。みんなクラシックなブラックのスーツを嫌味なく着こなし、磨き上げた革靴を上品にコツコツと音を立てながら廊下を歩くのだろう。ヒゲは残っててもあくまで清潔感を保ったままきちんと整えられ、あえて黒染めしない白髪からは風格というものが漂ってくるのだろう。商談が始まると「娘が最近ピアノをはじめまして‥」なんてどうでもいい話を(失敬) 挨拶代わりにされるかもしれない。想像しただけで背筋がピンと伸びる。
困った。そんなアダルト(大人)でピシッとしたビジネスマンとこんなぼくみたいな若造がどう張り合おうってんだ。でも舐められてはいけない。この重要な責務をぼくは任されたのだ。
まずはカタチから入るのが賢明じゃないか。たまたま最近スーツと革靴を新調してあったし、髪をきっちりとセットするジェルも買ってあった。
あとは足りないのは名刺だけだ。
新しい部署名をきっちりと記した名刺を用意すればよいのだ。そして「福原玉葱」と鮮やかに印字された名前を表にして深々とお辞儀をして礼儀正しく名刺をお渡しする。これで掴みはバッチリだ。「おーこの子はなかなかしっかりしてるね」と先方の間で評判になり「ちとこの子に懸けてみようじゃないですか。福原さんに我が社の未来を懸けます。つきましては1,000万円の追加投資をします!」なんてことにもなるかもしれない。そしたらいよいよ念願のモテ期だって到来すること間違いなしだ。
我ながら妙案じゃないか。「今日は頭が冴えてるぜ」と思わずひとりごとがこぼれる。
ぼくは早速社内の名刺発注システムを開いた。Web画面上で会社名、部署名、そして自分の名前を記入した。最終確認画面まで辿り着くと「印刷プレビュー」というボタンがあったのでクリックしてみる。すると小さいウィンドーが現れて中に名刺のサンプルが表示された。左上には「アマゾン合同会社 大型家電事業部」とあった。うんうん、問題なし。そして真ん中に大きくこう記されていた。
福原玉葱
見事だった。鮮やかなゴシック体で書かれたその名前が目に入ると思わず拍手をするところだった。少なくとも心のなかでスタンディング・オベーションをしていた。今ここでは福原玉葱というぼくのNoteのニックネームで書いているけれど、実際には「福原〇〇」という本名で書かれていたこともあって、その漢字の威厳といったら凄まじかった。名刺の真ん中の名前の部分だけが輝いているように映り、思わず瞬きをしてしまうくらいだった。ま、眩しい。
あまりの完成度に胸を打たれたので、ぼくはもう一度入力画面に戻った。部数を改めて入力するためだ。はじめ「50」と書かれたセルに「500」と打ち直した。きっとこの名刺はこれから長くお世話になることだろう。お得意先はもちろん、親戚や友達にも配りたい。モテ期に備えて美女に配る分も充分に用意しなくてはならない。新しい門出だ。小さくまとまってる場合ではないぞ、福原。ここは大きく出ようじゃないか。そう気合を入れて、ぼくは最終確認画面へと進み、意気揚々と発注ボタンを押した。
2週間が経った。ぼくはもう既に大型家電チームの仲間入りを果たし、フル回転で働き始めていた。なにせ人手不足でピンチを迎えていたチームなのだ。ぼくが頑張ってチームを助けなければならない。ディーン・フジオカの期待を一身に受け、ぼくは身を粉にして働いた。また夜中0時まで働き詰める日々が始まった。待ってろ、すぐにおれが助けるから!!と息巻いていた。
そんな折、一通のメールが届いた。そこにはこう書かれていた。
「名刺が届きました」
とうとうその日がやってきた。今日でぼくのキャリアが一変する。そんな予感がした。この名刺はただの名刺ではない。未来へのパスポートなのだ。将来誰かにインタビューを受けたときに「そうですね、思えばあの名刺がすべての始まりでした」とクールに答えている自分が自然と頭に浮かんだ。輝かしいキャリアの幕開けを告げる、そんな記念すべき一日だと思うと自然とお腹の奥底でぐっと力が入った。
ぼくは早まる気持ちを辛うじて抑えつつ、名刺が届いているという社内の郵便ボックスまで足を運んだ。ぼくの名前が書かれているケースを開くと、奥には名刺入れを三段重ねしたぐらいのサイズの立方体のケースが置かれていた。
あった。名刺だ。いや、未来へのパスポートだ。それは奥の方でキラキラと光っているように見えた。
さすがに500枚ともなるとなかなかのサイズだなと思った。ずっしりとした重さだ。ぼくはハムスターを手で抱えるかのような手つきで大事に大事にその名刺ケースを携えデスクまで戻った。
いよいよだ。デスクに座って名刺ケースを目の前に置いた。なんだか受験の合格発表を思い出した。緊張の面持ちでケースのフタを開けて、すっと一枚抜き出して手に取った。どれどれ、どんな仕上がりでござろう。
名刺を軽く宙に持ち上げて左上から読んでみる。小さい文字で「アマゾン合同会社 家電事業部」と綺麗に印字されている。印刷プレビューで見たものそのままだ。「よしよし」と静かに頷きながら、真ん中へと眼差しを向けた。そこにはこう鮮やかに書かれていた。
フクハラタマネギ
え?‥えぇぇぇ!?
なんで、‥なんで、‥
なんでカタカナなんだよ!!!
ぼくは自分の目を疑った。疲れ目なのかなと思い、何度か瞬きをしたり一度遠くを見つめたりした。そして気のせいであることを祈りながらもう一度名刺に目を向けた。そこにはクッキリとこう書かれていた。
フクハラタマネギ
なんだこれは。大体なんでカタカナなんだよ。
漢字はどこいったんだよ。これじゃまるで「振り仮名が大きくなっちゃいました」みたいじゃないか。しかも振り仮名なのにどうしてひらがなじゃなくてカタカナになっちゃったんだ。おれの漢字を返せ!!!
見ればみるほど暗澹たる気持ちになった。なんだよ、これじゃあ外国人野球選手の名前みたいじゃないか。カタカナが許されるのはディーン・フジオカぐらいであってフクハラタマネギだったらただのワルふざけにしか見えないじゃないか。
「なんでこんなことが起きたんだ」
両手で頭を抱えた。いくら記憶を辿っても思い当たるフシはなかった。
訳が分からないまましばらく途方に暮れていたところ、パッとあることに気付いた。
「きっとこの一枚だけが間違って印刷されちゃったのだ」
‥そうだよ。‥うん、きっと、そうだよ。そんな名刺の名前をぜんぶカタカナで刷っちゃうなんてアホみたいなこと起こるわけないじゃないか。
そう思ったらドサッと肩の荷が下りた気がした。
なーんだ、一枚しくじっちゃったんだな。まったくもうーーー。まあでも人間みな失敗はするものだよね。仕方ない仕方ない。気取り直そうぜ。ナイストライ!
そう思って名刺ケースから2枚目をすっと引き出した。手が少し震えていたことを覚えている。漢字が見たい。あの神々しいまでに美しく書かれた「福原玉葱」が見たい。あの印刷プレビューが映し出した鮮やかな「福原玉葱」という字を!
頼む‥‥‥頼んだ!!!!!
取り出した2枚目の名刺。真ん中にはこう書かれていた。鮮やかなゴシック体で。
フクハラタマネギ
いらない。一枚もいらない。こんな名刺を先方のお偉いさんに渡したらどうなるものか。舐めてるとしか思われないだろう。「ふざけんじゃないよーーーっ!!!」と怒鳴り散らして、せっかくのブラックのスーツも脱ぎ捨てきっちりと磨き上げた革靴もぶん投げてくるかもしれない。こんなふざけた名刺を渡してくる輩に未来を懸ける会社などないだろう。
3枚目も10枚目も、そして100枚目も、そこには誇らしげにフクハラタマネギと書かれていた。そんなに堂々としなくてもいいんじゃないかと思うぐらい威風堂々としていた。
ぼくは絶望の中でひとり取り残された。すると横に座っていたチームメンバーの女の子が話しかけてきた。
「新しい名刺できたんですか?」
まずい。彼女はこの前大学を卒業したばかりのピチピチの若い女の子だ。黒髪とくりくりとした目が特徴的だった。興味津々といった様子で曇りのない眼をこちらに差し向けているではないか。
ぼくは大事な助っ人なのだ。チームの要にならねばならない男だ。そんな男がカタカナの名刺を500枚も刷ってしまったことがバレたらまずい。
でもぼくは既に落ちた絶望の底から這い上がる気力もなくなっていた。
ぼくは観念したような表情を浮かべ、すっと名刺を一枚手に取り彼女に手渡した。
「名刺‥ ぜんぶカタカナで刷られちゃってさ」
とそう告げると0.3秒後ぐらいに彼女はアヒャヒャと笑い出した。突然の発作のごとく爆笑しはじめた。彼女が入社してこの方喋ってきた日本語の総量よりも、その数秒間に発した「アヒャヒャ」の量の方が遥かに上回っていた。腹を抱えて笑っている彼女を見かねて他のチームメンバーも「どうしたのー?」と言って集まってきた。もう逃げ場はない。ぼくは静かに名刺をすっと取り出して一枚一枚渡していった。
「え、なんでだよ!!?」と言いながらみんなアヒャヒャと笑い転げた。「外国人野球選手じゃないんだから」と口にしてるものまでいて「それおれも思ったよ」と心のなかで突っ込むと、途端に自分もおかしくなってきてしまった。もうどうでもいい。そう思うと笑いが止まらなくなった。
ぼくはアヒャヒャという笑いの洪水のなかで、頑なに握りしめた名刺をもう一度見つめた。みんなゲラゲラと笑っていたけど、きっとこう思ったに違いない。
「やばい奴、チームに入っちゃったよ。」
今振り返っても一体なんで名刺がぜんぶカタカナで刷られたのかは分からない。どんなトリックだったのか手掛かりすらない。完全に闇の中だ。
ぼくが名刺を発注する際に妙に肩に力が入ってしまい、間違えて「全カタカナ変換」ボタンを押してしまったのだろうか?だとしてもそんなそもそもボタンいる?一体誰が使うねん。謎は深まるばかりだ。
でもこの世の中、分からなくていいこともきっとある。人生とは理不尽な謎に満ちたものだ。ぼくはあのカタカナの名刺を思い出す度に、そう心を諭すのだった。
これでこの話はおしまいです。今日はそんなところですね。
それではどうも、お疲れたまねぎでした!
サポートとても励みになります!またなにか刺さったらコメントや他メディア(Xなど)で引用いただけると更に喜びます。よろしくお願いします!

