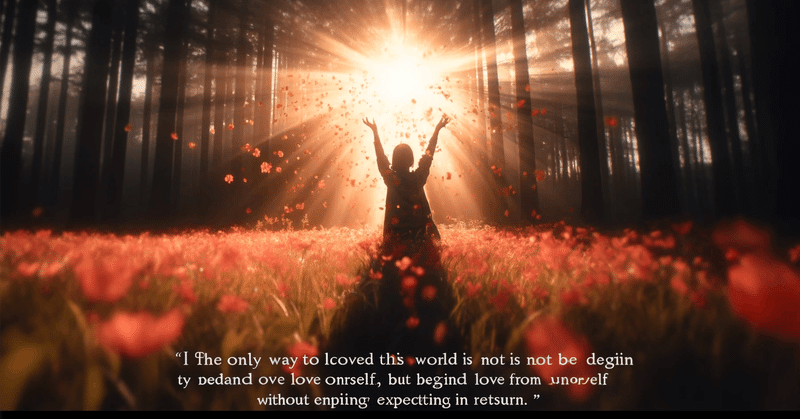
最期の記憶【ショートショート】
夕焼けが街を包み込む時間、科学技術の街は、まるで時が止まったかのような静寂に覆われていた。その中で、人々は自らの記憶をデジタルデータの海に委ねており、その行為がなんらかの救済であるかのように錯覚していた。
「悩みも後悔も、すべて洗い流してくれるんだろうか」
そんな淡い希望を胸に、彼らは一か所に集まっていた。
それは『記憶調整センター』と呼ばれる場所で、人々の記憶を加工し、理想の人生へと導くサービスを提供していたのだ。
「もう、過去に囚われたくない」
エミリもまた、そんな人々の一人だった。
彼女の心の奥底では、そんな切実な願望が渦巻いていた。幼い頃に亡くした弟の記憶は、彼女の心に深い傷跡を残していた。その苦痛から自由になるため、彼女はセンターの門を叩く覚悟を決めた。
記憶の編集者との対話の中で、エミリは自らの願いを吐露した。
「私、もう一度、清らかな気持ちで生きていきたいんです」
彼女の声には、希望と迷いが混在していた。記憶の編集者はエミリの言葉に深く共感し、手続きに取り掛かった。
手続きを進める中で、エミリは重大な選択を迫られた。弟と共に過ごした最後の日の記憶が、彼女の心に映し出されたのだ。
「こんなにも幸せだったのに……」と、彼女の内面では葛藤が巻き起こっていた。
弟の優しい言葉が、彼女の魂を揺り動かす。
「姉ちゃん、大丈夫だよ。ずっとそばにいるから」
その言葉を聞いたエミリの心は大きく揺れ動いた。
突然、彼女は弟の記憶を消去することをやめたいと強く願った。
「待って、これだけは消さないで!」
しかし、彼女の叫びは既に手遅れだった。
手続きが終わり、センターを出たエミリは、何かを失ったような深い孤独感に襲われていた。
「なぜ、こんなに心が寂しいんだろう……」
彼女は自分の内なる空虚さを感じ取っていた。それは、どんなに努力しても満たすことのできない深い穴のようだった。
記憶を消す技術がもたらす一時的な救いは、たしかに一瞬の安堵を与えるかもしれない。だが、エミリのように、本当に価値あるものを手放した時、その喪失感は心の奥底に深く刻まれ、永遠に消え去ることはないのだ。科学技術が紡ぐ幸せは、真の自己との向き合いや、心に残る切ない悲しみには、決して及ばない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

