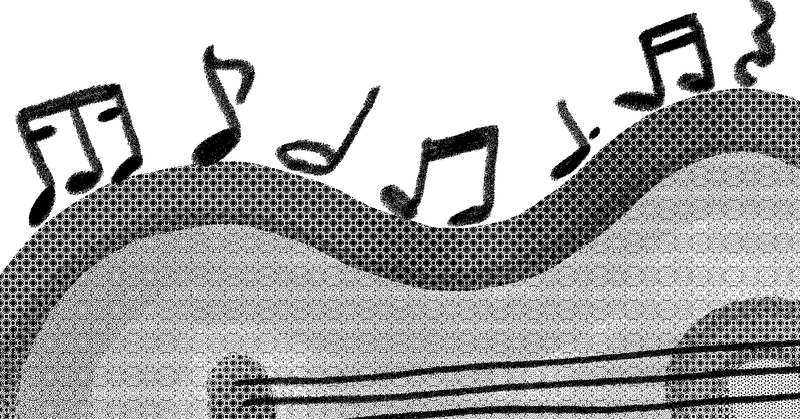
小沢健二論
小沢健二は変化した。特にその歌詞が。あるいは歌詞の裏にある意味が。また、その表現が。
人はいつまでも瑞々しいままではいられない。時間と共に歳をとり、必ず老いてゆく。それは決して悪いことではないし、変えようのない真実だ。けれど、もし神が許すなら小沢健二のあの若い頃の感性だけは変わらないままにしておいてほしかった。
もちろん今の小沢健二が悪いわけではない。若い頃よりもむしろ洗練された部分もあるし、歌詞の内容も具体性というか、エッセイ的になっていて面白いと思うところも多い。けれど、若い頃の小沢健二はまさしく「神がかって」いたと思う。
若い頃の小沢健二は
「抽象の具体化と、具体の抽象化」
「ありきたりな日々の経験からの普遍性の抽出」
のプロセスが半端じゃないくらい上手かった。
喜びに満ち溢れた恋、哀しい別れ、若々しさゆえの失敗、涙、汗、そして変わらないようで変わってゆく日々を、あれほど美しく描ける人は、ここ日本には若き小沢以外にそう多くはいないだろう。他の歌手や、作家も含めて。
それは小沢がただ誰もが経験したようなことを、そのまま描写するのではなく、限りなくそれを抽象化し、普遍性を取り出してゆく作業の精度がとてつもなく高いことを意味している。そして歌詞にそれを写し出すとき、小沢は難しい言葉を使わない。あくまでシンプルなワードで普遍の日々を示してゆく。
だから小沢の歌を聴く時、その歌詞は小沢自身の経験を描いているようにも、まるで遠く離れた私の経験を描かれているようにも感じる。でもそれは実は誰の経験でもない。普遍であって、抽象であって、本当は深遠すぎて共感しにくいような人間の「真理」に近いことを歌っている。
それでも私たちが小沢の曲を聞いて、心を打たれるのは彼の表現力、つまりワードセンスが限りなく洗練されているからだ。
難しいことを、シンプルに、簡単に。
これをできる人は頭がいい。とても賢い。そして小沢健二はやっぱり、東大卒なのだ。
では今の小沢健二は何が変わったのか。一言で言うと、
「難しいことを、難しいまま語る」
ようになってしまったような気がする。
歌詞の中に難解なワードが増えた。もっと分かりやすく言えば、熟語が増えたような気がする。あたかも昭和の教養人が書く文章のようになってしまった。
内容は非常にエッセイ的な部分と、加えて若い頃よりも「神」や「宇宙」といったテーマをよく語るようになった。
これは小沢健二の一つの成長なのかもしれない。好意的に、そう捉えることもできるだろう。小沢健二は新たなフェーズに入っている。身近な経験な普遍化から、外へ、宇宙へ。
でもそれは聴く人々を置いてゆく。共感は失われ、私たちは小沢健二を見上げることしかできなくなっている。かつては身近な、暮らしの中にあった小沢健二は、今は遠く彼方へと、限りない言葉と概念の高みへと歌詞を紡いでゆく。
それが美しくもあるし、同時に悲しくもある。そしてあえて言うなら、私は若い頃の小沢健二が好きだった。
それでも私は小沢健二を聴き続けるだろう。これからも、ずっと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
