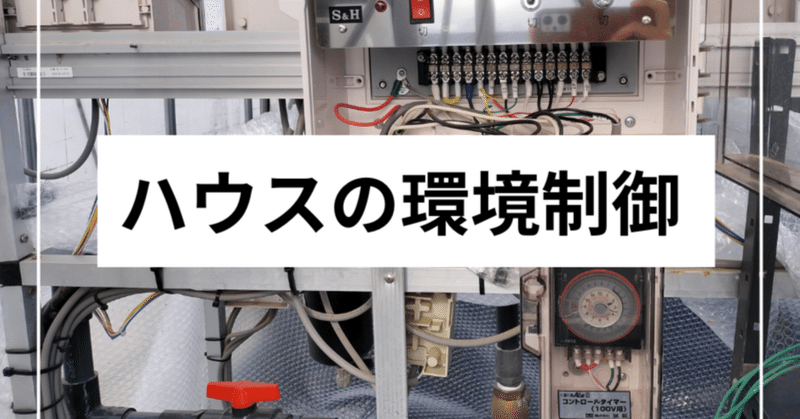
農業ベンチャーでのお話【7】:ハウスの環境制御、知識を得る喜び
こんにちは、農業ベンチャー企業を退職し、余生を前借り中の主婦 K Yoshieです。
閲覧いただき、ありがとうございます♪
今日は、ビニールハウス内の温湿度や光強度などを、植物にとっての理想状態に整える【環境制御】についてのお話と、育児しながら社員になった当時のお話を綴っていこうと思います。
植物栽培、育児をされている方の一助になれば幸いです。
環境制御との出会い
ハウス内で生育中のトマトが【うどん粉病】を発症し、どうやらハウスの中の湿度をコントロールしないと根本解決はできないことが分かった。
環境をコントロール。。
そもそも農業は天候次第と思っていた自分にとって、【人間がハウスの中の環境を制御する】という概念が全くなかった。
家では部屋が寒ければストーブを焚いたり、暑ければ窓を開けたりはしていたが、それが環境を制御しているという実感がなかったのだ。
まして、温度については肌感覚で分かるのだが、湿度を制御するというのが斬新だった。
社長の勧めで、以下の3冊の本を読むことにした。
面白くて徹夜で読破した。
具体的な環境制御の方法については、上述の本に細かに記載されているので割愛するが、これらの本は、施設栽培をされている方の多くに既に読まれている、基本となる本である。
特に、1冊目の『ハウスの環境制御ガイドブック』は環境制御の導入本としておすすめである。
著者、斉藤 章先生は、環境制御のセミナーやコンサルティングも行っておられる方。
私自身、何度か先生のセミナーに参加し、得た知識をハウス内で試行錯誤し、収量増(ミニトマト反収20t)にもつながった。
農家が利益を得るには、何よりも商品となる青果物を、安定的に収獲につなげることが大事。
成果物とは、光合成の同化産物そのもの。
だから、【いかに効率良く光合成を行わせるか】が大事になる。
今回のように病気を出すと、葉が物理的に光を受容できなくなり、光合成どころではない。
また、植物体内では、病気に立ち向かうための物質が合成され、これは大きな臨時出費、本来行うべき反応に使うエネルギーや物質が横取りされることになり、植物の生長や果実の肥大などの効率も低下してしまう。。
ハウス内の環境を制御することは、植物体を制御すること。
これらの本との出会いは、私がトマト栽培にのめりこむ、最も大きなきっかけとなった。
子どもの成長
パートとして働き始めて1年半が経とうしていた。
2人の子どもたちは地元の保育園に入園し、彼らの生活リズムもずいぶん整ってきていた。
私自身、一緒に働くママ友もでき、精神的に安定していた。
小児喘息とアトピー性皮膚炎、花粉症。
私と同じ体質を受け継いだ長男は、何かと病院へ連れていくことが多くかった。
入園間もない頃は、月に数回、保育園から呼び出しの電話がかかってきた。
(次男はケガは多いが、体調はいつも安定して良好だった。)
主人は当てにならず、すべて私が対応。
電話が鳴るたび、おびえた。
仕事を途中で抜け出しては、一人悶々とした気持ちを抱えることが多かった。
そんな長男も、年中さんになる頃には風邪すらひかなくなり、喘息発作や皮膚の状態も、ずいぶん落ち着いてきていた。
この頃には保育園からの呼び出しもほとんど無くなっていた。
【男の子は小さいうちは弱いけど、だんだん強くなっていくからね~】
看護師さんによく言われていたこと、正直、気休めだと思っていたのだが、本当だった。
もちろん、成長したことだけで症状が軽くなったわけでもないだろう。
適切に処方薬を使いながら、子どもたちが纏う服は綿製品にしたり、洗剤は石鹸ベースのものに変え、総菜やお菓子は買わずに昔ながらの調味料を使って手作りするなど、、、
神経質な私は、ネットや書籍でアトピーに良いとされる情報を調べては、家の中で試行錯誤していた成果も出始めたのかもしれない。
もっと働きたい
環境制御との出会いから、私はすっかりトマト栽培の虜になっていた。
育児と家事もこなしつつ、子供を寝かしつけるとすぐに本を読み漁った。
次男を授乳しながらも、頭はトマトのことでいっぱい。
主人は夜中まで帰ってこない。
彼も職場での実験に追われ、大抵0時過ぎの帰宅。
21時~0時までは私の勉強時間となった。
これまで受験勉強のために徹夜することはあったが、自分の興味のままに本を貪るのは、久しぶりだった。
新たな知識を得る喜び。
育児で混とんとしていた反動もあってか、主体的に学ぶ楽しさを実感した。
本を読むほどに、得た知識を現場で試したい、という気持ちが大きくなっていった。
自分:『管理作業だけでなく、ハウスの環境制御など、社員として、より踏み込んだ仕事をやってみたい』
社長へ伝えると、意外にもすんなり受け入れてもらうことができた。
小さい乳幼児を抱える私を社員に登用することは、出来て間もないベンチャー企業、まして農業法人にとっては、正直、相当な覚悟があったはずだ。
本当にありがたい。
子どもの急な発熱、学級閉鎖、学校行事など、、
差別するわけでは決してないが、乳幼児を抱える女性は【安定的な人手】とは言えない。
特に現場で農作業に当たる場合は、休んだ分の仕事は翌日やればいい、というわけにいかない。
農作業は適期に作業しないと後手に回り、その分作業が指数関数的に増大するからだ。
それを分かった上で、どうしても私は社員として働きたかった。
自分のこのワガママを通すため、【子供がいるから】と言い訳はしないことを、会社や主人、自分に誓った。
参考:保育園児との生活リズム
社員になった当時の私は33歳、今より随分体力がありました。
土日は休むことができたので、【疲れ】を感じることがなかったです。
当時は相当気を張っていたからだ、と今振り返ると思います。
当時の生活は以下のような感じでした。
5時:起床、身支度、洗濯を干す
6時:朝食と弁当づくり、子供の持ち物準備
7時:朝食、片付け、掃除
8時:保育園へ子供たちを送り届ける
9時:出勤
12時:休憩(1時間)
18時:退勤、保育園へ子供たちを迎えに行く
18時半:夕食準備
19時:夕食、片付け、掃除
20時:子供たちを入浴させる
20時半:本の読み聞かせ
21時:子供たち就寝、洗濯取り込み
21時半:読書
0時:就寝(夫帰宅)
私が社員になった頃には、もう1棟ハウスが増え、栽培面積は2.5反に。
スタッフもさらに増えて7名程度になっていました。
自分の親と同世代の男性や若くして子育てしているママまで、年代も20台~60代と幅が出てきていました。
社員も私のほかに同世代の男性が1名、同期で入社し、ライバル心もあったと思います。
社長や周りのスタッフの方は色々と心配してくださったのですが、、
【女だから】、【子供がいるから】と、特別扱いされることが、自分の負けを認めるような感じがして、どうにも嫌だったのです。。
後になって、当時から一緒に働いていたスタッフのIさんが教えてくれたのですが、、『前のYoshieさんは眉間にしわを寄せていることが多くて、なんだか気軽には話しかけづらい感じでしたよ~』と、、
周りの人に迷惑をかけたくなくて、自分だけで必死に頑張っているつもりが、結局は周りにも気を遣わせてしまっていた。。
自分のことで必死で、周りが全く見えていませんでした。。
子どもたちも同じことを感じさせていたんだろうなぁと思います。。
程よく周りの人を頼りながら、しなやかに過ごすこと。
まだまだうまくできないのですが、自分の弱さを受け入れて、気を付けて過ごしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
