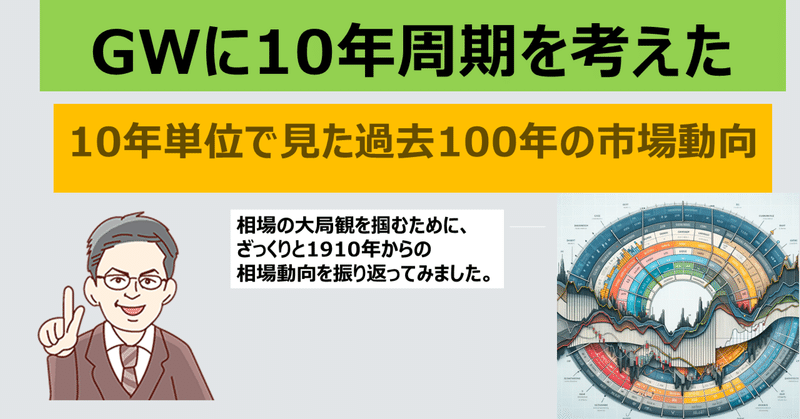
ゴールデンウィークに10年周期で相場を考えた
先日、伝説のファンドマネージャー坪田さんの話でも10年周期という話があったので、1910年代に遡って、10年ごとに相場の動きを見てみた。
景気は循環するもので、好調な時もあれば不調の時もある。
基本的には「好況→後退→不況→回復」の4つの局面が順番にやって来て繰り返されるわけだが、その長さにはその時その時によって異なる。
また、景気循環のサイクルには4種類あるとされていて、その4つが組み合わされて複雑な波を作る。
企業の製品在庫の変動に着目した波は「キチン・サイクル」、
企業の設備投資の周期に着目した波は「ジュグラー・サイクル」、
建物や施設の建て替えの周期に着目した波は「クズネッツ・サイクル」、
新たな技術革新が起こる周期に着目した波は「コンドラチェフ・サイクル」
と呼ばれている。
これらは、それぞれ景気循環の波を発見した人の名前にちなんでいる。
これらの波は、それぞれ長さが異なり、
「キチン・サイクル」は比較的短期で約40カ月、
「ジュグラー・サイクル」は約10年、
「クズネッツ・サイクル」は約20年、
「コンドラチェフ・サイクル」は最も長い約50年とされる。
アナリストの業績予想などは、「キチン・サイクル」を意識したものであることが多いが、大きな流れを見る時には「ジュグラー・サイクル」も意識している。「クズネッツ・サイクル」や「コンドラチェフ・サイクル」になると誤差も大きく、一般的には実際の業績予想には使いにくい。
暦年ベースで見た10年区切りに、どの様な意味があるか分からないが、商品市況も含めて見てみることで、企業業績などからだけでは見えない、株式市場の大きな流れが見えるかもしれない。
ちょうど、東海東京インテリジェンス・ラボの平川ストラテジストも同様の分析をされていたので、それを参考にして作ったのが下記の表である。

これをみると、最も明確なサイクルが観察できたのは商品市況で、30年ごとに大きなサイクルが来ている。足下も商品市況は強含んでいるが、この流れからすると2030年代が本番なのかもしれない。
物価は基本的には商品市況が上がる時には上がり、それ以外は落ち着いている。その中でも商品市況高騰の後に来る10年は物価が下がり、金利が低下、株価は上昇局面となっている。特に新技術関連で大相場となる事が多い。
1920年代の自動車やラジオ、1950年代のIC・トランジスタ・各種家電、1980年代は米国よりも日本などの株価上昇が目立ったが、1990年代のインターネット革命に向けた素地が出来つつあった。2010年代も相場としては堅調で、GAFAMを中心に米国テクノロジー企業の優位が確立された。前回と同じく次の10年のAI革命の素地が出来ていたようにも見える。
その次の10年は複雑になるが、株や商品よりも債券が金融市場の方向性を決めているようだ。ただ、金利は上昇するケースも低下するケースもある。
現在は商品サイクルを中心として見た場合、金利が方向性を決める時期にあたるが、その中でも金利が強含んだのは1960年代と足下。
共通するのは政府の債務が拡大している事だ。1960年代も冷戦とベトナム戦争で債務が拡大した。今も、中国との競争、ウクライナ・中東などの問題で軍事費が拡大傾向にあり、潜在的に債務が拡大しやすい状況にある。
週末に投資アイデアを考える #2 (4/28~5/4)でふれた、「5/1日経/FT 軍事費増、金利に上昇圧力」参照
米国株は商品市況が上昇する時期に停滞する傾向にはあるが、それ以外の時期は基本的には堅調となる事が多い。ただ、大恐慌が起こった1930年代とベトナム戦争などがあり政治的にも不安定だった1960年代は冴えなかった。2020年代は今のところ、株式市場自体は堅調を維持しているが、政治的な不安定さは高まっており、あまり安心できる環境にはない。
70~80年代は長期金利が上がると株が下がっていたが、現在は1950年代と同様に金利が上がっても同時にPERが上がっている。米国のグロース企業の業績は強いので金利が上昇しても大きくは下がらず、逆にバリュー株の堅調さが目立っている。
日本に関しては、米国株・米国金利・商品・物価などの世界的なトレンドに日本独自の要素を合わせて考えることが必要となる。
日本に関して、足もとは、円安・金利上昇基調の中で銀行・建設・電力ガス・保険・輸送機などが上昇しており、バリュエーションの水準感は違うが、物色動向は1990年代に近い。
ただ、グローバルで見た場合の立ち位置としては1950年代に近く、国内の需要が強いとは言えない中、米国経済圏での需要をどれだけ取り込めるのかがポイントとなる。
産業的には1950年代は重厚長大の製造業中心がだったのに対して、今回は半導体などが中心となりそうなところが違いだ。
1950年代は第二次世界大戦で徹底的に叩かれたところからの復活。今回は日米半導体戦争で完全に敗北し、韓国・台湾・中国にシェアを奪われたところからの復活となる。前回同様、米国がイデオロギーの異なる覇権主義国家と戦うにあたって日本を必要としているところも共通している。
米国は中国の台頭に対抗するために、防衛のみならず、様々な先端技術で日本と本気でタイアップしたいと考えている。これは、朝鮮戦争後、日本を防共の防波堤とした時と全く同じ構造だ。
1970~80年代に日米は、自動車・半導体など様々な分野でぶつかっていたが、今は180度対応が変わっている。日本経済は約30年ぶりの局面転換を迎えていると言える。商品サイクルが上昇サイクルに入る前に、どれだけ立ち位置を改善できるかがポイントとなりそうだ。
掲載されている記事は、個人の見解であり、執筆者が所属する企業の見解などを示すものではなく、証券投資や商品申込み等の勧誘目的で作成したものではありません。
記事の情報は信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その確実性を保証したものではありません。最終的な投資決定は、読者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
当コラムの閲覧は、読者の自己責任でなされるものであり、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。
なお、記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
いただいたサポートは主に資産運用や経済統計などの情報収集費用に使わせていただきます。
