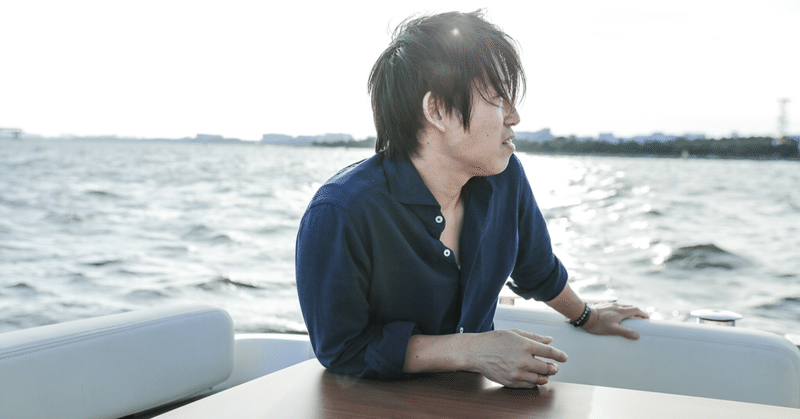
わたしの履歴書 Vol.1
「自分の父親の顔。気になるでしょ。死ぬ前に、一度くらい会ってみてもいいんじゃないの?」
と母は言った。
これは、ぼくの物語。
「お前の人生なんて、大した人生じゃない。勘違いするな」
と母は言った。
これは、ぼくの真実の物語。
人は誰しも、物語を持っている。
それぞれのドラマチックな人生を必死で生きている。
初めて自分の歩んできたその大したことがない人生について、赤裸々に書いてみようと思う。誰かの勇気に、ほんの少しの希望になるかもしれない。
わたしの履歴書 Vol.1
自宅にはピアノがあった。
黒いグランドピアノだ。
ボロ屋とまでは言わないけれど、ど田舎にある、ごく普通の家だ。いや普通というのはおこがましい、慎ましやかな家と表現しようか。
そんな家に置いてあるグランドピアノは、少し滑稽に見える。
物心がついたときに「なんでお金持ちでもないのにうちにはピアノが置いてあるのだろう」と少し不思議に思った。
誰かに買って貰ったのだろうか。
「お母さんが小さい頃、そうね貴方ぐらいの頃にうちのおばあちゃんに買ってもらったのよ」
おばあちゃんというのはぼくの祖母だ。
女手ひとつでうちの母を育てた。
相当な苦労人だったということは、まだ小学校低学年のぼくにも理解できた。
ぼくは、おばあちゃん子だった。
母よりも父よりも、誰よりも祖母に懐いていたし、いつも一緒に過ごしていた。
よく自転車の後ろに乗せてくれて、ぼくの大好きな串に刺したお団子を買いに連れて行ってくれた。スーパーの駐車場にあるちいさなお団子屋さんだ。
年に一度、大好物の鰻を食べさせに連れて行ってもくれた。
「お母さんには内緒だよ。怒られちゃうからね」
そうやってこっそり二人で買いに行って、スーパーの駐輪場に自転車を止めて食べたホカホカのみたらし団子の味は今も忘れられない。
ぼくにとって、人生最高の味だ。
「お母さんがね、きよとくらいの歳の頃に七夕の日に短冊に書いたのよ」
母は言った
「ピアノが欲しい。真っ黒なグランドピアノ」
「そうしたらその何年か後におばあちゃん、買ってくれたのよ」
高校生になる頃にもう一度その話になったことがある
「おばあちゃんは、とても貧乏で、女手一つでお母さんを育てていて。
あとで知ったんだけど、早朝から給食のおばちゃんやって、そのあとスーパーでパートして、深夜に交通整備の仕事して、ほとんど寝る間もなく働いて、グランドピアノ買ってくれたのよ。
わたしは小さかったから、何もわからないで短冊にピアノが欲しいって買いちゃってね。
貰ったのは何年もあとでね、そんなこと忘れてて。こんな使わないもの要らないよって、わたし言っちゃったのよね。いまでも、後悔している。嬉しかったけれど、本当に苦労させたなって」
ぼくが小学校高学年になる頃、最愛の祖母は癌で亡くなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
