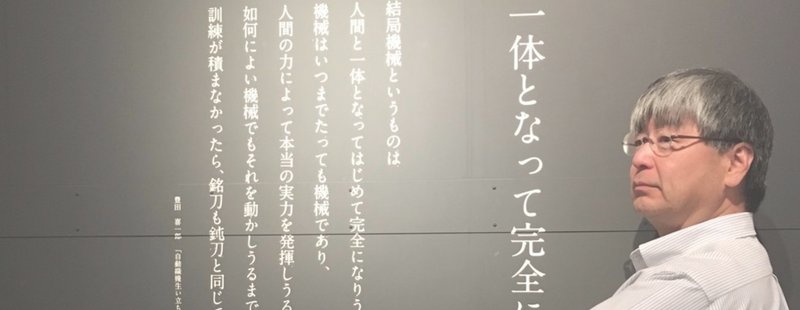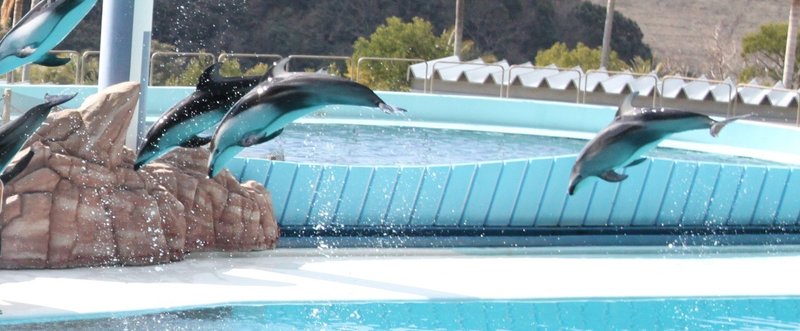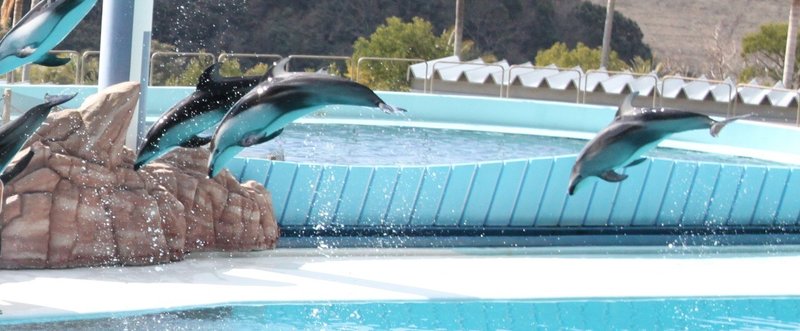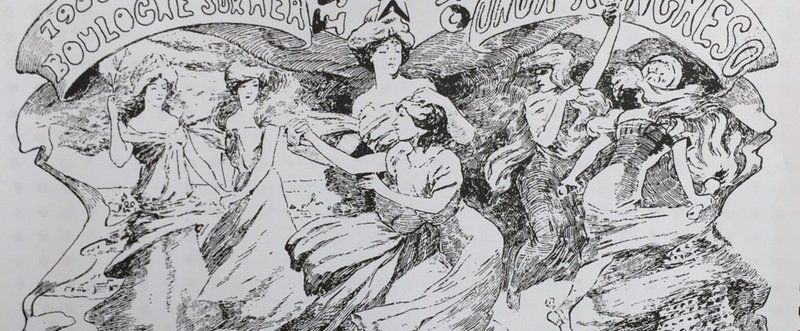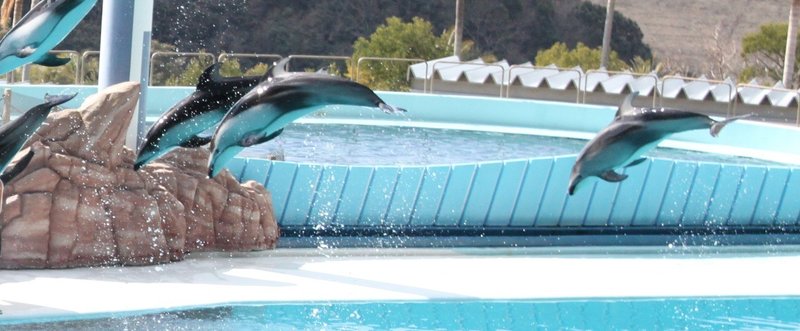#教える技術

【本】ダネル・スティーブンス、アントニア・レビ『大学教員のためのルーブリック評価入門』→大学だけでなくすべての教員と企業の人事担当者・マネジャーに有用
2017年3月16日 (木曜日はお勧めの本を紹介しています) ■要約ペーパーテストから成果物や実技によるパフォーマンステストに置き換えることで教育はより良くなる。パフォーマンスを評価するための道具がルーブリックだ。ルーブリックを使うことで、以下のことが可能になる。 (1) より早いフィードバックを手間をかけずにできる (2) 学生自身がどこができていて、どこか不足しているのかがわかる (3) 学生にルーブリックを検討してもらうことで、どんな能力が重要なのかがわかる

【本】市川尚・根本淳子編著『インストラクショナルデザインの道具箱101』→インストラクショナルデザイン入門の1冊目として実用的
2017年3月9日 (木曜日はお勧めの本を紹介しています) 市川尚・根本淳子編著『インストラクショナルデザインの道具箱101』(北大路書房, 2016) ■要約インストラクショナルデザイン(ID)とは学びの「効果・効率・魅力」の向上を目指した技法とモデルの総称である。それを101個集めたこの本を眺めて、自分の現場に導入していけばあなたの教える技術は高まるだろう。 ■お勧めのポイントIDの技法とモデルを101個も集めたら、それをどのように分類、構造化して示すかというとこ