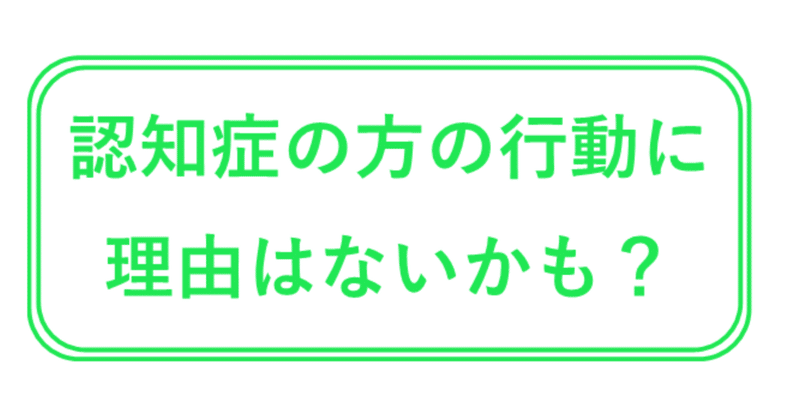
認知症の行動理由を考えることは基本だが、「特に理由がない」こともある
超高齢化社会に向けて、認知症は社会問題の1つとされている。
しかし、介護事業として認知症に携わるほどに、認知症は問題というほど問題ではないと思っている。
認知症とは、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症、その他と大まかな種類が確認されている。また、それぞれに対しての症状や傾向なども医学的に提示されている。
だからと言って、症状を完全に区分化できないのは、認知症による言動が対象者のこれまでの生き方や現在の生活環境に大きく影響するからだ。
そのため、認知症と診断された、あるいは認知症と思われる高齢者の行動にはしかるべき理由があると考えるのが、認知症ケアとしての基本である。
ちなみに、認知症と診断された高齢者の行動に対して「問題行動」と呼ぶことがある。これは専門職である介護従事者でも平気で使う人がいる。
しかし、前述のとおり認知症とは現在の生活環境に影響することから、問題行動の理由が介護者の関わり方に起因していると思われる場合もある。
例えば、記憶障害を引き起こしている認知症の方に対して「何で覚えていないの!」と怒鳴ったり、トイレの場所が分からず排便に失敗した方に対して「ちょっと~、勘弁してよ~」と大声で責めたりする介護者がいる。
何度も言うが、これは介護を知らない家族ではなく、資格がある介護従事者でも当事者たる高齢者に感情をぶつけることは珍しくない。
これはもちろん、介護のプロフェッショナルとして未熟である。しかし、このような態度をとってしまいたくなる気持ちも理解できる。
そのため、認知症高齢者に対して感情的にならないためは、メンタルコントロールやアンガーマネジメントも大切であるが、認知症に対する知識を基盤として「この方は、どうしてこのような行動をするのだろう?」と考えることを基本姿勢とすることが重要である。
例えば、トイレ介助のためにトイレにお連れしたのに、その場で立ったままズボンを下ろさない方がいたとする。そこで自分でズボンを下ろさないことに業を煮やした介護者が「ズボンを下ろすのを手伝いますね」といって手を掛けた途端、その方が介護者の手を思いきり叩いたとしたら・・・。
このようなときは介護者は驚くだろうが、それに対して「何するの!」と怒りをぶつけるのは愚策であるし、無理やり介助を続けることも相手にとってよろしくないことは理解できると思う(それでも続ける介護者はいるが)。
また、このような場面を「介護拒否」と呼ぶわけだが、仮に介護拒否とするならば、大切なことは「なぜ、介護拒否をするのか?」「なぜ、ズボンを下ろそうとしたときに手を叩いたのか?」という意味を考えるのだ。
そうすると、「〇〇さんは恥ずかしいのかもしれない」とか「一人でできることを他人の手を煩わせることが嫌なのかも」とイメージが湧く。ある意味、ここからが支援のスタートとも言える。
・・・が、場面によっては認知症高齢者の行動理由を考えても、全く想定できないこともある。
それは利用者に関する情報不足やコミュニケーション不足などもあるだろうが、1つの考え方として認知症の行動として「特に理由はない」「特に意味はない」ということもあるということを覚えておいたほうが良いだろう。
認知症と言えども、1人の人間である。
認知症でなくとも、私たちは何の意味もなく不機嫌になったり、何の前触れもなく怒りや悲しみが湧くこともある。
それはおそらく、認知症の方も同様だと思う。
そのため、認知症ケアにおいて「その方の行動の理由を考えましょう」と言ったところで、ときには「理由はない」「意味はない」として、一時的な行動として終わることもあるのではないか。
状態を時系列で見たときに「最近、〇〇さんんはこういう傾向がある」と分かることもあれば、「今日の行動は一体何だったのだろう?」と不思議な現象として捉えるしかないこともある。
そういうときは、もしかしたら認知症の行動ではなく、理由も意味もない一時的な行動をしただけかもしれない。
――― 何だか、介護のプロとして投げやりな考え方かもしれないが、人間相手として、ときにはこういう捉え方も必要ではないだろうか・・・。
ここまで読んでいただき、感謝。
途中で読むのをやめた方へも、感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
