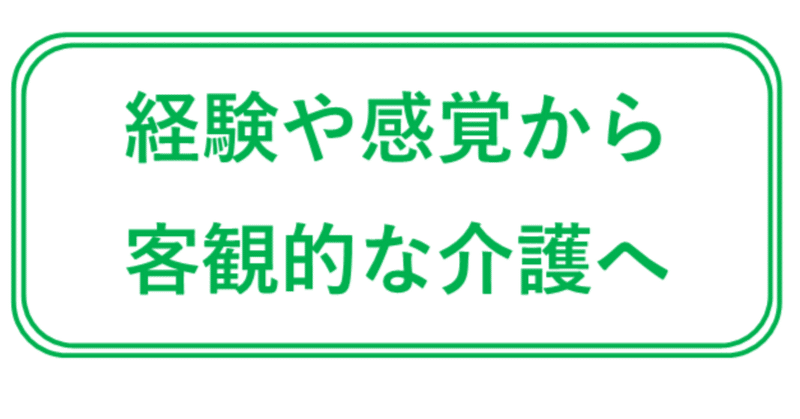
現場経験や感覚はエビデンスにならない
■ 介護のおいてエビデンスはなぜ必要?
「科学的介護」と言われても、未だにピンとこない人は多いと思う。
介護業界においても、データやシステムを活用した取り組みと思っている人たちは少なくない。
科学的介護の本質は「エビデンス」である。
つまりは「根拠」だ。
エビデンス(根拠)は、誰もが同一の認識を可能とする定量化されたデータのことである。
エビデンス(根拠)は、何事においても大切な要素だと誰でもわかる。そこにおいて、なぜ介護において今さら根拠の重要性が出ているのか?
それはこれまでの介護が、現場および介護者個人の経験や感覚をベースに行われてきたからだ。介護現場の根拠はすべて現場および介護者個人に委ねられてきた。
しかし、現場の経験も介護者個人も「主観」であって客観性に乏しい。
主観である介護者の経験や感覚はエビデンス(根拠)にはならない。
昨今では商品もサービスもエビデンスありきである。それは消費者やユーザが信頼性の担保を期待しているからだ。
それなのに、介護だけは「勤続年数××年のベテランのやり方」「介護現場で培った直感だけれど」といったことを平気で言いたがる。
介護もビジネスである。しかるべきエビデンスありきでサービス展開するべきだし、そこに世の中が信頼を求めていることに気づくべきだと思う。
■ その便の状態は? 量はどれくらい?
介護において主観で物事が進行していると感じることは色々ある。
例えば、利用者(高齢者)の排泄状態として「軟便多量」「普通便中量」などと報告することが多い。
しかし、どのような状態をもって”軟便”や”普通便”とするのか、どのくらいの量で”多量”や”中量”とするのかは個々の感覚である。
もちろん、多少の誤差があったところで問題はないし、あまり細かく区分分けしてしまうのも過剰というものだ。
それでも、排便状態というのはその後の食事や水分摂取、お薬などにも関わる話なので、大雑把でも共通確認できる何かしらの媒体は必要だと思う。
また、主観として「擬音で報告する」という介護者が多い。これも同じく排泄関連を挙げると、「尿取りにたっぷり失禁してました」という報告する場面をよく見かける。
「たっぷりってどれくらいだろう?」と思ってしまうし、その報告だけで納得している他の介護スタッフに対しても首を傾げてしまうことがある。
このような主観がまかり通ってしまうと、例えばオムツや尿取りの選定をするときに「〇〇さんはたっぷり失禁するから、吸収回数の多い尿取りにしよう」と適切なのか不適切なのか分からない方向になってしまう。
「たっぷり」などという擬音とした感覚を根拠とすることなく、ちゃんと客観性をもった消耗品や介助法を検討することが、やはりプロの介護者としてのあり方である。
■ 客観性をもたせる一番の方法は「数字」
では、どうすれば客観性をもたせることができるのか?
前記の失禁量(排尿量)の「たっぷり」に客観性をもたせるには、単純に尿量を測定すればいいだけの話だ。
排尿を吸収した尿取りパットを測定し、尿取りそのものの重量を差し引けば尿量が確認できる。
それを一定期間の計量および記録をすることにより、その利用者の普段の排尿量が見えてくる。これがエビデンス(根拠)となる。
エビデンスと言うと、何やら難しい分析法やシステムを用いると思っている方が少なくないが、客観的なデータを集めるというのはシンプルかつ地道な作業なのだ。誰でもできることばかりだ。
そして、その結果として分かりやすいのは「数字」である。
老若男女、国籍問わずに客観性をもたらせる数字が、エビデンスとして1番説得力がある。
上記のように失禁量(排尿量)が「たっぷり」と言うと、Aさんは「紙コップ1杯くらいかな?」と思い、Bさんは「片手で持てるくらいかな」となってしまうが、「計測したところ150mlでした」となると一気に客観的かつ共通認識が高まる。
もちろん、数字でなくても構わない。大切なことは手法やあり方ではなく、テーマに対して誰もが共通認識をもてる言語を用いることで、客観性を証明しようとすることである。
――― エビデンス、すなわち客観性をもったデータや情報は、多様化する社会において介護だってどんどん必要になってくる。
そこにおいて「たっぷり」などという個人の感覚や、これまでの経験で物事を語ることはリスクになりかねない。
介護業界は科学的介護の前に、まずは客観的な報告ができるようになることが先決ではないだろうか?
ここまで読んでいただき、感謝。
途中で読むのをやめた方へも、感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
