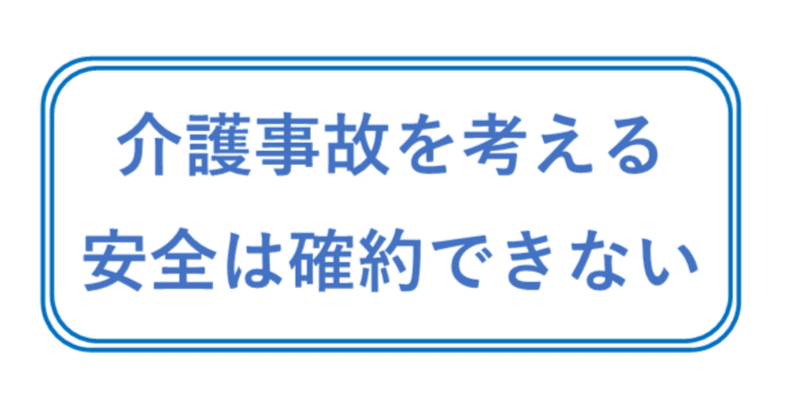
【介護事故】介護は高齢者の安全を確約できない
■ 介護事故は絶対に起こる
介護現場では事故が起こる。
事態によってはニュースになったり、訴訟問題になったりもする。
ある種の社会問題として扱われ、内容によって行政が全国の介護事業所や施設に通達を出したり、予防策を義務として課したりすることもある。
事故があった事業所や施設を運営している法人に対して損害賠償を要求されたり、過去には当事者たる介護職員個人へ責任を問われるケースもある。
高齢者という心身および日常生活の支援をしてきた結果として、それが事故という形となり、さらに社会問題や訴訟案件になってしまうのは残念としか言いようがない。
しかし、何より残念なことは、介護事故というと世間ではメディアで取り上げられるような内容しか知らないことだ。
そして、ときには「予測できたはず」「介護現場のレベルが低い」と非難されたり、「やはり人手不足が問題なのだ」「仕事に見合った賃金にすべき」などと話が脱線する。
それでも、ここでさらに非難されるようなことを言おう。
――― 予測や予防などを一気に超えて事故が起こる。
――― 介護現場のレベルに関係なく事故は起こる。
――― 人手不足や賃金を解消しても事故は起こる。
――― そう、介護現場では ”絶対に” 事故が起こるのだ。
■ 介護事故とは何か?
そもそも、メディアで取り上げられるような内容だけが介護事故ではない。
大なり小なり起きる出来事がすべて事故である。
どういうことかと言うと、厚生労働省の定義をかみ砕いて言えば、介護サービス提供中あるいは介護施設内において、利用者の心身を害するようなケースはすべて事故扱いになる。
分かりやすいところで、何かしらの出来事があって病院に行くまでのレベルになったら確実に事故扱いになる。
しかも、介護事故というのは事故状況がどうであれ、介護従事者あるいは介護施設の過失うんぬん関係ない。
極端なケースを言えば、施設の共用スペースで利用者が鼻をかんだ瞬間に、その勢いで肋骨を骨折しても事故である。
誰が原因ということでなく、何てことない日常行動をとっただけなのに、それで心身を害したら事故である。
だからこそ、介護現場では”絶対に”事故が起こるという理屈になるのだ。
それはまるで、赤信号で止まっていただけなのに、後続車に追突されただけで交通事故になってしまうようなものだ。
■ 想定外の「何で?」でも事故扱い
もちろん、世間一般および介護現場で想定される事故に対しては、予防策としてマニュアルや研修などを講じているだろう。
また、利用者たる高齢者ごとに行動パターンから、声掛けや室内環境の整備をもって事故が起こらないよう対策していることもある。
それでも、介護サービスを専門職として提供しているとはいえ、高齢者という人間相手にしている限り、利用者が想定を超えた行動をすることはある。
ここで「認知症の場合はでしょ?」と言う方がいるが、これまで幾度も事故案件に携わってきたが、その記録を眺めていると、実際のところ認知症の有無と事故に相関性は薄いと思っている。
そのときの環境要因や介護現場における情報共有不足など、これらの原因となる事故も確かに少なくないが、「 何でそのような行動をしたの?」「何でそこに行ったの?」という「何で?」という、利用者の摩訶不思議な行動によって引き起こされる事故も少なくない。
そのような事故であっても、少なくとも病院受診するレベルになったら、行政に事故報告書を規定期間内に提出するのが介護事業者としての義務である。それは「何で?」という事態であっても、だ。
それなのに、事故となったら世間などは介護に対して過失性が問うてくる。これを理不尽と言わずに何と言おう。
■ 事故が起きて知ることもある
一方、このような利用者の「何で?」という事故をきっかけに、その利用者について知ることもある。
例えば、施設入所前は「車椅子移動」と同居していたご家族やケアマネージャーから聞いていたが、入所後に館内の通路を車椅子で自走してテーブルに衝突・・・なんてこともある。
自宅は狭かったので、どうしても同居していた家族らに移動を頼らざるを得なかったが、施設は通路が広いことから「これなら自分で移動できる」と思ってトイレに行こうとしたらしい。
施設スタッフからすると「自分では移動できないはずの●●さんが、何であそこにいたの?」と疑問に思ったわけだが、原因というか本人に確認したところそういう理由と判明して納得した。
このケースの場合、おそらくどこかのタイミングで利用者の状態を知ることができたろうが、事故が起きたことによって「そういうことできたんだ」と知ることもある。
だからこそ、小規模の事故あるいは”ひやりはっと”で済んだケースにおいては、あながち事故案件に対してネガティブに捉えることもないと言える。
■ 介護は安全を確約できない
上記でのお伝えしたが、介護現場で事故が発生したとき、どうしても介護に対して過失性を問われてしまう。
状況はどうだったか?
どのように対応したか?
関係者に連絡はしたか?
原因は何か?
再発防止はどうするか?
・・・まるで「落ち度はなかったのか」「もっとやりようはあったのでは?」と言われているような気分になることもある。
しかし、大抵の場合は介護サービスを受けている利用者たる高齢者は「迷惑かけるね」とか「(事故後の受診で)何で病院に来たの?」とおっしゃることが少なくない。その後に状態が変わることもあるが、利用者本人がどうこうということはないし、利用者から再発防止を要請されることもない。
問題なのは、ご家族である。特に介護施設に入所している利用者の家族から「施設に預けているのに、どうして事故が起こるんですか!!」と言われることもある。
もちろん、「ご迷惑かけますね」「いつも大変でしょう」とおっしゃる方もいるが、やはり安全のために自分の親を施設に預けたのに、そこでトラブルがあったら感情的になるのは仕方ないと思う。
しかし、この場を借りてお伝えしたいことは・・・
「介護は安全を確約するものではない」
・・・ということだ。
介護の役割は「できることは本人、できないことは介護にて支援する」という自立支援が基本である。その範疇において責任はあるし、介護計画やサービス手順をおろそかにして起きた事故は過失である。
しかし、ご本人ができること、ご本人の意思で行動・選択したことなどにおいて安全性を求められても困るというのが本音だ。
――― 本記事を読まれた方の中には「介護のプロフェッショナルとして無責任では?」と言われるかもしれない。
しかし、介護現場と言えど、利用者視点で言えば ”生活の場” である。在宅では自宅であり、施設では住まいである。そこに介護スタッフがいるからと言って、24時間安心安全なんてことはない。
高齢者の自尊心を守るということは、それなりに自由(放置)するということでもある。自由とは必ずリスクが生じる。
そもそも、言っては何だが高齢でなくてもタンスの角にぶつけたり、自動車事故を起こすのに、それが心身状態が低下した高齢者であれば単独行動による事故率は高くなるのは当然だろう。
そこをどこまでカバーできるのかが介護に問われるところだが、改めてお伝えするように完全な安全を確約することなんで不可能だ。
長くなってしまったが、どうしても事故は感情論がつきまとうので、しっかりとした対応をしても、どちらかが腑に落ちないことは仕方ない。
この点は介護において先々もつきまとう課題なのだろう・・・。
ここまで読んでいただき、感謝。
途中で読むのをやめた方へも、感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
