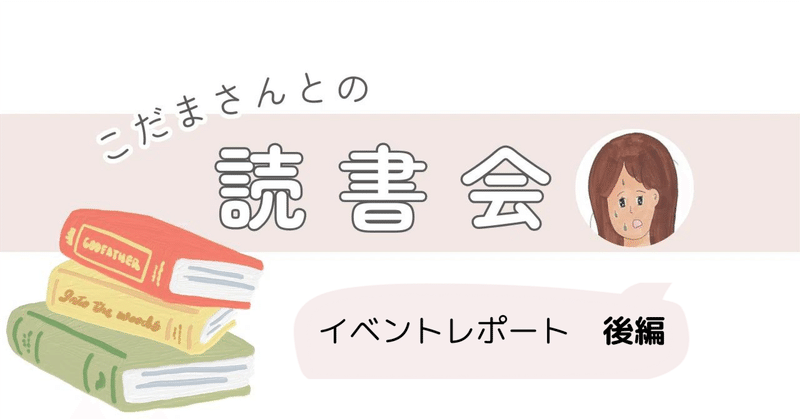
イベントレポート「こだまさんとの読書会」後編
前編はこちら。
イベントでは、参加者それぞれに好きなこだまさん作品を持参してもらい、自由に語っていただきました。以下、要約をご紹介します。
1人目
『夫のちんぽが入らない』(扶桑社/以下、「おとちん」)でこだまさんを知りました。いろいろなエピソードを読みながらこだまさんの人柄を知り、「この人の人生を応援したい!」と思うようになりました。
持参した本は『縁もゆかりもあったのだ』(太田出版)です。全部の作品が好きですが、この本を読んだときに初めて「作家」としてのこだまさんのファンになりました。私は、ある情景が、作家さんの目と描写を通して自分のなかに景色として浮かんでくる、それを味わうのが好きなんです。
この本は旅の本というのもあると思いますが、そうした描写の解像度がより上がった感じがしました。中でもいちばん胸に迫ったのは、「猫を乗せて」というエピソードです。
深夜には呼吸が荒くなり、白い泡状の液体を吐いた。もう胃の中は空っぽのはずなのに何度も何度も、痙攣に合わせてキジトラ模様の毛並みがどくんどくんとうねり、風が草を撫でるように波紋を描いた。
飼っていた猫の調子がだんだんと悪くなっていく様子をここまで鮮明に書いているのを読んで「文章を書く人の性(さが)だな」と思いました。あと、文中に「悲しい」「悔しい」「寂しい」という、感情を表す言葉が出てこないんですよね。
エピソードの最後、蕎麦屋さんでの場面も、近しい存在を亡くしたことがない人からしたらギョッとするかもしれませんが、失った人が初めて得られる普通の感覚なのかなと思いました。
●こだまさんのコメント
このときは猫を看取る悲しさはありましたが、同時に「今しかない」「自分がぜんぶ記憶して書き残さなきゃ」と思って、メモ帳を持って看病しました。「これはきっとエッセイに書くよな」と、悲しいのに書いている自分が目に浮かびました。
文章にするときは、リアルタイムで書いたメモを見ながら。また、読む人が想像できることは書かなくても分かるはずだから、「悲しい」とかそういう言葉は省きました。
2人目
「おとちん」が発売されたときからずっとファンです。なんでもいいからこだまさんの書いているものを読みたい、と思って『塩で揉む』(こだまさんのブログをまとめた同人誌)もネットで入手しました。こだまさんの文章、感性が好きです。
自分はそれまで本を遠ざけていた部分がありました。感想を強要されているというような思いを抱いてしまって、離れていたんです。でもTwitterでたまたま「おとちん」と出会って、読んでみて(これだ!)って。
『塩で揉む』は何度読んだか分からないです。このあとに出る作品のベースとなるエピソードがほとんど詰まっていて、そのときに感じたことがより生々しく書かれている気がします。毒気も強いし(笑)。私のどストライクで、本当はここまで思い切り書いてほしいなとも思います。
「おとちん」はじめ、どの本も2~3冊持っています。友人にあげたりもしたのですが、中には「作り話でしょ?」と言う人もいて不思議でした。読んでいて、心の叫びが痛いくらいに伝わってくる。自分をすごく見つめて書かれた本だと思うのに。
あと『ここは、おしまいの地』(太田出版)も、読む人が読んだら「これ、私が覆面つけて書いてるんじゃないの?」と思うくらい似た境遇の人も少なくないと思います。厳しかったお母さんが年をとって丸くなって…というようなことまで含めて。
自分とも似ていました。ただ、私はそうした記憶を封印して、ほとんど覚えていないのに、こだまさんはすごく引っ張りだして、それを問うて…産みの苦しみを抱えながら書いているんだと思いました。なのにユーモアもある。でも、ただ人を笑かしたいから書いているわけではないことも分かる。
入院生活について綴った「私の守り神」というエピソードとその中に出てくる「悲哀でも恨み節でもない」という一節は、自分も入退院を繰り返したときに何度も思い出しました。
こだまさんはそういう悲哀とか恨みから一歩前に進んで、すごくあたたかくてやさしい目で周囲を見ている。
まるで自分も同じ経験をしているかのように思わせてくれることで、ともすれば「なんで自分がこんな目に」と考えてしまいがちなところを、客観的に見られるようになった気がします。今も入院時には必ず持っていく本です。
こだまさんの作風が変わるごとに私も同じように成長させてもらって、人は何歳からでも変われるんだなと勇気をもらえます。「おとちん」のあとがきに書かれている言葉を読んで、私も最後に絶対そう思えるようになろうと決めました。
私たちは不運だったかもしれないけれど、決して不幸ではない
こだまさんの作品に会っていなかったら今がなかったと、ただただそれをお伝えしたかった。このイベントの告知も、『縁もゆかりもあったのだ』を読んでいるときに偶然SNSで見つけて、遠いけれど思い切って参加しようと思ったんです。
私が持っている本はサイン本で、一言メッセージとして〈死も入院も旅のひとつ〉と書かれていました。たまたま手に取ったものなので、私に宛てて書かれたものではないですが、すごくリンクする部分があって不思議でした。今日、一歩外に出られたので良かったです。
●こだまさんコメント
遠くから来ていただいてありがとうございます。『塩で揉む』はブログを読んでくださる人だけに向けて書いていたものだから、ああいう風な表現ができたと思います。商業出版だと知り合いが気づくかもしれないからと表現を変えたり、編集者や校正の方から指摘を受け、確かにこれは大衆の前に出せるワードや文章だろうかと怯んで書き換える時もありますね。
3人目
私はどうしてこだまさんの本を読み始めたんだろう?と振り返ってみたら、ブログを読み漁っていたのを思い出しました。「けんちゃん」に関するエピソードも好きでした。
また、通っている養成所で、「自分がいちばん感情を込めて読める文章」を朗読するという課題があったのですが、そこで「私の守り神」の、お母さんがお見舞いに来る部分を読みました。私も母との関係に似たようなところがあったので。
こだまさんの文はやさしい。なにか悪いことをした人に対しても、やさしく見守っているようなところがあって、でも毒はある。毒は持っていてもいいんだ、とか一つずつこだまさんに教えてもらったような気がします。
文章とか文体とか、専門的なことについては分からないし、なにがどうすごいかと上手くは言えませんが、すごく言葉を大事に書かれているなと思いました。「おとちん」を読んでいても、まるで映画のように映像が浮かんできます。
私もこだまさんのような田舎の出身で、男女平等ではない部分だったり、実体験として似ている部分もありました。
●こだまさんコメント
(3人目の方はかなり深刻なことがあった日にお越しくださったことが判明したので)大変なときに来ていただいて…(と、こだまさんもしばし言葉を失っていました)。
4人目
皆さんのお話を聞きながら、こだまさんのお話は喪失感やなくすことについて書かれたものが多いような気がしました。お父様を亡くされる頃の投稿もSNSでずっと追っていました。もしも心にスポンジがあるとしたら、こだまさんの言葉は、そこに水が染み込んでいくようにすっとなじんでいくものだなと感じます。
私がこだまさんの本を知ったのは、20代前半にとある男性から「おとちん」をお勧めされたことがきっかけです。「読んでみてよ、感想聞かせて」みたいな感じで、そのときは一生懸命読んだのですが、「あの(勧めてくれた)人には分からないよね」というのが率直な感想でした。でも私にはすごく伝わってきて。
私もとある集落に生まれ育ったので、本の中に書かれている言葉とか、他者との関係性が他人ごととは思えませんでした。今でこそ「シスターフッド」とか「フェミニズム」などの言葉が広く普及していますが、当時はそんな言葉すら知らなかった。
苦しいし、正直あまり読みたくないけど、苦しみの先にあるであろうなにかと接続したいという気持ちがありました。こだまさんの文章は、改めて必要な文章だと感じます。
その後も、ブログも読んで、ほかの本も読んで、それぞれに好きなエピソードがあります。でも友人には「毒が強くて気持ち悪い」と言われて、それがショックでした。
●こだまさんコメント
AmazonのレビューとかTwitterとかで、本についての嫌な感想も目にしました。「暗い」とかそんなのもあります。でもきっと、ぴったり合う人がハマってくれるんだなと思うとすごくうれしいです。
男女差別についての意識も最初はまったくなくて、私自身その感覚にどっぷり浸かったまま書いていたこともあるのかなと思います。
●発言者の返答
渦中でどっぷりというのはすごく分かります。私も読んだ当時は男女差別の文脈(そういう風土のなかに知らず知らずのうちに置かれているということ)には気づけなくて、上京して読んで初めて気づけました。本の中のこだまさんとハグしたい気持ちです。
5人目
こだまさんの文というより作品自体が好きで、というよりこだまさんに興味があり、…好きです。こだまさんに会えることになり、頭に浮かんだ作品は『でも、こぼれた』(2019年5月の文学フリマ東京で販売された合同同人誌)に収録されている「ミヤケの身の上話」です。
作品の感想というより、僕がこだまさんという人間を好きな理由は、うまくできないことが結構あって、でも頑張ってもがいている姿に共感するからです。こだまさんという人が生きているだけで勇気がもらえる。
うまくできない人ってたくさんいると思うんです。その中には、こだまさんのように文章で表現できない人もいると考えていて、だからこそ人にこだまさんの作品を勧めています。
こだまさんは、いざというときには「ぶっ殺す」と言える人だと思うんです。そういう熱さにも共感できるし、僕もいろんなことが無理で、できないことも多いから他人ごととは思えない。こだまさんを応援したくなるんです。
●こだまさんコメント
SNSで相互フォローしていますが、投稿される内容から周りを気にせず「自分は自分」という感じが見られて、私も応援しています。
6人目
自分は「おしまい定期便」(太田出版のwebサイト「OHTA BOOK STAND」上でのこだまさんの連載コーナー)第8回「新規ファンの斉藤」を選びました。
※補足説明:参加者さんが自ら該当記事をプリントアウトし持参。ところどころに下線を引いて、こだまさんの従兄弟・せいちゃんにまつわる「気になる表現」について解説されました。
脇の通路から平成のバンドブーム期を彷彿とさせる鋭利なウルフカットの男がぬるっと現れた。…
…認めたくないが私たちは顔が似ている。(中略)どんなに否定したところで「ほぼ等しい」の近似値。こんなの逃げようがないじゃないか。ウルフの血が濃すぎる。…
…ピチピチの黒い皮のパンツ、胸元が見えるほどボタンを外したシャツ。顔のラインに鋭角を張り付けたようなウルフカット。精一杯さりげなさを装っているが、不自然さは拭えない。いったい何をしたいのか。誰の案なのか。薄暗いバーでウルフは何を思っていたのか。…
「ウルフカット」はせいちゃんの特徴だったはずですが、途中で「ウルフの血」となり、こだまさんとせいちゃん二人の属性に変わってしまう。突然なのにリズム良く来るので最初は違和感がありませんでした。そんな感じで一度はこだまさんも「同じ血」だと表現したのに、最後にまた、せいちゃん一人の属性として切り離して小馬鹿にする。
こだまさんはよく登場人物にあだ名をつけますが、こういうトリッキーな展開は初めてだったので面白いなと思って今日持ってきました。
●こだまさんコメント
冷静に指摘されて恥ずかしいです。気になったものや好きなワードを書きたくて出しちゃったんでしょうね。こんなに考えてくれてうれしいです。
***
終了間際、話の流れでせいちゃんの歌声を聴くことに。こだまさんが音源を再生すると、小さな部屋に朗々と流れ始めるせいちゃんの歌声。「鼻につきますね」「ここは上手ですね!」「クセはあるけど上手いですね」「せいちゃん~」と全員で笑い合う、しあわせな時間になりました。
最後にこだまさんが一言。「今日はそれぞれにご自身を重ねたりとか、あとは文章や人柄に勇気をもらえたというようなことを言ってくださりうれしかったです。ありがとうございました」。拍手のなか終了しました。
今回、突然のご依頼だったにもかかわらず快く応じてくださったこだまさん。イベントに合わせて小さなエッセイ冊子まで作って配布してくださり、感謝が止まりませんでした。
イベントごとに短いエッセイを書いて渡そう、と急に始めて今回も綴じたのですが誤字が2箇所あった。ひとつは許しがたいミスで青ざめている。 pic.twitter.com/ScIvjJ2LTI
— こだま (@eshi_ko) April 25, 2024
こだまさんはとても恐縮されていましたが、「いやはや、さすがです!」としか言いようのない、伏線回収のようなミスに私はむしろ貴重ささえ感じましたね。

焦って修正したらさらに最高なミスが生まれたもよう。このスペシャルな冊子を手にしたのはどなただったのでしょうか…。
ミスはぜんぜん気にならず、糊で爆笑しましたがこれでさらに笑いました https://t.co/UjBUtkpBff
— 間借り書房 いりえ (@magarishoboIRIe) April 26, 2024
オチまで完璧な読書会だったのでした。
改めまして、こだまさん、場所と機会をくださったハリ書房さん、そして参加くださった皆さん、ご興味を持ってくださった方々、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
