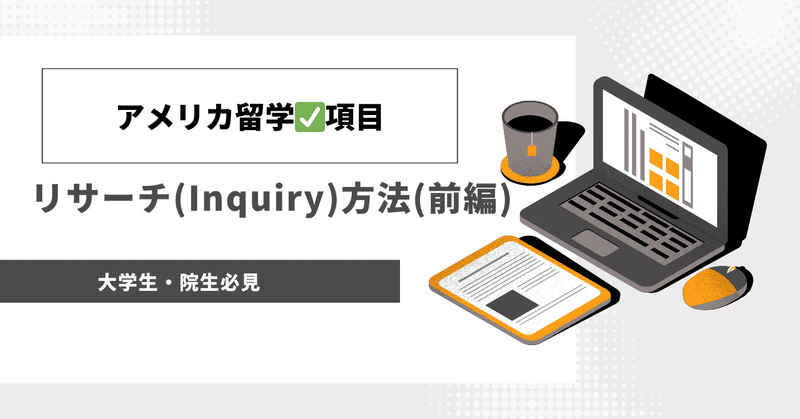
リサーチ(Inquiry)方法(前編)・・・大学授業に必須
はじめに
本稿はTOEFL Web Magazineの筆者のコラムFor Lifelong Englishに2021年「アメリカ留学2021 ✅項目(2)Inquiry(Research)の方法論―Inductive Reasoning(帰納的推論)、Deductive Reasoning(演繹的推論)、Abductive Reasoning(仮説的推論)」と題して掲載したものです。「アメリカ留学✅項目:多くの大学がモットーとする「光」「真実」の再起動なるか」(前編)(中編)(後編)」で、各大学の掲げるモットーに真理の追求の為にアメリカ伝統的なpragmatismの精神が反映され、そのキーワードがinquiry (調査・探求)であると述べました。手っ取り早く言えばresearch(リサーチ)のことですが、アメリカの大学、大学院では徹底的にこだわります。日本の大学、大学院でははっきり言えばあのような徹底的な訓練を受けたことがありません。アメリカ留学、特に大学院を目指している人に役立つ情報だと思います。少々長いので(前編)と(後編)に分けてお届けします。
アメリカの大学、大学院留学のメリット、Researchの仕方を徹底的に学ぶ
拙稿「アメリカ留学✅項目:多くの大学がモットーとする「光」「真実」の再起動なるか」(後編)の後段に述べたinquiry、即ち、researchの方法論についてです。筆者が見るアメリカの大学の強みの一つは、research方法論の実践訓練を通して徹底的に身につけさせるということです。大学1年生、2年生のcore curriculumのコースで基礎的な知識と訓練を、そして、3年生、4年生の専攻コースでそれぞれの専攻に特化したresearch方法論の知識と訓練を、大学院では、特に博士課程で更に専門的な方法論と訓練を受け、博士論文(Ph.D. Dissertation)はその集大成と位置づけられます。(*1)どの大学でも一貫しています。
日本でのレポート、学士論文、修士論文はResearch手解き無しの自己流
「アメリカ留学を振り返って:Memorable Teachers」シリーズ(その1)で述べた通り、筆者などは日本の大学、大学院ではさしたる手ほどきを受けず、レポート、学士論文、修士論文を書きました。大学受験で小論文が課され、(*2)受験雑誌にあった起承転結の手引きを読んで書く練習をしたような気がします。入学後は英文学の参考文献を見よう見まねし、もっともらしいレポート、学士論文、修士論文を書いて提出しました。確たるresearch方法は無いので内容は深まらず、体裁だけムリクリに起承転結に整えたものの、残るは「牛刀をもって鶏を割く」の感のみ。(*3)
アメリカ留学中の目標は「英語学でResearch Papers(学術論文)を書く」になる
留学前の筆者は、英語論文(academic papers)はその延長ぐらいに軽く考え、1、2年滞在して英語が上達すればマスターできるだろうと高を括っていました。大間違いでした。アメリカ留学初っ端でresearchのノウハウが欠けていることを思い知らされたのです。それ無くして最終目標のPh. D. Dissertation(博士論文)を書くことなどあり得ないとすぐに分かりました。当初は1年、長くて、2年アメリカで勉強したら帰国して博士課程に進もうと考えていましたが、急遽予定を変更し、そのまま留まることにしました。英語ネイティブに劣らぬacademic writing、presentation、discussionの力をつけること、そして、research能力をつけること、さしあたり、これが筆者の目標になったことは言うまでもありません。拙稿「アメリカ留学を振り返って:Memorable Teachers」シリーズ(その1)〜(その10)にその奮闘の様子を記しました。ちなみに本稿執筆現在は(その1)~(その8)までご覧になれます。(*5)
帰国して教職に就くや英語Research能力育成、多くの学生をアメリカ大学院に送る
それから10年後に英語学(English linguistics)でPh.D.論文を書き、目標を達成するや帰国し、慶應義塾大学経済学部、同湘南藤沢キャンパス(SFC)環境情報学部・大学院政策メディア研究科(*6)、合計36年間教鞭を執る事になりました。その教歴を通して筆者が拘ったのは、英語research能力(skills)の育成であったことは言うまでもありません。TOEFL®テスト(現在のTOEF iBT®テスト)、(*7)そして、SAT®、GRE®、GMATTM、LSAT、MCAT®などのアメリカの諸テストのVerbal Sectionは、critical thinking、research能力の有無を評価するものです。1978年、日本に帰国し最初に赴任した母校慶應義塾大学経済学部ではこれらのテストを推奨し、10年間の在籍中、相当数の学生にアドバイスし推薦状を書いてアメリカの大学院に送りました。Research能力を磨いてもらいたかったからです。
慶應義塾大学SFC、立命館大学でResearch重視のProject-based English Programを始める
その後1990年創設の慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)や、2008年創設の立命館大学びわこくさつキャンパス(BKC)新学部にてProject-base English Program(PEP)と称する英語プログラムを立ち上げ、professional skillsと称し、プロジェクトを通してresearchを行い、最初は日常会話もままならぬ学生を、(*8)2年間でacademic research、academic oral & written presentationができるよう指導しました。関心ある読者は、1、2年で使用する『プロジェクト発信型英語Do Your Own Project in English Volume 1』(鈴木佑治 南雲堂)、『プロジェクト発信型英語Do Your Own Project in English Volume 2』(鈴木佑治 南雲堂)そして、3年次の専門英語『Readings in Science』(鈴木佑治、南雲堂)(*9)を参照して下さい。TOEFL iBTテスト、SAT、GREなどの準備に、また、アメリカの大学の授業、学術学会を想定して執筆したものです。
入学2年後には専門分野のresearchを行い、academic papersを書き、学術学会形式のポスタープレゼンテーションができるようになります。筆者在任中、全学部生のほぼ全員がその能力を付け、大学が課していたTOEIC®テストでも抜群のスコア・アップの効果が出ました。(*10)
Research方法論としての科学方法論
Researchの方法論については、科学方法論(methodology of science)という分野が詳しく扱っています。拙稿「アメリカの諸分野に影響を与えたPragmatismについて」で述べたpragmatismもその一つですが、(*11)古くはソクラテス(Socrates)、プラトン(Plato)、アリストテレス(Aristotle)などの古代ギリシャ哲学にまで遡ります。近世に入りDescartes, Locke, Humeを経て現代の思想家らが、科学(science)とは何か、それに基づく方法論を巡って侃侃諤諤の議論を繰り返してきたわけです。(*12)
Stanford Encyclopedia of Philosophyの“Scientific Method”と称する無料サイトの記事が分かりやすく簡潔に解説しています。
“The Scientific Methods: Crash History Course of Science#14”などのYouTubeのサイトなどはDescartesらの科学方法論を分かり易い英語で説明してくれます。
他にも“scientific method”で検索すればたくさんあります。アメリカ留学を考えている読者に役立つ情報です。最近では、Descartesの方法論に真っ向から反論するDaniel C. Dennettの“Darwin’s Strange Inversion of Reasoning”など、興味深い視点も出てきました。(*13)
(2021年1月12日記)
後記
(後編)では リサーチ方法としての帰納法、演繹法、仮説的推論法などについて触れます。
(*1)アメリカで書かれた全てのPh.D. dissertationsは、University Microfilms International(現ProQuest)に保存され有料で入手できます。筆者の博士論文は、当機関番号7901787で登録されています。また、Ph.D. dissertationはA Generative Semantic Analysis of the English Modals(Nathanael Yuji Suzuki) でも見れます。
(*2)筆者は1962年2月に慶應義塾大学文学部を受験しました。2次試験に小論文がありました。当時、受験科目に小論文を課していたのは慶應文学部だけかもしれません。筆者は慶應の他学部や他大学を受験したことがないので分かりません。
(*3)学部卒業論文では「英文に伸びがない」とのコメント一言のみ、真意が分からず戸惑いましたが、この事を言われたのなら納得です。修士論文も博士論文も提出後何のフィードバックも無く、卒業間際の面談でコメントを受けただけでした。それに対し、筆者が世話になったアメリカの大学、大学院では論文は言うに及ばず、papersや試験の答案全てがコメント付きで返却されました。アポイントメントを取れば懇切丁寧に更に詳しく教えてくれました。
(*4)筆者の本コラムFor Lifelong Englishの記事のバックナンバーにあります。キーワード“lifelong English”でも検索できます。
(*5)Memorable Teachersシリーズは好評で、“memorable teachers”で検索しても見られるようになりました。本シリーズは後3回ほどを予定し、Ph.D.論文の執筆中の奮闘記にも触れる積りです。
(*6)慶應SFC創設目標の一つが、新たな科学方法論の模索でした。筆者もそれに賛同し設立メンバーに加わりました。それを目指して教職員学生が一丸となり喧々諤々の議論を交わした創立当初の数年間が懐かしく思い出されます。
(*7)第120回で述べたように、TOEFL iBTテストは、留学生がアメリカの大学・大学院でこれら2つのreasoningを駆使しcritical thinkingができるかどうかをチェックします。英文を丸暗記したり、ひたすら視聴したりするだけで、inductiveやreductive reasoningを伴う発信活動をしなければこの力は付きません。
(*8)できないと思い込んでいただけで、日常会話なら授業開始からしばらくすれば出来るようになります。
(*9)前身は『Do Your Own Project in Englishプロジェクト発信型英語Volume 1 & Volume 2』(絶版 郁文堂)です。本書Volume 1は日常生活の関心事をテーマに、Volume 2では日常生活の関心事を更にresearchして掘り下げ、学術的テーマに高め、academic papersを書いてpresentation、discussionをします。Readings in Scienceでは専攻テーマでresearchを行い、その結果をpapersにまとめposter presentationをします。授業でも、小グループでも、2、3名でもできます。また、SFC赴任時代にはアメリカやイギリスの大学とテレビ会議でジョイント授業をしました。In-personでもonlineでも対応できます。Readings in Science は、TOEFLテスト、SAT、GREテストなどの準備に役立ちます。ここで改めてお願いがあります。これらの教科書の執筆時には、大学の事情で当初計画したonline出版を諦め、紙で出版せざるを得ませんでした。出版社は筆者の趣旨に賛同し、多大な費用を掛けて出版にこぎつけてくれました。特に、Readings in ScienceはNature Newsの記事10本を使用し、高額な使用料金を払い許可をいただいております。筆者自身も、記事の選択、注・設問執筆に相当の時間をかけました。日本経済も知的所有権に負うところが多大で、それを守る為にもコピーなどcomplianceにもとる無断使用など無きようお願い、訴えております。
(*10)『グローバル社会に生きるための英語授業』にて、筆者在任中の2008年-2014年の6年間における生命科学部・薬学部のPEP Program全受講者のprojectsとTOEICテストの成果、および、授業評価について報告しました。本書は非売品です。尚、筆者退職年2014年以降の状況、成果については定かではありません。
(*11)The Rule of Reason, The Philosophy of Charles Sanders Perce(J. Brunning & P. Forster, Ed.)と称するC. S. Peirceのreasoningに関する論文集があります。方法論に相当こだわっています。
(*12)Humanities(人文科学)、social science(社会科学)、hard science全てscience(科学)です。筆者の専攻分野の言語学(linguistics)は、social scienceに入ります。言語学に於いても色々な方法論による言語分析が行われます。Noam ChomskyらはDescartes客観主義に基づく方法論で、George Lakoffらはそれに反する相対論的な方法論で言語分析を展開しています。Roman JakobsonやJ. L Austinらの著作は、言語分析を通して科学方法論そのものを考察しているように思えてなりません。これら言語学者の影響は、humanities, social science、hard scienceなどの境界を超え、個別型から融合的科学方法論への関心を高めそうです。
(*13)英語発信力を身に付けたければ、自分で情報を受信・発信する場を作って活動する事です。英語以外の情報もネット上の翻訳ツールで簡単に英訳できます。TOEFL iBTテストで高得点を上げるには、英語を外国語教科(English as a foreign language)ではなく、生活に必要な第二言語(English as a second language)として運用する場の創生が急務です。インターネットを使えば個人、グループでも活動できます。筆者が高価な書籍ではなく、ネット上のサイトを紹介するのは、それがほぼ無料、あるいは、安価で実現可能である事を示唆するためです。但し、注7でも述べたとおり、YouTubeなどを視聴するだけで終わらず、発信する場を作りましょう。
サポートいただけるととても嬉しいです。幼稚園児から社会人まで英語が好きになるよう相談を受けています。いただいたサポートはその為に使わせていただきます。
