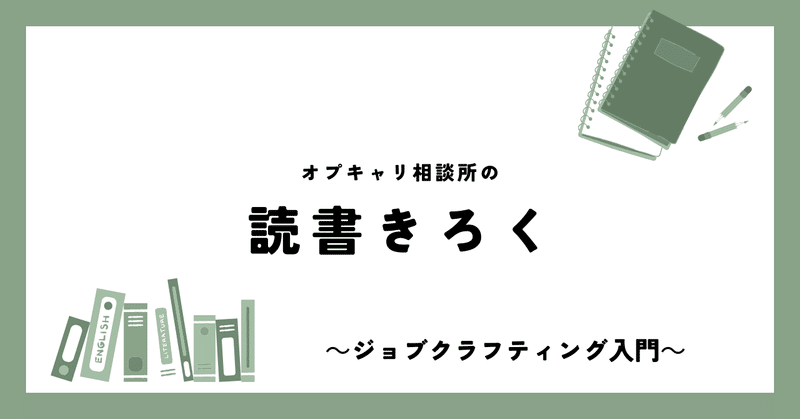
ジョブ・クラフティング入門(著・川上真史/種市康太郎/齋藤亮三)
「ジョブクラフティング」
近年、書店などでも見かけるようになったワードで、エンゲージメント向上やウェルビーイングなど企業活動の大切なキーワードです。結論、わたしの会社員人生の中で誇れる能力の1つはこれなんではないかと思えるほど共感し関連する本はいろいろと探索しました。(能力を持ち合わせているわけではなく、大切にしているだけなんですが)
そんなジョブクラフティング関連の本の中で、「最初に読むならこれ!」と思えるわかりやすさと網羅性があるので、おすすめの一冊としてご紹介します。
仕事の面白さを感じられる
習慣と志向を身につけよう
本は ”前書き” で8割決めてしまうタイプなのですが、本書の ”はじめに” はこのように書かれています。まさにジョブクラフティングをわかりやすく表現されており、読み進める気持ちができあがった瞬間でした。
何かを楽しめる人、良いところを見つけられる人であることは魅力的で、自分が一番大切にしている習慣です。
その後、ワークエンゲージメントとジョブクラフティングのつながりや、渋沢栄一さんを例に説明が始まっていくのですが、なるほどの一文がこちらです。
他者から与えられるものに対する感情は「満足感」です。それに対して、自分でつくりあげているものに対する感情は「幸福感」です。満足感を求めすぎると、かえって不幸になります。
わかりやすい!腹に落ちた!
いろいろな物語や事例を使いながら相手に伝えてきたわたしの仕事に対する価値観がシンプルに表現されています。満足感はもっと与えてほしいとなり未充足が続きます。ジョブクラフティングの本質だと思います。いかに自分にとって幸福感のある人生を送れるかは重要ですね。
・・・・・その動機は働く人の数だけあることでしょう。私たちの仕事に対する動機づけの変化を考えるカギとなるのが欠乏動機です。
本書の数多くの学びの中でも一味違った面白さがあったのがこちらの一文とそれ以降です。
欠乏動機は一般的な言葉ではハングリー精神。これが近年日本で大きく低下しているとつながっていくのですが、単純に「日本は満たされてきてハングリー精神がなくなってきている」という話ではないというところが実に興味深かったです。詳細まで書きませんが、将来期待値と現状の乖離、内的報酬の未充足がハングリーなのだと書かれています。ちなみに内的報酬とは「人や環境との関係」と「仕事そのもの」であり双方が満たされることが重要と書かれています。
このあと、エンゲージメントの誤解、人材マネジメントとの関係性など実学としての学びが続きます。書き続けると全章の感想に及んでしまいそうなので、ここまでとさせていただきます。ちなみに後半は具体的な施策やポリシー設計などにもつながっていき、考え方からアクションまで大いに学べる一冊となりました。
この本を読むたびに自身のジョブがクラフトされ、明日に向かっていけるように思える一冊です。
感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
